【原作と全然違う?】ドラマ『ロイヤルファミリー』原作との違い7選|改変理由と実話との関係を徹底解説
 ドラマ
ドラマ
2025.10.26
記事内にアフィリエ イト広告が含まれています。
結論から言うと、ドラマ『ロイヤルファミリー』は原作と「かなり違う部分」があります。
ドラマ『ロイヤルファミリー』を調べていて、「原作と全然違う?」「実話って聞いたけど本当?」「改変が多すぎない?」──そんな疑問に辿り着いた人は、きっと少なくないと思います。
検索結果には「原作改変」「実話ベース」「ひどい」「別物」といった強い言葉も並びますが、実際のところ、その評価はかなり混ざり合っています。 原作ファンの違和感もあれば、ドラマから入った人の納得感もある。 どちらかが間違っている、という話ではなさそうです。
この記事では、ドラマ『ロイヤルファミリー』と原作の違いについて、感想や好き嫌いではなく、 「何がどう違うのか」「なぜそうなったのか」を整理することを目的にしています。
- 原作とドラマの具体的な違い
- 物語は実話なのか?どこまでが事実ベースなのか
- ストーリーやキャラクターが改変された理由
- 原作ファンと視聴者の評価が分かれた背景
すべての改変が「悪」だったのか、それとも映像化として必要な選択だったのか。 原作未読の人でも理解できるよう、前提から順に整理していきます。
「原作と違うかどうか」を判断する前に、 まずは違いが生まれた構造から一緒に見ていきましょう。
この記事を読むとわかること
- ドラマ『ロイヤルファミリー』が原作と「別物」に感じられる理由と全体構造の違い
- 物語が実話と言われる背景と、事実とフィクションの線引きの考え方
- ストーリーやキャラクターが改変された具体的なポイントとその狙い
- ドラマオリジナル要素が追加された意味と映像作品としての役割
- 原作ファンと視聴者で評価が分かれた理由と納得しやすい受け止め方
この記事を読む前に|まず押さえたいポイント簡易まとめ
| 気になるポイント |
この記事で分かること(詳細は本文で解説) |
| 原作とドラマの違い |
「同じ話なのに印象が違う」理由が、構造レベルで整理されていく |
| 実話との関係 |
どこまでが現実を下敷きにしていて、どこからが物語なのか、その境界が見えてくる |
| ストーリー改変 |
なぜ順番や見せ方が変えられたのか、その狙いが段階的に明らかになる |
| キャラクターの違和感 |
「別人に見えた理由」が、人物設定の翻訳という視点から読み解かれる |
| オリジナル要素 |
原作にはなかった描写が、どんな役割を担っているのかが整理される |
| 改変への評価 |
原作ファンと初見視聴者で、なぜ受け止め方が分かれたのかが分かる |
1. ドラマ『ロイヤルファミリー』と原作の基本的な違い【原作と違うと言われる理由】
「え、これ原作と違う?」って思った瞬間って、だいたい心のどこかが置いていかれるんですよね
でも、その違いは“裏切り”じゃなくて、媒体が変わったときに起きる翻訳みたいなものかもしれない
ここでは細部に入る前に、ドラマ『ロイヤルファミリー』と原作の違いを全体像としてそろえます
| いちばん大きい前提 |
原作の再現ではなく、原作をもとにした“別の表現”として組み直されていると読み取れる |
| 原作の性質 |
背景や事実関係の手触りを重視しつつ、文章だからこそ可能な内面描写・余白で読ませるタイプ |
| ドラマ版の方向性 |
映像作品として、視聴者が迷わないように人物関係や出来事を整理し、感情の山を作っていく構成になりやすい |
| 違いが出やすい箇所 |
出来事の順番(時系列)/強調される対立軸/“誰の物語”として見せるか(視点の置き方) |
| 受け取り方のコツ |
「同じ話なのに違う」ではなく、同じ素材を別の言語(映像)に訳したと思うと、違いが整理しやすい |
基本の違い① 原作は「背景と温度」を積み上げる
原作を読むときって、派手な出来事よりも、行間の“ため息”みたいなものに引っ張られることがあります
説明されすぎないから、読者の中で「たぶんこうだったんだろうな」が育つ
そのぶん、同じ場面でも受け取り方が人によって揺れるのが、原作の強さかもしれません
ポイント:原作は「情報」だけじゃなく、「人の気持ちが言葉になるまでの遅さ」まで抱えていることがある
基本の違い② ドラマは「感情の道筋」を見失わせない
ドラマは映像なので、視聴者が迷子になると、その瞬間に置いていかれます
だから多くの場合、出来事の順番や関係性を整えて、感情が追えるようにする
この“親切さ”が、原作との違いとして最初に目につきやすいところです
原作は「読み手が追いつく」物語で、ドラマは「画面が連れていく」物語になりやすい──私はそう感じることがあります
基本の違い③ 原作=事実・背景重視 ドラマ=感情・ドラマ性重視
ここ、誤解されやすいんですが
ドラマが感情を重視するのは、事実を軽んじたからではなく、映像が感情の伝達に強い媒体だから、という面もあります
表情、間、光の当たり方ひとつで、説明がなくても届いてしまうんですよね
要点整理④ 「別物」と言い切るためじゃなく「迷わないため」に言語化する
この見出しの目的は、細かい違い探しではありません
“前提のズレ”を先にそろえることです
これが揃うと、次の見出し(実話との関係・改変点)で、感情が暴れにくくなる
- 原作:背景・内面・余白で「そうだったのかも」を育てる
- ドラマ:関係性・順番・対立軸を整理して「いま何が起きてるか」を伝える
- 違いの正体:優劣ではなく、伝え方のルールが違うことから生まれやすい
例え話⑤ 同じ旋律でも、楽器が変わると“刺さり方”が変わる
同じメロディでも、ピアノとギターで聴こえ方が違うみたいに
同じ素材でも、文章と映像では「刺さる場所」が変わります
原作が静かに滲ませた感情を、ドラマが強い輪郭で描くこともあるし、その逆もある
この先を読むための前提
ここではまだ「どこがどう変わったか」の細部には入りません
まずはドラマ『ロイヤルファミリー』と原作の違いが生まれる“構造”を押さえて、次の章で具体に降りていきます
注意点⑥ 「改変=劣化」にしないための見方
原作が好きな人ほど、違いに敏感になります
その感覚は自然だし、むしろ大事にしていい
ただ、ここで一度だけ言っておくと、改変は「壊した」より「組み替えた」に近い場合もあるんです
- 原作の“静けさ”が好きだった人は、ドラマの輪郭が濃く感じることがある
- ドラマから入った人は、原作の余白が「難しい」ではなく「深い」に変わることがある
- どちらも、間違いじゃない
2. 物語のモデルは実話?原作が描く事実関係
「これって、どこまで本当なの?」
『ロイヤルファミリー』を調べる人が、いちばん最初につまずくのがここかもしれません
実話なのか、フィクションなのか──その境界が曖昧だからこそ、不安になる
| 結論を先に言うと |
完全な実話ではないが、現実の出来事や社会背景を下敷きにしていると読み取れる |
| 原作の立ち位置 |
特定の事件や人物をそのまま描くのではなく、複数の事例・構造を再構成したフィクション性の高い作品 |
| 「実話っぽさ」の正体 |
権力構造、家族関係、組織内の歪みなど、現実社会に存在する問題がリアルに描かれている点 |
| ドラマ版での扱い |
視聴者が理解しやすいよう、人物関係や出来事を単純化・整理して提示している印象 |
| 注意すべき線引き |
公式に「この人物がモデル」と断定されている情報はなく、あくまで推測レベルで語られている |
実話との関係① 原作は「記録」ではなく「構造」を描いている
原作がやっているのは、出来事の年表をなぞることではありません
むしろ、「なぜこういう悲劇や対立が起きるのか」という構造そのものに焦点を当てています
だからこそ、特定の事件を知らなくても「ありそうだ」と感じてしまう
ここが誤解されやすいポイント
リアルに感じる=実話、ではない
「現実に起こり得る形」で再構成されている、という距離感が近いかもしれません
実話との関係② 「モデルがいる」と言われる理由
検索すると、「この人物がモデルでは?」という声を見かけることがあります
それは、設定や関係性に現実の類似点が多いから
ただし、それは“参照”であって“再現”とは限りません
- 社会的立場や権力構造が現実と似ている
- 家族内・組織内の対立が生々しい
- ニュースで見た構図と重なる部分がある
こうした要素が積み重なることで、「実話なのでは?」という印象が強まると考えられます
実話との関係③ ドラマ版で強まった“分かりやすさ”
ドラマでは、原作よりもさらに「理解しやすさ」が前に出ます
時系列を整理し、人物関係を単線化することで、
実話かどうか以前に「物語として追いやすい」構造になっている
実話かどうかを考える前に、「なぜそう見えるのか」を考えると、整理しやすくなる気がします
線引き整理④ どこまでが事実で、どこからが創作か
ここで大切なのは、白黒をつけすぎないこと
公式情報として断定されているのは、
「実在の事件をそのまま描いた作品ではない」という点です
- 事実:現実の社会構造・問題意識が反映されている
- 推測:複数の事例や人物像をミックスしている可能性
- 創作:物語として成立させるための再構成・脚色
安心ポイント⑤ 「実話じゃない=軽い」ではない
実話ではないと知って、拍子抜けする人もいるかもしれません
でも、原作もドラマも、
現実に起きている問題を“見える形”にするという役割は果たしています
この章のまとめ
『ロイヤルファミリー』は、実話を再現する物語ではありません
けれど、現実を知らずに生まれた物語でもない
その中間にあるからこそ、「本当にありそうだ」と感じてしまうのかもしれません
なお、『ロイヤルファミリー』の中でも特に話題になっている「馬のモデル」については、 実在の名馬や史実との関係が指摘されることもあります。
馬や騎手のモデル説について、もう少し具体的に知りたい方は、こちらで整理しています。
▶ ▶ ドラマ『ロイヤルファミリー』は実話?馬のモデルと原作との違いを解説|オグリ・名馬説・騎手モデル・史実との関係を完全解説【最新版】
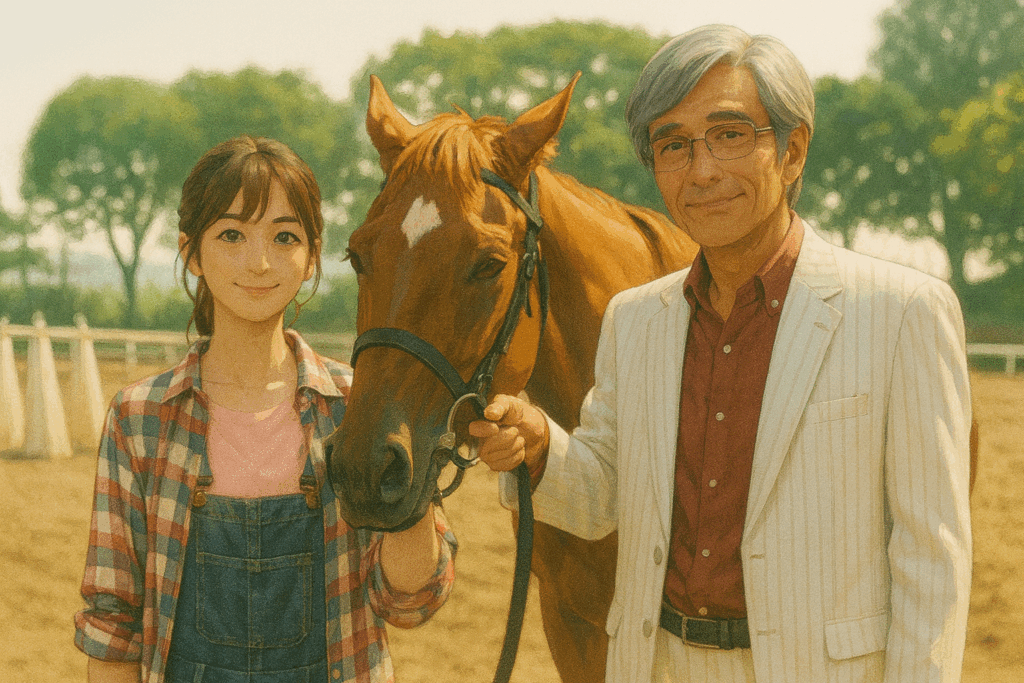
【画像はイメージです】
3. ドラマ版で大きく改変されたストーリー展開
原作とドラマの違いを語るうえで、
いちばん「違った」と感じやすいのが、このストーリー展開かもしれません
物語の“何をどこで見せるか”が、意図的に組み替えられているからです
| 改変の中心 |
原作の流れをそのままなぞるのではなく、時系列や見せ場を再配置している |
| 原作の進み方 |
背景説明や経緯を積み重ねながら、じわじわと全体像が見えてくる構成 |
| ドラマの進み方 |
序盤から対立構造を明確にし、感情のフックを早めに提示している |
| 省略・統合 |
複数の出来事や人物の役割が整理され、エピソードが一本化されている箇所がある |
| 視聴者への影響 |
理解しやすくなる一方で、原作特有の“遠回り感”が薄れたと感じる人もいる |
改変ポイント① 物語の分岐点が早く提示される
原作では、しばらく霧の中を歩くような感覚があります
「これが何につながるんだろう」と考えながら読み進める構造
一方ドラマでは、物語の軸となる対立や問題が比較的早く示されます
ここが違和感になりやすい理由
原作で“後から効いてくる”要素が、
ドラマでは最初から意味を持って配置されていることが多い
改変ポイント② 時系列の再構成と整理
原作では前後しながら描かれていた出来事が、
ドラマでは一本の時間軸にまとめられている印象があります
これは、映像での混乱を避けるための調整と考えられます
- 過去の出来事が回想として明確に区切られる
- 同時進行だった事件が順番に整理される
- 因果関係が一目で分かる構成になる
改変ポイント③ クライマックスの演出強化
原作のクライマックスは、
大きな爆発よりも「積み重なったものが静かに崩れる」タイプです
ドラマではそこに、音楽や間、演出で感情の山が加えられています
同じ出来事でも、「どこでピークを作るか」で、受け取る温度は大きく変わるんですよね
改変ポイント④ サスペンス性の付加
ドラマ版では、次回が気になる“引き”が意識的に作られています
原作では淡々と進む部分にも、
緊張感を持たせる編集が施されている印象です
ネタバレを避けて言うなら
何が起きるかよりも、
「いつ・どの順で明かすか」が大きく変えられている章だと言えそうです
整理⑤ 改変は“話を変えた”というより“話し方を変えた”
ストーリーが違うと感じる正体は、
出来事そのものよりも、見せる順番と強調点にあります
原作未読でも理解できるように、道筋が整えられているとも言えます
- 原作:遠回りしながら全体像が見えてくる構成
- ドラマ:迷わせずに感情を運ぶ構成
- 違い:内容よりも“体験の設計”
4. 登場人物設定の違い|原作キャラはどう描かれていた?
「話は同じはずなのに、なんだか人が違って見える」
原作とドラマを見比べたとき、多くの人が引っかかるのがこの部分です
ストーリー以上に、人物の“温度”は違いを感じやすい
| 原作キャラの特徴 |
内面描写が多く、迷いや矛盾を抱えたまま行動する人物として描かれている |
| ドラマ版の印象 |
性格や立場が整理され、役割が分かりやすく強調されている |
| 変化を感じやすい点 |
感情の出し方/行動理由の明示度/他キャラとの関係性 |
| 視聴者の反応 |
「分かりやすくなった」という声と、「単純に見える」という声が分かれやすい |
| 改変の方向性 |
人物の本質を変えるというより、伝わり方を調整している印象 |
人物設定① 原作キャラは“揺れている時間”が長い
原作では、登場人物がすぐに結論を出しません
迷って、ためらって、ときには間違えたまま進む
その揺れている時間が、文章の中で丁寧に描かれています
原作ならではの特徴
行動よりも先に、
「なぜそう思ってしまったのか」という内側が語られることが多い
人物設定② ドラマでは性格が“見える形”に整理される
ドラマでは、視聴者が一目で理解できることが重視されます
そのため、人物の性格や立場が、
行動やセリフとして外に出る形に調整されやすい
- 迷いが短縮される
- 対立構造がはっきりする
- 役割が象徴的になる
人物設定③ 関係性の描かれ方が変わる理由
原作では複雑だった人間関係も、
ドラマでは整理され、分かりやすい線になります
これは放送尺と視聴体験を考えた結果と考えられます
人が多すぎると、誰の感情を追えばいいか分からなくなってしまうんですよね
人物設定④ 「違和感」の正体
原作を知っている人ほど、
「こんな人だったっけ?」と感じる瞬間があります
それは、性格が変わったというより、強調点が変わったからかもしれません
注意したいポイント
キャラクターの違和感を、
俳優や演技の問題に結びつけすぎないこと
整理⑤ キャラ改変ではなく“キャラ翻訳”と考える
原作とドラマでは、
キャラクターが置かれているルールが違います
内面を語れる世界から、表情と行動で伝える世界への翻訳
- 原作:複雑で矛盾した人間像を描ける
- ドラマ:瞬時に理解できる人物像が求められる
- 違い:本質よりも見せ方
【ロングSPOT解禁】夢と情熱を呼び起こせ!TBSドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』
5. 原作では描かれなかったドラマオリジナル要素
原作とドラマを比べていて、
「これは原作にあったっけ?」と立ち止まる瞬間があります
それが、このドラマオリジナル要素です
| ドラマ独自の追加点 |
原作には描かれていないシーン・設定・関係性が複数追加されている |
| 追加の目的 |
物語の理解を助け、感情移入をしやすくするための補強 |
| 原作との違い |
原作では行間に委ねられていた部分を、映像で“見せる”形にしている |
| 評価が分かれる理由 |
説明的に感じる人と、親切だと感じる人に分かれやすい |
| 重要な視点 |
オリジナル要素=蛇足とは限らず、媒体差から生まれた補助線とも考えられる |
オリジナル要素① 原作の「空白」を埋めるシーン
原作では語られなかった出来事や、
さらっと流されていた関係性が、
ドラマでは具体的な場面として描かれることがあります
原作読者が感じやすいポイント
「あえて書いてなかったのに」と思う一方で、
「こういうことだったのか」と腑に落ちる場合もある
オリジナル要素② 感情を補強するための追加描写
ドラマでは、人物の感情を一瞬で伝える必要があります
そのため、原作にはなかった
感情の前振りや余韻のシーンが足されることがあります
- 沈黙の時間が長くなる
- 視線や仕草に意味を持たせる
- 感情の変化を段階的に見せる
オリジナル要素③ 映像ならではの表現
音楽、照明、間、カメラワーク
これらは原作には存在しない要素です
ドラマでは、それらを使って感情の輪郭を強めています
言葉にしなくても、音楽ひとつで気持ちが伝わることってありますよね
オリジナル要素④ 分かりやすさを優先した改変
原作では複雑だった設定や背景が、
ドラマでは整理され、単純化されることがあります
これは“省略”というより、翻訳に近い作業とも言えます
肯定的に見るなら
初見の視聴者が、
物語に置いていかれないための工夫
整理⑤ ドラマオリジナル要素は“足し算”のためにある
オリジナル要素は、
原作を否定するために生まれたものではありません
むしろ、原作の理解を助ける補助線として機能している部分も多い
- 原作:余白で読ませる
- ドラマ:具体で伝える
- 違い:情報量ではなく伝達方法
6. なぜ改変されたのか?制作側の意図と脚色理由
ここまで読んで、「違いがあるのは分かった」
でも次に浮かぶのは、きっとこの疑問です
「で、なんで変えたの?」
| 改変の根本理由 |
原作の否定ではなく、映像作品として成立させるための最適化 |
| 媒体の違い |
文章は内面を直接描けるが、映像は視覚と音で伝える必要がある |
| 視聴者層 |
原作読者以外の層にも届くよう、理解しやすさが重視された可能性 |
| 放送・配信の制約 |
話数・尺が限られるため、情報の取捨選択が不可避 |
| 脚色の方向性 |
複雑さを削るというより、感情の道筋を一本化する調整 |
制作意図① 文章と映像では「伝えられるもの」が違う
原作は、登場人物の思考や葛藤を
そのまま文章として差し出すことができます
でもドラマでは、それを表情・間・構図で表現しなければならない
ここが改変の出発点
内面を語れない分、
外側の出来事や行動を整理する必要が出てくる
制作意図② 視聴者を途中で離脱させないため
テレビドラマや配信作品は、
「分からない」と思われた瞬間に離脱されるリスクがあります
そのため、物語の軸や対立関係が早めに示されやすい
- 誰と誰が対立しているのか
- 何が問題なのか
- どこに向かう物語なのか
これらを明確にすることが、改変の大きな理由のひとつと考えられます
制作意図③ 放送尺・話数という現実的な制約
原作には、寄り道や余白がたくさんあります
でもドラマは、限られた話数の中で完結させなければならない
その結果、エピソードの統合や省略が起きるのは自然な流れです
削ったというより、「残すものを選んだ」と見るほうが近いかもしれません
制作意図④ 国際配信・広い視聴層を意識した可能性
近年のドラマは、
国内だけでなく、海外配信も視野に入れられることがあります
文化的背景を知らなくても理解できる構成が求められる場合もある
この視点で見ると
説明的に感じた部分が、
「翻訳として必要だった」と見えることもある
着地点⑤ 改変は「必要悪」ではなく「必然」
改変という言葉は、どうしてもネガティブに聞こえがちです
でも、媒体が変われば、表現も変わる
ドラマ版『ロイヤルファミリー』の改変は、映像作品として成立させるための必然だったと考えられます
- 原作:深く潜れる
- ドラマ:広く届く
- 改変:その橋渡し
7. 原作ファン・視聴者の評価はどう分かれたのか
原作とドラマの違いを見てきたうえで、
最後に気になるのはやっぱり「みんなどう思ったのか」だと思います
評価が割れた理由は、単純な好き嫌いではなさそうです
| 評価が分かれた理由 |
作品の良し悪しというより、期待していたものの違いが大きい |
| 原作ファンの傾向 |
心理描写や余白が減った点に、物足りなさや違和感を覚える声が多い |
| ドラマ初見層の傾向 |
分かりやすく、テンポが良い点を評価する声が目立つ |
| 共通している点 |
テーマや問題提起自体には、一定の評価が集まりやすい |
| 重要な視点 |
評価の違いは、入口(原作かドラマか)によって生まれやすい |
評価の分かれ方① 原作ファンが感じた「足りなさ」
原作から入った人ほど、
ドラマ版に対して「急いでいる」と感じることがあります
それは、物語というより感情の滞在時間が短くなったからかもしれません
- 内面描写が少ない
- 葛藤が早く処理される
- 行間を想像する余地が減った
評価の分かれ方② ドラマ初見層が感じた「見やすさ」
一方、原作を知らずに観た人からは、
「分かりやすい」「続きが気になる」という声も多い
物語としての導線の親切さが評価されやすい傾向があります
初見視聴者の評価ポイント
登場人物の関係が把握しやすい
テーマが明確で追いやすい
評価の分かれ方③ なぜここまで差が出たのか
評価の差は、
「どちらが正しいか」ではなく、
何を期待していたかの違いから生まれているように見えます
同じ作品でも、求めていた体験が違えば、評価も変わるんですよね
評価の分かれ方④ 原作とドラマは「競合」ではない
原作とドラマは、
どちらが上かを競う関係ではありません
それぞれが、違う角度から同じテーマを照らしている
ここを混同しないために
原作の評価が高い=ドラマが失敗、ではない
ドラマが評価される=原作が軽くなる、でもない
整理⑤ 評価が割れたこと自体が、この作品の特徴
全員に同じ感想を持たせる作品は、たぶん存在しません
『ロイヤルファミリー』は、
見る人の立場や期待を映し返すタイプの作品だったとも言えそうです
- 原作ファン:深さを求めた
- 初見層:分かりやすさを求めた
- 評価の差:そのズレから生まれた
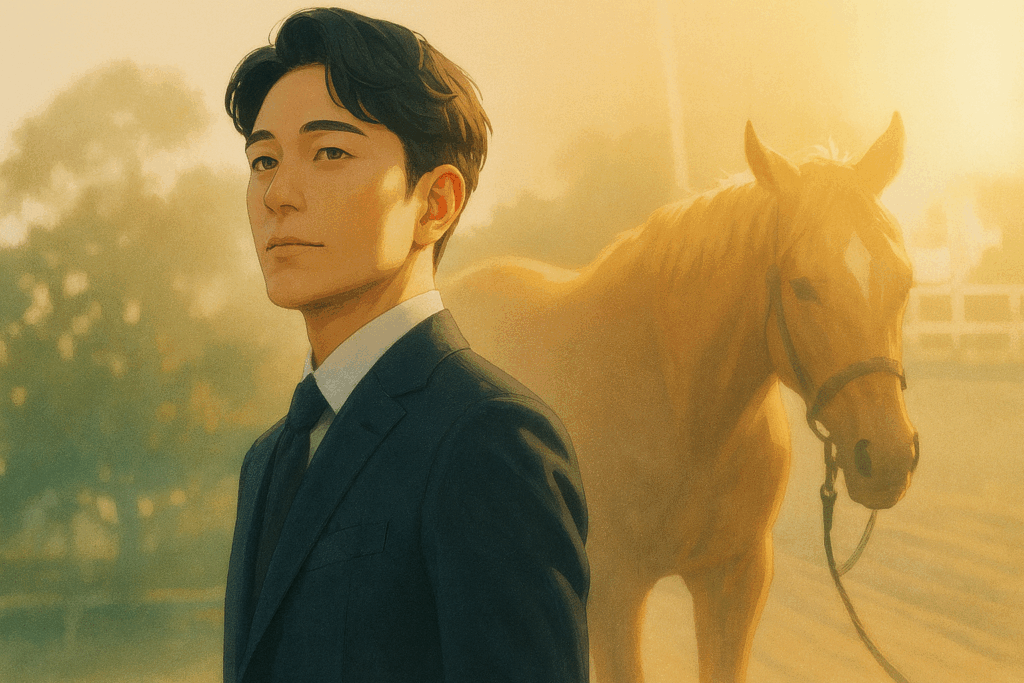
【画像はイメージです】
本記事まとめ|ドラマ版『ロイヤルファミリー』は何が違ったのか
ここまで、原作とドラマ『ロイヤルファミリー』の違いを見てきました
読み進めるうちに、「違う」という感覚が、少し輪郭を持った人もいるかもしれません
最後に、この作品の“違い”をどう受け取ればいいのか、静かに整理します
| 原作と違うのか |
ドラマ『ロイヤルファミリー』は原作と違う部分があるが、 物語の核や問題意識が失われたわけではない |
| 実話との関係 |
完全な実話ではなく、現実の構造や背景を下敷きにした再構成と考えられる |
| 改変の理由 |
原作軽視ではなく、映像作品として成立させるための調整 |
| 評価が割れた理由 |
作品の出来よりも、視聴者の期待値の違いが影響している |
| 受け取り方のヒント |
原作の再現ではなく、別の表現として見ると理解しやすい |
結論① 原作とドラマは「同じ物語の別ルート」
ドラマ版『ロイヤルファミリー』は、
原作をなぞることよりも、
より多くの人に届く形に翻訳することを選んだ作品だと考えられます
結論② 違和感は、理解が深まる入口でもある
「なんか違う」と感じたその感覚は、
原作を大切に思っている証拠でもあります
同時に、ドラマが別の角度から光を当てた証でもある
こんな人に向いているかもしれません
原作のテーマを、違う形でもう一度見てみたい人
整理された物語で、全体像を掴みたい人
結論③ 完璧に同じでなくていい
原作とドラマが、
完全に一致していたら、
きっとここまで語られることもなかったはずです
違いがあったからこそ、
「何を描こうとしたのか」を考える余地が生まれた
私は、そう思っています
原作を愛したまま、ドラマを受け取ってもいいし、 ドラマから原作に戻ってもいい その往復自体が、この作品の楽しみ方なのかもしれません
▶ 『ロイヤルファミリー』関連記事をもっと読む
キャスト・相関図・ストーリー考察・放送情報まで──『ロイヤルファミリー』に関する記事を、最新順でまとめてチェックできます。まだ知られていない深掘り情報も多数掲載中。
この記事のまとめ
- 『ロイヤルファミリー』は“原作改変”ではなく“再構築”──原作の精神を映像の言語で生かしたドラマ化
- 原作『ザ・ロイヤルファミリー』(早見和真)は家と血をめぐる文学的ドラマ、ドラマ版は“赦しと再生”を描く人間ドラマへと進化
- 取材と脚色の境界を曖昧にすることで、リアルと虚構を融合させた“現実のような物語”を実現
- 第4話までで見えた違い──原作の静的構造を動的ドラマとして再構成し、社会性と感情を両立
- 第5話以降では、SNS・世論・新世代など“現代のリアル”をテーマに拡張する可能性が高い
- 原作とドラマの差は劣化ではなく“進化”。異なる手法で同じ理念──「人間の尊厳」を描いている
- 原作×映像の響き合いが生んだ、新しい“時代のロイヤルファミリー像”こそ本作最大の魅力
【30秒SPOT解禁】夢と情熱を呼び起こせ!TBSドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』

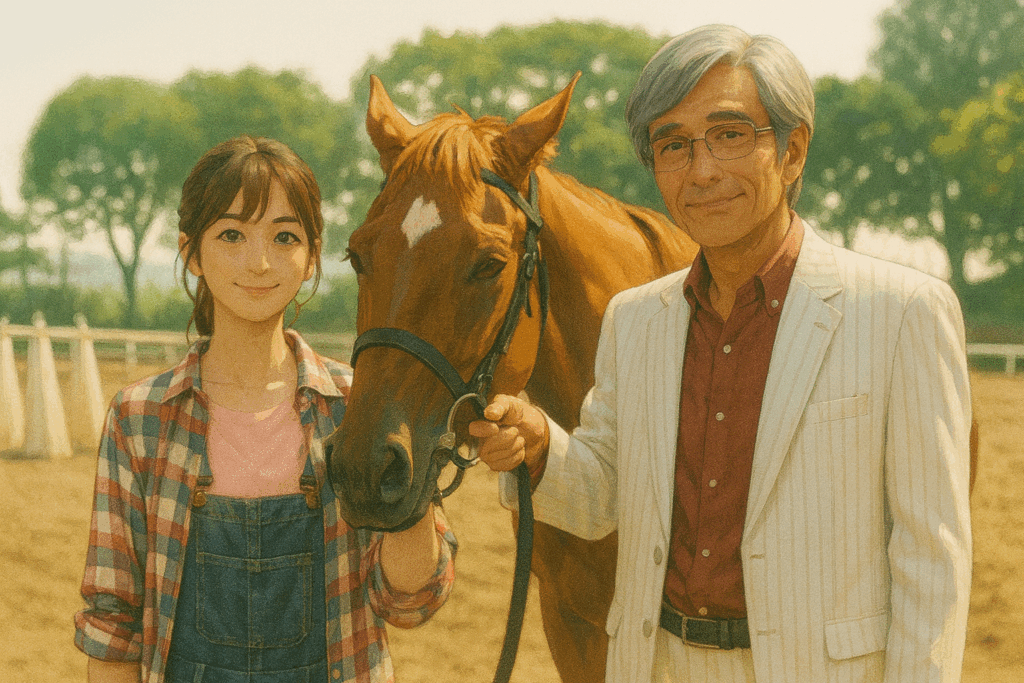
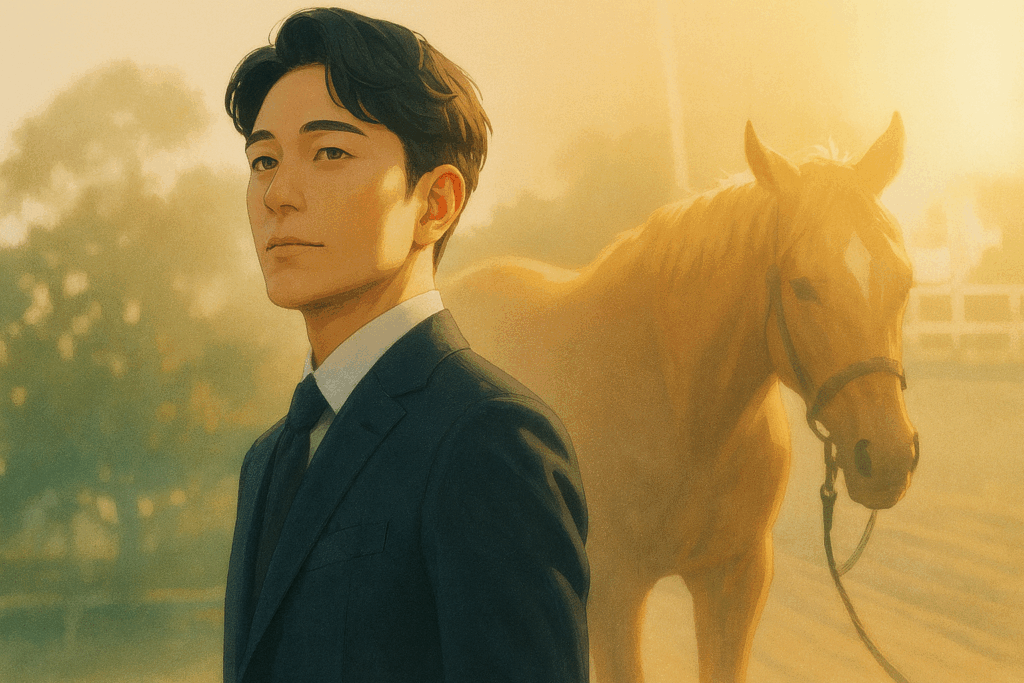
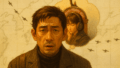

コメント