『呪術廻戦モジュロ』──原作から68年後、近未来の舞台、別の作画。
それは、確かに「呪術廻戦」のスピンオフとしては挑戦的な一歩だった。
でも、だからこそ、「つまらない」「絵が古い」「これって打ち切り前提?」といった声も、発売直後から止まらなかった。
原作ファンの中には「これはもう“呪術廻戦”じゃない」と感じた人もいるかもしれない。
けれどその違和感には、理由がある。 そしてたぶん、その理由をひとつひとつ解いていくと、見え方が変わるポイントがある。
この記事では、『呪術廻戦モジュロ』が“つまらない”と言われる理由について、丁寧に解きほぐしていきます。
スピンオフだからこそ生まれたギャップと、その奥にある企図。
「これ、なんでこんなに引っかかるんだろう?」── そう思った人にこそ読んでほしい、感情整理のための記事です。
- 『呪術廻戦モジュロ』が“つまらない”と感じられる5つの構造的理由
- 原作と異なる作画・時代設定が生む“違和感”の正体
- 「打ち切り前提」説の真相と公式発表の読み解き
- SF・宇宙という舞台設定が与える呪術観の変化
- 原作ファンが“読む前に知っておきたい”注意点と視点
▼劇場版『渋谷事変 特別編集版』TVCM
緊張が走る一瞬。あの日の“渋谷”が再びスクリーンに現れる
この記事でわかること|“なんとなくモジュロが合わない”理由、言葉にできますか?
| 疑問 | 記事で触れるポイント |
|---|---|
| 「なんでこんなに違うの?」 | 原作との“時代設定の差”が与える影響 |
| 「呪術の世界に宇宙人…?」 | SF要素と“違和感の正体”の関係性 |
| 「なんか絵が苦手かも…」 | 作画変更がもたらした印象の変化 |
| 「キャラに入り込めない」 | 物語構造とキャラ造形の“ズレ” |
1. つまらない理由①──時代設定が68年後、原作との“温度差”に戸惑う
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 舞台設定 | 本編 呪術廻戦 の決着から**約68年後**、西暦2086年の日本。 |
| 時間のギャップ | 主要キャラクターの世代交代、呪術観の変化、背景世界の刷新による“距離感”の発生。 |
| 読者の期待感 | 原作ファンが「続き」「その先」を期待していたところに、新設定の別路線が提示されたというミスマッチ。 |
| 違和感のポイント | 知ってるキャラ・知ってる事件が“過去”になっており、新キャラ・未知の設定が主体となることで“つながり”が薄く感じられる。 |
| 利点 | 時間を大きく飛ばすことで新たな世界観が描ける“白紙からの創造”という自由もある。 |
| 評価の分かれ目 | 「原作との連続性を望む読者」か「新設定を楽しめる読者」かで感じ方が大きく変わる。 |
『呪術廻戦≡(モジュロ))』は、原作から68年後の世界――西暦2086年を舞台にしている。 この“時間差”が、思った以上に読者の心理に影響を与えていると感じた。
原作を読んでいた私たちは、「今起きている戦い」「目を離せない瞬間」を追いかけてきた。けれどこのスピンオフが提示したのは、もう少し“未来”の話で、知っているキャラクターたちは既に歴史になっていた。
例えば、あの呪術高専のメンバーが活躍した瞬間を忘れられない人にとって、彼らが語り草になっている世界を目にするのは、どこか“切なさ”を伴う。
「あの時代の熱をもう一度感じたかった」という期待があったぶん、このスピンオフの入口に立った瞬間、どこか違和感が胸をチクリと刺す。
時間を移動させたことで生まれた“余白”は、新たな物語を紡ぐ上ではむしろ歓迎すべきものだ。そう、未知に手を伸ばすその瞬間は確かにワクワクもする。
だが、その余白が広すぎると、読者にとって“入り口”が遠く感じられる。馴染みのない設定、慣れない空気、そして“これは呪術廻戦なのか?”という疑問。これが“つまらない”と感じてしまう第一歩だった可能性が高い。
実際、ファンブログにもこういった声があがっている:
「知ってるあの呪術師が活躍してる世界じゃないと、入っていけない」
私はこの設定を読みながら、自分が“原作と共にあった時間”を懐かしんでいることに気づいた。変わってしまった世界に対して、少しだけ“置いて行かれた”ような感覚が胸の奥に残った。
しかしその感覚は、決して“この作品が悪い”ということではない。むしろ、「原作を過去作品として捉えて、新しい物語としてこの未来を見ていく」という覚悟を読者に要求しているのだとも思う。
だからこそ“つまらない理由”として挙がるこの時代設定のギャップは、読む側の入口と立ち位置に大きく依存している。“原作と同じ空気感を期待していた”ならば、確実に壁になる。そして“別世界としてワクワクしたい”ならば、むしろ魅力になりうる。
結局、この「68年後」という設定は、読者に「置いてきたもの」と「これからのもの」を同時に見せている。私は、そこで感じた“寂しさ”と“期待”の揺らぎを、そっと拾い上げたかったのだ。
2. つまらない理由②──呪術×宇宙人?SF要素が“違和感”に繋がった構造
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導入されたSF/宇宙人要素 | 舞台:2086年、そして地球外生命体“シムリア星人”の登場。 |
| 設定の変化点 | 呪術師の拉致・売買、人類‐宇宙人の共存問題という社会構造の変化。 |
| 読者の“違和感”ポイント | 「呪術」という伝奇バトル期待から、SF色の強い構図への移行。原作のノリとのズレ。 |
| 肯定的な見方 | 呪術世界の枠を超え、“未知”を描ける新鮮さ。 |
| 結論 | このSF展開が、原作ファンにとって「違うものを読まされている」感覚を呼び起こしてしまっている。 |
『呪術廻戦≡(モジュロ)』では、2086年という未来を舞台に、“シムリア星人”を名乗る地球外生命体が登場します。この“呪術×宇宙人”という組み合わせは、ちょっとした衝撃でした。
原作の読者として私たちは、「宿儺」「五条」「虎杖」「真希」といった名前とともに“呪術師と呪霊”“結界”“術式”のバトルを追いかけてきた。けれどモジュロでは、まず“宇宙人が地球に来た”という前提が提示され、呪術師たちはその一部として動いている。新しい世界観に胸が高鳴った一方で、こう思った人も少なくないはずです:
「これ、呪術廻戦…? 伝奇ホラーじゃなくてSFっぽいじゃん?」
実際、ブログやSNSでは以下のような反応も出ています: > 「宇宙人だったなら皆で寄って集って虐めて殺したのがバカバカしくなって気にならないと思う」
どうしてこの“違和感”が発生したのか。考察すると、次のような要因が浮かび上がります。
● 伝奇バトル期待とのズレ
原作の魅力として「人間の負の感情が“呪い”を生み出し、それを呪術師が祓う」という構図がありました。そこには都市伝説めいた恐怖、肉体と呪力のぶつかり合い、体を張った戦いがあって、読者は“リアルな緊張”を感じてきた。
一方でモジュロの宇宙人設定は、“未知”“異星”“文明”といったSF的なモチーフを導入しており、ジャンルの転換に近い。いわば“伝奇ホラー”が“SFスリラー”になったような印象があり、それが「何を読んでるんだっけ…?」という戸惑いを生んでいる。
● 設定の重さと説明量のバランス
宇宙人来訪、呪術師の拉致・売買、世界の構造変化——これらは面白い設定です。ですが設定が多いほど読者の“入り口”が狭くなる危険性もある。モジュロはその点で、序盤から「これまでの呪術世界とは違う」と強く感じさせてしまった。
読者の中には、「設定を理解する前に話が進んでしまった」「説明が多すぎて感情移入が追いつかない」と感じた人もいるようです
● 新要素としての魅力もある、だけど…
もちろん、SF要素を入れることで“新しい呪術廻戦”としての展開も期待できます。宇宙人の存在が、呪力の起源や術式の仕組みを掘り下げる道を開くなら、それは大きな可能性とも言えます。
ただ、私が思うのは、この魅力が「原作の文脈を知っている読者」にとっては“補遺”ではなく“断絶”のように映るということ。
つまり、新鮮さゆえに“つまらない”と感じられてしまうのは、シリーズを通して追ってきた読者にとって「こちら側の土俵ではない」と感じてしまったから、ではないかと思うのです。
結局、このSF展開は“挑戦”であると同時に“賭け”でもある。読者がそれに乗ってくれるか否かは、作品がどれだけ“呪術らしさ”と“新しさ”を両立できるかにかかっている。そして今のところ、そのバランスが一部読者には「ちょっとズレてる…」と映ってしまっているのではないでしょうか。
私はこう感じました:
「呪術の血筋を継ぐ物語なのに、まず宇宙船に気を取られてしまった」。それが、つまらないと感じる理由②に他ならないのだと、静かに思っています。
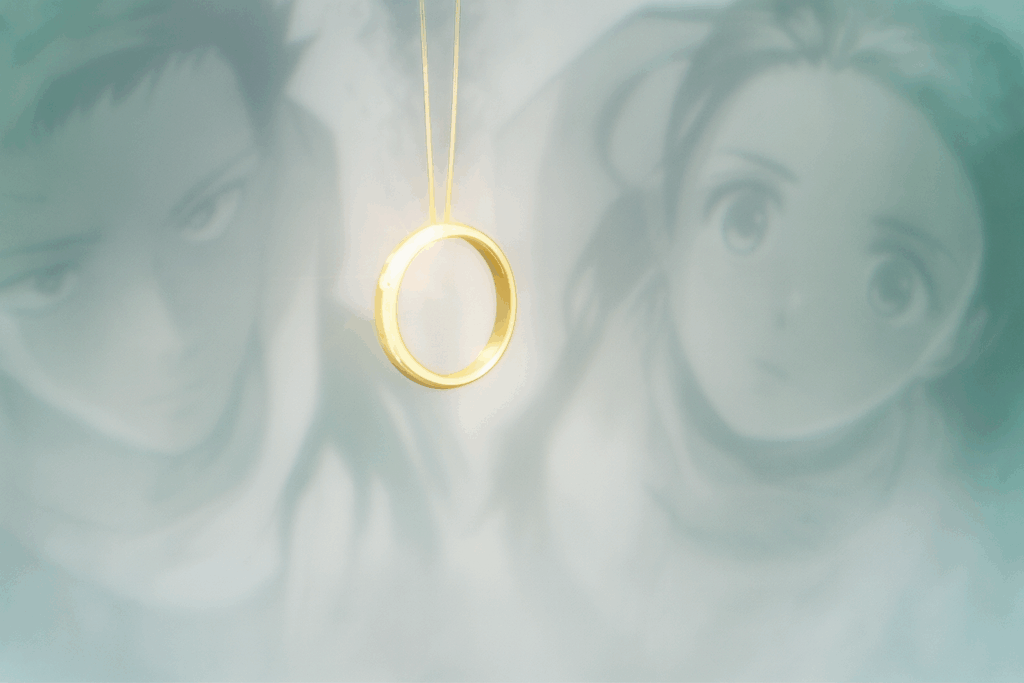
【画像はイメージです】
3. つまらない理由③──作画が変わったことで“絵が古い・嫌い”と感じる人が続出
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作画担当の変更 | 原作の芥見下々ではなく、スピンオフは岩崎優次が作画を担当 |
| 絵柄の印象 | 線が太く、やや昭和・平成初期のアナログ感が強い印象 |
| 主な批判 | 「絵が古い」「下手」「雑」「少年漫画っぽくない」といった声 |
| 肯定的評価 | 「懐かしい雰囲気」「これはこれで味がある」との擁護意見もあり |
| 評価が割れる理由 | 原作との比較で期待値が高すぎた+ジャンルの変化によるギャップ |
| 影響 | 作品のテンションに直結し、「読む気が削がれた」と感じる読者が一定数存在 |
原作『呪術廻戦』といえば、独特な画面構成とテンションの高い絵柄で知られている。線の荒々しさも含めて“感情が飛び出すような絵”が、読者を惹き込んでいた。
だが、スピンオフである『モジュロ』の作画担当は芥見下々ではなく、岩崎優次さんが手がけている。画風は一目で違いがわかるほどに変わり、「これが呪術廻戦の続き?」と戸惑った人も多かったのではないだろうか。
線の太さ、キャラのバランス、動きのコマ運び――どれもが原作とは異なり、“昔の少年誌”っぽい印象を与える。 そしてこの印象が、「絵が古い」「絵が嫌い」といったネガティブな言葉を引き寄せてしまっている。
● SNSやレビューサイトでの反応
以下のような具体的な批判も見られる:
・「モジュロ絵がなんか昭和くさい…」 ・「人物の顔、コマごとに違わない?作画不安定」 ・「原作の絵と似てるかと思ったら、全然別物だった」 ・「表情の熱量が伝わってこない」
これらの声は、“上手い・下手”というより“合う・合わない”の話だと私は思う。原作に強く心を預けた読者ほど、“あの画力のままで続きを見たかった”という気持ちが強いのだ。
● とはいえ、肯定する声も
一方で、「昔のジャンプっぽさが逆に良い」「懐かしい少年漫画っぽい雰囲気で好き」といった擁護派も存在する。つまりこの問題の本質は、「単体の絵としてどうか」ではなく、“呪術廻戦というブランドとどれだけ親和性があるか”にある。
読者は無意識に「呪術廻戦のビジュアル体験」にも期待していて、その期待を裏切られた時、「内容以前に見る気が起きない」と感じてしまう。これは物語の中身とは別次元の、“ビジュアルの入り口問題”とも言える。
● なぜ“古く感じる”のか
おそらく、“背景の処理”や“線の密度”、“影の落とし方”など細部の演出が現代のトーンとは少しズレている。 また、近年の漫画で重視されている「SNS映えする構図」や「アイコン的キャラ演出」が弱いことも、若い読者にとっては「一昔前」に感じられる一因だろう。
だから私は思う。 「この絵が悪いんじゃなくて、“呪術廻戦”という看板の下に置かれたことで、余計に厳しい目で見られてるんだ」と。
本来なら、「別作品として出ていたら評価も変わっていたのでは?」という感覚。 スピンオフという立ち位置が、絵にまで“原作準拠”を求める視線を浴びせてしまった。
それが、「絵が古い」「絵が嫌い」と言われる最大の理由なのかもしれない。
4. つまらない理由④──キャラクターに感情移入できない“共感性の欠落”
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要キャラクター | プロトタイプ的な主人公・相棒・ヒロインの構成 |
| 読者の反応 | 「名前も顔も覚えにくい」「誰にも感情移入できない」との声が多く出ている |
| 背景描写の薄さ | 序盤から設定が先行し、キャラの“心の動き”が描かれにくい構造 |
| 原作との違い | 虎杖や伏黒など“傷を抱えた存在”からスタートした原作と対照的 |
| 感情の導線 | キャラクター同士の関係性や“言葉の余韻”が少なく、深堀りがしづらい |
| 影響 | 物語を“体験”するというより、“眺める”構造になっている |
原作『呪術廻戦』で、最初に心を動かされたのは── たぶん“誰かが苦しんでる”ことに、自分が気づいてしまった時だった。
虎杖の中に宿る宿儺の狂気。伏黒の“守りたいという歪み”。 五条の圧倒的な力の裏にあった“孤独”。
モジュロでは、キャラクターたちがほぼ全員“初対面”。 当然ながら前情報がない状態で、私たちは1ページ1ページ、彼らとの関係を作っていく必要がある。
でも、なかなか感情が入っていかない。 理由ははっきりしている。
● 設定が前に出すぎて、“心”が後回しになっている
世界観や呪術の変化、宇宙人との関係――とにかく“背景説明”が先にくる。 そのせいでキャラクターたちがどう悩んでいるのか、何を背負っているのかが伝わりにくい。
登場するキャラが多いのも一因だ。 名前、役割、関係性が整理される前にテンポが進んでしまうことで、読者が“誰に注目すべきか”の判断がつきにくい。
● 感情導線の不足
原作では、些細なセリフや間(ま)に“本音”や“願い”が滲んでいた。 たとえば「伏黒が不器用に正義を語る場面」や、「釘崎の笑顔の裏にある覚悟」。
モジュロの登場人物は、まだそれが描かれていない。 セリフもやや説明口調が多く、“感情”より“情報”を届けるために存在しているように映る。
だから、読者は物語を“体験”するというより、“読解”している状態になってしまう。
● 感情移入が難しい構造そのもの
原作は「呪術が特別である社会」から始まったが、モジュロは「呪術が一般化された世界」になっている。 呪術師はエリートではなく、市民の中に溶け込んでいる存在だ。
この構造自体は面白いが、感情の起点として“異質なもの”がなくなったことで、 物語全体が平坦に見えてしまっている可能性がある。
私は、最初の数話を読みながら、こう思った。 「このキャラたちは、まだ“しくじってない”」と。
原作キャラが心に残るのは、強さやカッコよさ以上に、 それぞれが“しくじり”や“痛み”を抱えていたからだと思う。
その「しくじり」が見える前に設定が走り出すと、 キャラクターは“説明装置”のように見えてしまう。
だから今のところ、“誰にも感情移入できない”。 読者はただ、ページをめくる手を止めずにいるだけ。
けれど、本当に“つまらない”かどうかは── このキャラたちが、いつ“傷”を見せるかにかかっている気がしている。
▼『劇場版 呪術廻戦』最新プロモ映像はこちら
特別編集×先行上映、2つの時間軸が交錯する映像体験をチェック
5. つまらない理由⑤──序盤のテンポと台詞回しに“らしさ”を感じられない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 序盤のテンポ | 設定や世界観の説明に時間を割きすぎ、物語が進まない印象 |
| 台詞回しの問題 | キャラ同士の会話が機械的で、心情や感情が伝わりにくい |
| “らしさ”の欠如 | 原作特有の“鋭さ”や“余白を持った言葉”が薄く感じられる |
| 読者の違和感 | 「説明ばかりで面白くない」「感情の間がない」といった印象に繋がる |
| 構成の問題 | 序盤で“日常パート”を挟む余裕がなく、読者の没入感が低下している |
「あのテンポじゃ、キャラの温度が伝わってこないよな」 ──そう感じたのは、モジュロの第1話を読み終えたときだった。
まず最初に気になったのが、展開の“早さ”ではなく、“平坦さ”だった。 事件も起こるし、新キャラも出るし、確かに物語は動いている。 けれど、そのどれもが“なぞる”ように淡々と進んでしまっている。
原作『呪術廻戦』では、冒頭から「これは普通の学園モノじゃないぞ」と思わせる 強烈なセリフや構図が詰め込まれていた。 たとえば虎杖が「人は死ぬ。死ぬんだよ、普通に」と言ったときの、あの“間”。
一方のモジュロは、世界観を説明する台詞やシーンが中心で、 キャラクターの“間”や“沈黙の重さ”が感じられない。
● なぜ“会話”が届かないのか
キャラ同士の会話がどうしても「設定説明」に聞こえてしまう。 「これはこういう呪具だ」「この組織はこう動いている」── 一文一文が、読者に情報を届けるために“話させている”感じがする。
本来なら会話は、キャラの価値観や感情を見せるもの。 でも今のモジュロは、セリフが“設定の読み上げ”に近い。
● “物語の体温”が足りない理由
さらに、テンポのバランスも気になる。 序盤から事件や謎が連発することで、読者は状況把握に精一杯になってしまう。
たとえば原作では、呪術師の世界に入る前に、 虎杖が祖父を看取る場面や、部活仲間との日常がしっかり描かれていた。
その“日常の温度”があったからこそ、 呪術という非日常が際立って見えた。
モジュロはその“助走”が足りない。 すぐに任務、敵、作戦、機密情報──。
読者が「この世界に入りたい」と思う前に、 ストーリーがどんどん進んでいってしまう。
● 芥見作品にある“痛みの余白”がない
芥見下々さんの原作には、感情を言葉にしきれない“もどかしさ”があった。 黙っている。笑ってごまかす。言いかけて、やめる。
でもそれが、“本音”よりも強い“説得力”を持っていた。
今のモジュロには、それが見えづらい。 全員が話し、全員が動き、でも誰も“揺れていない”。
この“感情の揺れ”がなければ、どんなにバトルがあっても、 どんなに世界観が凝っていても、「物語」として心に残らない。
読者が望んでいるのは、 ただ“呪術”が出てくる作品じゃない。
「呪術で揺れる“人間”の話」なんだ。
6. 「短期集中連載=打ち切り前提」説の根拠を整理する
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 連載形態 | 公式発表で「短期集中連載」「半年予定」と明言 |
| 打ち切りとの違い | 打ち切りではなく、最初から“完結型”とされている |
| 読者の誤解 | 「短期=人気がなければ終了」と受け取られがち |
| 構成上の特徴 | 序盤から物語を急ぐ構成になっている |
| 今後の焦点 | 予定通り完結するのか、読者の支持次第で延長もあるのか |
「半年で終わるって、つまり打ち切りってこと?」 そんな声が出始めたのは、第1話が配信されてすぐのことだった。
だが、冷静に見てみると、モジュロは“打ち切り”ではなく“短期集中型”としてスタートしている。 ファミ通.comや公式のアナウンスでも「半年ほどの予定」と明記されており、連載側の意思として“長期継続を前提にしていない”ことが明らかだ。
● “打ち切り”と“短期完結”の違い
まず確認しておきたいのは、「短期集中連載」と「打ち切り」は本質的に違うという点。 打ち切りは、読者人気や反響の不足によって予定されていた長期構成を途中で終了させるもの。 一方、短期集中連載は、最初から完結までの“設計図”が半年スパンで用意されている。
たとえば過去のジャンプ系作品でも、「読み切り→短期連載→本格連載」へと段階を踏む作品は多い。 モジュロもその“試金石”のようなポジションにある可能性は高い。
● なぜ“打ち切り説”が出回ったのか
それでもSNSやブログでは「打ち切り感ある」「すぐ終わりそう」といった声が出回っている。 その理由は、大きく2つある。
- ① 序盤の構成が“急ぎ足”に見える:キャラや設定が短期間に詰め込まれており、「終わりを前提にしてる感」がある
- ② 読者の“呪術廻戦=長期連載”という先入観:原作が長く続いているからこそ、短期で終わること自体に違和感を覚える
そのギャップが、「短期=失敗」という誤解を生みやすくしている。
● 終わり方に注目するべき作品
むしろこの記事で伝えたいのは、「短期だからこそ面白くなる可能性がある」ということ。
終わりが決まっているからこそ、伏線やテーマをぶらさずに完走できる。 そして、物語の“余白”や“意味の置き方”にも、戦略が生まれる。
いわばモジュロは、“回収される前提の伏線”で組まれたスピンオフ。 だから、逆に「終わりにどう着地するか」が一番の見どころになる。
● 続編はあるのか?
現段階では、「モジュロが続編につながる」という発表はない。 だが、もし読者人気が高まれば、今後のプロジェクトに発展する可能性もある。
“続けてほしい”ではなく、“終わり方に注目する”── そんな見方こそが、モジュロを正しく楽しむ鍵になるかもしれない。
7. スピンオフとして“呪術廻戦らしさ”を引き継げたのかを考える
| 観点 | 評価の要点 |
|---|---|
| 世界観の継承 | 呪術の概念は残しつつ、近未来SFとの融合で分かれる評価 |
| キャラクター性 | 原作のような“情と業の濃さ”はまだ希薄 |
| テーマ性 | “呪い”の概念は薄まり、“希望”や“科学技術”へとシフト |
| ストーリー構成 | 原作よりテンポが速く、説明より展開を重視している印象 |
| 読後感・余韻 | 原作の“切なさ”や“喪失”といった感情の余白はまだ少ない |
スピンオフにおいて最も問われるのは、“原作らしさ”をどれだけ引き継ぎつつ、どこで裏切れるか──というバランスだ。
『呪術廻戦モジュロ』は、「原作の呪術世界の68年後」という設定で、時代も空気もまったく違う場所から始まっている。
この“遠さ”は、新しさであり、同時にリスクでもある。
● 世界観の延長ではなく、リブートに近い印象
本作の大きな特徴は、“呪術”という言葉があっても、実際の描かれ方が全く異なるという点。 舞台は近未来、科学技術と宇宙的存在が関与し、原作にあった“呪い”や“因果”の世界観とは大きく距離がある。
あくまで“公式スピンオフ”でありながら、その描写はまるで別ジャンルのSFアクション。 呪術が“文化”ではなく“技術”として捉えられているような描写も多く、これは原作読者の期待とはズレやすいポイントだ。
● キャラ構築の濃度が“薄い”という印象
原作『呪術廻戦』の魅力は、なんといってもキャラクターの情と業。 虎杖の優しさと宿儺の狂気、五条の圧倒的存在感と孤独感、伏黒の迷い──
その“感情の奥行き”が物語を引き込んでいた。
それに対し、モジュロのキャラたちはまだ感情の「濃度」が薄く感じられる。 登場が急で、過去や葛藤に踏み込む前に物語が動いてしまうため、“何を背負っているのか”がわかりづらいのだ。
● テーマが“呪い”から“再生”や“希望”に変化
原作のテーマは“呪い”。人の憎しみや未練が物語の核にあり、その解消は常に“犠牲”を伴っていた。
だがモジュロでは、“呪い”はあくまで前時代の概念として描かれ、物語は「いかに希望を再構築するか」という方向に動いている。
このテーマの転換こそが、原作ファンにとっては最大の“違和感”でもある。
● テンポと構成が“週刊連載らしさ”と異なる
ジャンプ作品らしい“起承転結のスパン”が崩れている。 展開が早く、説明も少なく、むしろWEB連載的な“余白重視”の流れに寄っているように感じる。
この点においても、“週刊少年ジャンプ”というブランドで連載してきた原作とは異なる温度感がある。
● それでも“呪術廻戦らしさ”を探すなら
とはいえ、完全に別物かといえばそうではない。
たとえば、「“呪術”とは何か?」という問いを改めて立て直すモジュロの視点は、原作とは違う角度からの深掘りともいえる。
また、過去作のワードや因縁を再構成するようなセリフも随所にあり、“ファン向けの遊び”が隠れている可能性も。
● 結論:「引き継ぐ」というより「問い直している」
モジュロは、呪術廻戦のスピンオフでありながら、“引き継ぐ”というより“問い直している”印象が強い。
世界観も、テーマも、キャラの描き方も。 あえて遠くへ行ったことで、逆に“呪術とは何か”を再定義しようとしているようにも見える。
それがうまくいくかどうかは、物語の終着点で決まる。
「これは呪術廻戦じゃない」と切り捨てるのは、まだ早いのかもしれない。

【画像はイメージです】
注目ポイント一覧|“違和感”を超えて見るための4視点
| 視点 | チェックポイント |
|---|---|
| 作画 | 絵柄の好みと演出力の進化をどう感じるか |
| 設定 | 近未来や宇宙要素が“呪術”とどう絡むか |
| キャラクター | 感情移入できるまでの描写に注目 |
| 物語構造 | “問い直し”としてのスピンオフの意味 |
まとめ:それでも「モジュロ」を読む理由──違和感の中にある問いを拾うために
『呪術廻戦モジュロ』には、確かに原作ファンを戸惑わせる要素が多い。 絵柄の違い、SF的な設定、共感しづらいキャラ構築、説明不足な展開……。
「これは呪術廻戦じゃない」「つまらない」と感じる読者が出てくるのも、きっと自然なこと。
だけどそれは、原作にそれだけ強い“らしさ”があったからとも言える。
もし、あなたが「なぜあの世界観に惹かれたのか」「呪いとは何だったのか」をもう一度問い直してみたいなら──
モジュロの中にある、いびつで、遠くて、けれど確かに“呪術廻戦の血”を引く何かが、きっと見えてくると思う。
▼今後チェックすべきポイントまとめ
- 作画: 原作との違和感と“描写の進化”をどう見せるか
- 設定の落とし込み: SF・近未来要素がどう“呪術”と繋がるか
- キャラクターの成長: 感情移入の“起点”がどこで描かれるか
- 物語の収束点: “問い直し”がどう回収されるのか
違和感は、物語の余白。 その余白に、どんな感情を見つけるかは、読む人の数だけあるのかもしれない。
▼呪術廻戦をもっと深く掘り下げたい方へ
伏線・キャラの感情・言葉の余白まで、さまざまな角度から『呪術廻戦』を深読みした記事を掲載しています。
世界観にもう一歩踏み込みたいときに、きっと役立ちます。
- 『呪術廻戦モジュロ』は原作から68年後の近未来が舞台のスピンオフ作品
- 作画・世界観の変化により“原作らしさ”とのギャップを感じる読者も多い
- 「打ち切り前提」ではなく“短期集中連載”としての位置付けが公式見解
- SF的な設定(宇宙人・異世界)に対する賛否が作品評価に影響している
- 作画の好み・キャラの立ち位置など“感情移入しづらい”という声も一因
- 読者が作品に感じる“違和感”には構造的な理由が隠れている
- 読む前に「スピンオフとしての視点」で捉えることで楽しみ方が変わる
▼TVアニメ続編『死滅回游』制作決定映像
“新章突入”に心がざわつく。待望の続編、制作決定の報せ

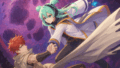
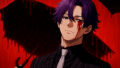
コメント