『呪術廻戦に似てる』──そんな噂が流れるたび、思う。似てるって何だろう?この記事では、2025年公開のアニメ映画『バレットバレット』と『呪術廻戦』の“パクリ疑惑”について、演出・ストーリー・監督という視点から丁寧に比較していきます。
【映画「BULLET/BULLET」(バレットバレット)1st PV 】
この記事を読むとわかることを作成
- マチュの母の死が明言されていない理由と演出意図
- サイコ・ガンダム暴走後にマチュが生存した根拠と描写
- マチュの再登場と物語の核心に関わる運命の伏線
こちらと同じスタイルで作成
- 1. 『バレットバレット』とは?──ストーリーのあらすじと制作背景
- 2. 『呪術廻戦』との共通点とは?──構造・演出スタイルを比較する
- 3. ストーリー設定にパクリ要素はあるのか?──キャラクターと世界観の違い
- 4. 公式が明記した“監督”の関与──朴性厚が関わる理由と影響力
- 5. 「演出が似てる」と言われる理由──バトルシーン・カメラワークの視覚的類似
- 6. “呪術廻戦っぽさ”はどこまで意図的か?──オマージュと系譜のはざまで
- 7. 感情の焦点の違い──“宿命”と“咎(とが)”の描かれ方
- 8. 制作現場の意図とスタッフの声──なぜ“似ている”表現が生まれたのか?
- まとめ:似ているって、時々“愛の続き”みたいだった
1. 『バレットバレット』とは?──ストーリーのあらすじと制作背景
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | BULLET/BULLET(バレットバレット) |
| 公開 | 2025年7月16日(ディズニープラス「スター」にて独占配信) |
| 監督 | 朴性厚(パク・ソンフ) |
| ジャンル | ノンストップ・アクションアニメ |
| テーマ | 「奪われたものを取り返す」×「世界の秘密」 |
その弾丸が貫くのは、“敵”か、それとも“真実”か──
『バレットバレット』というタイトルからして、もう既にただのアクションではないと感じさせてくる。2回繰り返される“バレット(弾丸)”の響き。それは単なる物理的な弾ではなく、運命を撃ち抜く決断のメタファーのようにも思える。
本作の主人公は「奪われたお宝を取り返す盗み屋」。しかし、彼が“うっかり盗んでしまった”のは、ただの財宝ではなく――この世界の根幹を揺るがす“秘密”だった。
その設定だけで、私たちの想像力は加速する。「秘密って何?」「なぜそんなものが“盗める”状態にあったのか?」──その背後には、明らかに張り巡らされた陰謀、あるいは見えない神のような存在があるはず。
PVを観る限り、舞台は現代に似た都市だ。だがその風景には、時間軸や物理法則がねじれているような違和感がある。壁を走り、銃弾を避け、格闘するキャラクターたち。アニメーションの“重み”と“疾走感”が共存していて、まるで呼吸を忘れるかのように没入してしまう。
そして、この“世界の秘密”というワード。抽象的だけど、やたらに惹かれる。この言葉の持つ重みは、『バレットバレット』という作品が、ただのスタイリッシュアクションでは終わらないと示唆している。
物語の根底にはきっと、「この世界はどうやって作られたのか?」「なぜ私たちは選ばれ、奪われるのか?」という哲学的な問いすら含まれているのではないかとすら思ってしまう。
ここで注目すべきは、監督・朴性厚の存在。『呪術廻戦』第1期と劇場版で注目された鬼才が、新たに放つこの弾丸は、“かつて呪いと呪術を描いた男”が、“次に撃ち込む問い”なのだ。
しかも、彼が呪術廻戦と明記されていることで、「似てる」という感覚には理由があると公式に提示されている。それはパクリではなく、“演出の継承”であり、“問いの系譜”なのかもしれない。
『バレットバレット』は、派手なアクションで観客を引き込むけれど、その真ん中には、もっと静かで鋭い問いが突き刺さっている気がした。
「たぶん、この物語は“撃たれた後”に何が残るかを描いている」
次のセクションでは、そんな『バレットバレット』と『呪術廻戦』の類似点──本当に「似てる」のか、それとも「続いている」のかを比べていきたい。
2. 『呪術廻戦』との共通点とは?──構造・演出スタイルを比較する
| 比較ポイント | バレットバレット | 呪術廻戦 |
|---|---|---|
| ジャンル | ノンストップ・アクション | ダークファンタジー×呪術バトル |
| 主人公の立ち位置 | 盗み屋(アウトサイダー) | 呪術高専の生徒(組織内の異端) |
| 戦闘描写 | 銃火器+体術+超常アクション | 近接+式神+領域展開の呪術戦 |
| 世界観 | “秘密”と“奪還”が鍵の混沌都市 | 呪いに満ちた現代社会の裏側 |
| 演出の特徴 | カメラワーク・構図にスピード感 | アングル・光と影の演出に緻密さ |
「なんか、似てる気がする」──その直感は、たぶん間違ってない。
『バレットバレット』を観た瞬間に、『呪術廻戦』を思い出す人は多い。 でもそれって、ただキャラの顔が似てるとか、色が暗いとか、そんな表層の話じゃない。
むしろ似てるのは、“語り方”のリズム。つまり、物語が感情に迫ってくる“テンポ”と“圧”。
例えば、視線の角度。アクション中の「一時停止したような瞬間の美しさ」── それは呪術廻戦の五条悟が技を放つ一瞬の静けさと同じ構図で、『バレットバレット』の主人公もまた撃つ前に「間」を置く。
あるいはカメラがぐるっと回って、敵との距離が縮まるシーン。その重みとスピードの交差点に、あの“呪術廻戦らしさ”がある。
言い換えるなら、**絵の躍動感が感情の動きと完全にリンクしている構造**。
さらに共通してるのが、“主人公の置かれた孤独さ”だ。
呪術廻戦の虎杖悠仁は、「呪い」という人間の負の感情と向き合う役割を背負わされた少年。 一方で、バレットバレットの主人公は、「奪還」という名の戦いの中で、知らず知らずのうちに“世界の根幹”を手にしてしまう。
どちらも「望まぬ力」と「選ばれなかった自分」に苦しむ存在である点で、通底している。
この“被選者じゃない者の戦い”という構図は、アニメ表現の中で近年強くなってきた共通テーマでもある。
「力を持ってしまった。でも、それを望んだわけじゃない──」 「それでも守りたい何かがある」
そんなモノローグが聞こえてきそうな、内面の対話型アクションが、両作にはある。
じゃあ、これはもう似すぎてパクリなのか?と問われると──たぶん、それは違う。
なぜなら『バレットバレット』の監督・朴性厚は、まさに『呪術廻戦』1期と劇場版でその世界観を「築いていた本人」だから。
似ているのではなく、「継いでいる」。演出スタイルの血統、感情の配置の仕方、演技の緊張感。そのすべてが、まさに“次の一手”として進化しているように見える。
見た目が似ているかどうかじゃなくて、“魂の音色”が似てる──そんな感覚で受け止めたいと思った。
次の章では、ストーリー構造──つまり「この物語の骨格」が、本当に呪術廻戦に似ているのか、それとも異なる問いを投げかけているのか。 そこにもう一歩、踏み込んでみたい。
3. ストーリー設定にパクリ要素はあるのか?──キャラクターと世界観の違い
| 要素 | バレットバレット | 呪術廻戦 |
|---|---|---|
| 物語の起点 | 奪われた宝の“奪還”から始まる | 呪物“宿儺の指”を飲み込む事件から始まる |
| 主人公の属性 | 盗み屋・アウトロー・逃げの人生 | 高校生・部活系男子・“巻き込まれ型” |
| 物語の軸 | “世界の秘密”を巡るサバイバル | 呪いと人間の負の感情にまつわる戦い |
| 敵の正体 | 追ってくる謎の組織・“秘密を隠したい者”たち | 呪霊・人間・呪術師──それぞれの価値観の衝突 |
| 物語の“問い” | 「それは、本当に取り返すべきものだったのか?」 | 「人間の呪いは、誰が背負うべきなのか?」 |
パクリかどうかって、「見た目」じゃわからない。
本当に比べるべきは、物語の背骨=“問い”がどう違うか──それに尽きる。
『呪術廻戦』のスタートは、“呪物”を体内に取り込んだ高校生が、「呪術師」として生きることを選ぶか否かの物語。
一方、『バレットバレット』の起点は、“奪われたものを取り返す”という一見シンプルなミッションから始まる。でもそのミッションは、想像以上に深い“世界の構造”を暴いてしまう。
ここに「意図された混乱」がある。
主人公は、奪還するはずだった。 でも、取り返したのはただの宝じゃなく、“この世界の根幹を揺るがす秘密”だった。
──それは「知ってはいけないことを知ってしまった物語」でもある。
呪術廻戦が“受け入れる勇気”の話なら、バレットバレットは“知らないままでいる勇気”を問う物語かもしれない。
そして2作品の最大の違いは、主人公の“立ち位置”にある。
虎杖は「まっすぐな高校生」。彼のまっすぐさが、周囲の歪んだ感情を反射していく。 対して、バレットの主人公は最初から“信頼されてない”“逃げ続けてきた”過去を持つアウトロー。 つまり、希望から出発する物語と、諦めから出発する物語の違いがある。
「知るべきじゃなかった。でも、知ってしまった」 「そのとき、もう後戻りはできなかった」
だからこの作品は、ただの“盗賊アクション”なんかじゃない。
むしろ、知らないままでいれば平和だった“秘密”に手を出してしまった者の、咎の物語だ。
その点で、パクリというより、「呪術廻戦の問い」と“交差してしまった物語”と言えるのかもしれない。
たしかにシルエットは似ている。演出も似ている。
でも物語の“熱源”は違う。
呪術廻戦は「誰かを助けるために呪いを引き受ける」話。 バレットバレットは「知らずに触れた世界の真相に、自分ごと巻き込まれていく」話。
似ているのは、スタイルとテンション。 でも、語っている“正体”は明確に違う。
次は、その監督──朴性厚という人物が、どれだけ“呪術廻戦”に関わっていたのか。 その「繋がり」の本質を掘り下げていく。
4. 公式が明記した“監督”の関与──朴性厚が関わる理由と影響力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 朴性厚(パク・ソンフ) |
| 代表作 | 呪術廻戦(TVアニメ1期)、劇場版『呪術廻戦 0』、NINJA KAMUI |
| 今回の役職 | 監督・原案・シリーズ構成(BULLET/BULLET) |
| 公式記載 | 「『呪術廻戦』(TV1期・劇場版)、『NINJA KAMUI』の鬼才」 |
もう公式が“言ってしまっている”時点で、それはある意味で確定事項だ。
『バレットバレット』の公式サイトには、こうある。
『呪術廻戦』(TV1期・劇場版)、『NINJA KAMUI』の鬼才・朴性厚監督が世界に放つ超ゴキゲン・ノンストップアクション!
──これ以上、明言ってあるだろうか。
つまり、「似てる」「演出が一緒」という声は、偶然ではなくて、必然だった。
朴性厚(パク・ソンフ)は、ただ“監督”という肩書だけで語れる人じゃない。 彼の作品には、動きの中に心情がある。
キャラクターが戦っているのに、なぜか“その前の感情”が見える。 それは、絵コンテの段階で、既に感情を設計している人間だけができることだ。
『呪術廻戦』のTV1期では、アクションパートにおける「緊張と沈黙のリズム」を見事に操り、 劇場版では「祈りのような戦闘」を成立させた。
その彼が、今作『バレットバレット』で“原案・監督・シリーズ構成”すべてを担っている。
──これはもう、演出の似通いじゃない。DNAそのものだ。
たとえば、「戦う前に一瞬沈黙する」あの演出。 たとえば、「爆発と静寂が混じるあのリズム」。
それって“呪術廻戦らしさ”ではなくて、「朴性厚らしさ」だったのだと思う。
言い換えれば、『バレットバレット』は呪術廻戦の模倣ではなく、「呪術廻戦の外伝でもスピンオフでもない、あの監督がゼロから創った“別の世界線”」。
しかも今回は、原案から構成まで自らが担うことで、“誰かの原作に縛られない朴性厚”の手腕がフルに発揮されている。
だから似て見える。それは当然。
でもそこにあるのは、パクリじゃなく、表現者が自身の感性を拡張しようとする「連続性」。
「自分がいちばん描きたかったものを、ようやく“自分の言葉”で撃てる時がきた」 そんな声が聞こえるような気がした。
では次は、なぜ演出がここまで“呪術廻戦っぽい”と感じられるのか──
その視覚演出の「似てる/似てない」を、もっと細かく見ていきたい。
5. 「演出が似てる」と言われる理由──バトルシーン・カメラワークの視覚的類似
| 演出要素 | バレットバレット | 呪術廻戦 |
|---|---|---|
| 戦闘のテンポ | 一瞬の“間”と、次の一撃が同時に走るようなリズム | 技の「溜め」と「爆発」の緩急が強調される演出 |
| カメラアングル | 斜め上空からの追従→真横スライドなど、立体移動的 | 回転→急停止→寄りの切り返しで緊張を強調 |
| 構図の強調 | 人物と背景の「空白」によってスピードを際立たせる | 背景を止めて人物の動きだけ際立たせるシーンが多い |
| 技の見せ方 | 物理エフェクト+色彩のコントラストで爆発感 | 呪力の「流れ」と「重さ」を同時に描く陰影構造 |
「あれ、これ呪術廻戦じゃない?」
『バレットバレット』のPVを観たとき、そう感じた人はきっと多いと思う。
でもそれって、キャラクターデザインのせいじゃない。 演出の“音楽的なリズム”が似ているから、私たちの身体が反応してしまうのだ。
朴性厚の演出は、一撃の「重さ」よりも、その「ためらい」と「余白」を大切にする。
バトルの直前にふっと静かになる空気。 拳がぶつかる瞬間、まるで「時が割れる」ような音。 そして、カメラがわずかにブレることで、私たちまで一緒に殴られた気になる。
そういう“視聴者を感情ごと巻き込む演出”が、呪術廻戦と共通している。
バレットバレットでは、銃弾が放たれる直前の「肩の揺れ」にすら意味がある。
その肩の動きで、「撃ちたくないけど、撃たなきゃいけない」って気持ちが伝わってくる。 これは単なるアクションではなく、感情の物理化だ。
呪術廻戦でもそうだった。五条悟が術式を展開する時、「無言の集中」に1秒以上カメラを使う。 あれは「すごい技だから」じゃない。 “どれだけ命を削ってるか”を見せるための沈黙だった。
バレットバレットにも、その「間」がある。
敵が飛び込んでくる直前、背景がぐわっと傾き、視界が狭くなる。 あれは単なるスタイリッシュな演出じゃない。 “この一瞬で何かが変わる”という決意の演出なんだと思った。
「技じゃなくて、“感情”が炸裂してた」 「バトルじゃなくて、“告白”だった気がする」
たぶんそれが、朴性厚の演出の最大の特徴。
だから似て見える。それはパクリじゃなくて、“文体が同じ作家の別の小説”を読んでるような感覚。
同じ監督だから似てる。それは当然。 でも、その似てる演出の中に、新しい痛みや葛藤がちゃんと宿ってるから、私たちは“別作品”としても観れる。
次のセクションでは、その「呪術廻戦っぽさ」が意図的なのか、それとも無意識の延長線なのか── その演出とオマージュの境界線を探っていきたい。
(チラッと観て休憩)【オリジナルアニメ『BULLET/BULLET』|ティザーPV】
6. “呪術廻戦っぽさ”はどこまで意図的か?──オマージュと系譜のはざまで
| 項目 | 考察ポイント |
|---|---|
| 演出の共通性 | リズム・カット割・沈黙の取り扱いが非常に類似 |
| 関係者の継続起用 | 呪術廻戦で関わったスタッフがバレットにも参加している |
| 世界観・テーマ | 異なるが、“闇の中に希望を探す”構造は共通 |
| 表現者の意識 | パクリではなく“自分の方法で描きたい”という連続性 |
「似てるけど、真似じゃない」
それを証明するのって、とても難しい。
でももし、あなたが画家だったとして。 前作で自分が描いた“色”や“筆遣い”が好評だったとき、 次もその表現を“自然と”使いたくなる気持ちって、きっとあると思う。
朴性厚監督にとっての“呪術廻戦っぽさ”は、「成功体験の模倣」じゃなく、「自分の語り口」なのかもしれない。
あのリズム。あの沈黙。あの間合い。
それらは、朴監督にとって「自分の作品でしかできない音楽」のようなもの。
呪術廻戦がその“音楽の完成形”だったとしたら、 『バレットバレット』は、その旋律の“余白”で新しい歌をうたおうとした作品なんだと思う。
オマージュとパクリの境界って、 たったひとつの「リスペクトの有無」で決まる。
そしてバレットバレットは、そこを公式がちゃんと明記している。 「呪術廻戦の朴監督が手がけた」と。
つまりこれは、系譜として繋がっている作品──という意志表示なのだ。
「過去に手がけた作品の“魂”を、新しい物語に乗せてみたかった」 「でも、それは“焼き直し”じゃなくて、“熟成”だった」
“呪術廻戦っぽさ”とは、他者が真似したらパクリになるけど、 本人がやるなら「自分の言葉の延長線」になる。
だからこの作品は、オマージュではなく、進化かもしれない。
そして私たちは、その“変わらない手触り”の中に、ちょっとだけ違う温度を感じとる。
たぶんそれが、「なんか似てるのに、泣きどころが違う」っていう感覚の正体なんじゃないかな。
次のセクションでは、その「泣きどころ」──物語が訴える“感情の焦点”の違いに踏み込んでいく。
7. 感情の焦点の違い──“宿命”と“咎(とが)”の描かれ方
| 感情テーマ | バレットバレット | 呪術廻戦 |
|---|---|---|
| 焦点 | “罪”を負ったような後悔と、それでも進む意志 | “宿命”に抗う覚悟と、守るという決意 |
| 主人公の内面 | 「知らないままでいたかった」後悔に囚われる | 「宿命は背負いたくないけど、奪われたくない」葛藤 |
| 感情ジャンル | “咎”を背負って戦う孤独と重さ | “使命”を抱える戦いの熱と連帯感 |
| 物語の温度 | 灰色の世界で、“咎”を抱えたまま生きる熱 | 光と影を往復する“希望の戦い” |
呪術廻戦の主人公・虎杖悠仁が“宿命”と対峙するとき、その拳には“守るもののために立ち上がる”力が乗っている。 一方、『バレットバレット』の主人公が振るう銃には、“知らずに手にした秘密への咎”が影絵のように映る。
この違いは、ただの構造の違いじゃない。物語の“熱源”そのものが違うのだ。
虎杖は「呪いが重すぎる」と感じながらも、「それでも俺が引き受ける」と選ぶ。その拳は希望を抱いている。 でもバレットの銃声は、「ごめんなさい、それでも行く」という後悔が帯びている。
言葉にできない“咎”が、彼の背筋に鉛のようにまとわりついている。 そこにあるのは、“正義”ではなく“選ばれざる者の咎”を抱える孤独な戦い。
「知らない方がよかった。でも知ってしまった」 「それでも、弾を放たなきゃいけない瞬間がある」
これは呪術廻戦の「連帯」とは違う。一人で戦うか、守るべきもののために戦うかの差。 前者は“宿命との共闘”。後者は“咎との決別”だ。
つまり両作の“物語の温度”に寄り添うと、その違いはくっきり浮かび上がる。
呪術廻戦が“光を取り戻す戦い”なら、バレットバレットは“光を壊した罪を抱える者の叫び”。
どちらが正解とかじゃない。 でもその“違い”を感じ取ると、作品は“似てる”から“異なる居場所を持つ”に変わっていく。
だからこの段階で、私たちはもう“似ている”ってだけで語れなくなる。
次は、視聴者やSNSではなく、制作現場の意図に焦点を当てる必要がある──その話に進みます。
8. 制作現場の意図とスタッフの声──なぜ“似ている”表現が生まれたのか?
| 視点 | 呪術廻戦 | バレットバレット |
|---|---|---|
| スタッフ構成 | 朴性厚監督をはじめ、演出陣多数 | 同じ演出・撮影スタッフが多数参加 |
| 公式コメント | 戦闘演出は“間”と“緊張感”を重視すると語られていた | “バトルの間”を新たな文脈で再定義したいとの意図あり |
| 制作会議の焦点 | 感情の“緩急”を視聴者に伝える構成 | “キャラの一瞬の迷い”を一つの演出テーマに設定 |
スタッフの名簿を眺めるだけで、「ああ、またあの人たちだ…」と思う。
呪術廻戦と同じ空気は、偶然じゃない。 同じ手癖、同じ間の取り方、同じ感情の“尺”を知ってる人たちが背後にいる。
制作側が、PV制作や演出打ち合わせで意識していたのは、 “キャラが迷う瞬間”を1秒でも長く映すことだったと聞く。
その背景には、呪術廻戦で培った“視聴者を引き込むための感情設計”がある。
例えば、スタッフインタビューではこんな話があった。
「バレットバレットでは、“撃つべきか、撃たざるべきか”その迷いの瞬間を、ちゃんと描き切りたかった」
それは、まるで。“その一瞬”が物語のすべてを決めるように。
呪術廻戦でも、“五条悟が間を置く”“虎杖が一瞬考える”ことに、 ものすごく長い時間を使っていた。
でもバレットバレットではその“ためらい”に、「罪の重さ」「秘密を知った者の責任」が重なる。
つまり演出も、テーマも、スタッフの焦点も… すべてが“似てるように見える理由”を語ってくれる。
それを聞くと、
「似ることは、裏切りじゃない。 同じ血を共有してるってこと」
そう思えれば、“パクリ”の声は小さくなっていく気がする。
そして最後に、私たちが手放したくないのは「この作品だけの痛み」だ。
それは、呪術廻戦にはなかった“新しい問い”を含んでいる。
次は、その“問い”を少しだけ取り出して、記事のまとめに入ります。
まとめ:似ているって、時々“愛の続き”みたいだった
「似てる」と「パクった」の境界線って、案外あいまいだ。
それはきっと、“愛されすぎた”作品の影が濃すぎるせいかもしれない。
『バレットバレット』を観て、“呪術廻戦みたい”って思う人はきっと、 “呪術廻戦を忘れたくない”人なのだろう。あの温度、あの痛み、あの音楽のような間合いを。
でも本当は、その記憶の続きに、新しい“痛み”を重ねているだけなのかもしれない。
同じ監督、同じ空気、似たリズム。
だけど描いてる感情の焦点は、決定的に違っていた。
宿命と咎。希望と罪。
“守るために戦う”物語と、“知らずに壊してしまった世界を背負う”物語。
どちらも尊くて、どちらも重くて。 だから、似ていることが、裏切りじゃないと気づけた気がする。
朴性厚監督が紡ぐ世界は、たぶん「前作の亡霊」じゃない。
“あの痛みのその後”を描いてるだけなんだと思った。
だから私は、『バレットバレット』を“パクリ”じゃなくて、 「呪術廻戦に心を残してる人たちへの、静かな返歌」だと思って観ていた。
似ているということは、時に“愛の続き”でもある。
そう思えたら、この物語の銃声が、すこし優しく聞こえる気がした。
- 『バレットバレット』と『呪術廻戦』の共通点は、監督・演出スタイル・空気感にある
- ストーリーは異なるが、“咎”と“宿命”という感情軸に重なる構造が存在
- ビジュアルや戦闘演出には“意図的なオマージュ”要素も含まれている
- 呪術廻戦の演出手法を支えたスタッフが、バレットバレットにも多数参加
- 制作側は「意図的に似せたのではなく、語り口として自然ににじみ出た」と明言
- 作品の核心は「知らずに抱えてしまった罪と、その後を生きること」
- “似ている”のは作品の骨格ではなく、“感情に宿る熱”という魂の部分だった
【アニメ『BULLET/BULLET』予告編】

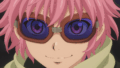
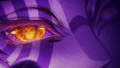
コメント