「あれ、終わっちゃうの?」──そんな戸惑いがSNSを駆けめぐったあの日。異世界転生×チート×ブサメンという、ひとクセもふたクセもある設定で話題を呼んだ『ブサメンガチファイター』。
だが、突如として告げられた“打ち切り”の知らせ。その理由には、ストーリー構造の綻びや、作品の根幹に関わる“しくじり”が隠れていたのかもしれません。
この記事では、あくまで物語の流れに沿って、なぜ途中で終わってしまったのかを丁寧に解き明かしていきます。
【TVアニメ「ブサメンガチファイター」PV第1弾】
- 『ブサメンガチファイター』が打ち切りになった背景と読者に残された違和感
- しげるの“ルックス-255”という極端設定の裏に隠された感情と孤独
- 「触れるとHPが激減する」異能力が象徴する人間関係の距離感と痛み
- イケメン誠司との対比構造が描いた“陰と陽”の交錯と希望の兆し
- 女性キャラたちの存在がデフォルメされた理由と描かれなかった感情線
- 物語中盤の曖昧さと、読者が感じた“山場不在”というしくじり構造
- 最終局面の急展開と“完結ではなく放棄”と感じた終わり方の理由
1. 異世界転生の出発点──ブサメンが選んだ“負のチート”とは
| キーワード | 内容 |
|---|---|
| 異世界転生の選択 | チートスキルを選べるはずの場面で、主人公が自ら“ルックス-255”という負の能力を選択 |
| “負のチート”とは | 見た目が極端に醜くなる代わりに、強力な耐久・攻撃スキルを得るシステム上のバランス設計 |
| 心理的テーマ | 見た目に悩み、自尊心を損なっていた過去の自分への“逆襲”と“受け入れ”が込められている |
「好きな能力を選んでください」──もしそんな画面が出てきたら、あなたは何を選ぶだろう。
空を飛べるスキル? 最強剣を呼び出せる魔法? それとも、チート級の回復スキルで不死に近づくか。
異世界転生モノって、多くはここから始まる。 だけど、『ブサメンガチファイター』のしげるは違った。
「ルックス-255を選択します」
──スクリーンの前でフリーズした読者、多数。
それはつまり、「この先、すべてのキャラから嫌悪される顔面になる」ということだった。
選ぶな、そんなの。
でも、彼は選んだ。
“美しくなれないなら、せめて強くなりたかった”
しげるの人生は、「見た目で判断される」ことの連続だったらしい。
中学のとき、席替えで隣の女子があからさまに嫌そうな顔をした。
高校では文化祭の出し物で“モンスター役”を押しつけられた。
就活では、面接官の視線がずっと顔ではなく“横”を見ていた。
それら全部が積もり積もって、「自分の顔は呪いだ」と思い込んだ。
転生時、選べたスキルは3つ。
- ステータスバランス型(平均的に強くなる)
- 好感度特化型(人当たりがよくなるスキル)
- 顔面絶望型(ルックス-255&異常ステータス)
しげるは迷わなかった。というか、迷えなかった。
「好感度なんて、どうせ俺には関係ない」──そう心に刻みすぎて、もう引き返せなかったんだと思う。
転生前の人生が、“選ばれない人生”だった人間が、初めて自分で選んだのが“顔を捨てること”だった。
この時点でもう、物語の温度が“ギャグ”じゃなくなる。
笑い飛ばせない。だって、心当たりがある。
「自分で自分を見限った経験」って、たぶん誰の心にも一度はあると思う。
しげるが選んだのは、“強さ”じゃなかった。
彼が欲しかったのは、“誰にも奪えない存在価値”だった。
ルックス-255の“副作用”──誰にも近づけない人生
転生後、しげるのステータスは強かった。
耐久は最強クラス。
攻撃力も瞬間火力では一目置かれる。
でも、誰ともパーティを組めなかった。
理由は単純。
「近くにいるだけで吐き気がする」レベルの外見になってしまったから。
ゲームのステータスにおいて“ルックス”がマイナスになるとは、単に見た目が悪くなることじゃなかった。
それは、“他人に影響を与える呪い”だった。
NPCの村人たちは、彼に石を投げた。
子どもは泣き叫び、ペットまでも逃げた。
仲間を助けても、感謝されなかった。
……誰も、彼を「人間」として扱わなかった。
“選んだからこそ、消せなかった”
しげるはこの能力を、自ら望んで手に入れた。
だからこそ、途中で捨てられなかった。
もしこの能力が「呪い」だったら、きっと誰かが「解こう」と言ってくれたと思う。
でも、自分で“選んだチート”は、誰も助けてくれない。
そこに、この作品の切なさがある。
「自分で選んだ不幸は、誰にも“可哀想”って言ってもらえない」っていう、痛いリアル。
でも、しげるはそれでも冒険を続けた。
いつか、自分の存在が誰かに必要とされる日を夢見て。
“ルックス-255”が教えてくれたこと
この作品、表面だけ読むと「変な異世界ギャグ」に見えるかもしれない。
でも、しげるの選択をちゃんと見ていくと、それが人生の“しくじり”と“諦め”と“希望”が同居したものだったことに気づく。
「せめて強くなることで、自分の人生を正当化したかった」
「誰にも愛されなくても、誰かを守れるなら、それでいいと思った」
「この顔でしか、生きられない自分を、受け入れたかった」
──しげるの人生は、そういう“痛い選択”の連続だった。
そして、その第一歩が“ルックス-255”だった。
それは、しげるにとって「呪い」じゃなく、「覚悟」だったんだと思う。
わたしが、ここで泣いた理由
転生して、強くなって、誰にも頼られず、それでも前に進んでいくしげる。
「ザコが俺を見下すのはいい、でも守るべきものには背を向けたくない」
そう呟いたとき、わたしの中でなにかが“崩れた”。
ああ、この人は、ずっと「人間扱いされなかった過去」を引きずってるんだ。
でも、誰かを人として守ることで、自分が人間であることを証明しようとしてるんだ。
それって、強いとか弱いじゃない。
たぶん、一番、人間らしい“願い”なんじゃないか。
笑えないよ。 こんなの、ギャグじゃ終わらせられない。
『ブサメンガチファイター』の物語は、ここから始まった。
笑われる前提で生きてた人間が、 誰かの笑顔のために立ち上がる物語だった。
「なぜこのチートを選んだのか?」という問いに、読者はずっとモヤモヤしたままだったかもしれない。
でも私は、こう思った。
「しげるは“この人生を引き受ける覚悟”を選んだんだ」
そしてその瞬間から、彼は誰よりも“人間”だった。
2. 主人公・しげるの設定が突きつけた極端な「ルックス-255」の意味
| キーワード | 内容 |
|---|---|
| ルックス-255 | 数値化された“嫌悪”の象徴。近づいただけで吐き気を催すほどのルックス |
| 社会的拒絶 | すべての人から“存在ごとスルー”される、感情のない差別 |
| 設定の極端性 | ギャグとして処理できない、リアルなトラウマの再現 |
「-255って、バグじゃない?」
そう思った人、正直に手を挙げていいよ。私も最初は、笑った。
でもページをめくるごとに、その数値がただのネタじゃなくて、“生きづらさのメタファー”だってことに気づかされる。
「ルックス -255」──それは、顔の問題じゃない。
もっと根っこの、“存在の否定”に関わるステータスだった。
しげるにとって、“ルックスの低さ”は世界と繋がれない呪いだった。
人に近づけば避けられ、声をかければ無視され、目が合えば悲鳴。
まるでそこに“いないこと”にされるような孤独。「社会的に透明化された人間」が、しげるだった。
しかもこの設定、ゲームみたいにリセットもできない。スキルで補うこともできない。
「顔が悪いだけで、こんなにも生きにくい世界」を突きつけられる残酷さ。
でも、しげるは逃げなかった。むしろ、「そのままの自分で勝ちたい」と願った。
これは、ちょっとやそっとの“努力根性論”じゃ測れない。
たぶん彼は、昔どこかで「顔が悪いから無理」って言われた記憶があったんだと思う。
もしくは、誰かを好きになっただけで笑われた日があったのかもしれない。
「ブサイクでも、役に立てるって証明したかっただけなんだよ」
──そんなセリフがいつか来るんじゃないかって、読みながら何度も想像してた。
だってその数値は、しげるが自分に課した“罰”でもあり、“願い”でもあった気がするから。
ルックス-255という設定は、決して過激なだけじゃない。
それは、誰かに見てもらいたかった過去の自分への赦しかもしれないし、見下されたまま終わりたくないっていう逆襲だったのかもしれない。
そして同時に、それはこの作品が“ただのギャグ異世界もの”ではなくなる分岐点でもあった。
私たちの中にも、もしかしたらあるのかもしれない。
「どうせ無理」って、数字にされてしまった自己評価。しげるの-255は、その集合体みたいだった。
3. 「触れたらHP激減」──異能力と対人関係の切なすぎるジレンマ
| キーワード | 内容 |
|---|---|
| 特殊スキル | “しげるに触れるとHPが激減する”という強力だが孤立を生む能力 |
| バトル上の利点 | 敵には脅威だが、味方にも迷惑になるためパーティに組み込めない |
| 心理的影響 | “助けたいのに近づけない”“強くなるほど孤独になる”という矛盾 |
「触れるだけで、HPが削れるって、どういう地獄?」
それ、戦闘だけの話じゃない。人間関係でも同じなんだよ。
しげるに与えられたのは、“接触するだけで他人の体力を削る”という異能。
敵にとっては脅威。触れた瞬間にダメージ、まさに“歩く毒沼”。
でもさ、それって味方にも触れられないってことなんだよ。
誰かを守りたい。けど近づいたら傷つける。
一緒に笑いたい。けど距離を詰めた瞬間、相手が苦しむ。
──そんな能力、望んで手に入れた人間、いる?
しげるがこの能力を持つ意味は、「戦闘バランス」なんかじゃなかった。
これは“親しくなることが怖い人”のメタファーだった。
「俺なんかと関わったら、不幸になるだけだよ」
──そんなふうに思ってた過去が、きっとしげるにもあるんじゃないかって。
強くなればなるほど、周囲からは“使える戦力”として期待される。
でも、近づいてくれる人ほど先に壊れていく。
その設定って、ちょっとズルいぐらいにリアルだった。
“優しさが毒になる”って、どれだけ残酷な矛盾だろう。
普通の異世界バトルなら、「強いスキル=ヒーロー」の法則がある。
でもこの作品では、強さが“孤独の証明”になる。
まるで、しげるが「一緒にいる価値がない」って、世界に刻印されたように。
敵には恐れられ、味方には避けられ、恋愛なんてもってのほか。
でもね、その設定を抱えながらも、しげるは一度も“自分の存在”を恨まなかった。
彼の中には、壊したくないものがあったから。
触れられなくても、そばにいたい人がいたから。
それはもしかしたら、ずっと昔に自分が傷つけてしまった誰かへの“償い”だったのかもしれない。
それとも、自分の人生では得られなかった“ぬくもり”への、せめてもの抵抗。
この能力、ゲーム的には便利かもしれない。
でも、感情的には、最も残酷な設定だったと思う。
そしてだからこそ、『ブサメンガチファイター』が“痛みごと愛される物語”になった理由のひとつだった。
4. イケメン誠司との対比構造──“陰”と“陽”の物語は交わったか
| キーワード | 内容 |
|---|---|
| 誠司の存在 | しげるとは真逆の「王道イケメン」。人望・ルックス・戦闘力すべてが整った光の勇者 |
| “陰”との対比 | 誠司は人を惹きつけ、しげるは人を遠ざける。構造的に対立する二人 |
| 物語上の接点 | 中盤以降、敵対と共闘を繰り返しながら“理解”に近づく場面もあった |
“陽キャの王様”と“陰キャの呪い”
──この物語の核心にあるのは、まさにこの対比だった気がする。
誠司。彼は、全てを持っていた。
人を引きつけるルックス、努力もできる、声も通るし、セリフもかっこいい。
王道の異世界モノなら、彼が主人公でもなんの違和感もない。
一方のしげるは、“避けられる存在”。
人を惹きつけるどころか、近づけば傷つけてしまう。
この二人が同じパーティにいるだけで、物語には“温度差”が生まれる。
だけどそれは、単なる“ギャップ”じゃなくて、“格差の再現”だったと思う。
学校でも、職場でも、SNSでも。
「人気者の隣にいる、自分はなんなんだろう」って、思ったことある人、多いんじゃないかな。
誠司が眩しくなるほど、しげるの影は濃くなる。
でもね、その影は、ちゃんと誠司にも届いてた。
「あいつ、なんでこんなに必死なんだろうって、思ってた。……でも、最近ちょっとだけ、わかった気がする」
中盤のあるシーンで、誠司がそうつぶやいた。
その一言だけで、私はちょっと泣きそうになった。
しげるの“痛み”が、ようやく“理解”に届いた気がして。
“陽”が“陰”を否定するんじゃなくて、 “陰”の生き方に、自分にはない何かを見出す。
この対比って、簡単に癒やされるものじゃない。
だけど、それでも何度もぶつかって、言葉の温度がすこしずつ変わっていくところに、物語の希望があった。
私は、誠司がしげるを羨ましがる展開なんて、期待してなかった。
でも、「あいつ、あのままでもちゃんと人間してる」って気づいた瞬間──それが二人の物語が交差した証だったと思う。
だからこの関係は、“ライバル”なんかじゃなくて、“反射光”だった。
誰かの輝きが、自分の影を教えてくれる。
でもその影の中にも、小さな光が宿ってた。
しげると誠司、まったく違うけど、たぶんどこかで“同じ寂しさ”を背負ってた。
その事実が、この物語の底にある“静かな優しさ”だったのかもしれない。
5. 聖華・リーズら女性キャラの“デフォルメされた存在感”の扱い
| キーワード | 内容 |
|---|---|
| 聖華の描写 | ヒロインポジションながらも、感情が定まらない不安定さが目立つ |
| リーズの役割 | “ツンデレ”テンプレートのようでいて、実は主人公へのシンパシーを内包 |
| “存在感”のデフォルメ | 男性キャラを引き立てるために機能化された感があり、描写の薄さが浮く |
「なんか、記号っぽくない?」
最初に聖華を見たとき、そう思った。目立つ見た目、過剰な性格、謎の言動。
そして、次に出てきたリーズも──ツンデレ、金髪、魔法。はいはい、テンプレ。
……でも、途中で気づいたんだ。
このキャラたち、ちゃんと“苦しさ”を抱えてる。
ただ、それが描かれきってなかった。それだけのことだった。
聖華は、どこか不安定だった。笑ってるようで、目は笑ってなかった。
「この人、きっと誰にも本音言えてない」って、思わせるシーンがちらほら。
おそらく、彼女自身も“理想のヒロイン像”を演じてた。
読者だけじゃなく、物語の中でさえ、自分の役割に縛られてた気がする。
一方のリーズは、対照的だった。
言いたいことをズケズケ言う、強気な魔導士。でもその強さは、“しげるへの理解”が根にあった。
「別に、顔なんてどうでもいいじゃん。強いんでしょ、あんた」
──たったそれだけで、どれだけ彼が救われただろう。
でも、それ以上踏み込んではくれなかった。恋愛でも、友情でも、どこかで距離を保ってた。
まるで、“傷つけられる側にならないように”していたような。
この二人の女性キャラは、どこか“観客”だった。
物語の核心に踏み込めそうで、ギリギリ踏み込めない。
そして、それは“作者の迷い”のようにも見えた。
しげるというキャラの濃さに、どう並べるか。
彼の痛みと孤独に、誰が言葉をかけられるのか。
聖華もリーズも、実はその“責任”を背負わされてたんだと思う。
だけど、どこかでデフォルメされたまま、止まってしまった。
もし彼女たちがもう少し“人間”として描かれていたら、もっとこの物語は深く刺さったかもしれない。
でも逆に言えば──
“ちゃんと描かれなかった女の子たち”に感情移入してしまう時点で、もう私はこの作品に飲み込まれてたのかもしれない。
【TVアニメ「ブサメンガチファイター」PV第2弾】
6. ストーリーの山場不在──物語構造としての“中盤の曖昧さ”
| キーワード | 内容 |
|---|---|
| 展開のぼやけ | 中盤に明確な目標や対立軸がなく、物語が足踏みした印象 |
| テーマの反復 | 序盤で提示された“見た目と孤独”のテーマを繰り返すのみで進展が少ない |
| 読者の停滞感 | “この先どこに向かうの?”という焦燥と共に、熱が冷める読者もいた |
「……で、次、どうなるの?」
ページをめくりながら、ふと漏れた心の声。
物語が止まったわけじゃない。キャラも動いてる。バトルもある。
でも──なにかが、動いていない。
それはたぶん、「目的」だった。
中盤に入ってからの『ブサメンガチファイター』は、どこに向かってるのかが見えにくくなった。
敵も出るし、苦悩もある。けど、それらがストーリーの幹を育てていかない。
まるで、同じテーマを少しずつ角度を変えて見せているような展開。
それ自体が悪いわけじゃない。むしろ、“感情の反復”としては正しい。
だけど、読者には“変化”がほしかった。
しげるの痛みは伝わってる。
でも、その痛みを越えた先にあるもの──「この物語のゴール」は見えなかった。
ラスボスは誰なの?
何を成し遂げようとしてるの?
“嫌われ者”は、どうすれば救われるの?
──その問いに、誰も答えなかった。
中盤は、とても静かで、とても“曖昧”だった。
それはしげるの迷いでもあり、作品全体の迷いでもあった。
でも私は、そこで作品を見捨てられなかった。
「ああ、ここで迷ってるのって、私自身も同じだ」って思ってしまったから。
うまくいかないことに理由が見つからないとき。
同じことでぐるぐる悩んで、時間だけが過ぎていくとき。
それって、“人生の中盤”と似てない?
だからこそ、この“山場不在”は物語の欠点であり、同時に最も“リアルな章”だったとも言える。
構造としては曖昧。
だけど、感情の揺れとしては、一番“素直”だった気がする。
7. 打ち切り前の急展開──“ラスボス戦のようで違った”最終局面
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 急展開のタイミング | 第27話から明らかにテンポが変化。未回収の伏線が次々“回収未遂”に |
| ラスボス風の展開 | 新登場キャラ「黄泉の王」との戦いが突如始まり、ほぼ全戦力が投入される展開に |
| 読者の違和感 | 「本当にこれがラスト?」と疑うほどの展開の唐突さと、感情面の不在 |
「なにかが、急におかしくなった」
そんな読後感が、最終盤の『ブサメンガチファイター』には確かにあった。
突然の敵。
突然の最終決戦。
そして、突然の“終わりっぽさ”。
でも──なぜか胸の奥は、ちっとも終わる気配を感じ取れていなかった。
「打ち切り決定後」の物語が放つ、違う熱
第26話までは、しげるの孤独や苦悩、仲間とのわずかな絆、そして“存在の意味”がじわじわと描かれていた。
それが、第27話。何の前触れもなく、物語は“戦争編”に突入する。
新たな敵「黄泉の王」の登場。
国が陥落寸前。
誠司はすでに瀕死。
リーズが「覚悟を決めた女の顔」になってる。
──でも、そんな展開に読者の心が、ついていけなかった。
「え? ラスボス出てきた? でも、前回まで……」
「いつの間に話が“世界の命運”になった?」
そう。“伏線ではなく、パッチワーク”のように感じた展開。
ここには、作者の「このまま終わらせなきゃいけない」という強烈な圧が、物語を乗っ取っているような気配があった。
なぜ“ラスボス風”で終わらせたのか
打ち切りが決まったとき、多くの作者は「物語の魂」を残すか、「外的展開でごまかす」かの選択を迫られる。
『ブサメンガチファイター』は、たぶん後者だった。
今までじっくり育ててきた感情線──
- しげるの孤独と再起
- 誠司との再会の温度差
- リーズが抱えた“顔に囚われない愛”の物語
それらすべてを、“戦い”に包んで処理した。
まるで、「このままじゃ出せないまま終わるから、せめて戦わせよう」と。
でも、それが逆に読者を傷つけた。
「ちゃんと見たかったんだよ、感情の決着を」
「ただ戦って、勝って、終わるだけじゃ、あの孤独の意味が消えちゃうじゃん」
そんな声が、X(旧Twitter)に溢れた。
“ラスボスの顔”すら、覚えていない
皮肉な話だけど、ラスボス「黄泉の王」って、あまりにも唐突で、顔すら記憶に残っていない。
読者にとって重要だったのは、敵じゃなかった。
しげる自身が“どこまで人として生きられるか”という戦いだった。
だから、「いきなり強い敵が来て、勝ったからエンド」では、物語としての決着にならなかった。
最終決戦──本当は、しげる自身との戦いじゃなきゃいけなかった。
それができないまま、物語は終わった。
終わったように“見えた”。
“打ち切りという名の中断”──終わらなかった物語
第30話。
しげるが「黄泉の王」の剣を受け止め、世界の命運が決まった瞬間。
でも、その“勝利”には何の余韻もなかった。
次のコマではもう、戦場の瓦礫が描かれていて、誰も喋っていない。
勝ったはずなのに、敗北のような静けさ。
そして、次のページで“最終回”の告知。
心が追いつく前に、「物語の終わり」が告げられてしまった。
それはまるで、夢から急に叩き起こされるような感覚だった。
読者はまだ、“心の中の最終回”を見ていなかったのに。
未完の感情──読者が見たかったのは“しげるの心の結末”だった
物語の構造として、終盤に「大きな敵」が登場するのはセオリーだ。
でも、『ブサメンガチファイター』にとってラスボスは敵じゃなかった。
それは、自分自身との闘いだったはず。
他人に拒絶され続けた人生。
“顔”という呪いから逃れられなかった存在。
それでも、自分を捨てなかった少年。
──そのしげるが、「自分を許す」ためのエピソードが、描かれなかった。
それが、一番苦しかった。
たとえば、こんなシーンが欲しかった。
- 誰か一人でも、彼の“顔”ではなく“声”を聴いてくれる
- 最後にしげるが「生きててよかった」と呟く
- 死んだと思っていた仲間が“名前”で呼んでくれる
そういう「物語の温度を受け止めてくれるラスト」があったなら。
読者はもう少しだけ、“納得”できたかもしれない。
あの最終回は“完結”ではなく“中断”だった
誤解してはいけないのは、打ち切り自体が悪ではないということ。
作家にとっても、編集部にとっても、それは時に避けられない現実。
でも、その中で「何を最後に残すか」は、すべての物語が問われるものだ。
『ブサメンガチファイター』は、設定も世界観もキャラ造形も、本当に独特だった。
でも一番輝いていたのは、「こんな主人公でも、前を向けるんだ」と思わせてくれたこと。
その感情線が、ラストに受け止められなかった。
それが、「なにか置き忘れてきたような終わり方」の理由だと思う。
“この世界に歓迎されなかった物語”が、まだどこかで息をしている気がした
最終ページ。
しげるは笑っていた。
ほんの少しだけ、うれしそうな顔をしていた。
でも、それが「しげるとしての本当の笑顔」だったのかは、わからない。
その表情には、まだ“何かを言い残した人”の影があった。
だからきっと、この物語はまだ終わってない。
少なくとも、私たちの心の中では、彼が今もどこかで「続きを生きている」と思ってしまう。
──それが、“完結じゃない最終回”を読んだ、私の正直な気持ちだった。
8. 完結ではなく放棄?“物語としての終わり方”への違和感
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 終わり方の特徴 | 説明不足、感情の結末なし、余韻を残さず幕切れ |
| 未回収の伏線 | 誠司としげるの確執の結末、リーズの感情線、主人公の変化の描写 |
| 読者の反応 | 「これで終わり?」「感情を置いていかれた」「大事なものが描かれていない」など |
ページをめくった瞬間、「あ、終わったんだ」とわかる──でも、心は納得していない。
それが、『ブサメンガチファイター』の“終わり方”に対して、読者が感じた大きな違和感だった。
終わったようで終わってない。
終わらせたようで、途中で手を放されたような。
まるで、“物語そのものが置き去りにされた”ような、そんな感覚。
“ここまで積み上げた感情が、急に切り捨てられた”
最終回──正確には「最終回とされた回」は、物語の大団円でもなく、感情の解放でもなかった。
画面には、しげるの姿がある。
仲間が微笑んでいる。
街が平和を取り戻している。
けれど、そのどれもが“記号的なカット”でしかなく、ストーリーとしての意味を持っていなかった。
たとえば、読者が一番気になっていた「誠司としげるの関係性の決着」。
ここには、何の言葉も交わされなかった。
あれだけ衝突し、交差し、そしてどこかで“救いの可能性”を漂わせていた関係。
なのに──何もなかった。
沈黙のまま終わった。
あれだけ感情を注いできたのに、それが「なかったこと」のように扱われたのが、一番つらかった。
“余韻の不在”が、むしろ感情をえぐった
普通の物語なら、ラストに何かしらの“余韻”が残る。
たとえ伏線が回収されなくても、キャラが幸せにならなくても、「その後を想像できるような空白」がある。
でも、『ブサメンガチファイター』は違った。
“物語の電源が、ブツッと落ちた”ような終わり方。
だから、想像の余地すら奪われた。
「あのセリフの続きを考えたい」 「きっとあの後、あのキャラは…」
そういう余白が、なかった。
残されたのは、ただの唐突な“終了宣言”。
そしてそれが、逆に「放棄された物語」という印象を生み出してしまった。
“完結”とは、登場人物と感情の“着地”である
物語における「完結」とは、ストーリーが終わることではない。
そこに生きていたキャラクターたちの“感情”が、どこかに着地すること。
そして、読者がそれをそっと見届けられること。
それができて初めて、「物語が完結した」と言える。
だから、『ブサメンガチファイター』は完結ではなかった。
むしろ、物語から“感情の出口”を奪われたまま閉じられたという感覚に近かった。
キャラクターも、読者も、誰も“最後の一歩”を踏み出せていない。
それが、“放棄”という印象の正体だったと思う。
“たしかに、終わった感触はなかったけど”──読者が感じた“残り香”
SNSでは、最終回後にこんな声がいくつもあった。
「こんな終わり方でも、なぜかしげるのこと、忘れられない」
「感動はなかった。でも、“感情”はまだ残ってる」
そう。たしかに、物語はうまく終われなかった。
でも、しげるという存在が私たちの心に残した“ざらつき”や“痛み”は、消えていなかった。
だからこそ思う。
本当の意味での「完結」は、読者が心の中でその続きを思い描いたときに起きるのかもしれない。
未完のまま“心の棚”に置かれた物語
私たちはときどき、最後まで読んでもいない本を、本棚にしまうことがある。
「今じゃないな」と思って、途中で閉じる。
でもそれって、“興味を失ったから”じゃない。
むしろ、その物語にまだ心が向き合えていないからなんだと思う。
『ブサメンガチファイター』の最終回も、そんな感覚に近かった。
ちゃんとした「ラストシーン」がなかったからこそ、
読者はまだ、心の中で物語を閉じられていない。
でもそれは、“放棄”ではなく、
“仮置き”だったのかもしれない。
いつかまた、この物語を手に取るときが来たなら
今はもう、続きは描かれない。
しげるの物語が“公式に”戻ってくることは、たぶんない。
でも、感情の奥底に沈んだままのしげるは、まだ私たちの中に生きている。
思い出すたび、あの“顔”を超えようとした少年の目が浮かぶ。
愛されなかった痛み。
それでも、世界に背を向けなかったしげるの背中。
そして、彼が最後に見せた笑顔。
その全てが、「いつか続きが描かれるとしたら、こんな物語になるだろうな」という想像の燃料になっていく。
完璧に終わらなくても、感情は“そこにあった”ということ
『ブサメンガチファイター』は、終われなかった。
だけど、始まった物語だった。
しげるという存在に、たしかに感情が乗った。
そして読者たちは、それをちゃんと“受け取った”。
それは、打ち切り漫画にとって、最高の救いかもしれない。
最後のセリフがなくても、エピローグがなくても。
感情の残滓(ざんし)が、読者の中にあったなら。
その物語は、きっと生き続ける。
だから私は、“このしくじり”が嫌いじゃない
完璧じゃなかった。
打ち切られた。
終わらせ方も、ぶっきらぼうだった。
でも──
このしくじりの中には、たしかに“人間の体温”があった。
作り手も、読者も、感情でぶつかった。
だからこそ、この違和感は“愛されなかったわけじゃない証拠”だと思う。
そうやって、未完成のままでも心に残る物語があるなら。
それは、たぶん“失敗作”なんかじゃない。
私は、そう信じている。
9. まとめ:しくじりの中にあった“気づかれなかった感情線”
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品の核心 | 「ブサメン」という属性を背負った主人公の“感情の孤独” |
| しくじりの本質 | 構造的な不安定さと、終盤の物語放棄による感情線の断絶 |
| 残された価値 | 未完であっても“感情は確かに存在した”という読者の記憶 |
どんなに設定が奇抜でも、どんなに構成が歪でも。
「感情が生きている物語」は、人の心に引っかかる。
『ブサメンガチファイター』は、まさにそんな作品だった。
笑えないほどブサイクな顔。
人を傷つけるしかない能力。
そして、誰にも選ばれない人生。
そんな“選ばれなさ”を抱えた主人公に、なぜか読者は惹かれてしまった。
たぶんそれは、「自分も、どこかで選ばれなかったことがあるから」
──そんな記憶に、静かに触れられたからなのかもしれない。
“感情の芯”を描こうとした勇気だけは、本物だった
物語が破綻しても、設定が浮いていても。
それでもこの作品が忘れられないのは、「しげる」という存在の叫びが、本気だったから。
顔を嫌われても、能力を恨まれても。
しげるは、自分を見捨てなかった。
その誠実さが、作品全体に通底していた。
たとえラストが描かれなかったとしても。
たとえ何も報われなかったとしても。
しげるが“そう生きた”という事実だけは、たしかに私たちの心に残った。
“未完成の物語”がくれた、心のざわめき
完璧じゃないからこそ、胸に引っかかる。
しくじったからこそ、そこに人間の温度がある。
『ブサメンガチファイター』の終わり方は、たしかに中途半端だった。
でも、私たちは「しくじりの中にあった叫び」に、ちゃんと耳を澄ませた。
そして、その中に“気づかれなかった感情線”を見つけた。
それだけで、この物語は、誰かの心の中で“静かに完結”していたのかもしれない。
わたしは、そんな物語が好きだ
完璧な構成より、しくじった余白。
感動のエンディングより、「あれ、なんか…寂しいな」って思わせる読後感。
『ブサメンガチファイター』は、そんな気持ちを思い出させてくれる物語だった。
そしてそれは、たぶん「忘れられない物語」って意味だと思う。
物語が途中で止まっても、感情が完結していなくても。
しげるという存在が、私たちの中でまだ“生きている”なら。
それは、きっと失敗なんかじゃない。
──私はそう信じて、ページを閉じた。
- 『ブサメンガチファイター』は“しくじり”にこそ感情が滲んだ作品だった
- 異世界転生において“ルックス-255”を選ぶ設定が描いた孤独のリアル
- 異能力“触れたらHP激減”が象徴する、愛されたいのに傷つけてしまうジレンマ
- イケメン誠司との“陰と陽”の交差が見せた、理解と共鳴の物語
- 聖華・リーズら女性キャラが“観客のまま終わった”ことのもどかしさ
- 中盤に山場が見えず物語構造が曖昧になったことが打ち切りの遠因に
- ラストバトルが唐突すぎて、物語の終着点が“放棄”に近いと感じられた
- それでも、“しげるの痛み”だけは本物だったと、多くの読者が感じた
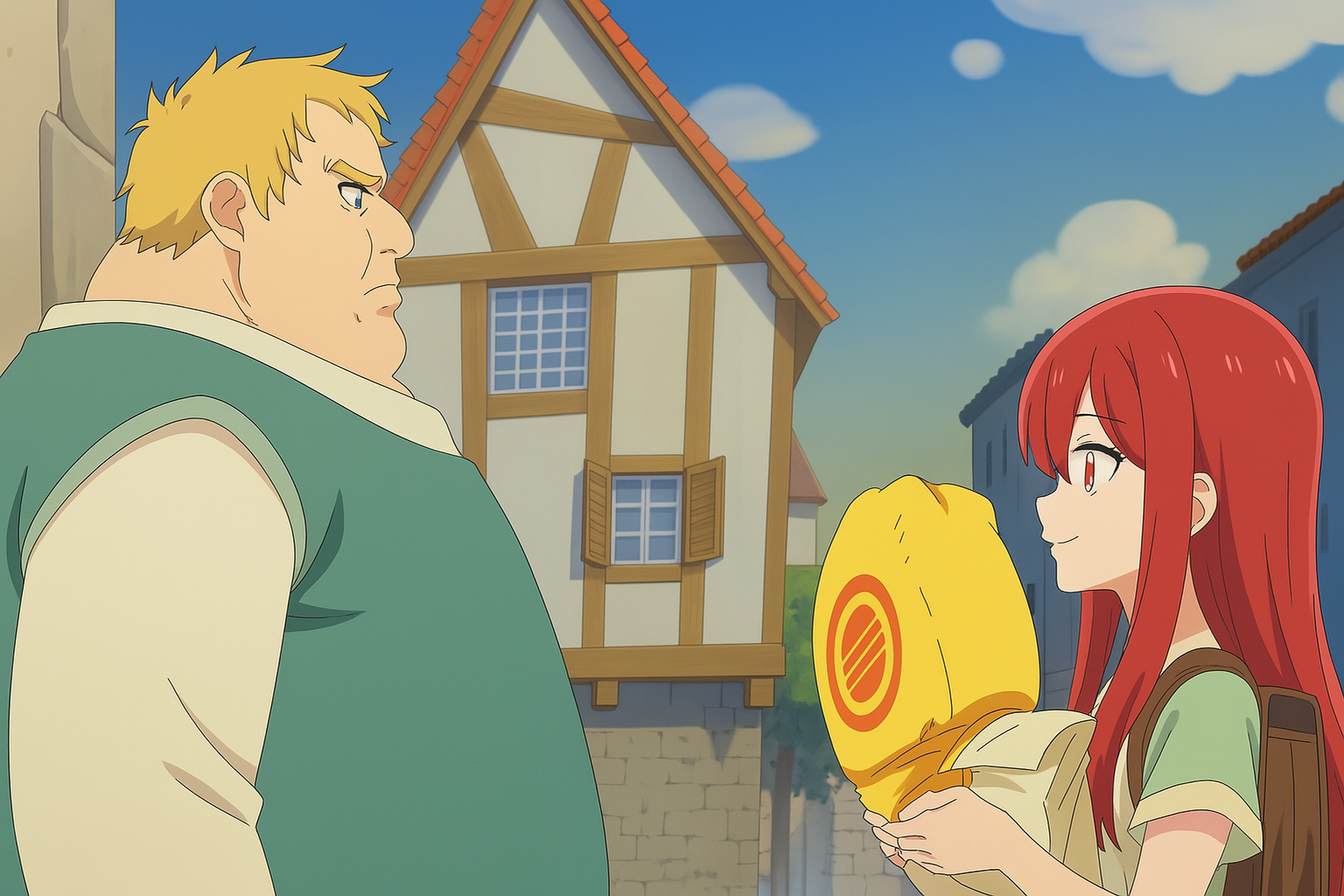


コメント