| 見出し |
2. ニャアンとの関係性に物語的必然性が感じられない──つながりが“設定”でしかないもどかしさ |
| 要点① |
ニャアンとマチュの出会いや関係性の成り立ちが端折られて描かれている |
| 要点② |
感情的な関係が深まるプロセスが描かれず、共闘や言葉が唐突に感じられる |
| 要点③ |
二人の会話が情報伝達に終始し、“心を預け合う”空気感が不足している |
| 要点④ |
ニャアンが物語を動かすキャラというより“説明役”にとどまってしまっている |
ニャアンというキャラクターは、マチュのそばにずっといた。
なのに、彼女の言葉がどんなに真っ直ぐで、どんなに優しくても、なぜだか心に届かない瞬間が続いていた。私はずっと考えてた。「このふたり、ほんとに“物語”で出会ったんだろうか」って。
ニャアンとマチュの関係性──それはこの物語のもう一つの軸になるはずだった。けれど、どうしても「設定上の関係」にしか見えない。“感情の蓄積”が抜け落ちたまま、ふたりは仲間として描かれてしまっている。そこが惜しい、ほんとうに惜しいんです。
そもそも、ふたりの出会いの描写が薄い。なぜ一緒に戦っているのか、なぜ信頼しているのか──視聴者が自然と“感じ取れる瞬間”が用意されていない。たとえば、助け合った記憶、何気ないやり取り、ささやかな微笑み──そんな積み重ねがあれば、もっと感情の解像度は上がったはず。
ところが、物語ではふたりが出会って数話後にはもう「共闘関係」になっていて、会話も任務や状況整理ばかり。“親密”ではなく“効率的”な関係性に見えてしまう。これでは、彼女が何を思ってマチュに声をかけるのかも、マチュが彼女に何を委ねているのかも、視聴者には伝わらない。
さらに言えば、ニャアンはマチュの“補助役”に留まっていて、彼女自身の心の揺れや葛藤が描かれない。彼女の言葉がただの台本に聞こえてしまうのは、キャラクターが「生きていない」からかもしれない。生きていれば、迷いも、余計な言葉も、ぶつかりもあったはずなのに。
たとえば、こんな演出があったらと思う──
- ふたりが出会った直後、夜明け前の時間を静かに過ごすシーン
- 戦闘中に一瞬見せたマチュの焦りを、ニャアンが無言で支えるカット
- ミスや誤解による口論があって、でもお互いに向き合う場面
- 任務外で偶然言葉を交わす、日常のような一瞬
こうした“何でもない時間”の中にこそ、視聴者は「絆」の予兆を見出すものだと思う。関係性は、台詞ではなく余白で語るものだから。
そしてニャアンは、本来もっと物語を動かせるキャラクターだと思っていた。だって彼女の視線には、あきらめの色と優しさの匂いがある。過去を知りすぎているからこそ、前を向こうとする「苦しいほどの強さ」がある。だけど、それが物語の中で十分に活かされていない。
結果として、ニャアンは“マチュを支えるキャラ”という枠の中に押し込まれてしまっていて、キャラ単体としての深みや自立性が描かれない。これでは関係性が「お互いの心に触れ合っている」ようには見えず、機能的なパートナー止まりになってしまう。
物語として重要なのは、「このふたりが出会った意味」がどこにあるか、です。それが見えた瞬間、ようやく私たちは「このふたりを見届けたい」と思える。視聴者は恋愛が見たいわけじゃない。“ここにいてくれてよかった”と思える相互作用が見たいんです。
今のジークアクスでは、残念ながらそれが伝わりづらい。もったいないのは、素材としてのポテンシャルがあるのに、それを料理していないところ。ニャアンの微笑みがもう少し“過去の傷”とリンクしていたら、マチュの沈黙に“信頼の証”が含まれていたら──そのたびに、私の中の何かが反応していたかもしれない。
設定ではなく、関係性の“運動”を見せてほしかった。信じるか迷って、でも一緒に歩いて──そんな“揺れ”のある道を、ふたりが進んでくれたなら、私はきっと、もっとふたりを好きになれたと思います。
関係性は、筋道ではなく、感情の“粒”でできている。その粒がまだ見えないままなのが、今のジークアクスの惜しさであり、可能性なのかもしれません。
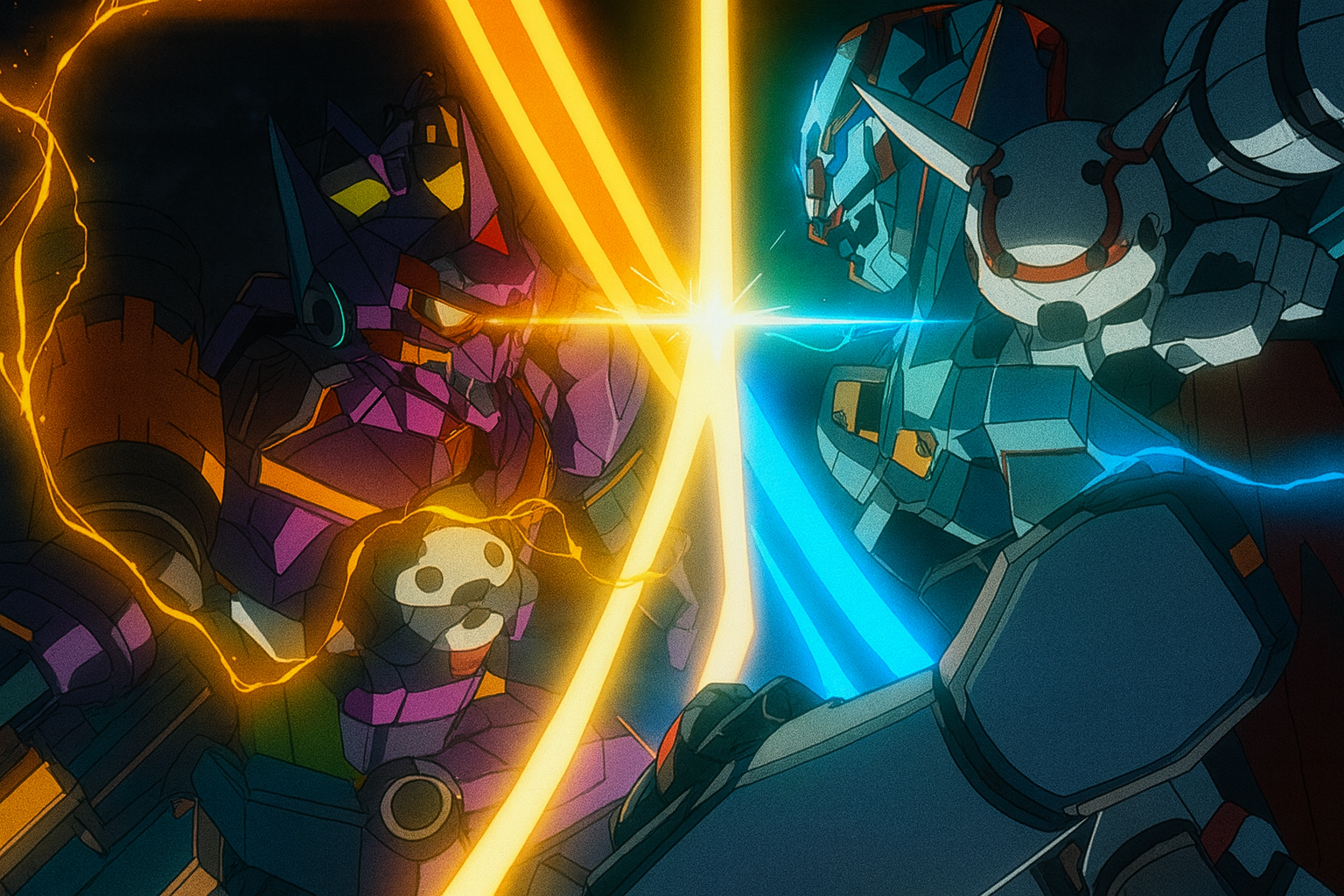
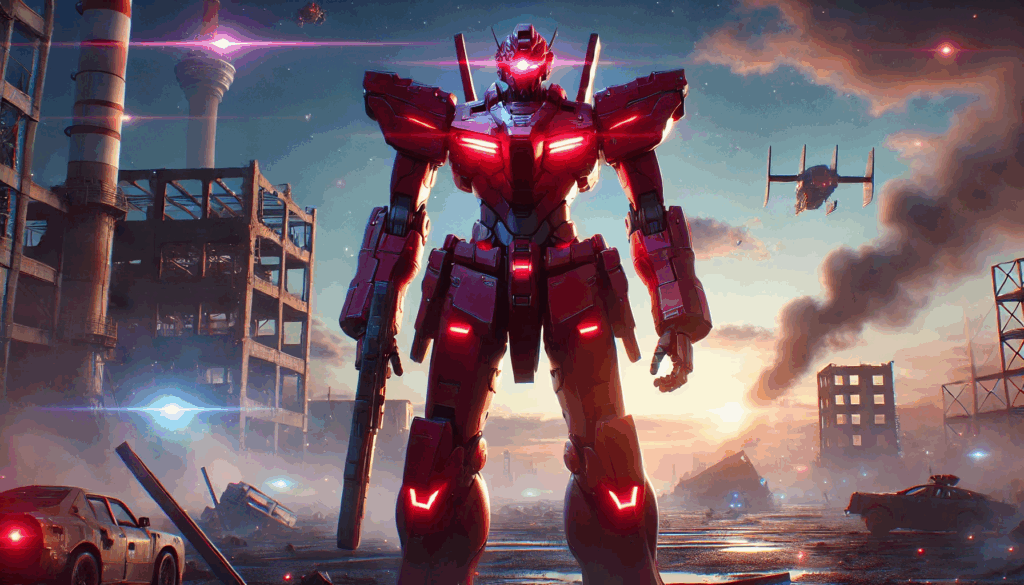
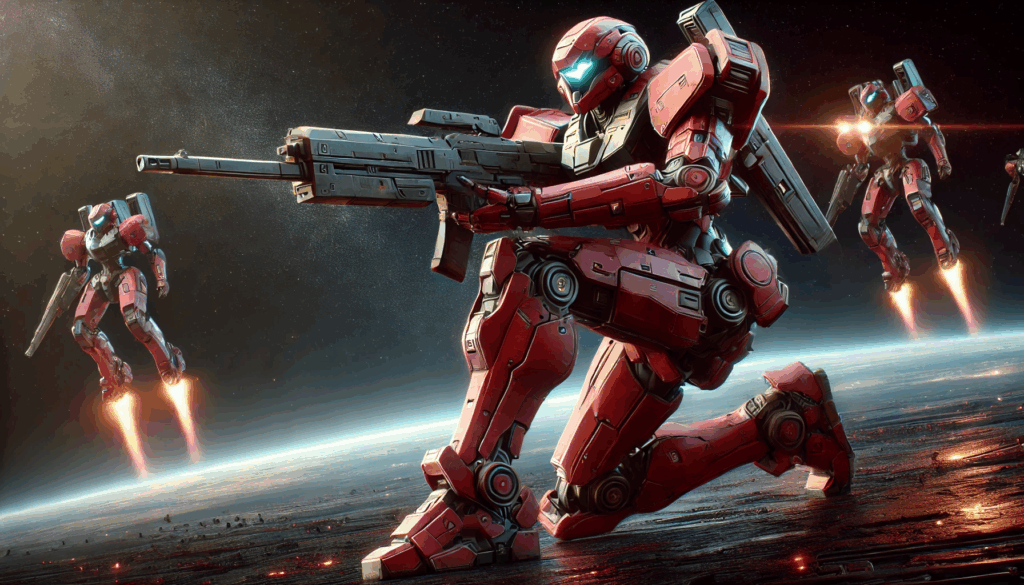
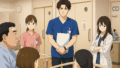
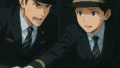
コメント