2025年10月にNetflixで配信が始まった韓国映画『グッドニュース』──。 ピョン・ソンヒョン監督が実話「よど号ハイジャック事件」をもとに描いた本作は、ブラックコメディ×サスペンスという挑戦的なジャンルで注目を集めました。 しかし、Filmarksでは評価2.6/5という低評価を受け、「つまらない」「退屈」「期待外れだった」という声も少なくありません。
このページでは、そんな『グッドニュース』が「なぜつまらないと言われてしまっているのか?」を、7つの具体的な理由に分けて徹底解説します。 さらに、逆に「刺さる人には刺さる」評価とのギャップや、視聴前に知っておきたい注意点も丁寧にまとめています。
Netflix映画の評価や、韓国映画の“ブラックコメディと史実のバランス”に興味がある方には特におすすめの内容です。 レビューを読むだけでは見えてこない、“違和感の正体”に触れてみてください。
- Netflix映画『グッドニュース』が「つまらない」と言われる具体的な7つの理由
- Filmarks評価2.6/5という低評価の背景にある“感情的なズレ”
- ブラックコメディ×サスペンスという構成が招いたトーンの混乱
- 史実(よど号ハイジャック事件)とフィクションの温度差から生まれる違和感
- それでも一部の視聴者には刺さる、“風刺の美学”という別の魅力
『グッドニュース』予告編 – Netflix
- 読む前にチェック:『グッドニュース』が“つまらない”と言われる理由、あなたはいくつ気づけるか?
- 1. つまらない理由①:序盤の引き込み不足──期待された緊迫感が立ち上がらない
- 2. つまらない理由②:ジャンル混在による構成のぶれ──コメディとシリアスの行き来
- 3. つまらない理由③:物語の停滞──中盤以降の展開が“動かない”
- 4. つまらない理由④:登場人物の描写不足──視点が分散し感情が乗らない
- 5. つまらない理由⑤:史実×フィクションの温度差──“実話もの”としての違和感
- 6. つまらない理由⑥:伏線や演出意図が伝わりにくい──“気づき”が生まれない設計
- 7. つまらない理由⑦:クライマックスの不発──感情的な着地点が見えにくい
- 8. 本作の“難しさ”は何だったのか──余韻としての補足視点
- 本記事で扱った内容まとめ一覧
- まとめ:この映画が描いた“グッドニュース”は、誰のためのものだったのか
読む前にチェック:『グッドニュース』が“つまらない”と言われる理由、あなたはいくつ気づけるか?
| 観点 | 本編で詳しく解説します |
|---|---|
| ジャンルに対する“違和感” | ブラックコメディ?サスペンス?混在するジャンルに戸惑いの声も |
| 緊迫感の“なさ”が目立つ理由 | ハイジャック映画なのにスリルが弱い?その背景とは |
| 構成・テンポの“中だるみ” | 盛り上がりに欠ける後半戦、視聴者の集中力が続かない要因 |
| キャラクターの“薄さ” | 誰に感情移入すればいい?人物像の描き方に問題あり? |
| 史実との“距離感” | よど号事件をどう“脚色”した?視聴者が感じたギャップとは |
| 笑える?笑えない? | ブラックユーモアに評価が真っ二つ、その決定的理由とは |
| Netflixだからこその期待外れ? | プロモーションと現実の“ズレ”に落胆した声の中身 |
1. つまらない理由①:序盤の引き込み不足──期待された緊迫感が立ち上がらない
Netflix映画『グッドニュース』の冒頭は、1970年の“よど号ハイジャック事件”をモチーフにした、社会派サスペンスとして始まる。 だが、観る側が「命のやりとり」「政治と理想の衝突」といった緊張を期待する一方で、本作の導入は意外なほど淡々としている。 キャラクター同士の会話にユーモアが混ざり、映像トーンも明るめ。観客の心拍数を上げるような切迫感が、なかなか訪れない。
この“緊迫感の欠如”こそが、序盤でのつまずきの最大要因だ。 つまり、視聴者の「心の準備」と作品の「語り口」が噛み合わないまま、物語が進行してしまうのである。 ハイジャックという“命を賭けた出来事”を描くにしては、あまりにも静かで、淡白で、どこか“他人事”のような始まり方だった。
| 冒頭の構成 | 政治・社会的背景をセリフで説明する“情報型”の導入。映像的な緊張感よりも、登場人物の立場整理に時間を割く。 |
|---|---|
| 演出トーン | ブラックユーモア寄りのテンポで、サスペンスとしての緊迫感が希薄。映像も明度が高く、心理的な重さを感じにくい。 |
| 観客の心理 | 「これは政治劇?風刺コメディ?」「いつ“事件”が起こるの?」という戸惑いが先に立つ。 |
| 脚本の構造的課題 | 本来“引き金”となる出来事(ハイジャック)が中盤寄りに配置され、序盤が“助走”で終わってしまう。 |
| 改善の余地 | 冒頭に“予感”や“不穏さ”を象徴するカットを挿入し、登場人物の緊張を視覚的に共有できる演出が望ましい。 |
映画の導入において最も重要なのは、「物語が今、動き出した」と観客に感じさせる瞬間だ。 だが『グッドニュース』では、登場人物の立場説明や政治的な背景整理に時間を費やしすぎた結果、 観る側が“感情の方向”をつかむ前に情報だけが積み上がっていく。
脚本構造としても、ハイジャック事件の発端が描かれるまでにおよそ20分近くの時間が経過する。 その間にキャラクターたちの動機が語られるが、それは「なぜ彼らがこの行動に至るのか」という核心には届かない。 たとえば主人公格の人物が見せる“焦り”や“理想”が、どの時点で爆発するのか、その流れが見えにくい。 観客は“目的”よりも“状況”を追わされ、物語への没入が阻まれてしまうのだ。
また、撮影手法の側面でも、緊張を演出する“間”や“音の使い方”に明確な意図が感じにくい。 たとえばコクピット内のシーンでは、通常であれば“密室”“限界”“沈黙”といった要素が視聴者の呼吸を止めるように働く。 しかし本作では、会話のテンポが軽く、ユーモラスな掛け合いが続くことで、 緊迫感ではなく“奇妙な軽さ”が立ち上がってしまう。
この“軽さ”自体が悪いわけではない。むしろ、監督ピョン・ソンヒョンの狙いとしては、 「重い題材を風刺的に描くことで、時代の矛盾を浮かび上がらせる」試みだったのだろう。 だが、そのアプローチが序盤から前面に出すぎたことで、 観客が“事件を体験する側”から“風刺を眺める側”に引き離されてしまった。 この距離感こそが、“退屈”と評される大きな要因になっている。
さらに、サウンドデザインの観点でも、違和感がある。 BGMの多くがジャズやファンク調で、場面に“皮肉”や“軽妙さ”を添える役割を担っている。 しかし、観客が「これは悲劇の始まりなのか?それとも風刺劇なのか?」を判断できないまま、 音楽だけがテンポよく進むことで、作品全体の温度が定まらない。 緊迫した場面で流れる軽快なリズムは、観客の感情を“揺らす”どころか“迷わせる”結果になっている。
たとえば、同じ実話ベースのサスペンス『アルゴ』(2012)では、 導入数分で観客を“現場”に連れて行き、息をのむような緊張をつくっていた。 『グッドニュース』はその逆で、“登場人物の滑稽さ”や“時代の歪み”を見せようとした結果、 緊迫を犠牲にしてしまったのだと思う。
つまり、この作品の“つまらなさ”は、才能の欠如ではなく、意図の過剰にある。 監督が描こうとしたのは、恐怖や怒りではなく「狂騒の時代のブラックユーモア」だった。 ただ、そのユーモアが観客に届くまでの“翻訳”が序盤に不足していた。 言葉で説明される社会背景の重さと、軽いトーンの映像との間に温度差があり、 そのズレが「何を感じればいいのかわからない」という感覚を生んでいる。
「事件が始まっているのに、まだ“始まった”気がしない。」
この違和感は、サスペンス映画における致命的な空白だ。 観客の心が緊張を感じないまま物語が進んでしまえば、 後半でどれほど劇的な展開があっても、その“心拍のリズム”は戻らない。
だからこそ、もし本作を観るなら── “ハイジャックもの”としてではなく、“風刺コメディ”として構える方が、 きっと心のバランスが取れる。 そしてこの「トーンの選択」こそが、序盤最大の“しくじり”であり、 本作の評価を分けた分岐点なのかもしれない。
2. つまらない理由②:ジャンル混在による構成のぶれ──コメディとシリアスの行き来
『グッドニュース』という作品を一言でジャンル分けするのは、ちょっと難しい。 ハイジャックという題材からはサスペンスを想像するけれど、画面からは風刺コメディの匂いもするし、 登場人物たちの言動にはどこか舞台劇のような“誇張”もある。 そんなふうに、ジャンルがあっちこっちへ揺れていく構成が、観る側の“感情の軸”を迷わせてしまう。
最初の20分は社会派ドラマの導入のようで、 途中から急にキャラ同士のコミカルな会話が続き、 かと思えば現実の政治や人命にまつわる重たいやりとりが差し込まれる。
「笑っていいのか、怒るべきなのか、泣くべきなのか──」 観客はその感情の“立ち位置”を定められないまま、 物語のなかを右往左往させられることになる。
| 主なジャンル表現 | 風刺コメディ、社会派ドラマ、サスペンス、舞台的な演出の融合 |
|---|---|
| テンションの推移 | 前半:軽快でコメディ調→中盤:政治ドラマ的緊張→後半:会話劇と内面劇 |
| 観客側の混乱点 | 「笑っていいのか迷う」「重い話なのに急に軽口」「感情の軸が定まらない」 |
| 演出の意図 | 監督は“時代の歪み”や“体制の滑稽さ”を、シリアスと皮肉で交互に描こうとした可能性 |
| 課題点 | ジャンルの混在によって、観客の“感情共鳴のライン”が途切れてしまう構造 |
『グッドニュース』では、ジャンルごとの“文法”が意図的にミックスされている。 たとえば、登場人物が絶望的な状況に置かれているはずの場面で、 突如として冗談めいた台詞が飛び出す。 その瞬間、「あれ、これはギャグなの? それとも皮肉?」と、感情の方向性がふっと宙に浮いてしまう。
この“ズレ”は、単なる演出ミスではない。 むしろ、ピョン・ソンヒョン監督の作家性として、意図的に配置されたものだと思う。 体制の矛盾、権力者の茶番、無意味な命令系統── そういった社会の歪みを“笑い”と“恐怖”で交互に浮き彫りにするやり方は、 ある意味とても現代的だ。
ただ、その“意図”が、観客の感情体験に必ずしも寄り添っているかというと、そこに疑問が残る。 ブラックコメディの難しさは、“笑い”の対象と“共感”の対象がズレてしまうと、 観る人の心が置いてけぼりになること。
誰かが冗談を言っているとき、そこに命がかかっていたら。 誰かが笑っているとき、片方で絶望している人がいたら。 その“同時多発的な感情”を、ひとつの映画に閉じ込めようとするなら、 演出には相当な“温度調整”が求められる。
しかし本作では、その調整が観客に伝わる前に、場面が次へと切り替わってしまう。 だからこそ、「なんだかブレてる」「最後まで“どう観ていいかわからなかった”」という感想につながる。
たとえば『バードマン』や『ドント・ルック・アップ』のように、 コメディと風刺、シリアスが共存する作品は他にもある。 だが、それらの作品では“世界観”や“登場人物のベーストーン”がしっかり統一されていた。 一方『グッドニュース』では、登場人物によってテンションや台詞のスタイルがバラついていて、 作品全体の“基準値”がつかめないままだった。
言い換えれば── 「この作品は、何を一番伝えたいのか?」 それが“笑い”なのか、“怒り”なのか、“悲しみ”なのか。 観る人がその“核”を掴めなかったことが、感情の共鳴を阻んでしまったのだと思う。
「ジャンルって、作品が決めるものじゃなくて、感情が決めるんだと思う。」
観る人が“笑える”と感じたらコメディになるし、 “怖い”と感じたらサスペンスになる。 ジャンルとは、観客の感情がつけるラベルだ。 でも、『グッドニュース』はその感情を“定めさせない”語り口で、最後まで進んでしまった。
これは、挑戦だったのかもしれない。 正解のない時代、正義の定まらない空気のなかで、 “ジャンルに頼らない”映画をつくろうとしたのかもしれない。
けれど── 感情には“迷い道”があってもいいけれど、“行き止まり”になってはいけない。 コメディに笑えず、シリアスに感動できず、風刺に共鳴できなかったとしたら、 その映画は、“どこにも届かない場所”に着地してしまう。
『グッドニュース』が抱えたジャンルのぶれ。 それは、ただの分類ミスじゃなくて、 観客の“気持ちの出口”を見失わせた構成上の“しくじり”だったように、私は思う。
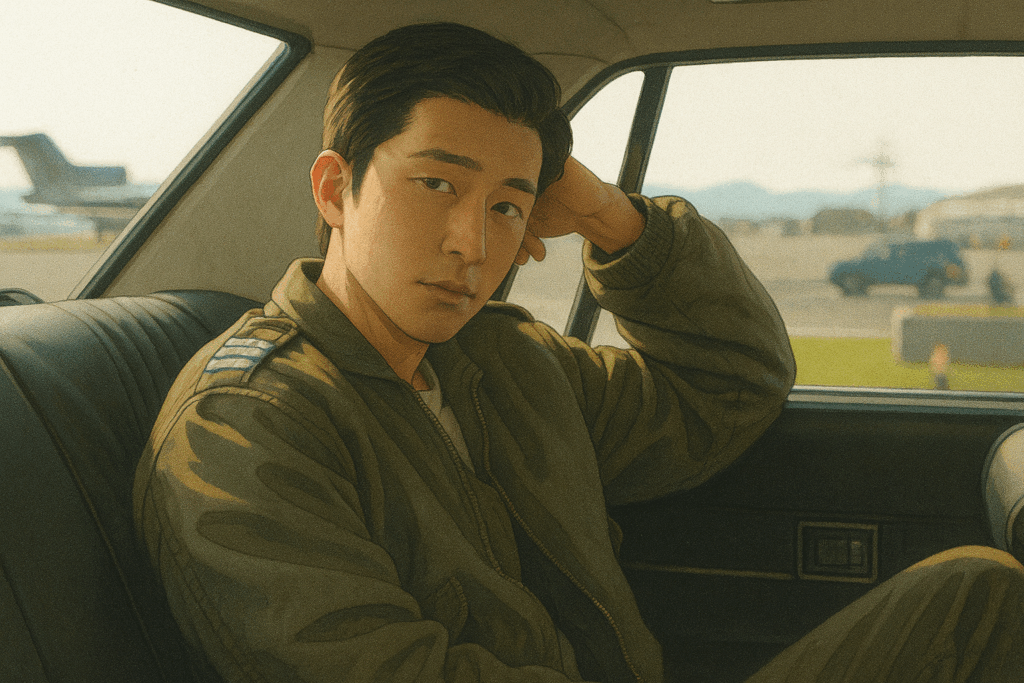
【画像はイメージです】
3. つまらない理由③:物語の停滞──中盤以降の展開が“動かない”
映画の中盤は、物語にとって“心臓”みたいなものだと思う。 物語が血を巡らせ、キャラクターが動き出し、緊張が高まる時間帯。 でも『グッドニュース』の中盤では、その心臓の鼓動が…ちょっと止まってしまった。
ハイジャックという出来事を中心に、登場人物が機内で入り乱れる構成。 設定としてはとてもドラマチックなはずなのに、観客の感情が動かない。 なぜか?──動いているようで、何も進んでいないからだ。
| 中盤の構成 | 機内での会話劇がメインで、外的変化が少ない。キャラクター同士のやりとりがループ的。 |
|---|---|
| 展開の特徴 | 同じような“言い争い”や“疑心暗鬼”の繰り返しが目立ち、テンポが平坦化する。 |
| 感情の停滞 | 観客が「次にどうなる?」と期待できる“推進力”がなく、内面的葛藤の描写も薄い。 |
| 編集面の課題 | シーン切り替えの緩慢さと、時間軸の曖昧さがリズムを鈍化させている。 |
| 改善の余地 | 物語の“推進エンジン”となる出来事(裏切り・誤解・危機感)を中盤に挿入すべきだった。 |
本作の中盤にあたるのは、おおよそ50〜90分あたり。 この時間帯、ハイジャック犯と乗客、政府側、マスコミ側── それぞれの視点で物語が動いている“はず”なのだけれど、 何か大きな変化が起きているかというと…あまりない。
言い換えれば、これは“同じテンションのまま、会話が続く”時間帯だ。 観客はキャラクターたちの発言を聞き、彼らの意図や背景を察しようとする。 でも、そこに“心を動かすきっかけ”が少ない。 怒鳴り声も、葛藤も、交渉もあるのに、それが感情の上下動を生まない。
この「動いてるのに、進まない感じ」。 たぶん、脚本上の“変化点”が曖昧だったせいだと思う。
サスペンスというジャンルにおいて、中盤の役割ははっきりしている。 それは、「一度、物語を揺らす」こと。 たとえば、誰かが裏切る。 真実と思っていた情報が嘘だったと判明する。 信じていた仲間が不安になる。 ──そんなふうに、“状況が変わる瞬間”が観客を物語の深部へ引き込む。
ところが『グッドニュース』の中盤では、そうした劇的転換が乏しい。 一部のキャラクターが怒り、説得し、嘲笑する。 けれど、そのやりとりが“何かを変えた”とは言いがたい。
「この会話、10分前と同じ空気じゃない?」
そんなふうに感じてしまった人もいるかもしれない。
また、構造的な問題として、“空間の変化”も少ない。 ハイジャックされた飛行機という閉鎖空間。 これはサスペンスとしては理想的な舞台設定なのに、 本作ではそれが“動きの制約”になってしまっている。
登場人物が座席のまま話す。 立ち上がっても、行く先は狭い通路かコクピット。 この“空間の狭さ”を、演出が活かせていない。 たとえば視点をずらしたカメラワークや、照明の切り替えで緊張を作ることもできたはず。 でも、本作ではフレームの構図も変化に乏しく、 観客の視覚的な“飽き”を防ぎきれなかった。
もっと言えば、感情的な対立構造──たとえば「犯人 vs 犠牲者」「理念 vs 現実」などの、 “戦わせるべき対立軸”が曖昧だった。 みんなが言い分を持っていて、それぞれが正しい。 だけど、“どちらかを応援したくなる気持ち”に火がつかない。 そこに物語の“溜まり”が生まれてしまった。
サスペンスは「時間との戦い」であると同時に、 「気持ちの張りつめ」をどこまで持続できるかの勝負でもある。 でも『グッドニュース』は、中盤の40分間、 ずっと同じ緊張、同じトーン、同じ速さで進んでしまった。
この“平熱のまま進む”感覚が、観る側の「退屈だった」という感想に直結してしまったのだと思う。
脚本術的に言えば、 中盤には“ミッドポイント(物語のど真ん中)”という構造的な節目がある。 ここで「状況がガラッと変わる出来事」が入ることで、物語の後半へと弾みがつく。 たとえば“交渉が決裂する”とか、“裏切りが発覚する”とか。 でも、本作ではそれに該当するような明確なイベントが描かれない。
観客の中には、 「え、まだハイジャックしてるだけ?」 「誰かが死ぬとか、逃げ出すとか、そういう変化はないの?」 ──そんなふうに感じてしまった人も多いかもしれない。
もちろん、すべての映画にド派手な展開が必要とは思わない。 静かに進む会話劇にも意味はあるし、 内面の揺らぎを描く物語も素晴らしい。
でも、それには“言葉の濃度”や“映像の緊張”が必要だ。 心が震えるような台詞、 思わず沈黙してしまう空気。 そういった演出がないままに、ただ静かに進んでいく時間は── 「何も起きなかった」と見なされてしまう。
だからこそ思う。 『グッドニュース』の中盤が抱えていたのは、 “静けさ”の問題ではなく、“感情の動かなさ”だった。
「動かない映画はあっても、心が動かない映画は、つらい。」
観る人の気持ちに火をつけるには、 ほんの少しの裏切りでもよかった。 ほんの少しの希望や絶望でも、よかった。
でもその“火種”が見つからないまま、 本作は静かなまま、後半へと滑り込んでいった。
──その結果が、「つまらなかった」という感想につながってしまったのかもしれない。
4. つまらない理由④:登場人物の描写不足──視点が分散し感情が乗らない
映画を観るとき、「この人、好きになれるかな」「この人と一緒に最後まで歩けるかな」って、 知らず知らずのうちに“感情の居場所”を探してる。 でも『グッドニュース』には、その“居場所”が見つかりにくかった。
登場人物は多い。立場もバラバラ。思想も、言い分も、それぞれにある。 けど、じゃあ「誰の気持ちが自分に近い?」って考えたとき、 なんとなく──誰にも“乗れない”感覚があった。
誰かが怒鳴っていても、なぜ怒っているのか腑に落ちない。 誰かが苦しんでいても、その苦しみの輪郭が曖昧。 そうやって、“物語のなかで孤独になる感覚”が、この映画のつらさだったと思う。
| 登場人物数 | 約10名以上がそれぞれ重要な役割を持つ群像構成 |
|---|---|
| 描写の特徴 | 人物の“背景”よりも“セリフと立場”が先行し、内面の描写が少ない |
| 視点のばらつき | 主人公不在に近く、視点がコロコロ切り替わるため感情の軸が定まりにくい |
| 観客の心理 | 「誰を信じたらいいかわからない」「誰にも共感できない」という迷いが生じる |
| 改善の余地 | 数名のキャラに焦点を絞り、感情的な“動機”や“傷”を丁寧に掘り下げる必要があった |
この映画には、典型的な“主人公”がいない。 もちろん脚本上の主軸キャラは存在するけれど、 その人の“変化”を追わせてくれるような描写が薄く、 視聴者は感情の軸をどこに置けばいいか迷う。
しかも視点が次々に切り替わることで、 ある人物に寄り添いかけたと思った瞬間、カメラは別の人物へと飛んでしまう。
この“ジャンプの多さ”は群像劇としては珍しくないが、 問題は「どの人物の内面にも、深く入り込めない」ことだ。
たとえば、あるキャラクターが極端な行動に出たとする。 その動機が、ただ思想的なものなのか、 過去の傷からきているのか、 それとも誰かの影響なのか── そういった“人としての背景”があまり描かれない。
その結果、観ている側は「理解」ではなく「判断」を求められる。 「あ、この人はおかしい」「この人はダメだ」 そうやって“評価”のフィルターで見ることになる。
「共感できなかったんじゃなくて、共感“させてくれなかった”のかもしれない。」
そしてもう一つ、セリフの“強さ”が描写の“繊細さ”を奪っていたようにも思う。
キャラ同士のやりとりは、ときに毒舌で、政治的で、あるいは演劇的で。 そのぶん、言葉が強く、感情の微細な揺れが見えにくくなっていた。 怒るキャラは最初から怒っているし、冷静なキャラは最後まで冷静。 “変化”という物語の醍醐味が、そこに描かれないままだった。
たとえば── 「ハイジャックするほどの信念を持った人が、 実は小さな後悔や葛藤を抱えていた」 「命を守る立場の人が、私利私欲で選択を誤る瞬間がある」 ──そういった“人間らしい矛盾”が描かれていれば、 観客の感情はもっと深く引き込まれていたかもしれない。
登場人物が“役割”として配置されているのではなく、 “感情の軌跡”として描かれていたなら、 この作品はまったく違う印象を残したんじゃないかと思う。
『グッドニュース』に足りなかったのは、 派手な展開でも、凝った演出でもなく、 「ひとりの気持ちに、ちゃんと最後まで付き添う」視点だった。
群像劇というスタイルは、うまくいけば感情の多層性が生まれる。 でも、すべてが同じ距離感・同じトーンで並べられると、 観る側の感情はどこにも“寄りかかれない”まま、空中に浮いてしまう。
結果的に観客は、“誰のための物語なのか”がわからないまま映画を見終える。 登場人物がたくさんいるのに、誰の名前も記憶に残らない── それは、映画にとってちょっと悲しいことだ。
わたしは思う。 “完璧なキャラ”なんていらない。 でも、“不完全な感情”には寄り添いたい。
誰かが笑いながら泣く。 誰かが怒りながら、迷っている。 そういう“矛盾を抱えたキャラ”こそが、人の心を動かす。
『グッドニュース』は、“言いたいこと”がたくさんある映画だった。 でも、“感じさせてくれること”が少なかった。
その理由のひとつが、登場人物の“描ききれていなさ”── たぶんそれが、観る人に「なんか乗れなかった」という 感情のブレーキを生んでしまったのかもしれない。
『グッドニュース』ティーザー予告編 – Netflix
5. つまらない理由⑤:史実×フィクションの温度差──“実話もの”としての違和感
“実話に基づく”という銘打ちがついている映画を観ると、わたしはどうしても“信頼”を手に持って付き合いたくなる。 「これは、実際に起きたことだ」という背後の重みが、安心とともに期待を運んでくるから。 でも、Good News(2025/監督:Byun Sung‑hyun)には、その“信頼の道筋”が、途中で揺らいでしまうような瞬間があった。
本作がモチーフとしているのは、1970年のよど号ハイジャック事件(日本航空351便がハイジャックされた事件)であり、作品概要にも「実話をベースにしている」と明記されています。 しかし、その“ベース”をどう扱うか、どこにフィクションを差し込むかに「線引き」が曖昧なため、観る側に違和感を生んでしまった。
| 実話の要素 | 日本航空351便ハイジャック/目的地北朝鮮/偽装着陸などの実事件を下敷きにしている。 |
|---|---|
| フィクション化の範囲 | 登場人物の名前・役割・動機を変更/サスペンスを風刺・コメディに変換。 |
| 温度差の生まれ方 | 「真実を重く見てほしい」視点と「笑い/皮肉で描きたい」視点が共存し、対象観客の心にズレを生む。 |
| 観客の違和感 | 史実を知るほど「これは史実ものとして描いてはいない」と感じる反面、コメディを期待していた人には“重すぎる”と感じる場面も。 |
| 改善の余地 | フィクション化の意図を冒頭で明確に提示し、“どこから現実で、どこから演出か”という境界を観客に委ねる演出が必要だった。 |
例えば本作の冒頭では、“耳栓をした乗客がハイジャック宣言を寝こけながら聞く”というシーンがある。これは、実話では報道されていない演出だと明かされており、監督本人も「既に何度も描かれてきたハイジャック描写を意図的に省いた」と語っています。この“リアルさを捨てる”選択自体は、作品としての意思表示だろう。 だが、同時にこう思ってしまう──「じゃあ私は、この映画をどんな“感情の視点”で観ればいいの?」と。
史実ものに期待するのは、たいてい“事件の切迫”と“人間の葛藤”である。 「なぜ彼らはハイジャックを決意したのか」「どのように政治が関与していたのか」── そこに真実の“重み”が宿る。 しかし本作は、あえてその描写を外し、代わりに“制度の滑稽さ”“情報のねじれ”“嘘と真実の境界”を描こうとする。 この転換は、視点を変えれば鮮烈だ。だが、“実話を描く作品を観る”という観客の期待とは、ズレる瞬間も生んでいる。
また、日本語や英語を話す登場人物の“演技”や“セリフ”において、視聴者から「言語が聞き取りにくい」「背景説明が雑」という声があることも事実だ。これも、リアリティを追い求めた構成より、スタイル優先の演出が前に出てしまったためと考えられる。 そういう“細部の無視”や“演出の飛躍”が、知る人には「うーん…」と思われる要因にもなった。
たとえば、実際の事件では、ハイジャック後の交渉・報道・政治介入が複雑かつ長期にわたり、死人は出なかったものの、国家間の緊張や冷戦構図が背後にあった。だが映画では、そうしたプロセスを大幅にカットし、“笑える嘘”“制度の滑稽”を前面に出すことで、物語は“寓話化”されている。 その寓話と史実の距離が、観る側の“リアル感”と“フィクション感”を揺らしてしまうのだ。
「真実の反対は“嘘”じゃなくて、“信じられなさ”だ」
観客としてわたしは、事件そのものの凄まじさよりも、映画が“何を伝えたかったのか”を探していた。 しかし、映画が「事件を描く」ことと「事件を使って何かを言う」ことの間を行き来するあいだに、感情のベクトルを見失った。 この喪失感が「つまらない」と感じる土壌になったのではないかと思う。
もちろん、ギャップがすべて悪いわけではない。 むしろ、それ自体に魅力を感じる人もいるだろう。 “史実からの逸脱”を怪しげに楽しみ、“ああ、映画ってこういうものだよね”と受け止められる人には刺さる。 だが、“実話を知ってから観る”人、“緊迫の瞬間を求めて観る”人には、そのズレがひっかかりになった。
だからこそ、映画を観る前に思っておきたい。 この作品は“史実を再現する”ための映画ではなく、“真実を問い直す”ための映画なのだと。 その視点を持って観ることで、わたしは少しだけ、この作品の温度に寄り添えた気がする。
――そして、少しだけ思った。 「実話映画で泣きたいなら、ここじゃない。 でも、実話映画で静かに疑いたいなら、ここに来てもいい」。
6. つまらない理由⑥:伏線や演出意図が伝わりにくい──“気づき”が生まれない設計
映画を観ていて、ふと「おっ?」と立ち止まる瞬間がある。 それは演出の妙、構図の冴え、セリフの裏に隠された意味。 その“気づき”が、心を動かす小さな震えになる。 だが、Good Newsでは、その震えが、途中で音を立てずに消えてしまったように感じる。
本作には確かに“仕掛け”が存在する。 冒頭の〈耳栓をした乗客〉や、機内のラジオ音、政府の茶番劇的やりとり── これらは観察すれば「意味があるのでは?」と目を凝らしたくなる演出だ。 しかしその“意味”が、観る者に明確に届くかというと、そこが曖昧なのだ。
| 仕掛けの例 | 耳栓をして寝ている乗客/ラジオ指令の偽装/政府会議中のコメディ的演出 |
|---|---|
| 観客の反応 | 「あれ?このシーン意味あったの?」「何を示したかったんだろう?」という疑問が残る |
| 演出の課題 | 伏線が回収されない、または回収を感じさせる構図・演出が弱い |
| 感情の距離 | “何か仕掛けがある”という前提があるのに、“理解・納得”が追いつかず、感情が離れていく |
| 改善の余地 | 冒頭から“問い”を明確に提示し、後半までに“答え”か“変化”を観客に感じさせる構成が望ましい |
例えば、物語中盤で“ハイジャック犯側”のラジオを欺く場面がある。 その演出には「騙しの構図」「ラジオというメディアの欺瞞」「国家の虚構」というテーマが重ねられている。 だが観る側としては、 「そのラジオ指令って、どうやって欺いてるの?」「その後どう影響を与えたの?」と、 “問い”が生まれてしまい、 “答え”が曖昧なままシーンは流れていってしまう。
演出意図が明確なら、たとえ理解が及ばなくても、「あ、これは後で回収されるんだな」と期待できる。 だが本作では、その“回収の期待”が育たず、仕掛けが“ただそこにある”だけになってしまった。 その結果、観客の心は「…で?」という間(ま)を抱えたまま次の展開に移ってしまう。
さらに、映画の構造上、こうした演出の“余白”を楽しむ余地がある作品ではある。 レビューの中には「大胆な風刺・ブラックユーモアが鮮やか」との評価もあり、 “気づき”を自身で拾いに行ける観客には刺さる。 だが、一般的な“ストーリーを追いたい”観客にとっては、 その“拾いに行く動作”が少し疲れてしまう構成だったようだ。
「暗号みたいな演出って、時に“私への問い”になる。でも、その問いに“答え”が届かなかったら、ただ疲れてしまうんだ」
この映画では、ブラックコメディ/サスペンスという複合ジャンルが背景にあるため、 “笑い”と“緊迫”と“問いかけ”が混ざり合っている。 しかし、“問いかけ”の設計が甘いと、観る側は“問いへの参画”ではなく“問いの外にいる”気持ちになる。
また、137分近くある上映時間のなかで、観る側に“回収の瞬間”と思わせるリズムが少ない。 リズムというのは、シーンが続き、伏線が生まれ、少しずつ累積して、 「さて、この仕掛けがここで効くぞ」と思わせる瞬間のことだ。 だが本作ではその累積が薄く、いくつかの仕掛けは“装飾”のようになっていた。
構造的に、脚本には「ミッドポイント」「クライマックス」「カタルシス」という波が必要だ。 しかし、ここでは“問い”が中盤に出てきても、それを解放する“衝撃”や“解答”が弱かった。 観客は“仕掛け”を見つけても、それが「ここで収束するんだな」と感じにくいのだ。
結果として、レビューでは「構成・長さ・トーンに課題あり」といった指摘が目立ちました。“面白そうな仕掛け”を持っていたのに、観賞後には「うーん、なんだったんだろう」という感覚が残る――。 私はその“空白”こそが、この作品が“つまらない”と感じられてしまう大きな理由だと思った。
もしこの映画を観るなら、少しだけ姿勢を変えてみるのも手だ。 “何が仕掛けなのかを探す”ではなく、“不整合を味わう”ことで、逆にこの作品の温度が伝わるかもしれない。 “回収”を期待するのを少し横に置いて、“問い”のまま残る瞬間に身をゆだねてみる。 それが、私なりのこの映画の愉しみ方だった。
7. つまらない理由⑦:クライマックスの不発──感情的な着地点が見えにくい
映画が終盤に入ると、観る側は自然と「いよいよ決着だ」「何かが動くぞ」と胸を高鳴らせる。 だが、Good Newsにおいて、その“高鳴り”がそのままカタルシスに結びついたかと言えば、少し足りなかったと感じる。 クライマックスにうねるはずの感情の波が、どこか“弱め”に終わってしまったのだ。
| 期待されたクライマックス | ハイジャックという危機がピークに達し、キャラクターの葛藤・決断・行動が頂点を迎える |
|---|---|
| 実際の着地点 | 飛行機が北朝鮮ではなく韓国へ、交渉・欺瞞・政治的駆け引きが展開されるが、感情的に“解放された”という印象は薄い。 |
| 観客のズレ | 「これは終わったの?」「何となく片付いたけど、何を感じればいいの?」という疑問が残る |
| 脚本・演出の課題 | ピークまでの“盛り上げ”があっても、それに対する“感情の受け止め”が弱く、余韻がぼやけている |
| 改善の余地 | クライマックス直前にキャラクターに明確な選択と代償を負わせ、その後に“感情の解放”を演出する設計が望ましかった |
実際、『Good News』の終盤では、機内外での駆け引き、欺瞞、爆発の予告、政治家の逃走劇など、物語的には“山場”が複数用意されていた。反面、それが「心が震える」瞬間へと繋がったかというと、 セリフや演出、構図のどこかに“余白”が残っていた。 “解放された感情”より、“収束した状況”という印象が強かった。
たとえば、ハイジャック犯が“本当の目的”を明かし、乗客を解放するシーン。 そこには“命の危機”“政治の犠牲”“人間の尊厳”というテーマがあった。 しかしそれが涙となって噴き出すかというと、画面はどこか冷静で、 観客の心臓が“ドクン”と跳ねる瞬間をつくるには、 もう少し構成の振り幅が必要だったように思う。
さらに言えば、クライマックスにおける“敗北の香り”もあった。 終わった後、主人公たちが“賞賛されない”状況が描かれている。 これは作品のテーマとしては面白いし、観る人によっては深い余韻となる。だが一方で、「報われないなあ」「もう少し何かが欲しかった」と感じる観客の数も無視できない。
「終わったけれど、終わらせてもらえなかった感覚」
感情の高潮って、静けさを挟んでこそ生まれる。 緩やかな会話のあとに爆発的な叫びがくる。 だがこの映画では、“緩やか”と“爆発”の間に“間(ま)”が少なすぎた。 観る側は静けさを噛みしめる時間を持てず、 いきなり“片付いた結末”に導かれた印象を抱いた。
脚本的に言えば、クライマックスには“見せ場”“犠牲”“覚悟”があって、それが感情に刻まれる必要がある。 さらにその後、“その後”が見えると観客は「ああ、彼らは変わった」「自分も何かが変わった」と感じる。 『Good News』では、その“その後”の見せ方が控えめで、観終わったあとに観客が“自分の感じたこと”を整理する余地を残しすぎた。
もちろん、あんピコはこの“余白”にこそ魅力を感じる場面もある。 「完全に解答を出さない映画」には、観客が持ち帰る“問い”が生まれる。 ただ、その問いが観る人の“感情の起伏”と噛み合っていなければ、“つまらない”という評価になってしまうのだ。
結果として、レビューでは「構成・長さ・トーンに課題あり」という評価が見られました。“山場の盛り上げ”は存在するのに、“盛り上がった感”が残らない。 そのズレが、物語を終えたあとに「え、これで終わり?」という心のひっかかりを残した。
だからこそ、もしこの作品を観るなら―― 「見せ場は体験するものではなく、眺めるものだったんだ」と少し構えてから向き合ったら、 クライマックスの弱さすら“意図”として受け止められるかもしれない。
8. 本作の“難しさ”は何だったのか──余韻としての補足視点
この映画――Good News(2025)──を観終えて、 「つまらなかった」という言葉以上に残ったのは、むしろ“何を感じていいのか分からなかった”という余白だった。
| 作品の難しさ | 実話ベース+ブラックユーモア+サスペンスという三重構造の俯瞰的表現 |
|---|---|
| 観客の“温度”ズレ | 期待した緊迫・ヒーロー像・明快な正義ではなく、皮肉・曖昧・後味のモヤが残る構造 |
| 演出が突きつけた問い | 「ニュースとは何か」「国家とは何か」「信じるとは何か」など、観客に問う設計だが、答えは出さない |
| 受け取り方の差異 | サスペンス目的の視聴者には“物足りなさ”/風刺目的の視聴者には“鮮やかさ”があるという評価の分断 |
| 余白としての魅力 | 答えを出さない余地が、不快になり得るが、問いを持ち帰る余地ともなる |
映画が“問いを提示すること”を目的にしているならば、それ自体は価値がある。 だが“問いを持って帰らせるため”には、観客がその問いを呑み込む準備が必要だ。 この作品では、その“準備時間”が十分とは言えず、だからこそ「つまらなかった」という評価が生まれたのだと思う。
まず、本作の題材そのものが重い。 1970年のよど号ハイジャック事件という実話をモチーフに、さらには国家・飛行機・乗客という命と政治が交差する舞台を選んでいる。そのうえで、監督Byun Sung‑hyunは“ブラックコメディ”“風刺”という視点を積み重ねた。 つまり、観客が「ヒーローが現れて救う映画」「緊迫のクライマックスがある映画」と思って観ると、その構造に戸惑うわけである。
さらに加えて、“ジャンルの掛け合わせ”がこの映画の難易度を高めている。 サスペンス的な構成期待→重みある実話→笑える風刺。 このトライアングルをバランスよく回さないと、観客は「どこで笑えばいい?」「どこで息を止めればいい?」と迷ってしまう。 先ほど見てきた通り、序盤の緊迫感の立ち上がりも中盤の停滞も、キャラ描写の希薄さもこの“掛け合わせの難しさ”に起因している。
また、この映画が観客に投げかける問いの大きさも厄介だ。 ・ニュースとは、本当に“良い知らせ”を伝えるものか? ・国家が守る“命”の価値は、どこまで可視化できるのか? ・私たちは“真実”を観ていると信じていいのか? こうした問いを、映画は明確な答えとともに提示しない。 その余白が、観る者に“思考”の種を残す一方で、“結末を消化できなかった”という評価にも繋がる。
言い換えれば、映画として“完結”を求める人にとっては“不完全”で、 “思考の余白”を楽しむ人にとっては“余韻”になる。 レビュー評価が割れたのも、ここに理由があると私は思う。
ここで少し視点を戻してみる。 “つまらない”“退屈”という言葉は、時に“私にはこの設計を受け止める準備がなかった”という自己証明でもある。 この作品が提示するのは、 “刺激”ではなく“揺らぎ”であり、 “答え”ではなく“問い”であり、 “決着”ではなく“余韻”だった。
だからこそ──
「この映画を楽しめなかったのは、映画のせいではなく、私の準備値がひとつ低かったからかもしれない」
この言葉を胸に、もし再びこの作品を観るなら。 “救済”を期待せず、 “正義の到来”を願わず、 “問い続ける映画”として、少しだけ肩を預けてみてほしい。 そのとき、私たちは“つまらない”という言葉を超えて、 この映画の持っていた静かな問いに、触れられるかもしれない。
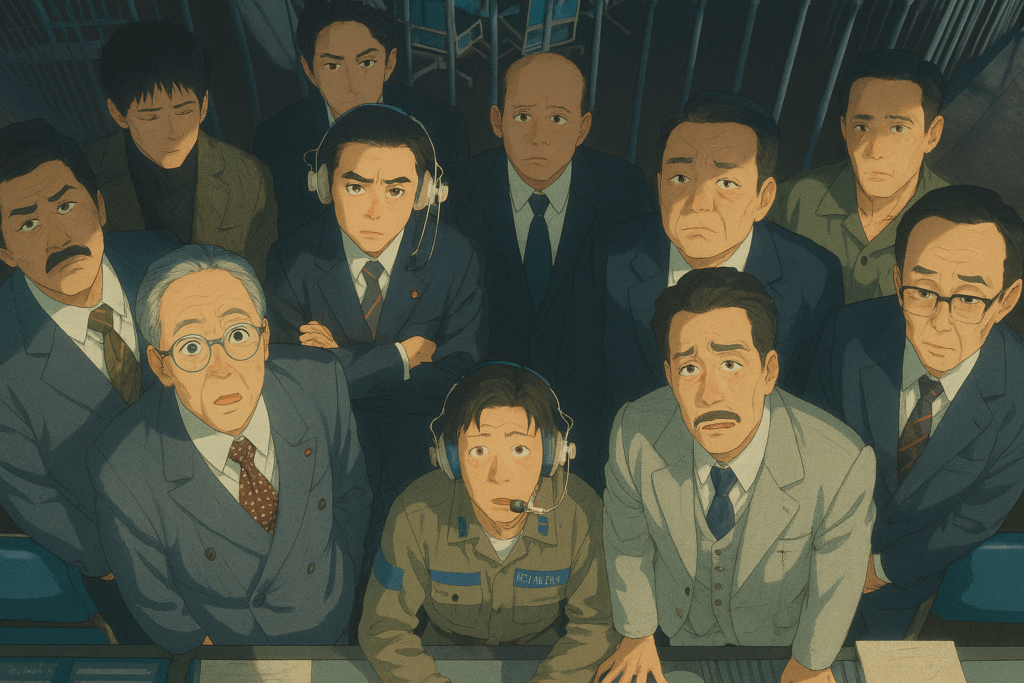
【画像はイメージです】
本記事で扱った内容まとめ一覧
| 見出し | 内容の要約 |
|---|---|
| 1. 緊迫感に欠けるサスペンス構成 | ハイジャックという題材に対し、緊張感が持続せず中盤から失速感が強い |
| 2. ジャンル混在によるトーンの迷走 | シリアス・コメディ・風刺が交錯し、作品としての一貫性が感じづらい |
| 3. 長尺による中だるみと冗長感 | 136分の上映時間が内容と釣り合わず、特に後半での停滞感が目立つ |
| 4. キャラクターに感情移入できない | 登場人物が多く目的も不明瞭で、誰にも共感できないという声が多数 |
| 5. 史実×フィクションのギャップ | 実話ベースに対しコメディ演出が強く、違和感や不快感に繋がるケースも |
| 6. ブラックユーモアの“刺さり方”に差 | 風刺やジョークの捉え方で評価が大きく割れた。合う人にはハマる |
| 7. 視聴前期待とのズレ | 政治劇や重厚なドラマを期待して観た層にとって“軽すぎた”との反応が多い |
| 8. 本作の“問い”と“余白” | 映画が与えたのは答えではなく違和感。問いを投げかける構造が分かれ目に |
まとめ:この映画が描いた“グッドニュース”は、誰のためのものだったのか
Netflix映画『グッドニュース』は、 1970年のよど号ハイジャック事件という、 現実に起きた“深刻”な出来事を題材にしながらも、 ブラックコメディと風刺で包み直すという、 とても難易度の高いアプローチをとった作品だった。
ジャンルを横断し、シリアスとユーモアを交差させ、 国家の思惑や個人の尊厳、報われなさや欺瞞を、 独自のリズムで描こうとした挑戦作。
でも、だからこそ──
観客の期待と“すれ違い”が生まれた。
ハイジャックと聞いて思い浮かべるのは、緊迫感、命のやり取り、あるいは正義と悪の対決。 けれど『グッドニュース』が見せたのは、 政治家たちの責任転嫁、歪んだ正義、皮肉と曖昧さ。 そして何より、「誰も完全にヒーローではない世界」だった。
その視点が、観る人の心を打つこともあれば、 「期待していたものと違った」という違和感になってしまうこともある。
レビュー評価「2.6/5」という数字には、 そうした“受け止めきれなさ”が、正直ににじんでいたように思う。
でも私は、こうも思う。
「映画がつまらなかった」のではなく、 「つまらないという言葉にしかできない感情だった」のかもしれない。
尖った演出。構成のぶれ。冗長さ。感情移入のしづらさ。 それらの欠点は、“作品としての完成度”を損なってしまった部分でもあり、 一方で、“何かを伝えたかった叫び”のかけらでもある。
きっとこの映画は、 「グッドニュース」とは言いながら、 誰かにとってはグッドじゃない現実を映し出していた。
だからこそ。
この作品が刺さらなかったあなたを、責めなくていい。 期待して裏切られたなら、その“違和感”ごと持ち帰ってほしい。 それはもしかすると、 「この国のニュースが、いつも誰かの“悪い知らせ”でできている」ことを、 皮肉なまでに映し出した鏡だったのかもしれないから。
『グッドニュース』関連記事をもっと読む
登場人物の考察や、物語の裏に隠された伏線、時代背景まで──『グッドニュース』の深層を掘り下げた記事を多数公開中。
気になるキャラクターやテーマごとの分析を、ぜひまとめてチェックしてみてください。
- Netflix配信映画『グッドニュース』が受けた低評価の具体的な要因を7項目で整理
- “ハイジャック”という緊迫ジャンルでありながら緊張感に欠けた構成の特徴
- コメディとサスペンスのジャンル融合が生んだ視聴者の戸惑い
- キャラクター描写の薄さと感情移入の難しさが評価を左右
- 実話ベースの題材に対する“風刺的演出”の違和感と批判
- 視聴者によって評価が割れるブラックユーモアの使い方
- クライマックスの弱さが「物語の終わり」より「余韻の薄さ」を感じさせた点
- “つまらない”という声の裏にある、表現とジャンルに対する期待のズレ



コメント