「終わらせたかったのに、終わらせられなかった」
『イカゲーム』シーズン3の結末を見たとき、私はそんなギフンの心の声が聞こえた気がした。
けれど、もし“もう1つのエンディング”が存在していたとしたら?
この記事では、Netflixが配信する大ヒットシリーズ『イカゲーム』の最終章=シーズン3に込められた葛藤と選択、監督が明かした幻の結末について深く掘り下げていきます。
【『イカゲーム』シーズン3 ティーザー予告編 – Netflix】
- Netflix『イカゲーム』シーズン3に存在した“もう1つのエンディング”の詳細と、なぜ採用されなかったか
- 主人公ギフンが“終わらせる者”として選んだ死の意味と、父としての葛藤
- プレイヤー222番の赤ん坊に託された未来の象徴性と、命の連鎖が描かれる構造
- “悪が勝つ”という結末が視聴者に突きつける現代社会の構造とテーマ
- 監督ファン・ドンヒョクの世界観と哲学に基づいた演出意図の深読み
- ギフンの死が物語としての「終わり」ではなく、“現実への問いかけ”であること
1. Netflix『イカゲーム』シーズン3の物語──ギフンの最終章
| 作品名 | Netflix『イカゲーム』シーズン3 |
| 主人公 | ソン・ギフン(演:イ・ジョンジェ) |
| 主なテーマ | 犠牲・終止符・意思継承・暴力の連鎖を断つ |
| 舞台 | 命を賭けたゲームと、それを観る富裕層たちの“娯楽空間” |
| ポイント | ギフンの自己犠牲/VIPとの対決/命の引き継ぎ/未完のラスト |
ギフンが立っていたのは、「終わらせる」ための場所じゃなかった。
「終わらせさせない」ために、誰かが笑って手を叩く場所だった。
Netflix『イカゲーム』シーズン3は、そんな“構造の残酷さ”をギフンの目線でえぐってくる。
第1シーズンで命を繋ぎ、第2シーズンで心を失い、そして最終章となるシーズン3で──ギフンは命そのものを「渡す」ことになる。
今作では、ギフンが「ゲームを止めたい」と願いながら、またその場に引き戻されるという構図が、皮肉というより呪いのように繰り返される。
あの場所に足を踏み入れるたび、ギフンは「生きること」と「正しく死ぬこと」の狭間に立たされる。
命が軽んじられる空間で、命に意味を与えようとする人間であり続けたのが、他ならぬ彼だった。
今回のゲームでは、プレイヤー222番の赤ん坊を救うという行動が物語の軸になる。
数字でしか呼ばれない参加者たちの中で、赤ん坊は“名前すら与えられていない命”の象徴として登場する。
「誰かが“ゲームの外”に命を持ち出さなきゃいけない」──
それが、ギフンの最後の役割だったのかもしれない。
ゲームの中でギフンがとった行動は、かつての彼からは考えられないほど迷いがなく、静かな決意に満ちている。
かつては娘との再会すら躊躇った男が、今は“知らない命”を背負って立っている。
これはもう、「勝つ/負ける」の物語じゃなかった。
「命を受け継ぐか、それとも絶やすか」
ギフンがゲームに託したものは、「終わり」ではなく「次の命の証明」だったのだと思う。
そして皮肉にも、ゲームの外側にいる富裕層のVIPたちが、最後に「悪の勝利」を手にしたようなラストが描かれる。
ギフンの死──それは、彼にとって“抵抗”であり“メッセージ”だった。けれどその意思すら、エンタメとして消費されてしまう構造の前では、無力に見える。
そう、これはエンディングじゃなくて、“反撃の入口”だったのかもしれない。
本当のゲームは、たぶんこの先、誰かが“あの赤ん坊”として引き継ぐ。
そして、そのとき私たちはまた、画面越しに問い返されるのだろう。
「君は、見てるだけの側にいたいのか?」
と。
シーズン3の物語は、ギフンの最期と引き換えに、“命のバトン”を差し出すようにして終わる。
観ている私たちにも、どこかそのバトンが渡されたような気がして、
一瞬だけ、画面の中と現実の境界が曖昧になる。
「終わった」はずなのに、胸の中で「まだ続いてる」
そんな感覚が、シーズン3のラストには詰まっていた。
2. 主人公ギフンが背負った“償い”という名のゲーム
| ギフンの役割 | 観察者から「壊す者」へ──ゲームの構造に踏み込む存在 |
| 彼の“償い”とは | 過去の選択、犠牲、そして傍観──生き残った者としての責任 |
| ギフンの進化 | 無力な参加者→怒りと覚悟を持った“プレイヤー外の戦士”へ |
ギフンは、もう“参加者”じゃなかった。
シーズン3の彼は、「壊しに来た人間」だった。
だけど──その手にあったのは武器じゃなくて、悔いと覚悟だった。
あのゲームにまた戻るって、どれだけの苦しみを飲み込んだんだろう。
思い出してみて。シーズン1、ギフンは「選ばれてしまった者」として、偶然のように参加させられた。
借金、疲弊、敗北……日常から逃げるようにして「ゲーム」に乗せられた彼は、一度“死にかけて”、生き残ってしまった。
でもそこからが、彼の“償い”の始まりだった。
シーズン2で、ギフンはゲームの外に戻りながらも、何も変えられなかった。
怒り、疑念、そして諦め。「何もできないまま、見ていた自分」に対する嫌悪感が、彼をまた“あの場所”に連れ戻した。
たぶんギフンは、もう一度死にに行ったんじゃない。
「何かを残すために、今度こそちゃんと終わらせに来た」んだ。
それは、自分の命を使ってでも訴えたかったこと──
「こんなゲームを、もう続けさせるな」という、死者側からの最後通告だったのかもしれない。
今回、ギフンは“壊すための戦略”を持っていた。
ただ生き残るんじゃない。構造そのものを終わらせる意志を持っていた。
彼が向き合った相手は、“ゲーム”ではなく、“ゲームを笑って見ている人間たち”だった。
VIPたち──富と暴力と快楽で膨らんだ者たちの前で、ギフンが投げたのは命という異物だった。
222番の赤ん坊を救うために、彼は命の重さを選び取った。
あの子はただの赤ん坊じゃない。ギフンの「償い」の証明だった。
誰かを救えなかった過去、背を向けた罪、傍観してしまった選択。
全部引き受けたうえで、それでも“誰かの命”を外へ出したギフンは、静かで確かな“意思”の人間になっていた。
最後まで笑わなかったギフンが、最も人間らしかった。
その無表情の奥にあったのは、たぶん怒りじゃなくて、祈りだった。
「もう、これで終わりにしようよ」
そう言いたかったのは、私たち自身だったのかもしれない。
ギフンの“償い”は、誰かの代わりに戦うことでも、過去を帳消しにすることでもない。
「命の重さを、次の誰かにちゃんと手渡す」ことだった。
そして彼はそれを、完璧じゃない形で──でも、誰よりもまっすぐにやってみせた。
だからこそ、この章は“終わり”じゃなくて、“始まり”なのかもしれない。
ギフンという人間が消えたあとに、確かに「意志」だけが残された。
それは次の誰かの“声にならない叫び”を、そっと背負ってくれるかもしれない。
3. プレイヤー222番の赤ん坊──命を繋ぐ選択の重さ
| 登場人物 | プレイヤー222番とその赤ん坊 |
| 赤ん坊の象徴性 | “命の連鎖” “意思の継承” “無垢の希望” |
| ギフンとの関係性 | 直接の血縁ではないが、“未来を預ける相手”として選ばれた存在 |
「守るべきものは、自分じゃない」
その決意が、ギフンのすべてを変えた。
プレイヤー222番の赤ん坊──
ただそこに“在った”命が、シーズン3でもっとも重く、もっとも希望だった。
あの子にはセリフも、名前も、意思すらない。
でもギフンは、その「声なき存在」に自分のすべてを託す決断をする。
この選択がなぜ尊いのか。それは、ギフンが「もう誰も守れなかった」人間だったから。
過去に、多くの命を見送り、見殺しにし、自分だけが残ってしまった男。
「誰かに託す」ことは、過去を忘れることじゃない。
“これまでの痛み”を、未来に生かすってことだ。
222番が遺した赤ん坊は、いわばゲームという構造が生み出した“最後の命”でもある。
システムの中で削られ、奪われ、諦めの果てに残された、小さな鼓動。
ギフンはその存在を、誰かの“救い”じゃなくて、自分の“答え”として抱きかかえた。
この物語において、「命を救う」なんて言葉はもう使えない。
「命を次に渡すかどうか」
それだけの判断でしか、未来は繋げなかった。
ギフンが自分の命と引き換えにその子をゲームの外に出した時、勝敗は消えた。
勝ち負けよりも、「残せるかどうか」だけが、この物語の意味だった。
そして皮肉にも、ギフンと赤ん坊は、同じ構造に名前を持たなかった。
“参加番号”という記号で扱われるプレイヤーたちと、
“まだ社会に存在を許されていない”命。
けれどその2つが出会い、手を繋いだとき、この作品は初めて「未来」という言葉を浮かび上がらせた。
それは、涙ではなく、静かな肯定だった。
誰かの“償い”によって、命が繋がった。
“誰かを守れなかった過去”を抱きしめたまま、ギフンはその命を託した。
この赤ん坊は、未来そのものじゃない。
でも、“あの世界に抗った者の証”として、たしかに命の意味を受け取った存在だった。
4. 最終回で示された“悪が勝つ”という衝撃のエンディング
| エンディングの特徴 | “悪”が勝ったように見える非カタルシス型結末 |
| ギフンの最期 | 命を差し出して終える、反撃にも似た犠牲 |
| 観客(VIP)の反応 | 命のやり取りすら娯楽として消費する無感情さ |
「悪が勝ったエンディングだった」──
その声に、何度も心がざわついた。
けれど、それは“敗北”だったんだろうか。
Netflix『イカゲーム』シーズン3の最終回。
ギフンは、赤ん坊の命と引き換えに、自らの命を差し出す。
誰にも称賛されることのない犠牲、拍手すら冷たく響く中で。
その光景を、富裕層のVIPたちはシャンパン片手に笑っていた。
ゲームは終わった──ように見えた。でもその構造は、微動だにしなかった。
それどころか、“誰かの犠牲すらもコンテンツ化する装置”が、なお力を増したように感じられた。
ギフンの死は、反撃じゃなかったの?
そう問いかけたくなるほど、エンディングは無表情だった。
だけどたぶん、このエンディングが“正解”だった。
「勧善懲悪」でも「勝者が生き残る物語」でもない。
この作品が描いたのは、“命の価値すら消費される世界”の残酷さ。
そしてその中で、ギフンという存在だけが、「それでも、命には意味がある」と叫んでいた。
でも──その声はかき消された。
あまりにも静かな最期に、誰も気づけなかった。
これは、「悪が勝った」のではない。
「悪の世界に、誰も勝てなかった」エンディング。
観客たちは笑う。
演者たちは死ぬ。
そしてゲームは、何事もなかったかのように次へ進む。
だけど、そのサイクルの中に、ひとつ“異物”が残された。
それが、ギフンの「命を投げ出す」という行動だった。
この世界では、勝つことよりも「壊れること」の方が、何倍も勇気がいる。
壊れたふりをして生き延びる人間が多い中で、壊れてでも訴えようとするギフンの姿は、明らかに浮いていた。
だからこそ、あのエンディングが突き刺さった。
「勝ちたかった」じゃなくて、「負け方に意味を持たせたかった」
──そんな気配が、最後のギフンに漂っていた。
これは、「希望が勝つ物語」ではない。
「希望を繋ぐために、誰かが負ける物語」だったのかもしれない。
5. 監督が語った“もう1つのエンディング”──ギフンが娘に会いに行く未来
| もう1つのエンディング | ギフンがゲームを終わらせ、アメリカで娘に再会する未来 |
| 監督の発言 | 「このストーリーのエンディングで伝えたいことは何かを考えた」 |
| 選ばれなかった理由 | 世界の現実に対して“より強いメッセージ”を残すため |
「もしかしたら、こんな終わり方もあったかもしれない」
そう言われた瞬間に、心が少しだけ泣いた。
ギフンがゲームを終わらせて、アメリカへ行き、娘に会う。
──それが、当初考えられていた“もう1つのエンディング”だった。
でもその選択肢は、実現しなかった。
代わりに、ギフンは命を差し出し、娘との未来を手放すことで、“世界への声”を選んだ。
「ギフンが幸せになる物語」は、
きっと誰かの“救い”になったかもしれない。
でも「ギフンが訴える物語」は、
誰かの“気づき”になる可能性があった。
ファン・ドンヒョク監督はこう語っている。
「世界中で起きていることを目撃するなかで、ギフンには、世界に(その死をもって)力強く、影響力のあるメッセージを送らせたかった」
言葉にすれば簡単だけど、それは“幸せを差し出す決断”だった。
ギフンにとっても、観る者にとっても。
たとえば──娘に会いに行くギフンを描いたら、それは「正しいエンディング」になったかもしれない。
過去を清算し、希望に向かって歩く。そんな“映画的満足感”が残ったかもしれない。
でも、あの世界では、“希望”もまた商品として売られていた。
その構造の中で、ギフンだけが「買われたくなかった」んじゃないかって、思う。
娘との再会は、ギフンの“願い”だった。
でも、あの命の引き換えでしか得られない未来なら、彼はたぶん、自分の願いを封印した。
それが、ギフンなりの「父親」という答えだったのかもしれない。
そして──あえてそのエンディングを選ばなかった監督もまた、この作品を“メッセージ”として残したかったのだろう。
ギフンが娘に会えない物語。
それは、愛する人に背を向けることで、誰かの未来に向き合った人間の記録だった。
残酷だったけど、リアルだった。
優しさが“個人の救済”じゃなく、“世界への怒り”になった瞬間だった。
この“もう1つのエンディング”は、選ばれなかったけど──
たしかにその余白があるからこそ、今のエンディングが切なくて、苦しくて、でも強かった。
きっとギフンの娘も、いつか知るのだろう。
父がいなくなった理由を、父が誰かの命に変わった事実を。
それを想像しただけで、心がきゅっと、痛くなる。
【『イカゲーム』シーズン3 予告編 – Netflix】
6. なぜ「ギフンの死」という結末を選んだのか?──監督の哲学と世界観
| 選択された結末 | ギフンの死=命を使ったメッセージの発信 |
| 監督の意図 | 「世界に対して強いメッセージを遺すため」 |
| 表現されたテーマ | 連鎖する暴力の中で“命を渡す”という選択 |
「なぜギフンを殺したのか」
──たぶん、この問いには簡単な答えなんてない。
でも、わざわざ“その痛み”を選んだ理由が、ちゃんとこの作品にはあった。
ファン・ドンヒョク監督は、世界の現状を語りながら、こう話している。
「世界は最悪の状況に向かっているように思えます。あらゆる形で、ますます悪化しているようです」
その上で、ギフンという存在に“象徴としての死”を託した。
ただ“勝ち抜いた者”で終わらせるのではなく、“メッセージを遺す者”として消えていく。
それはまるで──誰かの代わりに、世界に叫びを残す“犠牲の書き手”だった。
ギフンの死は、物語のカタルシスでも救済でもない。
「まだ終わっていない、これからも続いてしまう」
──その現実に、最後まで背を向けなかった人間の証明だった。
だからあの結末は、「悲しい」よりも「痛い」。
そしてその痛みこそが、観る者に深く刺さる。
ギフンは、世界を変えることができなかった。
でも──“変えようとした事実”だけが、最後に本物として残った。
命をかけて「変わらなかった世界」を証明すること。
それって、もしかしたら、いちばん過酷なラストかもしれない。
この物語には、わかりやすいヒーローも、喝采のラストもない。
あるのは、選ばなかった方の道に、深い意味を持たせようとした監督の執念。
ギフンが娘と再会しなかったのも、
ゲームが完全に終わらなかったのも、
あの世界の構造が無傷で残ったのも──全部、現実の“そのまま”に近づけたからだと思う。
希望じゃなくて、現実の「重さ」そのものを、ギフンに託した。
その哲学が、どこまでも苦しくて、どこまでも本気だった。
だからこそ、この物語は忘れられない。
「救いのなさ」が、むしろメッセージとして力を持ったから。
ギフンは世界を救えなかった。
でも、彼の死によって私たちは“見なかったことにしてきた現実”を突きつけられた。
それこそが──物語がやりたかったことなのかもしれない。
7. “ゲームを終わらせる者”の役目と象徴としてのギフン
| ギフンの立ち位置 | 「終わらせたい」と願った唯一の存在 |
| 象徴としての意味 | 命を使って“終わり”を可視化する役目 |
| ギフンの選択の重さ | 終わりを望みながら、終わらせきれなかった葛藤 |
「ゲームを終わらせたい」──
それは、ギフンがずっと願ってきたことだった。
けれど、その願いは“勝ちたい”とか“暴きたい”とは、どこか違っていた。
もっと根っこのほうにある、「こんな世界、続いてほしくない」という祈りのようなものだった。
シーズン3のギフンは、プレイヤーじゃなかった。
彼は「壊す側」に立つ覚悟をした人間だった。
でも──“終わらせる”って、ただ暴くことじゃない。
構造そのものを止めるには、「自分ごと壊れる」しかなかった。
ギフンが選んだのは、命を捧げるというかたちの「終止符」だった。
でもね、それは「世界が終わる」ことじゃない。
むしろ、「誰かが終わらせようとした事実が残る」という、ひとつの意思表示だった。
このゲームの世界では、すべてが“続くこと”を前提に作られてる。
参加者がいなくなっても、代わりが来る。
犠牲があっても、観客が笑えば続けられる。
──まるで、命が更新される仕組みみたいに。
だからこそ、「終わらせたい」と願ったギフンだけが異端だった。
命をリセットするのではなく、終わりを差し出すことで「これ以上の繰り返し」を止めたかった。
それって、ゲームの構造にとっては“バグ”でしかない。
でも、人間らしさって、そういう「非効率な感情」にこそあるんじゃないかと思った。
ギフンは、象徴だった。
続いていくループの中に「終わりたい」という意思を持ち込んだ唯一の存在。
その役目を果たすために、彼は“父親”であることも、“個人”であることも手放した。
「命の使い道」として、“終わりの象徴”になった。
そして皮肉にも、その死によってゲームはまた“ドラマ”として消費されていく。
──でも私は思うんだ。
たとえゲームが続いたとしても、ギフンの選択だけは、どこかの誰かの中で“止まって”残る。
その静けさは、連鎖を断ち切る音だった。
だからギフンは、ゲームを完全に終わらせられなかったかもしれない。
でも、「終わらせようとした人がいた」という事実は、確実に未来へ投げられた。
それって──とても人間らしい敗北で、
同時に、とても強い意思の証明だったと思う。
8. 世界はどこへ向かっているのか──シーズン3が投げかけた問い
| 作品が示した現実 | 命の軽視、暴力の連鎖、観る側の無関心 |
| 問いかけられたテーマ | 「あなたは、まだ見ているだけの側でいいのか?」 |
| 視聴者への暗黙のメッセージ | 感情を止めないで、傍観者にならないで、という呼びかけ |
『イカゲーム』シーズン3の最後に残されたのは、
物語じゃなかった。
それは、“問い”だった。
ギフンが命をかけて差し出した行動、
赤ん坊が渡された未来、
笑う観客たちの無関心──
そのすべてが、まるで「これは現実のどこかだ」と語りかけてくる。
この物語に出てくる“ゲーム”は、フィクションだけど、
「命が軽く扱われる世界」は、すでに私たちの現実にある。
ニュースで流れる災害や戦争。
SNSで拡散される暴力と正義の言い合い。
スクロールするだけで、誰かの苦しみを“コンテンツ”として消費する日常。
その中で、『イカゲーム』は私たちに向かって問いかける。
「あなたは、まだ“見ているだけ”でいられるのか?」
あの作品は、希望も救いもなかった。
でも、無関心ではいられない“違和感”だけは残してくれた。
たぶん、それこそがメッセージだったんだと思う。
涙も拍手もいらない。
ただ、「この世界、おかしくない?」って、誰かが呟ける空気を残すこと。
ギフンが示したのは、「正義」じゃない。
「それでも、こうしなきゃと思った」
という、“個人の小さな抵抗”だった。
その小さな声を拾うようにして、この物語は終わる。
──いや、終わらなかった。
だって、それは私たちの側に投げられた「続きを書くバトン」でもあったから。
この世界は、どこへ向かっているのか。
その問いを、ギフンの命が私たちに残した。
それは答えを求めてない。
でも、感じることを止めないで、って、たぶんそう言ってた。
観てしまった私たちに残されたのは、
「見なかったふりをしない」っていう、最初の一歩。
まとめ:終わらせる勇気、終われなかった想い──イカゲームが遺したもの
| ギフンの物語が残したもの | “終わらせたい”という感情と、“終われなかった現実”の矛盾 |
| 観る者に残る余韻 | 「これでよかったのか?」という問いと、見逃せなかった違和感 |
| イカゲームの意義 | 物語としての“結末”より、感情としての“継承”を選んだ作品 |
Netflix『イカゲーム』シーズン3の終わり方には、
拍手も涙もなかった。
ただそこには、静かで重たい“決意”が横たわっていた。
ギフンという男が、自分の命を“終わらせた”こと。
それは、単なる犠牲ではなく、「終わらせる勇気」を選んだ証だった。
けれど──世界は終わらなかった。
ゲームは止まらなかった。
誰かが笑い、誰かがまた参加する。
この矛盾は、たぶん今も続いている。
現実でも、画面の外でも。
だからこそ、この作品は「見たあとが、はじまり」なのだと思う。
ストーリーの結末よりも、
その後に残った“感情”こそが、本当の物語だった。
「終われなかった世界で、終わらせようとした人がいた」
──それだけでも、私は泣けた。
ギフンの死は、希望じゃなかった。
でも、諦めることをやめた人間の、最後の証明だった。
『イカゲーム』が教えてくれたのは、
“完璧な救い”なんてなくても、命を投げ出してまで伝えたいことがあるということ。
それはつまり、物語が終わった後も、感じ続ける覚悟を受け取ったということ。
観てしまった私たちに残されたのは、
一人ひとりが「どう在るか」を問われる時間。
ギフンの声なきメッセージが、
どこかの誰かの、最初の小さな“違和感”になりますように。
イカゲームの伏線、感情、あの沈黙の意味──
もっと深く知りたい人へ。
- Netflix『イカゲーム』シーズン3には、ギフンが生き残る“もう1つのエンディング”が存在した
- 最終的に選ばれたのは、ギフンが命を投げ出して“終わらせる者”となる重厚な結末
- プレイヤー222番の赤ん坊に託された“命の連鎖”が、次世代への伏線として描かれる
- “悪が勝つ”という衝撃的なラストが、現実の社会構造や暴力の連鎖を象徴
- 監督ファン・ドンヒョクがギフンの死を選んだ理由に、世界への強いメッセージが込められていた
- ギフンは希望ではなく“違和感”を残し、物語の続きを私たちに託した
- 『イカゲーム』はストーリーの終わりではなく、“感情の継承”という新たな問いを提示した
【『イカゲーム』シーズン3 最終ゲーム 予告編 – Netflix】

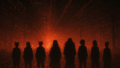

コメント