「上弦の鬼って、結局どうなったんだっけ?」──そんなふとした疑問に、正面から答えるまとめを作りました。この記事では、アニメ『鬼滅の刃』に登場する上弦の鬼たちの“最後の瞬間”に焦点を当て、誰が倒したのか、誰が倒されたのか、そして生き残った者は誰か──戦いの全容を物語順に追いながら整理していきます。
【アニメ「鬼滅の刃」プロモーションリール 2025】
- 鬼滅の刃に登場する上弦の鬼が誰によって倒されたのかを詳細に把握できる
- 上弦の鬼たちの“最期の瞬間”に秘められた過去や感情が読み解ける
- 無限城編へとつながる伏線と、生き残った上弦の鬼の有無が明確になる
1. 上弦の鬼とは?──鬼舞辻無惨直属の最強精鋭たち
| 上弦の数字 | 鬼の名前 | 初登場 | 特徴・能力 |
|---|---|---|---|
| 壱 | 黒死牟 | 無限城会議 | 元・剣士。月の呼吸を操る。悲しき“兄”の業 |
| 弐 | 童磨 | 遊郭編ラスト〜 | 氷とカルト的信仰。狂気と無垢の二面性 |
| 参 | 猗窩座 | 無限列車編 | 武を極めし男。煉獄との名勝負は語り草 |
| 肆 | 半天狗 | 刀鍛冶の里編 | 怯えと狂気の分裂体。弱者を装う嘘 |
| 伍 | 玉壺 | 刀鍛冶の里編 | 芸術家気取りの異形。水を操る戦闘スタイル |
| 陸 | 妓夫太郎&堕姫 | 遊郭編 | 兄妹一対の鬼。嫉妬と執着の象徴 |
鬼滅の刃の“闇”を背負う存在──それが「上弦の鬼」。彼らは単なる敵キャラじゃない。どの鬼も、どこかに“人だった頃の悲しみ”を背負っていて、それを“強さ”で封じ込めたまま戦っていた。
鬼舞辻無惨の直属である彼らは、鬼の中でも最上位──いわば“選ばれしエリート”。ただの力比べじゃない。感情も、過去も、歪んだ救いも、すべてを武器にしていた。
たとえば、黒死牟──彼は「壱」の数字を持つが、戦う動機は“強さへの執着”という名の呪いだった。剣士としての美学ではなく、誰よりも長く、誰よりも強く、生きることしか考えていなかった。
童磨はどうだろう。見た目は無邪気で言葉も柔らかいけど、その本質は“空虚”だった。信者を救うフリをして、自分の中の空っぽを埋めようとしていたように見える。
猗窩座は、強さに純粋だった。でもその純粋さが、逆に“救えなかった後悔”を閉じ込めてしまった。彼は煉獄を殺し、炭治郎たちを苦しめた。それでも、どこかで「誰かを守りたかった」って叫んでた気がする。
他の鬼たちも同じ。半天狗は「弱さの仮面」に隠れて暴れ続け、玉壺は「芸術」の名のもとに殺戮を楽しみ、妓夫太郎と堕姫は“生きているだけで否定された人生”を、恨みという武器に変えた。
でもね、ただの“悪”として終われなかったのが、鬼滅の物語の優しさだと思う。
“どの鬼も、かつては人間だった。
そして誰もが、人間だった頃の気持ちを、捨てきれずにいた──”
上弦の鬼という存在は、戦闘力だけで語るには惜しい。むしろ、「どんな痛みを抱えていたか」で読み解くほうが、この物語に深く触れられる気がしている。
だからこそ、この記事ではそれぞれの鬼が「どんな最期を迎え、誰がその手で止めたのか」を順に見ていきたい。
彼らの“終わり”には、ちゃんと意味があった気がするから。
2. 上弦の陸・堕姫と妓夫太郎の最期|炭治郎・宇髄たちの死闘
| 鬼の名前 | 倒した人物 | 舞台 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| 堕姫 | 善逸&伊之助 | 遊郭・京極屋 | 頚斬りの同時成功が鍵 |
| 妓夫太郎 | 炭治郎&宇髄天元 | 遊郭・地中戦闘 | 猛毒&血鎌の連撃に死闘 |
「人は、愛された分しか強くなれない」──この言葉が、あの兄妹には届かなかったのかもしれない。
上弦の陸・堕姫と妓夫太郎。ふたりでひとつ。頚を斬られても死なないその構造は、まさに“依存”そのものだった。
舞台は遊郭・吉原。その華やかさの裏に、絶望と恨みが沈んでいた。
堕姫は、美しさを武器に、人間を見下しながら生きてきた。だけどその根っこには、ずっと「認められたい」という幼い願いがあったように見える。
妓夫太郎は、その妹を“守るためにしか存在していない”兄だった。彼の言葉、行動、すべてが「自分を犠牲にしても妹だけは守りたい」という歪んだ愛で構成されていた。
この戦いは、ただの鬼退治じゃない。“依存”と“自立”のぶつかり合いだったと思う。
宇髄天元は、音柱としての戦い方以上に、「命を賭ける覚悟」を見せた。猛毒に蝕まれながら、なお“派手に”命を燃やす姿は、まるで「生き様を音で響かせる」かのようだった。
炭治郎はどうだったか? 彼の戦い方は、剣技以上に“祈り”に近かった。
「どうか、もう誰も死なないで──」
そんな願いが、あの刀には宿っていた気がする。
戦闘終盤、堕姫と妓夫太郎の頚を、善逸・伊之助・炭治郎たちが“ほぼ同時に斬る”という奇跡が起きる。
あの瞬間、剣の軌道は「命を奪うため」じゃなくて、「誰かを止めるため」のものだったように感じた。
斬られたあと、兄妹が最後に言い争うシーン──あれは鬼としての強がりでも、人間としての感傷でもなく、“もう戻れない場所への後悔”だったんじゃないかな。
だけど最後の最後に、妓夫太郎が堕姫を背負って冥府へ歩いていく場面で、物語は静かに優しさを取り戻す。
“二人で地獄へ堕ちる”というその描写は、絶望でありながら、確かに「一緒に生きた」という証でもあった。
鬼滅の刃の中で、この兄妹のエピソードが際立つのは、「悲しみが強さの根源になる」という構図を、初めて真正面から描いたからだと思う。
倒すことが救いだったのか。
救えなかったことが罪なのか。
その問いは、鬼を斬った側にも、深く突き刺さっていた気がする。
3. 上弦の伍・玉壺と上弦の肆・半天狗──刀鍛冶の里での二重戦線
| 鬼の名前 | 倒した人物 | 戦場 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 玉壺(ぎょっこ) | 時透無一郎 | 刀鍛冶の里 | 壺と水の異形芸術家、狂気の創造主 |
| 半天狗 | 炭治郎・禰豆子・玄弥・不死川玄弥 | 刀鍛冶の里 | 分裂と感情体の化け物、弱者を装う怨霊 |
ふたりの上弦が、同時に襲いかかる──そんな“詰み”のような状況が訪れたのが、刀鍛冶の里編だった。
玉壺と半天狗。このふたり、共通点があるとすれば「歪んだ自己肯定感」だったように思う。
まずは玉壺。壺から現れ、魚を操り、水を歪ませるその姿は、もはや生物ではなく“芸術を名乗る災厄”。
彼は、「人を殺す=美しい」と語る。その言葉にゾッとしつつも、“美しさにしか価値を見出せなかった過去”が滲んでいた気がする。
対峙したのは、霞柱・時透無一郎。無表情で冷静な彼が、初めて“自我”を取り戻すまでのプロセス──それがこの戦いの本当の意味だったのかもしれない。
「なんでだろう、思い出せない。
でも、あの子が笑ってくれた気がする」
無一郎は記憶を取り戻し、自分が“何のために剣を振るうのか”を、やっと思い出した。
その結果としての、玉壺への勝利。鬼にとっての“芸術”を、人の“想い”が上書きした瞬間だった。
一方、半天狗の戦いは、もっと混沌としていた。
彼の能力は分裂──怒・哀・楽・喜…いくつもの感情に分かれて戦うその姿は、“感情の責任を取らない大人”のようだった。
怯えて震えながら、実は裏で人を殺している──それはまさに“被害者の皮をかぶった加害者”。
炭治郎・禰豆子・玄弥たちの連携によって、ついにその“本体”にたどり着く。
でもここで描かれたのは、単なる物理的勝利ではなく、「誰の感情を信じるか」というテーマだったように思う。
禰豆子が、自分の命を投げ出すような行動をとったとき、炭治郎は一瞬迷う。でも、その迷いを“誰かを信じる強さ”が上回った。
「禰豆子が笑った。
泣きそうな笑顔で、『行って』って目で言った──」
半天狗の“最後の嘘”を見抜き、炭治郎が刀を振るったその一太刀には、全員の信頼と想いが込められていた。
このエピソードの怖さは、“感情が切り離されると、どれだけ歪むか”を教えてくれること。
そして、“感情ごと抱きしめる強さ”こそが、鬼を超えるために必要なものだったということ。
ふたりの上弦を同時に討ったこの戦い。勝ったのは、剣の強さじゃない。
「想いをつなぐ力」が、鬼の過去を超えたんだと思う。
4. 上弦の参・猗窩座の決着と“救いなき戦い”の結末
| 鬼の名前 | 倒した人物 | 戦場 | 戦いの決着点 |
|---|---|---|---|
| 猗窩座 | 炭治郎・義勇/自己崩壊 | 無限城~雪原の記憶 | 過去の記憶が自我を壊した |
“強くなければ生きられない。優しくなければ生きる意味がない”──猗窩座という鬼の中には、その矛盾が渦を巻いていた。
無限列車編で煉獄杏寿郎を討った張本人。あの戦いの夜、炎と武が交差した場所で、彼は人間だった頃の想いを完全に封印した。
彼は“強さ”を極めることに執着した鬼だ。武術、闘気、殺意──どこまでも純粋な闘争本能。だけどその裏には、どこか壊れた「救いたかった記憶」が見え隠れしていた。
無限城で再び登場した彼は、炭治郎と義勇に襲いかかる。かつて煉獄を殺した男──それが“個人的な復讐”で終わらないのが、鬼滅の物語の深さだった。
義勇は、水の呼吸で冷静に対峙し、炭治郎は“かつての炎”を背負って戦った。
「杏寿郎さんが笑ってくれた。
“君ならできる”って、あの時、確かに言ってくれた──」
猗窩座の動きは、圧倒的だった。空間識覚、連撃、破壊殺…。だけど、どこか“自滅的”だった。
彼は、戦いの中で「何か」を思い出していた。
そしてその“思い出すこと”が、彼にとっての“死”だった。
過去──狛治という名前。病弱だった最愛の人。守れなかった命。自分が鬼になる前の、「誰かのために強くなろうとした少年の記憶」。
その記憶が戻った瞬間、彼は自壊を始める。
“こんな戦い、したくなかった”
“本当は誰とも殺し合いたくなかった”
剣ではなく、“記憶”が彼を倒した。
ラスト、猗窩座の身体は自ら崩れ、消えていく。
戦闘不能にしたのは炭治郎と義勇だったけれど、本当に彼を“終わらせた”のは、自分の中の「愛された記憶」だった。
この戦いは勝利じゃない。
誰も喜んでない。ただ、“間に合わなかった再会”に、涙が零れただけ。
鬼としての彼を倒すために必要だったのは、剣ではなく、過去に向き合うことだった。
そしてそれは、鬼になってまで守りたかった「強さ」の正体が、実は“誰かを愛すること”だったという、あまりにも皮肉な真実だったのかもしれない。
(チラッと観て休憩)【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』特報】
5. 上弦の弐・童磨の敗北と“信仰”の崩壊──しのぶ&カナヲの逆転劇
| 鬼の名前 | 倒した人物 | 戦場 | 戦闘のキーポイント |
|---|---|---|---|
| 童磨 | 栗花落カナヲ&嘴平伊之助(+しのぶの毒) | 無限城・氷の間 | 長期毒攻撃+トドメの斬撃 |
童磨は“空っぽな信仰”を抱えていた鬼だった。
笑顔で人を殺し、「救ってあげるよ」と優しく語るその姿は、誰よりも冷酷で、誰よりも哀しかった。
信者を喰らい、愛という言葉を都合よく使い、自分の心には“何も感じない”と断言する。
そんな彼の言葉を、唯一許さなかったのが──胡蝶しのぶ。
姉・カナエを殺された想い。正義でも復讐でもない、“感情の叫び”が、しのぶを童磨との戦場へ導いた。
でも、しのぶは肉体的には彼を圧倒できなかった。
それでも彼女は、「毒」という方法で“時間ごと”勝とうとした。
自らを“毒の塊”にすることで、童磨に「食われること」さえも作戦に組み込んだしのぶ。
この作戦に、どれだけの怒りと覚悟が込められていたか──想像するだけで苦しくなる。
「もう、どうなってもいいと思った。
ただ、あの子たちが生きてくれたら──」
そして現れる、栗花落カナヲ。感情を表に出すことができなかった彼女が、しのぶの“命のバトン”を受け取り、本当の自分を解放する。
童磨が「愛」を語るたびに、その言葉は“うすら寒いもの”として響いた。
けれど、カナヲの剣が届いた瞬間。
その冷笑も、余裕も、氷のように崩れた。
童磨は、最後の瞬間まで“死”を理解していなかった。
だけど、しのぶの面影を見た瞬間、ほんの少しだけ「何かを感じた」ような描写があった。
「……君、怒ってたんだね。
ああ、そうか。愛って、そういうことかも──」
愛されなかった童磨が、ようやく“愛の形”を知る時。
それは、自分を壊す毒として、心に降りかかった。
勝利ではない。
この戦いも、やっぱり“哀しさの上に積み上がった終焉”だった。
しのぶの死は、大きな痛みだったけれど。
カナヲの剣は、“愛された人の想いが剣になる”という物語の象徴になった。
童磨を倒すために必要だったのは、技術でも力でもなく──
「怒りと哀しみを言葉にできないまま戦った、誰かの気持ち」だったのかもしれない。
6. 上弦の壱・黒死牟の最期|月の呼吸と霞の剣の果てに
| 鬼の名前 | 倒した人物 | 戦場 | 戦いの決着点 |
|---|---|---|---|
| 黒死牟 | 不死川実弥・時透無一郎・悲鳴嶼行冥・玄弥(連携) | 無限城・深層部 | 肉体崩壊と“弟への未練” |
「人の“終わり”って、どこから始まるんだろう──」
そう思わせたのが、上弦の壱・黒死牟の戦いだった。
彼の本名は“継国巌勝(つぎくに・みちかつ)”。
かつて“日の呼吸”を使いこなした剣士・継国縁壱の実の兄。
弟が天才すぎた。
それだけで人生が狂ってしまった男──それが黒死牟の正体だった。
彼は“鬼”になってもなお、「弟を越えたい」と願っていた。
でもその執念が、何百年にも渡って彼を“化け物”に変えていった。
戦場は、無限城の深層。
岩柱・悲鳴嶼、風柱・不死川、そして霞柱・時透という“柱3名”が連携し、
さらに玄弥の血鬼術が支援するという、まさに総力戦。
黒死牟は、技もスピードも桁違いだった。
剣から無数の斬撃を生み出し、月のように満ち欠ける構えで全員を圧倒した。
でも──
その技の根源には、ただ一つの思いがあった。
「どうして、あの男だけが“完璧”なのだ」
「どうして、俺だけが“凡人”なのだ」
彼の刃は、弟への羨望と、自分自身への呪いでできていた。
戦いの中で、無一郎は“命を削る決意”を見せ、玄弥は“鬼の力さえ味方にする”という覚悟で挑んだ。
不死川の“譲れない怒り”と、悲鳴嶼の“慈悲にも似た無慈悲”。
そのすべてが、“弟を超えられなかった男”を削り取っていった。
やがて黒死牟の身体は、自らの“理想”に耐えきれず崩壊する。
そこにあったのは──「弟のようになりたかった」という、涙にもならない後悔。
彼は死の間際、鏡のように弟の姿を思い出し、こう問う。
「俺は…あの男のようになれたのか?」
答えは、たぶん──「なれなかった」
でも、それでも。
誰かを追いかけ続けた人生が、間違っていたとは思えない。
黒死牟という存在は、強さと執着が紙一重であることを教えてくれた。
その刃は、他人に向けたものじゃなかった。
ずっと、自分自身に向けられていた気がする。
7. 生き残った上弦はいたのか?──無限城編へとつながる伏線
| 上弦の鬼 | 最期を迎えた章 | 倒された人物 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 陸:妓夫太郎&堕姫 | 遊郭編 | 炭治郎・宇髄・善逸・伊之助 | 頸同時斬りが鍵 |
| 伍:玉壺 | 刀鍛冶の里編 | 時透無一郎 | 毒の無効化・自我覚醒が鍵 |
| 肆:半天狗 | 刀鍛冶の里編 | 炭治郎・禰豆子・玄弥 | 感情体撃破後の本体特定が勝因 |
| 参:猗窩座 | 無限城編 | 炭治郎・義勇 | 自己崩壊が決定打 |
| 弐:童磨 | 無限城編 | カナヲ・伊之助(+しのぶ) | 毒の蓄積が鍵 |
| 壱:黒死牟 | 無限城編 | 柱連携(無一郎ら) | 自己崩壊・記憶の解放 |
上弦の鬼たちは、全員が倒された──確かにそう言える。
でもその“倒された”という言葉の中には、剣の勝利だけじゃない。
「心がほどけた」とき、人は“終わり”を迎える。そんな感覚に近い。
妓夫太郎と堕姫は、一緒に堕ちていくことで“孤独”から解放された。
玉壺は、自らが否定した“感情”に圧倒されて崩れ、
半天狗は、弱者のふりをした嘘が剥がれ落ちた瞬間に、静かに終わっていった。
猗窩座は、戦いの中で“自分自身”を思い出したとき、もはや鬼ではいられなかった。
童磨は、「空っぽだった自分」が、愛という感情に触れた瞬間、初めて壊れた。
黒死牟に至っては、弟という存在に“追いつけなかった自分”を認めたことで、すべてが崩壊した。
だから──
生き残った上弦の鬼は、いない。
肉体が消えたからではなく、“人だった頃の感情”に再会してしまったから。
そしてこれは、次の章=無限城編・最終決戦への、静かな合図だった。
「鬼は人間だった。
そして、人間は感情を捨てきれない。」
無限城編では、鬼舞辻無惨がついに動く。
でもその前に、“感情を宿した鬼たち”との対話が必要だった。
すべては、ここからが本番。
「鬼とは何か」ではなく、「人とは何か」が問われる戦いが始まる。
まとめ:鬼の最期に込められた“人間の記憶”──その戦いは、何を遺したのか
「鬼を倒す物語」だと思っていた。
でも、それはきっと“人間の感情を解きほぐしていく物語”だったのかもしれない。
上弦の鬼たちは、それぞれに強く、恐ろしく、憎しみに満ちていた。
けれどその根っこには、いつも“孤独”と“後悔”が埋まっていた。
誰かを守れなかったこと。
誰かに愛されなかったこと。
誰かを超えたかったけれど、叶わなかったこと。
鬼になっても、人だった頃の“痛み”は消えなかった。
だからこそ、その最期がただの“討伐”で終わらなかったのだと思う。
炭治郎たちが斬っていたのは、鬼の首ではなく、
過去の呪いの連鎖だったのかもしれない。
その中には、自分たちの“心”さえ映っていた。
「鬼を憎む気持ちと、鬼にも涙を感じてしまう気持ち」
「どちらかだけを選べないからこそ、この物語を好きになった」
この記事では、鬼滅の刃に登場した「上弦の鬼」たちの最後に焦点を当て、
誰が倒され、誰が倒したのか。そしてそこにどんな感情があったのかを見つめ直してきた。
もしあなたの中にも、「嫌いになりきれない鬼」がいたなら、
それはきっと、あなたの中にも“名前のない感情”が眠っているからだ。
完璧じゃなかった彼らの戦いが、
どこかで自分の不完全さと重なる。
──そんなふうに、静かに共鳴してくれる物語だった。
上弦の鬼ひとりひとりの背景や戦い、感情に迫る特集を、こちらのカテゴリーでじっくりまとめています。
彼らの“しくじり”と“哀しみ”をもっと深く読み解きたい人は、ぜひこちらも覗いてみてください。
- 鬼滅の刃に登場する上弦の鬼6体の最期とその倒され方を網羅的に理解できる
- 各戦いで活躍した剣士たちと、それぞれの感情や覚悟が明らかになる
- 倒された鬼たちが抱えていた“過去”と“未練”がドラマとして浮かび上がる
- 無限城編への伏線としての意味、そして「鬼とは何か」という問いが深掘りされる
- 感情の物語としての鬼滅の刃の魅力と、人間の記憶としての“鬼の最期”を再確認できる
【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』特報第2弾】

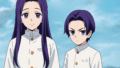

コメント