「鬼滅の刃」と「鬼人幻燈抄」──一部で“似てる”と言われるこの二作品。ネット上では「どっちが先?」「パクリなの?」という声も見かけます。でも本当にそうだろうか。この記事では、物語の構造や設定、時代背景などを丁寧に比べながら、表面の“似てる”を超えて、その中身に迫ってみようと思います。
【TVアニメ「鬼人幻燈抄」ティザーPV】
- 「鬼滅の刃」と「鬼人幻燈抄」が“似てる”とされる主な共通点とその理由
- 両作品の世界観・ストーリー構造・主人公の動機に潜む決定的な違い
- パクリ疑惑が生まれた背景と、“印象の重なり”が起きた心理的要因
- 和風ファンタジー作品における「鬼」と「妖」の象徴的意味のちがい
- ビジュアルや衣装デザインに込められた感情表現の考察
- 1. 「鬼滅の刃」とは──大正時代を舞台にした鬼と人の戦い
- 2. 「鬼人幻燈抄」とは──江戸末期を生きる少年と妖の物語
- 3. 発表時期はどっちが先?連載開始日の時系列比較
- 4. 舞台設定と時代背景──“和風×鬼”の共通点と違い
- 5. 主人公の旅と動機──鬼に家族を奪われた少年たち
- 6. 鬼や妖の描き方──能力・存在意義・世界観の違い
- 7. キャラクターデザインや衣装の比較──視覚的な共通点とは?
- 8. ストーリー構造の類似点と分岐点──「使命」と「救済」のちがい
- 9. 「似てる」「パクリ」と言われた理由とは?構成と印象の考察
- 10. 鬼と妖、それぞれの“救えなさ”──人間ではないものをどう描いたか
- まとめ:似てるようで、似てなかった──“鬼滅”と“幻燈抄”を正しく読み解く
1. 「鬼滅の刃」とは──大正時代を舞台にした鬼と人の戦い
| 作品名 | 鬼滅の刃(きめつのやいば) |
|---|---|
| 連載期間 | 2016年2月~2020年5月(週刊少年ジャンプ) |
| 時代設定 | 大正時代の日本 |
| 主要テーマ | 鬼との戦い/家族愛/喪失と再生 |
| 主人公 | 竈門炭治郎(かまどたんじろう) |
「鬼滅の刃」を語るとき、まず“匂い”がある物語だなって思う。薪の香り、濡れた草の匂い、血のにおい。大正という時代が持つ湿度や陰りまで、画面越しに感じてしまうほど。
主人公の竈門炭治郎は、炭を売って家族を支えるまっすぐな少年。でも、その日常は一夜で崩れ落ちる。鬼に家族を皆殺しにされ、唯一生き残った妹・禰豆子は“鬼”に変わってしまう。
たった一人を守りたくて、たったひとつの願いを胸に、彼は剣を握った。
でも、この物語が“ただの復讐譚”に終わらなかったのは、鬼にすら“涙の理由”があるという構造にあったと思う。
敵を倒すことで感動させる作品はたくさんある。でも、鬼滅の刃は違った。
「どうしてこんなふうになってしまったのか」――鬼の過去に触れるたび、観る者は涙の意味を塗り替えられていく。
鬼殺隊の剣士たちの戦いは、技の派手さ以上に、“命をかける理由”の重みで私たちの胸を打つ。
善逸の震える剣、伊之助の暴れる仮面の下にある孤独、煉獄さんのまっすぐすぎる覚悟。
それぞれが自分の“しくじり”や“喪失”を抱えながら、誰かのために立ち続けていた。
だからこそ、「鬼滅の刃」はファンタジーでありながら、どこか現実の“あの頃の自分”を映してくれる気がする。
戦いの中に描かれたのは、たぶん「うまく泣けなかった人たち」の再生の物語だった。
そして炭治郎が走るたび、「優しさって、こんなに強いんだ」って、私は何度でも思わされる。
2. 「鬼人幻燈抄」とは──江戸末期を生きる少年と妖の物語
| 作品名 | 鬼人幻燈抄(きじんげんとうしょう) |
|---|---|
| 連載期間 | 2016年~(ジャンプSQ.連載) |
| 時代設定 | 幕末・江戸末期 |
| 主要テーマ | 妖との共存/記憶と再生/人の本性 |
| 主人公 | 広瀬旭(ひろせあさひ) |
もしも「鬼滅の刃」が剣戟と血煙の中で愛を叫ぶ物語なら、「鬼人幻燈抄」は、記憶と心を辿る光のフィルムみたいな作品かもしれない。
舞台は幕末。動乱と混乱の空気が流れる江戸の片隅で、ひとりの少年・旭(あさひ)が、“鬼”ならぬ“妖”と関わる不思議な世界に足を踏み入れていく。
この作品の特徴は、「派手さ」ではなく「余白」。 登場人物たちの間に流れる空気、言葉にならない気持ち、忘れかけた風景。それらがまるで古い映写機のフィルムのように、静かに、でも確かに胸に焼きついてくる。
旭は、心にぽっかりと穴をあけた少年だ。 人を信じきれず、でも信じたいと思っていて、 過去を忘れようとしながら、忘れたくない何かを必死に握っている。
そんな彼が出会うのは、“人ならざるもの”たち。 怖い存在のはずなのに、なぜか彼らは「人間よりも人間くさい」言葉を吐いたりする。
この作品が描く“妖”は、敵じゃない。 排除の対象でもなく、時に恐れられ、時に愛される、“生き物”としての在り方が描かれている。
だから「鬼人幻燈抄」を読んでいると、ふと不安になる。 「人間って、どこまでが人間なんだろう?」 「自分は、どんな“妖”を心の中に飼っているんだろう?」
答えは出ない。でも、その問いの前で立ち尽くす時間こそが、きっとこの作品の醍醐味なんだと思う。
3. 発表時期はどっちが先?連載開始日の時系列比較
| 作品名 | 連載開始日 | 掲載誌 |
|---|---|---|
| 鬼滅の刃 | 2016年2月15日(週刊少年ジャンプ第11号) | 週刊少年ジャンプ |
| 鬼人幻燈抄 | 2016年4月27日発売(ジャンプSQ.5月号) | ジャンプSQ. |
「連載開始日が近かったから、片方がもう片方を真似したんじゃ…?」そう思う気持ち、すごくわかる。 でも、この“たった2ヶ月”には、世界を変えてしまうほどの重みがあるんだと、私は思う。
炭治郎が初めてジャンプのページで出会ったのは、2月15日。 その時点で編集部の期待、担当との会話、作家の構想、すでに動き始めていた。
一方、旭が幕末の影と出会う物語が世に出たのは、4月27日。 でもその作品も、もちろん構想は絵に描くよりずっと前から動いていたはず。
“世に出た日”は記号になるけれど、そこに至るまでの過程は見えない。 企画書を書いた日、キャラを描き込んだ夜、テーマを探し続けた時間―― それらは雑誌をめくる日の前に、ひとつひとつ積み重なっていく。
だから私は思う。発表日だけで「どっちが本物か」を決めるのは、物語への敬意を怠ることだって。
でも、時系列が違えば、読者の印象も違って当然だ。
- 先に出た作品は、その世界観の“匂い”を最初に感じさせる。
- 後から出た作品は、先行作品との比較を避けられない。
それが偶然でも、タイミングが重なってしまったからこそ、印象として「似てる」と思わせてしまう。
私は、どちらかが先というだけで“真似”と呼ばれるのは悲しい。
なぜなら、たとえば新聞で“鬼”を扱う特集が同じ時期にあったら、どちらも記事に触発されてテーマを検討するかもしれない。
それは“パクリ”じゃなく、“同じ時代の空気から生まれた声”なんじゃないかと、私は思うのです。
もちろん、企画の着手はもっと前だろう。 でも“世に出た日”―それは誕生日みたいなもの。そこから読者の記憶は始まる。
だからこそ、私は問いかけたい。
「似ていると感じるのは、いつ出会ったかよりも、
どんな“心の響き”を感じたか、じゃないだろうか?」
そう、“どっちが先か”を競うよりも、“どちらが私の中に何を残したか”のほうが、ずっと大事なんじゃないかなと。
そして改めて思います。二つの作品は、タイムライン上では近かったかもしれない。 でもその距離感が、比較も偏見も生む“きっかけ”であって、本質じゃない。
出発点だけじゃなく、心に響くまでの距離感を大切に感じたい。
4. 舞台設定と時代背景──“和風×鬼”の共通点と違い
| 鬼滅の刃 | 鬼人幻燈抄 |
|---|---|
| 大正時代(1912–1926年) 都会と山村が共存する“文明の狭間”の日本 電力や洋館、街灯がちらつく中に残る古い格子戸 |
幕末〜江戸末期(1850年代頃) 鎖国のゆらぎ、人々の不安と期待が混じる空気 古い木戸の軋み、提灯のゆらめき、夜の闇に紛れる影 |
| 炭治郎たちが徒歩で縦断する“旅の構図” 山、渓流、夜叉祭り、街道――息の詰まる多様性 |
江戸中心の“横の交流” 小道、借家、裏路地、祭り囃子に交じる風の音 |
どちらも“和風×鬼”という土台は同じだけど、 その上で立っている空気は別の世界だった。
「鬼滅の刃」では、大正の風を吸って炭治郎たちが旅をする。 節目節目で、「文明が少しずつ進んでいく匂い」を感じる場面が多い。
橋の上に立つと電柱が見える。 街の片隅にはまだ木造家屋。 その境目に、鬼が潜んでいる。
その“境”が、物語そのものだった。
それに対して、「鬼人幻燈抄」は、幕末の江戸にずっと留まる。 波打つ人の声、陰る提灯、江戸川の川風。 「この町は、もうすぐ消えてしまうかもしれない」という記憶の予感がいつも漂っている。
登場人物たちは、“同じ町の中を歩きながら、自分の傷と向き合い”続ける。
- 炭治郎=山を越え、川を渡り、世界を知りに行く。
- 旭=江戸の中を歩き、風景と記憶を照らし合わせる。
それぞれの旅は、“どこに立っているか”で色が変わる。
その違いが、物語が持つ感情の温度にも直結する。
・鬼滅の刃=進む“熱量”。季節も、風も、“加速”していく。
・鬼人幻燈抄=立ち止まる“熱量”。思い出は、光と影の間に静かに揺れる。
そして、その背景は単なる装飾じゃない。“その時代にしか描けなかった感情”が詰まっている。
幼い子どもの笑い声が川風に消える夜、 夜光虫のように瞬く提灯の灯り、 乾いた空気や木訥とした呼吸までが、ひとつの“感情景”になっていた。
私たちは、そこにいるわけじゃないけれど、どこかでその匂いを懐かしんでしまう。
歴史はただの背景ではなく、感情を映す“鏡”だったのかもしれない。
5. 主人公の旅と動機──鬼に家族を奪われた少年たち
| 炭治郎(鬼滅の刃) | 旭(鬼人幻燈抄) |
|---|---|
| 家族を鬼に殺され、鬼となった妹を人間に戻すため剣を握る | 家族を失い、妖と関わる中で“心の穴”と向き合う旅へ |
| “失ったもの”を取り戻す旅 | “埋まらないもの”を見つめ続ける旅 |
家族を奪われた少年――それが、どちらの物語にも共通している“はじまり”だった。
炭治郎は、ほんとうに普通の子だった。
山で炭を焼き、家族に優しく、妹と笑い合う、そんな“暮らし”の真ん中にいた子。
でもある日、その日常は血に染まる。 唯一生き残った妹・禰豆子は鬼と化し、炭治郎の時間は“誰かを守る”ためだけに進み始めた。
彼の旅は、「鬼を倒す」ためじゃない。
本当は、「もうこれ以上、大切なものを失いたくない」っていう、ただそれだけの祈りだった。
だから炭治郎の剣は、怒りよりも、願いでできている。 それがこの物語を、“復讐譚”ではなく“救いの物語”にしていた。
一方の旭(あさひ)は、家族を失ったことすら、どこか実感できずにいた。
死に目にも会えず、誰のせいかもわからない。 ただぽっかりと、心に穴だけが空いていた。
「どうして自分だけ、生き残ってしまったのか」 その問いを胸に、妖たちと出会い、言葉を交わしながら、 “自分の輪郭”を確かめるように歩いていく。
旅の形は違っても、ふたりとも“なくしたものの重さ”を抱えていた。
炭治郎は、「絶対に戻したい」という強さに変えて。 旭は、「戻せないのなら、せめて忘れないでいたい」という優しさにして。
この章を読みながら、わたしはずっと思ってた。
「どんなに立派な目的があっても、 たった一人を守りたいって気持ちのほうが、ずっと強いのかもしれない」
彼らが向かう先は、“勝利”や“正義”じゃない。 たぶん、「もう一度、誰かとちゃんと笑いたい」って願いなんだと思った。
(チラッと観て休憩)【TVアニメ『鬼人幻燈抄』第1弾PV】
6. 鬼や妖の描き方──能力・存在意義・世界観の違い
| 鬼滅の刃における「鬼」 | 鬼人幻燈抄における「妖」 |
|---|---|
| 人を喰らい、圧倒的な身体能力を持つ存在 太陽を嫌い、再生力に長ける 鬼舞辻無惨を中心とした階級構造 |
人に近く、記憶や感情を宿す“異形” 能力は多様で個体差が大きく、善悪が曖昧 人間との境界に揺れる存在 |
“敵”として登場する存在。 でも、それがただの「悪役」で終わらないのが、どちらの作品にも共通する“奥行き”だった。
「鬼滅の刃」における“鬼”は、人を喰らい、力を誇示し、時には惨たらしく笑う。
でもその奥には、「人間だった頃の傷」が必ず残っていた。
たとえば累。家族に飢え、つながりを求めすぎた末の姿。
たとえば妓夫太郎と堕姫。あまりにも過酷な過去が、醜さに変わっただけ。
鬼になるというのは、“感情の破綻”であり、“愛の行き止まり”でもあった。
だからこそ炭治郎は、鬼を斬るたびに泣いた。
彼の刃は“断罪”ではなく、“許し”のようにさえ見えた。
一方で、「鬼人幻燈抄」の“妖”は、もっと静かに、もっと人間くさい。
彼らは強くない。人間を襲うわけでもない。 ただ、そこに“存在してしまっている”だけの、“曖昧な生き物”だった。
そして、ときに語る。「昔は人間だった」と。 あるいは「人間と友達になりたかった」と。
この妖たちは、誰かの“見なかったことにした感情”の化身みたいな気がした。
怒り、寂しさ、妬み、忘れられた記憶。 人間の内側で澱のように溜まっていく感情が、形を持って現れたもの。 それが“妖”として、彼らの前に立ちはだかる。
だから旭たちは、妖と戦うんじゃなく、対話しようとする。
そこには勝ち負けじゃない、“相手を知ろうとする勇気”があった。
「鬼滅の刃」の鬼が、「こんなに苦しかった」と叫ぶ存在なら、 「鬼人幻燈抄」の妖は、「気づいてほしい」と囁く存在だった。
恐ろしさの質が違う。 前者は、力の恐怖。後者は、気づかぬうちに呑まれてしまう、感情の沈黙。
そしてどちらも、“異形”の姿をしていながら、一番怖いのは「人間」なのかもしれないと、教えてくる。
7. キャラクターデザインや衣装の比較──視覚的な共通点とは?
| 鬼滅の刃 | 鬼人幻燈抄 |
|---|---|
| 和柄・市松模様・羽織や隊服が特徴的 キャラごとのテーマカラーが強調される |
江戸の町人風和装・地味な配色の中に個性がにじむ 妖はシンプルで不可思議な姿が多い |
「似てる」と言われる理由のひとつに、ビジュアルの和風テイストがある。
でも、“似てるのは素材であって、仕立て方がまるで違う”。 そう感じたのが、このキャラクターデザインの比較だった。
「鬼滅の刃」といえば、市松模様の羽織。 炭治郎の緑と黒が交差する衣装は、もはや“記号”として定着している。
そのうえで、善逸の黄色、伊之助の獣皮、煉獄さんの炎柄── キャラごとの配色や模様が、内面の“感情の色”とシンクロしていた。
つまり衣装は、ただの服じゃない。「その人が背負ってきた人生の模様」だった。
対して「鬼人幻燈抄」の衣装は、どこか素朴で、くすんでいて、派手さがない。 だけどそれが逆に、“物語の空気”にとてもよく馴染んでいる。
旭の羽織は地味で、歩いていても目立たない。 でもその中に、どこか“消えたくない気持ち”が、そっと刺繍されてる気がした。
妖たちはもっと不思議。 人のような、獣のような、影のような存在で、はっきりした輪郭がないことも多い。
それがむしろ、「わたしたちの中にもいる存在」みたいに見えてくる。
一見すると、どちらも“和風ファンタジー”な装い。 でもそのデザインには、物語の“伝えたいもの”がちゃんと織り込まれていた。
- 鬼滅の刃=色と形で“心の叫び”を見せる
- 鬼人幻燈抄=色を削って“心の余白”を浮かび上がらせる
どちらが派手か、どちらが美しいかじゃない。 衣装が“語るもの”の方向性が、根本から違うんだと思った。
だから私は、こうも感じた。 「服って、感情の外側なんだな」って。
そう思える作品って、意外と少ない。
8. ストーリー構造の類似点と分岐点──「使命」と「救済」のちがい
| 共通点 | 分岐点 |
|---|---|
| ・“家族喪失”から物語が始まる ・人ならざる存在との邂逅 ・“何かを守る”ために進むストーリー |
・鬼滅の刃:明確な敵とのバトル構造、隊組織の中での成長 ・鬼人幻燈抄:明確な敵は不在、個人の記憶と向き合う静的構造 |
「似てる」と言われるストーリーの核──それは、どちらも“奪われた日常”から始まること。
家族を喪い、“鬼”や“妖”と出会い、 そして、何かを取り戻すために旅に出る。
その流れだけを見ると、たしかにプロットは近い。
でも、その旅の“意味”を掘り下げると、見えてくるものが違った。
「鬼滅の刃」は、“鬼を倒す”という明確な“使命”が物語の軸になる。
柱という最強の剣士たち、任務、階級、指令── それはまるで、“悲しみを戦いで超えていく”システムだった。
でも、「鬼人幻燈抄」には、そんな明確な戦いはない。
妖と出会い、自分の内面と向き合い、記憶をなぞっていく。 その構造は、戦う物語ではなく、“感じる物語”だった。
つまり──
- 鬼滅の刃=使命によって動かされる物語
- 鬼人幻燈抄=救済に導かれていく物語
どちらも“悲しみ”が起点だけど、 前者はそれを“行動”に変えていく。 後者はそれを“問いかけ”として抱え続ける。
だから「鬼滅の刃」は、読後に“胸を叩かれる”ような熱が残るし、 「鬼人幻燈抄」は、読後に“胸の中が静かに濡れる”ような余韻が残る。
物語の方向性が似ているからこそ、進み方の違いがより鮮明に見える。
そして、どちらの主人公も、戦ってはいるけれど、 本当はきっと、誰かに「あなたは悪くないよ」と言いたかっただけなのかもしれない。
使命の刃を振るうか、救済の声を探すか。 似た出発点から、別々のゴールを目指したふたりの旅が、ここで交差する。
9. 「似てる」「パクリ」と言われた理由とは?構成と印象の考察
| 「似てる」と言われた主な理由 | ・和風の世界観 ・“鬼”や“異形”が登場する設定 ・家族喪失+少年主人公という共通構造 ・初期連載時期が近かったこと |
|---|
「似てる」と感じるとき、人は何を見ているんだろう。
設定? キャラ? 構図? きっとどれもあるけど、“物語の温度”が近いとき、人は「似てる」と感じるのかもしれない。
「鬼滅の刃」も「鬼人幻燈抄」も、 最初に読み始めたときに感じる“雰囲気の湿度”が、すごく似てる。
静けさの中にある切実さ。 薄暗い部屋に差し込む光みたいな、“静かな熱”。
でも、物語を深く読み進めるほど、違いははっきりしてくる。
- 鬼滅の刃は、「運命に抗う物語」
- 鬼人幻燈抄は、「記憶に寄り添う物語」
“鬼”や“妖”という要素は同じでも、 それが象徴しているものはまるで違う。
鬼滅の刃の“鬼”は、「もう戻れない悲しみ」。 鬼人幻燈抄の“妖”は、「まだ誰にも見つけられていない感情」。
つまり、「似てる」っていうのは、 「違いを知る前の、印象だけで語られた感想」だったのかもしれない。
でもそれは、悪意じゃない。 人は、自分の中にある“未処理の感情”を引っかけて、何かを似てると感じてしまう。
だから、どちらかがパクリかどうか―― そこに答えを出すことよりも、 「どうして似て見えたのか」を言葉にするほうが、きっとずっと意味がある。
作品が生まれるとき、その背後には、 構想、偶然、社会の空気、作家の心の揺れがある。
それらを踏まえずに「似てる=パクリ」と決めつけるのは、 どちらの作品にも、失礼だ。
物語の奥にあるものまで見ようとするなら、 “似てる”と騒ぐ前に、“何が違うのか”を感じようとする目が、必要なんだと思った。
10. 鬼と妖、それぞれの“救えなさ”──人間ではないものをどう描いたか
| 鬼滅の刃の「鬼」 | 鬼人幻燈抄の「妖」 |
|---|---|
| ・人を喰らう明確な加害性 ・かつて人間だった者たちの悲劇 ・倒されることで“供養”される構造 |
・直接的な加害性はほとんどなし ・人の心に棲む影としての存在 ・理解されることで“癒し”が起こる構造 |
「鬼滅の刃」と「鬼人幻燈抄」。 どちらの物語にも、“人間ではないもの”が出てくる。
でも、その“異形”たちが持っている役割と、物語上での扱われ方は、まったく違った。
鬼滅の刃の「鬼」は、人間を喰らう存在であり、 明確に“倒すべき敵”として立ちはだかる。
でも、倒すその瞬間に見えてくるのは、 かつて人間だった頃の記憶、 誰にも見つけられなかった願い、 そして、愛されなかった悲しみ。
「人に戻してあげたい」── 炭治郎の剣は、“怒り”よりも“祈り”のようだった。
一方、鬼人幻燈抄の「妖」は、誰かを襲ったりはしない。
彼らは、人間の感情や記憶に寄り添ってくる、気配のような存在。
それは時に、過去の過ちを映す鏡であり、 時に、誰にも言えなかった思いを代弁する“声”でもある。
妖たちは、倒されるのではなく、見つめ返される。
だから、そこにあるのは“戦い”ではなく“問い”だった。
──君は、まだその記憶と共に生きていけるか。
この違いは、すごく大きい。
- 鬼=過去を断ち切るための象徴
- 妖=過去と共に歩むための象徴
どちらも、“救えないもの”を描いているけれど、 鬼滅は“どう救えなかったか”を問う物語で、 幻燈抄は“救えないまま、そばにいる”という選択を描く。
その距離感こそが、物語の色温度を決めていた。
人間ではない存在を、どこまで理解できるか── それはつまり、自分の中の「わかってもらえなかった気持ち」と向き合うことでもあった。
だから、きっと私たちは、 鬼や妖の目の奥に、自分の“言えなかった部分”を見てるんだと思う。
まとめ:似てるようで、似てなかった──“鬼滅”と“幻燈抄”を正しく読み解く
「似てる?」という問いから始まった今回の比較。
たしかに、設定も、時代も、キャラの境遇も、どこか重なって見えた。 でも、じっくり観察してみると、その“似てる”の奥には、それぞれが選んだ違う道筋があった。
鬼滅の刃は、運命と戦う物語。
鬼人幻燈抄は、感情と向き合う物語。
どちらも、“失ったもの”を出発点にしてるのに、
その痛みの扱い方が、まるで違う。
前者は、その痛みを“剣”に変え、誰かを守ろうとする。 後者は、その痛みを“記憶”にして、そっと灯りをともす。
似ていたのは、物語の骨ではなく、その表情。 “あの日の喪失”に立ち尽くす少年の背中が、偶然にも似ていただけ。
そして私たちはたぶん、そんな背中に、自分を重ねたくて、 「似てる」と感じたんだと思う。
でも物語はいつも、その先を見せてくれる。 違いを知ることで、世界が広がっていく。
「似てる?」じゃなくて、「どこが違った?」と問い直せたとき、 私たちはようやく、“自分の感じたこと”を言葉にできるのかもしれない。
そして、それぞれの作品が照らしてくれる心の輪郭に、そっと触れたくなる。
完璧な答えはいらない。 でも、“ちゃんと観た”って言える視点だけは、残しておきたい。
- 「鬼滅の刃」と「鬼人幻燈抄」の間にある世界観・キャラ構造の重なりと差異
- “鬼”と“妖”の違いが象徴する、物語の根っこにある感情のちがい
- ビジュアルや衣装デザインに見られる内面の表現方法の対比
- ストーリー構造上の「使命」と「救済」というテーマの分岐
- 読者が“似てる”と感じる心理の仕組みと、パクリ疑惑の正しい捉え方
- 両作品がそれぞれに持つ“物語の温度”と読後に残る感情の違い
- 「似てる?」ではなく、「何が違った?」と問い直すことの意義
【TVアニメ『鬼人幻燈抄』第2弾PV】

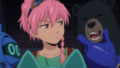
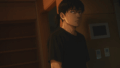
コメント