『鬼滅の刃』完結から5年──作者・吾峠呼世晴(ごとうげ・こよはる)さんの“現在”に関する関心が再び高まっています。「引退したの?」「次回作は?」「素顔や性別は?」といった疑問がネット上で繰り返し検索されている今、本記事では2025年最新の情報をもとに、作者の近況・真偽不明の噂・創作活動の有無などを徹底的に整理します。
この記事では、
- ● 吾峠呼世晴の現在の活動状況
- ● 引退説の出どころと事実関係
- ● 素顔・性別・本名に関する公式スタンス
- ● 次回作(新作)の可能性と構想の内容
──といった多角的なテーマを、信頼できる情報源(出版社・書籍・ニュース報道)をもとに網羅。検索で上位表示されている“噂寄り”のまとめサイトには載っていない一次情報を含め、読者の“本当に知りたかったこと”に迫ります。
「引退してしまったのか?」「また作品が読める日は来るのか?」── そんな想いを抱えるあなたに向けて、事実と希望の両方を込めてお届けします。
- 吾峠呼世晴が“引退した”という説の出どころと、その真偽
- 2025年時点の活動状況と、現在の創作意欲を示す具体的な証拠
- 素顔・本名・性別などプロフィールに関する“公式の立場”
- 次回作として言及された“SFラブコメ”構想の出典と真相
- ファンブックや映画特典に記された“作家としての現在地”
- 信頼できる一次情報と、噂・憶測との明確な線引き
第2弾特報では、新規カットや映像演出がさらに追加されています。
- この記事を読む前に|“いま”の吾峠呼世晴をめぐる注目ポイント
- 1. 吾峠呼世晴のプロフィールと『鬼滅の刃』完結までの歩み
- 2. 引退説の真相とは?──公式発表と噂の出どころを検証
- 3. 現在(2025年)の活動状況|“沈黙”と“継続”の境界線
- 4. 素顔・性別・実名の公開状況と本人不在のSNS騒動
- 5. 次回作の可能性は?“SFラブコメ”構想の背景にあるもの
- 6. 『鬼滅の刃』IPの継続展開と作者の関与有無
- 7. ファンブック・特典コメントに見る“作家としての現在地”
- 8. 引退していない、“今”も作家であり続けている
- 総まとめ|“吾峠呼世晴の現在”を整理する10のキーワード
- 本記事まとめ|沈黙の中に宿る“物語の灯火”
この記事を読む前に|“いま”の吾峠呼世晴をめぐる注目ポイント
| 現在の姿 | 表立った活動はなく、“沈黙”が続く中でも、書籍や特典での発言が注目されている。 |
|---|---|
| 引退説の真相 | 一部で噂された“引退”は公式に発表されておらず、実際には裏付けが取れていない。 |
| 次回作の期待 | “SFラブコメを描きたい”という発言は確認されているが、作品発表は今のところなし。 |
| 素顔と性別 | いまだ公開されておらず、公式書籍でも“匿名性”を重視するスタンスが維持されている。 |
| 読者への姿勢 | 本人は前面に出ないが、届けられる言葉の節々に、変わらぬ“誠実さ”がにじんでいる。 |
1. 吾峠呼世晴のプロフィールと『鬼滅の刃』完結までの歩み
『鬼滅の刃』の作者として知られる吾峠呼世晴(ごとうげ こよはる)は、2016年から2020年にかけて一大ブームを巻き起こした人物です。物語を描き切ったあと、表舞台から姿を見せることはほとんどなくなりましたが、その軌跡には今も多くの注目が集まり続けています。ここでは、吾峠呼世晴さんの基本プロフィールと、『鬼滅の刃』が連載開始から完結に至るまでの歩みを時系列で丁寧に振り返ります。
| 生年月日・出身地 | 1989年5月5日、福岡県出身。地方在住の新人漫画家としてジャンプへ持ち込みを行った。 |
|---|---|
| デビューのきっかけ | 2013年、『過狩り狩り』が「ジャンプトレジャー新人漫画賞」にて佳作受賞。その後『鬼滅の刃』の原型となる読み切りを掲載。 |
| 代表作 | 『鬼滅の刃』(2016〜2020)週刊少年ジャンプで連載。全23巻で累計発行部数は1億5000万部を突破。 |
| 受賞歴 | 野間出版文化賞、芸術選奨新人賞、手塚治虫文化賞特別賞、日本漫画家協会賞などを受賞。作品自体の社会的影響力が高く評価された。 |
| 連載完結 | 2020年5月18日発売の『週刊少年ジャンプ』24号で最終回。長期化を避け、物語を“描き切る”姿勢が話題となった。 |
吾峠呼世晴さんは、連載開始当初から「読者に伝えたい物語」を明確に持っていたとされます。人気のピークを迎えても物語を予定通り完結させた姿勢は、多くの漫画家とは一線を画していました。社会現象となったアニメ化や映画化の大ヒットにより、彼女(※性別は公式未発表)自身の存在も脚光を浴びましたが、連載終了後は表舞台への露出が一切なくなり、“沈黙の作家”という印象が定着していきます。
その一方で、公式書籍・映画特典・ファンブックなどには定期的にコメントが掲載されており、完全な引退や活動停止とは異なる「静かな活動継続」の姿勢も見て取れます。プロフィールと作品の歩みを押さえることは、後に触れる「引退説」や「現在の活動」の背景を理解するうえで欠かせないポイントです。
2. 引退説の真相とは?──公式発表と噂の出どころを検証
吾峠呼世晴さんの名前を検索すると、必ずといっていいほど目にするのが「引退説」です。しかし、実際のところ公式に「引退」を発表した事実は一度もありません。ここでは、この噂がどこから広まったのか、そして公式に確認されている情報とどのようなズレがあるのかを、事実ベースで整理していきます。
| 公式発表 | 2025年10月時点で、集英社・作者本人いずれからも「引退」の発表はなし。連載終了=引退ではない。 |
|---|---|
| 噂の発端 | 2020年、文春オンラインの「家庭の事情で実家に戻る」という記事が孫引きされ、各サイトで“引退説”として拡散。 |
| 一次情報の現状 | 元記事はすでに非公開であり、出版社や作者の公式なコメントは確認できない。 |
| 誤解されやすいポイント | 「週刊連載を終えた=引退」と受け止められやすい構図が、ネット上の“既成事実化”を助長した。 |
| 実際の活動 | 映画特典やファンブック、書籍などに定期的にコメント掲載あり。創作活動そのものは完全停止していない。 |
吾峠呼世晴さんの「引退説」は、公式な発表に基づくものではなく、一部報道とそれを拡散した二次・三次情報の積み重ねによって形作られた“印象”に過ぎません。とくに2020年の『鬼滅の刃』連載完結は社会現象的な注目を集めたため、その直後の沈黙が“引退”という言葉に置き換えられてしまった側面があります。
一方で、公式書籍や劇場版の特典コメントなどにおいて、彼女(※性別は非公表)は定期的に作品世界に関わる発言をしており、「完全に筆を置いた状態」とは明らかに異なります。引退という言葉の使われ方自体が、ネット上での誤認やセンセーショナルな見出しに影響されていることを意識しておくことが重要です。
結論として、「引退」は公式には存在しない──この一点が、現時点で最も確実な情報です。
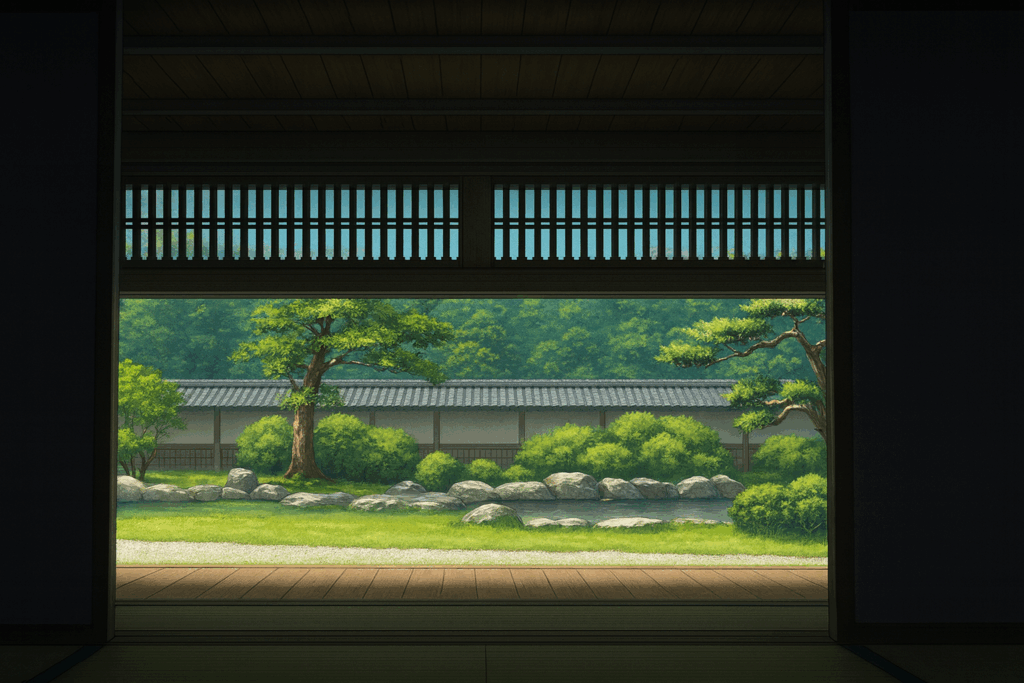
【画像はイメージです】
3. 現在(2025年)の活動状況|“沈黙”と“継続”の境界線
『鬼滅の刃』の完結から5年──現在の吾峠呼世晴さんは、公に新作発表をしているわけでもなく、SNSなどで動向を発信しているわけでもありません。一見すると“沈黙”のように見えますが、実際にはいくつかのメディアや公式書籍を通じて、彼女の創作活動が完全に止まっていないことがわかります。ここでは、2025年時点で確認できる“現在”の姿を、客観的な情報に基づいて整理していきます。
| 新作発表の有無 | 2025年10月時点で、次回作の連載や読切などの発表はなし。 |
|---|---|
| コメントの確認状況 | 映画特典やファンブックへの寄稿は継続中。完全な沈黙ではない。 |
| 公式SNS | 本人のアカウントは存在せず、過去に偽アカウント騒動も。現在もSNS発信は確認されていない。 |
| IPへの関与 | 『鬼滅の刃』の劇場版やイベントが展開される中、作者の直接関与は明言されていない。 |
| 現在の印象 | メディア露出ゼロだが、水面下では一定の“作家活動”が続いている印象。 |
「連載が終わった=何もしていない」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、吾峠呼世晴さんの現在は、まさに“沈黙と継続”の境目にある状態です。確かにSNSでの発信や公の場への登場はありません。しかしその一方で、映画特典への寄稿や、ファンブックでのコメント掲載といった「創作の気配」は途切れていないのです。
たとえば、2023年の劇場版『鬼滅の刃 無限城編』第一章では、劇場特典冊子に吾峠先生の描き下ろしメッセージが含まれており、ファンの間では「まだ物語を見守ってくれているんだ」との安心感も広がりました。
このように、メディアには姿を見せなくても、作品の“裏側”で息をするように関わり続けているのが、2025年時点での“現在”といえるでしょう。
4. 素顔・性別・実名の公開状況と本人不在のSNS騒動
『鬼滅の刃』が国民的ヒットとなったことで、作者・吾峠呼世晴さんの素顔や性別、本名に対する注目も一気に高まりました。しかしその一方で、彼女自身は意図的に“匿名性”を保ち続けている人物でもあります。この章では、公式に確認されているプロフィール情報や、ネット上で起きた“なりすまし”騒動を踏まえながら、「吾峠呼世晴という作家がなぜ顔を出さないのか」を整理していきます。
| 素顔の公開状況 | 顔写真や実写でのメディア露出は一切なし。単行本・公式資料では一貫して“ワニ”の自画像を使用。 |
|---|---|
| 本名 | 非公開。編集部やメディアでも実名は明かされていない。 |
| 性別について | 女性であると報じた旧メディア記事は存在するが、公式発表ではなく、あくまで“噂”扱いが適切。 |
| SNSの状況 | 本人名義のアカウントは未確認。2020年には“なりすましアカウント”が話題となり、集英社側が否定コメントを発表。 |
| 現在の姿勢 | 公の場に出ることなく、作品・コメントなどを通じて読者と“距離を取った関係”を保っている。 |
吾峠呼世晴さんは、デビュー当初から「自分自身より、作品で語りたい」というスタンスを徹底しています。顔や性別、私生活などに関しては、SNS時代に逆行するかのような“沈黙”を保ち、今に至るまでそのベールを脱ぐことはありません。
2020年には、SNS上に“吾峠呼世晴”を名乗るアカウントが出現し話題となりましたが、集英社が「本人ではない」と公式に否定。これにより、読者やファンの間では「やはり本人はSNSをやらないのか」という共通認識が広がりました。
また、「女性漫画家である」とする報道も一部存在しますが、これもあくまで旧記事に基づく“間接的証拠”であり、確定情報として扱うことはできません。現在も、性別・本名・顔写真のいずれもが非公開のままであり、“ワニ先生”という通称のまま、作品を通じてのみ自己表現を行っているのが吾峠さんの現在地です。
休憩がてら、迫力ある特報映像をどうぞ。
5. 次回作の可能性は?“SFラブコメ”構想の背景にあるもの
『鬼滅の刃』の連載を終えた吾峠呼世晴さんについて、ファンの間で最も気になる話題のひとつが「次回作はあるのか?」という点です。2021年に刊行された公式ファンブックの中で、彼女自身が語った“SFラブコメを描きたい”というコメントが、多くのメディアでも取り上げられました。この記事では、その発言の意味と、現在に至るまでの動きから見える「次回作の可能性」について深掘りしていきます。
| 次回作の構想 | 『鬼殺隊見聞録・弐』にて、「SFラブコメを描いてみたい」とのコメントを本人が掲載。 |
|---|---|
| 報道されたメディア | オリコン・リアルサウンドなど複数メディアが該当発言を引用し、注目された。 |
| 具体的な発表の有無 | 2025年10月現在、タイトル・掲載媒体・時期などの情報は未発表。 |
| ファンの期待感 | 「恋愛要素」や「日常的な笑い」を描く吾峠作品を見たいという声がSNSでも多く見られる。 |
| 実現の可能性 | 希望としての言及はあるが、企画進行や執筆状況は不明。将来的な可能性を残した発言と見るのが妥当。 |
「SFラブコメを描いてみたい」との発言は、あくまで「希望」や「構想」レベルの表明であり、具体的な新作タイトルや連載開始日は示されていません。とはいえ、『鬼滅の刃』でのシリアスで重厚な物語とは対照的に、“日常×笑い×SF”という軽やかなジャンルへの興味が語られたことは、多くの読者にとって新鮮な驚きでした。
またこの発言は、『鬼滅の刃』で見せたドラマ性や感情表現とは別の一面を見せてくれる可能性を示唆しており、「吾峠先生の筆で描かれる恋愛ってどんな感じなんだろう」と期待を集めています。
2025年現在も、新作発表に関する公式な情報はありませんが、ファンブックの言葉が編集部を通じて公開されたことから、少なくとも“描きたい気持ち”は消えていないと読み取れます。
「描くなら、また描いてほしい」。その言葉を、今はそっと胸にしまって待つしかない──それが現時点での“次回作との距離感”と言えるかもしれません。
6. 『鬼滅の刃』IPの継続展開と作者の関与有無
『鬼滅の刃』は2020年に本編が完結したにもかかわらず、今なお“IP”として拡大を続けているコンテンツです。2025年には劇場版『無限城編』の公開やアニメ新シリーズの発表などが話題を呼びました。しかしこの華やかな展開の裏で、「吾峠先生は今も関わっているの?」という疑問が多くのファンの間に残っています。本章では、『鬼滅の刃』というIPの現在地と、作者の関与の有無について解説していきます。
| IP展開の状況 | 2025年も劇場版『無限城編』などが好評公開中。コラボやグッズ展開も継続して活発。 |
|---|---|
| 作者の関与 | 脚本や演出などへの直接参加は明言されておらず、関与の程度は不透明。 |
| 特典・冊子での存在感 | 劇場特典冊子にコメントを寄せるなど、部分的に創作に関与している痕跡あり。 |
| 出版社・制作陣のスタンス | 「原作の世界観を尊重する」という形で、原作と距離を置きつつ展開を続けている印象。 |
| 今後の可能性 | スピンオフや公式ガイドブックの再登場はあり得るが、本人主導の動きは現時点で確認されていない。 |
『鬼滅の刃』は、いまや単なる漫画作品を超えた巨大なコンテンツビジネスへと進化しています。映画、アニメ、舞台、コラボ企画、展示イベントなど、その拡がりは年々多様化していますが、そこに吾峠呼世晴さんの「生の声」がどれほどあるのか──という点には明確な線引きが存在します。
2023年の『無限城編』映画では、特典冊子に寄せられた彼女のメッセージが注目を集めましたが、それ以外の場面で彼女の“関与”を感じる機会はごくわずか。「作品の外に立って、見守る立場」であることが見て取れます。
原作を重んじつつも、その先を作っていく制作陣の中に、吾峠先生が名義以上の存在として参加しているかは不明です。ただ、その「不在」が悪い意味ではなく、むしろ“描き切った者としての潔さ”として評価される風潮も強まっています。
作者の手を離れたあとも、愛され続ける物語。それはある意味で、「完結したのに終わらない」という奇跡的な状態なのかもしれません。

【画像はイメージです】
7. ファンブック・特典コメントに見る“作家としての現在地”
公の場には姿を見せず、SNS発信も行わない吾峠呼世晴さん。しかし、ファンブックや映画特典などで寄せられる短いながらも印象的なコメントからは、彼女がいまも“作家”として生きていることが読み取れます。この章では、公式に確認されている書き下ろしコメントやファンブック記載の言葉を通じて、現在の吾峠さんがどのような想いを抱えているのかを探っていきます。
| 掲載された媒体 | 『鬼殺隊見聞録・弐』(公式ファンブック)や劇場特典冊子など。 |
|---|---|
| 代表的な発言 | 「SFラブコメを描きたい」「一人でも多くの人に物語が届くように」など前向きな創作意欲がうかがえる言葉。 |
| 文章の特徴 | ユーモアや人間味がありつつも、読者への誠実さがにじむ丁寧な文体。 |
| 創作意欲の継続 | 直接的な作品発表はないが、コメントから“描くことへの熱”は完全には失われていないと読み取れる。 |
| 現在のスタンス | 表には出ずとも、自身の言葉で“少しだけ”姿を見せる距離感を保っている。 |
吾峠呼世晴さんの言葉には、いつも「読み手への配慮」と「創作への愛情」が込められています。たとえば『鬼殺隊見聞録・弐』に収録された“SFラブコメ構想”の記述は、単なる次回作への布石という以上に、「まだ自分は物語を考え続けている」という意思表示にも受け取れます。
また、劇場版『無限城編』の特典小冊子では、「観てくださる皆さんのおかげで作品が生きている」という趣旨の感謝メッセージが掲載され、“作品が自立して動き続けていること”への驚きと感謝がにじみ出ていました。
こうしたコメントの数々は、短いながらも“現在も作家としての心は灯ったまま”であることを示してくれます。完全な沈黙ではない──「語るべき時にだけ語る」という、誠実な作家としての現在地がそこにはあります。
8. 引退していない、“今”も作家であり続けている
『鬼滅の刃』の完結後、作者・吾峠呼世晴さんが表舞台から姿を消したことで、一部では「引退したのでは?」という噂も流れました。しかし、本記事で確認してきたとおり、公式に“引退”を表明した事実は存在していません。むしろ、コメントや書き下ろしメッセージを通して、彼女が今も“物語を考える人”であることは確かです。ここでは、これまでの情報をふまえて、“作家・吾峠呼世晴”の現在地を総括します。
| 引退発表の有無 | 一切なし。出版社からも本人からも引退に関する公式コメントは出ていない。 |
|---|---|
| “引退説”の出どころ | 2020年の旧記事で“家庭の事情で実家に戻った”とされるが、出典は非公開で真偽不明。 |
| 作家活動の痕跡 | ファンブック、映画特典などで継続的にコメントを発表。新作構想も明言。 |
| 現在の創作姿勢 | 公の場には出ず、必要なときだけ言葉を届ける“沈黙と誠実のあいだ”を貫くスタイル。 |
| 今後の可能性 | 次回作やスピンオフなどの発表は未定だが、作家としての灯は確実に生きている。 |
引退の公式発表はなく、現在も“表現者としての気配”は途絶えていない──それが、2025年時点で確認できる事実です。SNSのような即時的な場には現れず、マスメディアでの露出もない。しかしながら、彼女の書いた文章や残した言葉は、今もなお新しい情報として公式媒体に掲載され続けています。
また、“引退”という言葉が一人歩きした背景には、2020年の文春報道や憶測の広がりがありました。しかし、これらはいずれも本人の発言や出版社の認可を伴わない推測にすぎません。現在も断定できる情報はなく、むしろファンブックや特典冊子で継続的に語られる言葉が、「まだ終わっていない」ことを証明しているのです。
吾峠呼世晴という作家は、作品をもって語り、沈黙をもって尊厳を保つ──そんな静かな表現者であることが、ここまでの検証から見えてきます。再び彼女の作品が世に出る日を、ファンとしては静かに、しかし確信を持って待ちたいところです。

【画像はイメージです】
総まとめ|“吾峠呼世晴の現在”を整理する10のキーワード
| 現在の活動 | 公式発表はなし。新連載・読切等の発表は未確認。 |
|---|---|
| 引退の有無 | 引退は公表されておらず、噂の出どころは信頼性に欠ける。 |
| ファンブックでの発言 | 「SFラブコメを描きたい」と明言。構想は存在する。 |
| 顔・性別・本名 | 全て非公開。自画像は一貫して“ワニ”のイラスト。 |
| SNS騒動 | 本人を名乗る偽アカウントが否定された報道あり。 |
| IP展開 | 『鬼滅の刃』は映画・グッズ・展示等で継続的に展開中。 |
| 作者の関与 | 映画特典冊子への寄稿など、限定的な関与が確認される。 |
| 表現スタイル | 派手な露出はせず、“必要なときだけ言葉を届ける”姿勢。 |
| 読者への姿勢 | 沈黙を保ちつつ、誠実なコメントが随所に見られる。 |
| 今後の可能性 | 発表は未定だが、創作意欲の灯は消えていない様子。 |
本記事まとめ|沈黙の中に宿る“物語の灯火”
『鬼滅の刃』完結から5年──今なお語られ、愛され続ける吾峠呼世晴さんの現在について、本記事では多角的に検証してきました。引退説、素顔、新作の噂──それらに振り回されるのではなく、確かな公式情報と彼女自身の言葉から見えてきた“作家としての現在地”を、最後に整理します。
| 引退の有無 | 公式発表はなし。現在も「引退した」と断定する根拠は存在していない。 |
|---|---|
| 新作構想 | “SFラブコメを描きたい”というコメントあり。実際の連載発表は未定。 |
| 素顔・性別 | 公表はなし。ワニのアイコンと匿名性を保ち続けるスタイルを継続中。 |
| 作家活動の形 | 表舞台からは距離を置きつつも、特典冊子やファンブックで言葉を届けている。 |
| “今”の姿勢 | 沈黙しつつも、読者に物語の余韻を残し、静かに創作の灯をともし続けている。 |
吾峠呼世晴さんの“現在”を語るうえで重要なのは、「作品で語り、沈黙で背中を見せる」という作家としての信条です。メディア露出や自己アピールではなく、物語そのものの力で人の心を動かしてきた彼女は、いまもその姿勢を崩していません。
そして、数行のコメントの中に、読者やスタッフ、関係者への誠実な敬意を込めるその筆致は、「一作家として、まだ何かを描こうとしている」ことを物語っています。
新連載の報はまだ届きませんが、その沈黙の中にはきっと、また新しい物語が育まれているはずです。私たちはその時を信じて、引き続き“公式の言葉”を軸に、静かにその背中を見守っていきましょう。
『鬼滅の刃』のキャラ、物語、そして“感情の余韻”に
もう少し触れていたくなる夜がある。
そんなときは、こちらの特集から静かに覗いてみてください。
上弦の鬼ひとりひとりの背景や戦い、感情に迫る特集を、こちらのカテゴリーでじっくりまとめています。
彼らの“しくじり”と“哀しみ”をもっと深く読み解きたい人は、ぜひこちらも覗いてみてください。
- 吾峠呼世晴は2025年時点で“引退を公表していない”
- “現在”も作家としてコメントを寄稿するなどの活動は継続中
- “SFラブコメを描きたい”という次回作構想が公式に存在
- 顔・性別・本名などの個人情報は一貫して非公開
- “引退説”の出どころは信頼性に欠ける噂レベルの情報
- 『鬼滅の刃』IP展開(映画・特典等)は活発に継続中
- 公式情報に基づき、今後の創作活動に期待が持てる状況
LiSAの新曲と共に映像が彩られる特別CM。作品の熱量をさらに感じられます。



コメント