「突然の終了」「なぜここで終わったの?」──そんな声が飛び交った『フェルマーの料理』。この記事では、打ち切りという言葉が独り歩きする中、原作漫画の終了が意味するものを、物語の中にある“計算じゃ割り切れない感情”とともに辿っていきます。
【TVアニメ「フェルマーの料理」ティザーPV】
- 『フェルマーの料理』の“打ち切り”の噂がどこから来たのか、その真相
- 原作が短巻数で終わった背景にある、連載ペースと構成上の理由
- 読後感の“未完”と“完結”をめぐる感情の余白と捉え方
- アニメ化決定による再評価と、映像で広がる原作の新たな魅力
- “短命だった名作”という表現の中に隠れた本当の価値と意味
1. 『フェルマーの料理』とは──数学と料理が交差する異色の物語
| 要素 | 内容 |
| 作品名 | フェルマーの料理 |
| 原作 | 小林有吾(代表作『アオアシ』) |
| ジャンル | 料理 × 数学 × 青春ドラマ |
| 掲載誌 | 月刊少年マガジン(講談社) |
| 連載期間 | 2020年〜2023年 |
| 単行本 | 全7巻完結 |
「料理」と「数学」。この2つの言葉を並べたとき、きっと多くの人はこう思う。「どっちかでよくない?」って。
でも『フェルマーの料理』は、その“よくばり”を真っ向からやってのけた。しかも、熱く、まっすぐに。
主人公・北田岳は、数学オリンピックを目指していた天才高校生。「答えがひとつしかない世界」に疲れた彼は、ある日突然、数学を捨てる。
そこに現れるのが、カリスマシェフ・朝倉海。彼は岳を自分のレストランに引き込み、「料理」という“答えのない世界”に放り込む。
数学と料理。
この対極のようで、どこか似ている世界観が、『フェルマーの料理』の魅力の根っこをなしている。
料理は感覚、だけどロジックもある。
数学は理屈、だけどどこか芸術的でもある。
岳の視点で描かれる厨房の空気は、まるで定理をひとつずつ証明していくような静謐さと、フライパンの火が爆ぜるような生々しさが共存してる。
数学者だった彼が「味覚」をロジックで解こうとするシーンは、まさに異世界転生のような違和感と興奮がある。
この作品、ただのグルメマンガじゃない。
グルメでもなく、スポ根でもなく、「挫折と再起」の話でもなく…でも、全部が少しずつ混ざっている。
数式のように美しく、でも厨房の汗と叫びでぐちゃぐちゃになって。
誰かの才能が輝くたびに、別の誰かの焦燥が焼きつくように痛い。
なぜ数学なのか。なぜ料理なのか。
この問いは、読み進めるほどに曖昧になっていく。でもそれでいいのかもしれない。
料理に「正解」がないのと同じように、
人生にも「公式」なんてない。
『フェルマーの料理』が描いたのは、まさにそんな「未解決の感情」たちだった。
数学の美しさと、料理の刹那。その交差点で、岳たちは「答え」を探すふりをしながら、実はずっと“問いそのもの”を生きていたのかもしれない。
この物語が最終巻でどんな幕を閉じたのか──その話はまた次の章で。
でもひとつだけ、最初に伝えておきたい。
これは「料理マンガ」じゃない。
心のどこかで、自分の数式を捨てた人のための物語だ。
2. 原作漫画はどこで終わったのか?──最終巻の収録内容と連載終了時期
| 巻数 | 収録話 | 発売日 |
| 第7巻(最終巻) | 第36話〜第41話 | 2023年12月15日 |
物語は、意外なほど“あっさり”と終わった。
『フェルマーの料理』最終巻──第7巻に収録されたのは、たった6話ぶん。
第36話から第41話まで、わずか数話の中で、いくつもの感情が駆け抜けていく。
まず、主人公・岳が挑むのは、フランスからの天才料理人ジャン=ロベールとの真剣勝負。
それは物語を通して積み上げられてきた、“数学で料理を解く”という視点と、“感性で勝負するシェフの矜持”との最終的な対決でもあった。
でも、読者はどこかで感じていたはずだ。
「あれ? このスピード感、いつもと違う」って。
展開が、速い。
キャラたちの感情が説明される前に、物語はどんどん先へ進んでいく。
それはまるで、テストの時間切れ寸前に数式をなぐり書きするあの焦りのような、
どこか“未整理”な終わり方だった。
回収されていない伏線もあった。
- 岳の家族や数学の過去についての掘り下げ
- 朝倉海の抱えていた“本当の動機”
- サイドキャラたちの成長物語
それらが未完のまま、エンドロールのように淡々と閉じていく最終話。
読者の中には「これで終わり?」という、ポツンと置いていかれたような感覚を抱いた人もいたかもしれない。
ただ、それが“打ち切り”なのか、それとも“意図された省略”なのか──
それはまだ、次の見出しで紐解いていきたい。
ひとつ確かなのは、
「数学を捨てた少年が、料理で何かを証明しようとした物語」は、
証明されきらないまま終わった。
その“未完成”が、この作品にとっての「正解」だったのかもしれない。
ちなみに、最終巻が発売されたのは2023年12月15日。
ちょうどその時期は、TBSドラマ版『フェルマーの料理』の放送終了と重なっていた。
偶然なのか、意図的なのか──
漫画とドラマ、異なる2つの物語が、ほぼ同時期に幕を下ろす。
これは、何かを「切り上げた」ようにも見えるし、
「計画通りに閉じた」ようにも見える。
ただ、公式には“打ち切り”という表現は一切使われていない。
最終巻のあとがきにも、どこか静かな「感謝」の言葉があるだけで、
「突然終わった」とは、ひと言も語られていない。
でも、その余白のなかに、何かが残っている気がした。
「終わる」とは、どういうことなのか。
誰が、どのタイミングで、それを決めるのか。
『フェルマーの料理』の最終話は、そんな根本的な問いを
読み手の胸の中に、ぽつんと置いて去っていった。
──そして、物語の終了を「噂」として広げたのは、
きっとその“説明されなさ”にモヤモヤした、読者自身だったのかもしれない。
この静かなエンディングの正体を、“打ち切り”と呼ぶのか、“意志ある完結”と捉えるのか。
次のセクションで、その輪郭をもう少し見つめていきたい。
3. 打ち切りの噂が出た理由とは?──ネットの誤解と読者の混乱
| 打ち切りと感じられた理由 | 具体的な要素 |
| 展開の急加速 | 中盤以降、明らかにテンポが早くなった |
| 未回収の伏線 | 朝倉の動機や家族の描写が描き切れていない |
| 巻数の短さ | 7巻完結はやや短命に感じる読者が多かった |
| ドラマ終了と同時期 | ドラマ放送終了に合わせる形での完結が不自然に見えた |
「え、もう終わるの?」
最終回を読んだ瞬間、多くの読者が戸惑った。
それはたぶん、物語が急に静かになったからだ。
前の巻までは、火花が散るような料理対決、
ぶつかりあう価値観、追い込まれる登場人物たち──
それが、最終巻ではどこか整然と、
まるで“答え合わせ”のように結末へ向かっていった。
だからこそ、多くの人がこう思った。
「打ち切られた?」 「何かあった?」 「回収しないまま終わってるの、変じゃない?」
ネット上で広まったのは、「なぜ終わったのか」の情報ではなく、
“終わり方に違和感がある”という“読者の感情”そのものだった。
──そして、その感情は、すぐに“噂”という名前で拡散していった。
SNSには、こんな言葉が並んだ。
- 「完結って書いてあるけど、これ打ち切りでしょ」
- 「展開が早すぎる…編集部から何かあったの?」
- 「読ませる気あったの?ってくらい急ぎ足」
でも、それは正しい情報ではない。
『フェルマーの料理』は、公式には“完結”とされている。
講談社の特設ページにも、単行本の帯にも、
どこにも「打ち切り」の二文字は存在しなかった。
じゃあ、なぜこの“打ち切り説”はここまで根強くなったのか。
理由はシンプルだ。
「感情が置いてけぼりになった」から。
最終話を読んでも、気持ちが追いつかない。
感動というより、「理解できないまま終わった」ような静けさが残る。
その「わからなさ」は、時に“怒り”や“疑問”に変わりやすい。
理解できなかったから、作品が悪い。 展開が速かったから、打ち切りだ。
そう決めてしまった方が、心はラクだった。
だけど──。
『フェルマーの料理』の最終話に漂っていたのは、
投げやりな打ち切りの空気ではなく、「届かなかった想い」みたいな余韻だったと、私は思ってる。
たぶん、それは“未熟”ではなく、“意図された未完成”。
ネットの噂は、ときに“感情の代弁者”になってしまう。
誰かのモヤモヤが、誰かの混乱に火をつけて、
やがて「事実」みたいな顔をしてしまう。
でもそれは、「物語の全体」を見失う危うさでもある。
この章のまとめとして、私はこう書いておきたい。
“打ち切り”という言葉が強すぎて、 本当はもっと繊細だった終わり方の“理由”が、 見えなくなってしまっていたのかもしれない。
次の章では、実際の連載終了の背景──
編集部や作者の意図に、もう少し耳を澄ませてみようと思う。
4. 実際の連載終了の背景──『月刊少年マガジン』編集部コメントの考察
| 公開情報 | 内容 |
| 講談社からの公式発表 | “打ち切り”という表現は一切なし。あくまで「完結」 |
| 編集部コメント | 具体的な終了理由への言及はなく、「お疲れ様でした」の一文のみ |
| 作中のラストページ | 作者コメントに「最終回」「完結」「読者への感謝」あり |
「編集部からの発表は?」
「作者のあとがきは?」
“打ち切り”というワードが飛び交う中で、読者たちは情報源を探し回った。
でも、そのどこにも、「突然の終了です」という言葉はなかった。
講談社の公式サイトでも、最終巻の帯でも、
書かれていたのは「完結」「感謝」「ありがとうございました」──
ただそれだけ。
編集部のコメント欄も、最終話に添えられた言葉も、
まるで“予定されていたゴールにたどり着いた物語”のように、静かに終わっていた。
だけど…私は思う。
「“何も言わない”って、すごく強いメッセージだな」って。
編集部や作者が沈黙を選んだのは、
きっと“誤解されてもいい”という、覚悟の表れだったんじゃないかと思う。
つまり、それって──
本当に描きたかった終わり方を、貫いたということじゃないのかな。
もし本当に“打ち切り”だったのだとしたら──
もう少し取り繕った表現や、読者への“フォロー”があったはず。
でも、『フェルマーの料理』の終わり方は、それとは真逆だった。
説明も、予告も、言い訳もなかった。
それは一見、読者を突き放すように見えるかもしれないけど、
私はむしろ「信頼されていた」感覚を覚えた。
「きっと、ここまで読んでくれた人なら、
この終わり方の意味も、ちゃんと感じ取ってくれるだろう」
そう言われてるような、
ちょっと誇らしくなるような、静かな対話の余韻があった。
もちろん、それがすべての読者に届いたとは限らない。
でもこの作品は、たぶん最初から“説明過多”とは無縁だった。
数学の難解な比喩、料理の専門用語、登場人物の沈黙。
すべてが「わかりやすさ」よりも、「空気を感じる力」を求めてくる。
だからこそ、最後まで「読み手を信じていた」作品でもあったんだと思う。
──最後に。
作者・小林有吾さんのあとがきにあった言葉を、そっと記しておきたい。
「この物語は、数学の世界から降りてきた少年が、
厨房で人の心に触れた記録です。」
“打ち切り”とか“完結”とか、そんなジャンル分けではなく。
「記録」として残された物語だった──私はそう受け取りたい。
次は、そんな記録がどんなラストを迎えたのか。
「完結」か「未完」か、その温度を感じにいこう。
5. 結末は“未完”なのか“完結”なのか──読後感の温度差をめぐって
| 視点 | 受け取られ方 |
| 物語としての構造 | 主要対決・成長は描かれており、一応の終結は見える |
| 伏線や余白の量 | 回収されていないエピソードが多く、余韻が残る |
| 読後の感情 | 「静か」「物足りない」「考えさせられる」など人により温度差あり |
“終わり”って、どういうことなんだろう。
ページを閉じたあと、私はずっと考えてた。
『フェルマーの料理』のラストは、
クライマックスらしい激しい対決や、感動の号泣シーンではなかった。
だけど、不思議と心に“ざわり”とした余韻だけが残っていて。
それは、うまく言葉にできない感情だった。
朝倉と岳の関係は、解決したようで、してないようで。
岳の“数学を捨てた理由”も、どこかまだ曖昧で。
だけど不完全というより、「言葉にならないまま終わることを許された物語」のように感じた。
正解がない。説明がない。
なのに、ページをめくる手は止まらなかった。
そして、読み終わったとき、こんな言葉が浮かんだ。
「これ、未完じゃない。
たぶん、“私たちが完成させる物語”だったんだ。」
作者が描かなかった部分。
編集部が語らなかった裏側。
キャラクターが沈黙した理由。
その全部が、私たちの“想像”にゆだねられている。
人によっては「それは不親切だ」と思うかもしれない。
「回収されてない=未完」と断じたくなる気持ちも、わかる。
でも、私はむしろ、そこに“作家としての誠実さ”を感じた。
誰かの人生だって、全部説明なんてされない。
伏線なんて張られないまま、急に展開する日常だってある。
『フェルマーの料理』のラストは、そんな“現実の余白”に似ていた。
そしてそこに、私は少しホッとした。
完璧に計算されて、伏線をすべて回収して、
気持ちよく終わる物語はもちろん好き。
だけど、そればかりじゃ疲れてしまう。
わからなかったことがある。
気になるままのキャラがいる。
それでも、「これは終わりだった」と自分で決められる物語。
そんな読者の“余白を信じる力”を育ててくれるラストは、そう多くない。
未完か、完結か。 それは“ページ数”じゃなくて、“自分の心の収まり方”で決めていい。
そして私は、この物語にちゃんと収まった。
読者によって感じ方の“温度”が違うのは当然だと思う。
でもその温度差こそが、
この作品が「誰かの心に触れていた証拠」なんじゃないかな。
次のセクションでは、なぜこの作品が“短い巻数”で終わったのか、
その制作上の事情や挑戦について、もう少し見つめてみよう。
(チラッと観て休憩)【TVアニメ「フェルマーの料理」PV】
6. 人気の割に巻数が少ない理由──構成上の挑戦と掲載ペース
| 視点 | 要素 |
| 連載雑誌 | 『月刊少年マガジン』連載(月刊誌のため進行が遅い) |
| ストーリー構成 | 対決メインではなく「内面描写」重視で進行 |
| 巻数と話数 | 全7巻・41話(1巻あたり約6話収録) |
「えっ、これで終わり? もっと続いてよかったのに…」
そんな声が多かったのも、正直わかる。
『フェルマーの料理』の世界観には、もっと見たい景色がたくさんあった。
だけど、この全7巻という“短さ”には、ある種の“挑戦”が含まれていた気がする。
まず、連載されていたのは『月刊少年マガジン』。
週刊誌と違い、月に一度の掲載だから、当然進行ペースはゆっくりだ。
それでも約3年で7巻分──
掲載期間でいえば妥当なボリュームだけど、体感としては「駆け足」に感じる読者も多かったと思う。
なぜなら、この作品は“時間をかけて読みたくなる構造”をしていたから。
台詞の行間、登場人物の沈黙、
そして、数式のように張り巡らされた比喩の数々。
それらを一つひとつ咀嚼するには、もっと“余白”が必要だった。
でも逆に言えば、
この密度の物語を10巻、15巻と続けるには、“読者の集中力”との戦いでもあったはず。
作者・小林有吾さんは、もともと『アオアシ』のような長期作品を手がけてきた方。
その彼が、ここで7巻というスケールで物語を閉じた理由──
それはきっと、“物語の中身に必要だった分量だけ描く”という決断だったんじゃないかと思う。
世の中には、「引き延ばして評価を落とす」作品もある。
でも『フェルマーの料理』は、むしろ逆だった。
“終わりどきを見極めた”物語という印象。
物語が飽和する前に、
キャラクターの熱が過熱しすぎる前に、
読者が感情を失速させる前に──
この作品は、静かに自分の幕を下ろしていった。
もちろん、それが「物足りない」と感じる人がいるのも当然。
だけど私は、そこに“信頼感”を覚えた。
長く続けばいいってもんじゃない。 本当に描きたかったことが描けたなら、それで十分なんだ。
そしてこの作品において描かれたのは、
派手なバトルや感動のエンディングじゃなかった。
もっと静かで、繊細で、「他人の価値観と向き合うこと」の苦しさと美しさだった。
それを7巻で伝えるのは、逆にすごく難しいこと。
でも小林有吾さんは、それをやりきった。
この挑戦が“短さ”に見えてしまうのなら、
それは、私たちが“長さ=正義”だと思い込んでいた証かもしれない。
次は、この“密度高め”の原作が、
どうアニメで再解釈されるのか──その期待について語ってみたい。
7. アニメ化が決まった今、再評価される原作の魅力
| 再評価のポイント | 具体的な魅力 |
| 登場人物の内面重視 | 映像化で表情や間(ま)がより深く伝わる |
| 比喩の多層構造 | 映像・音響での“翻訳”により感情が届きやすくなる |
| 展開のスピード感 | 短巻数ゆえにアニメ化しやすく、テンポ良く展開 |
2025年夏、TVアニメ『フェルマーの料理』が放送される。
完結から1年半──
このタイミングでのアニメ化に、少しだけ“意志”を感じた。
たぶんこれは、「まだこの物語は終わってない」っていう
もうひとつの合図だったのかもしれない。
原作が終わったあとにアニメ化されることで、
あらためて“読むべきタイミング”を与えられた作品。
そして今、改めて原作に向き合うと気づくことがある。
あの沈黙は、あの表情は、きっとこんなふうに映像になるんだろうな──って。
言葉じゃなくて、「余韻で語る」物語。
説明じゃなくて、「気配で理解する」関係性。
これは、まさに“映像の力で広がる物語”なんだと思う。
漫画では想像に委ねられていた“あの瞬間”が、
アニメになったとき、どんな音で、どんな光で語られるのか。
それを考えるだけで、ちょっと息が止まりそうになる。
そして同時に、原作を読んだ人だけがわかる“深読み”もきっと出てくる。
「あ、このセリフ、あの伏線だよね」 「なるほど、だからあそこが急展開だったんだ」 「映像になると、こんなに切なかったんだ…」
漫画のときには見えなかった“裏の表情”が、
アニメで初めて浮かび上がってくる。
その瞬間、“短かったけど濃かった”この作品の輪郭が、
ようやく完成する気がしてる。
──次は、そんな“今だからこそ読みたい”原作を
未読の人にどう伝えるか、最後に整理してみたい。
8. いま読み返す意味──“短命だった名作”という言葉の真意
| 言葉の印象 | 再解釈の視点 |
| “短命だった名作” | “短さ”ではなく“濃さ”で記憶に残る作品という意味 |
| 読み返す価値 | ラストを知った上で読むことで、最初の一話の意味が変わる |
| 今読む意味 | アニメ化で再注目される今だからこそ、心の温度で読む価値がある |
「打ち切りだったらしいよ」
そんな声だけを拾って、この作品を“終わったもの”にしてしまうには、
あまりにももったいない。
『フェルマーの料理』は、たしかに長くは続かなかった。
でもその“短さ”を責める前に、“何がそこに詰まっていたか”を見てほしい。
たとえば、数学を捨てた少年が、料理の世界で
“他人と向き合うことの意味”に目覚めていく過程。
たとえば、対話よりも静寂で語る人たちの関係性。
それは、今この時代に必要な“やさしい距離感”だったと思う。
長く語りすぎると、肝心なことがぼやける。
説明しすぎると、想像が死ぬ。
『フェルマーの料理』は、
そのギリギリのラインを保ったまま、“気づいた人にだけ届くメッセージ”を残していった。
だから私は、この言葉を肯定的に受け取りたい。
“短命だった名作”──それは、“生き急いだ物語”じゃなくて、 “余白ごと抱きしめてくれた作品”のこと。
そして今、この作品をもう一度読むと、
きっと最初のページのセリフの意味が変わって見える。
「あれ、こんなに優しかったっけ?」
「この一言、最後の伏線だったんだ」
物語って、終わってからが本番だ。
アニメ化をきっかけに、そんな再発見をしてくれる人が、
ひとりでも増えたら嬉しい。
──きっと『フェルマーの料理』は、
静かに、でも確かに、読者の“心のどこか”に残っている。
まとめ:打ち切りじゃなかった──“余白の物語”が残したもの
『フェルマーの料理』にまつわる“打ち切り”の噂。
でも実際には、講談社も作者も「完結」としてこの作品を送り出していた。
たしかに、物語にはまだ語られていないことが多く、
すべてがスッキリ回収された終わり方ではなかった。
でもそれを“未完”と決めつけるのは、
この作品の「描かなかった選択」を否定してしまう気がした。
■ 本記事のポイントをあらためて整理すると:
- 公式発表は「打ち切り」ではなく「完結」
- ストーリーは静かに終わる構成で、“余白”を重視
- 月刊誌連載ゆえの巻数の少なさ、構成上の挑戦
- アニメ化によって再注目される“言葉にならない魅力”
“終わり”はいつも曖昧だ。
でもこの作品のラストには、「たしかに終わった」という手触りがあった。
それは、感情の伏線を張りめぐらせたまま、
最後の一皿を差し出してくるような読後感だった。
たぶん、これは「計算式の答え」じゃない。 「余韻という名の余白」を、私たちに渡した物語だったんだと思う。
だから、“打ち切り”じゃない。
むしろ私は、こんなふうに言いたい。
──きっとこの物語は、「読む人の中で、まだ続いている」って。
- 『フェルマーの料理』の“打ち切り”という噂の出どころと事実との違い
- 原作が7巻で完結した背景と、月刊誌ゆえの進行・構成の事情
- 物語ラストの“未完感”と“完結感”を読み解く感情の余白
- 主要キャラたちの関係性と心理描写が物語に与える深層的意味
- アニメ化によって再評価される原作の演出と静かな熱量
- “短命だった名作”という言葉の中にある作家の選択と哲学
- 読者の心に残る“余白を抱いた物語”としての価値と読後感


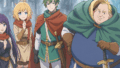
コメント