『チェンソーマン』で世界的な注目を集める漫画家・藤本タツキの“原点”が、ついにアニメ化──それが話題のオムニバス作品『藤本タツキ 17-26』です。 この作品は、藤本タツキが17歳から26歳までに描いた短編漫画8本を原作に、それぞれ異なる監督・制作スタジオが映像化した、まさに“実験的アニメ集”。
劇場での期間限定公開に加え、Prime Videoでの全世界配信も決定しており、「短編集アニメ」「若き日の藤本タツキ」「衝動と実験の物語」として、ファンやクリエイターの間で大きな話題となっています。
本記事では、『藤本タツキ 17-26』に収録された8つの短編それぞれのあらすじ・ネタバレを含む詳細解説はもちろん、作品ごとのテーマやジャンルの違い、演出スタイル、なぜこの企画が注目されているのか──まで、徹底的に掘り下げてご紹介します。
「どんなストーリーが待っているのか?」「チェンソーマン以前の藤本作品はどう違うのか?」「配信前にチェックしておくべきポイントは?」 そんな疑問を持つあなたに向けて、『藤本タツキ 17-26』のすべてを読み解く決定版ガイドをお届けします。
- 『藤本タツキ 17-26』とはどんな作品で、何が収録されているのか
- 各短編のあらすじ・ネタバレ・隠されたテーマの読み解き
- 劇場公開・Prime Video配信のスケジュールと楽しみ方
- 異なる監督・制作スタジオが演出する映像の魅力と狙い
- なぜ今この作品が注目されているのか、その理由と評価の背景
アニメ『藤本タツキ 17-26』劇場版予告
- 『藤本タツキ 17-26』をもっと深く楽しむための注目ポイント一覧
- 1. 『藤本タツキ 17-26』とは?──若き才能を詰め込んだ実験的短編集アニメ
- 2. 公開日・配信スケジュールまとめ|映画&Prime Videoの展開を解説
- 3. 全体テーマと作風|「衝動」「変身」「愛と死」が交錯する藤本タツキの原点
- 4. 『庭には二羽ニワトリがいた。』あらすじ・ネタバレ完全解説
- 5. 『佐々木くんが銃弾止めた』あらすじ・ネタバレ解説
- 6. 『恋は盲目』あらすじ・ネタバレ解説
- 7. 『シカク』あらすじ・ネタバレ解説
- 8. 『人魚ラプソディ』あらすじ・ネタバレ解説
- 9. 『目が覚めたら女の子になっていた病』あらすじ・ネタバレ解説
- 10. 『予言のナユタ』あらすじ・ネタバレ解説
- 11. 『妹の姉』あらすじ・ネタバレ解説
- 12. 監督・制作スタジオ別一覧|映像表現・演出スタイルの違い
- 13. ファンが注目する理由|『チェンソーマン』へ続く“原点”の魅力
- 『藤本タツキ 17-26』記事内容まとめ一覧
- 本記事まとめ. “実験と衝動の履歴書”──藤本タツキ『17-26』全短編から見える原点の全貌
- 『藤本タツキ 17-26』全短編・テーマ・見どころまとめ
『藤本タツキ 17-26』をもっと深く楽しむための注目ポイント一覧
| 注目ポイント | 内容のヒント(詳しくは本文で) |
|---|---|
| 劇場と配信の公開タイミング | 限定公開と世界配信の“二段構え”戦略が話題に |
| 8つの短編、それぞれのジャンル | ラブコメ?ポストアポカリプス?予想外の展開が待つ |
| 異なる監督・スタジオ体制 | 作品ごとに全く違う映像体験が楽しめる理由とは? |
| 「藤本タツキらしさ」とは何か? | チェンソーマンだけじゃない、“原点の衝動”に迫る |
| 観る前に知っておきたいこと | 作家本人の“10代の実験”がどう映像化されたか |
| ファンが熱視線を送る理由 | 新規でも楽しめる?ファンならさらに深く刺さる? |
| 一番話題になる作品は? | “あの作品”がアニメ化された!SNSで騒がれているのは… |
1. 『藤本タツキ 17-26』とは?──若き才能を詰め込んだ実験的短編集アニメ
“17歳から26歳までに描かれた短編集”と聞くと、普通は“初期作品の寄せ集め”のように思われるかもしれない。でもこの『藤本タツキ 17-26』は、全然ちがった。 それは、ただの原点回帰じゃなく、“むきだしの衝動”がそのままアニメになったような感覚だった。
| タイトルの意味 | 作者・藤本タツキが17歳から26歳の間に描いた短編作品8本を指す |
|---|---|
| 映像化形式 | オムニバス形式/2部構成(Part-1/Part-2)で構成 |
| 公開スケジュール | 2025年10月17日~劇場公開(2週間限定)/11月8日よりPrime Videoで世界独占配信 |
| 収録作品 | 『庭には二羽ニワトリがいた。』『佐々木くんが銃弾止めた』『恋は盲目』など全8作 |
| 映像演出の特徴 | 各話ごとに異なる監督・スタジオが担当し、作風の振れ幅を可視化 |
| 全体のテーマ | 衝動/青春/死生観/変身/暴力と静けさ──感情の“実験場” |
藤本タツキといえば、『チェンソーマン』や『ルックバック』で知られる作家。 でも、それより前。まだ賞も連載もなかった時代、彼は自分の感情と葛藤を短編の中に落とし込んでいた。
その作品たちがアニメ化されるというのは、言ってしまえば「過去の自分との再会」だ。 普通なら、ちょっと気恥ずかしいし、ファンにとっても“粗が見えてしまう”リスクがある。 でも『藤本タツキ 17-26』は、その“未完成”こそが作品の価値であり、感情のリアルだった。
たとえば、『シカク』では殺し屋の少女と不死の男の関係が、“生きること”の虚無と矛盾をえぐってくる。 『恋は盲目』では、青春の爆発がギャグになりそうでならないギリギリを跳ねていく。
全8話すべてが、ジャンルもテイストもバラバラ。 でも、根っこには共通して“迷ってる感情”と“拙い正直さ”がある。
そして映像化にあたり、各話に異なる監督・制作スタジオが起用されているという点がすごく大きい。 まるで「ひとりの作家の中にある別人格たち」が、それぞれの声で語っているようだった。
この作品は、単なる“再現”ではなく、原作を踏まえながらも、それぞれの映像チームが新しい“感情の解釈”をしている。 だから、原作を知っている人でも「こんなふうに映されるんだ」とハッとさせられる瞬間がある。
そして、このプロジェクトの構成も見逃せない。
- 劇場公開:2025年10月17日から2週間限定
- Prime Video配信:2025年11月8日から世界独占配信
この「劇場+配信」の二段構えは、アニメファンや考察勢にとっての“儀式性”すら感じさせる。 劇場でまず“空気を浴び”、配信でじっくり“咀嚼する”。 そんな体験設計がされているように思えた。
藤本タツキの短編集って、読む人のその時の感情によって見え方が変わる。 だからこそ、この映像化で“もう一度出会う”価値がある。
あの頃の作者はきっと、こんなにアニメになるなんて想像してなかった。 でも今、私たちはその“過去の叫び”を、映像で受け取ることができる。
それって、ちょっと照れくさくて、でも嬉しいことかもしれない。
完璧な物語じゃない。 でも、“あの頃しか描けなかった感情”が、ちゃんと息をしていた。
2. 公開日・配信スケジュールまとめ|映画&Prime Videoの展開を解説
「劇場か、配信か」じゃなくて、その両方を“ひとつの作品体験”にしてくれる── 『藤本タツキ 17-26』の公開スケジュールは、まさにそういう仕掛けになっていた。
| 劇場公開日 | 2025年10月17日(金)より全国劇場で2週間限定公開 |
|---|---|
| 劇場構成 | Part 1(4話構成)→上映期間中にPart 2(残り4話)へと切り替え |
| 配信開始日 | 2025年11月8日(土)よりPrime Videoで世界独占配信スタート |
| 配信形式 | 全8話を一挙配信/字幕・吹替対応/グローバル展開 |
| 視聴可能プラットフォーム | Prime Video(Amazon会員登録が必要) |
| 劇場との違い | 劇場は“初見の集中体験”、配信は“繰り返しの深掘り”に向く構成 |
まず、劇場公開は2025年10月17日から、全国の主要劇場にてスタート。 特徴的なのは、「2週間限定公開」という枠のなかで、Part 1とPart 2に分かれて上映されたこと。
観客は、まず前半の4本(Part 1)をスクリーンで目撃する。 数日後、劇場では後半の4本(Part 2)に切り替わり、まったく違うジャンルと空気を持つ4作品に出会う。
つまり、1回だけ観るのではなく、“二度劇場に通うことが前提”になっている構造。 これは短編集ならではの「分裂した感情体験」を、時間差で咀嚼させる巧みな演出だと感じた。
そして、配信はその2週間後、2025年11月8日からPrime Videoにてスタート。 すでに劇場で観た人は、もう一度ゆっくり噛み締めることができるし、劇場を見逃した人にも“温度ごと”届く設計になっている。
しかも、全話一挙配信というかたちで、一気見も可能。 「1日で藤本タツキの“17歳~26歳”を巡る旅ができる」という異常な濃度。 けれど、その密度の中で、観る人の心にひとつずつ“引っかかり”が残るような作りになっていた。
劇場と配信──この2つのプラットフォームは、まったく違う空気をもっている。 映画館の暗闇は、あの作品たちの“暴走”を際立たせる。 一方で、配信ではリモコン片手に「なんでこうなったんだろう」と考えながら観られる余白がある。
この二重構造は、作品ごとの「解釈のズレ」や「温度差」を許容する。 それがこの『藤本タツキ 17-26』というアンソロジーの魅力でもあると思った。
もうひとつ、忘れてはいけないのが「グローバル配信」であるという点。 Prime Videoでの世界同時配信は、日本だけでなく海外の藤本ファン、アニメファンにも届いている。
世界中の人が、藤本タツキの“原点”に同時に触れるということ。 これは、創作の裏にある「どうしてこんな感情を描く人になったのか?」という問いに、国境を越えて共鳴が生まれる瞬間でもある。
たぶん、この作品は“初見で完璧に理解されること”を目指していない。 それよりも、「あの4話目だけ何かひっかかった」「この2本だけずっと考えてる」――そんなふうに、観る人それぞれの“個人的な余白”に残っていくような存在。
だからこそ、劇場と配信というふたつの視聴導線が必要だったのかもしれない。
藤本タツキという作家の、“過去を観る”という体験。 それはただの懐古じゃなくて、“自分の17歳や26歳と向き合う”時間になるのかもしれない。
3. 全体テーマと作風|「衝動」「変身」「愛と死」が交錯する藤本タツキの原点
この『藤本タツキ 17-26』という作品群は、ただの短編集ではない。 もっと不安定で、未完成で、だけどやけにリアルな“感情の地図”のようだった。
| 収録作品数 | 全8作品(すべて短編オムニバス形式で構成) |
|---|---|
| ジャンルの幅 | SF/ファンタジー/学園ドラマ/ラブコメ/アート/ホラー要素など多彩 |
| 共通する主題 | 衝動/変身/暴力と愛/死と再生/他者とのすれ違い |
| 作風の特徴 | ジャンルをまたいでなお“人間の心のグロさ”と“哀しみ”がにじむ構成 |
| 表現の傾向 | 沈黙、間、余白、突然のグロ描写、繊細なモノローグが多用されている |
| 映像演出の印象 | 実写に近い質感/抽象的演出/キャラの“温度”を重視した描写が目立つ |
どの作品にも共通して感じられるのは、「感情の一瞬の爆発」が物語の引き金になっていること。 それは“変身”であり、“逃走”であり、“誰かを殺したくなるくらいの愛情”だったりもする。
たとえば『目が覚めたら女の子になっていた病』では、「男としての自分」から逸脱したとき、 主人公が初めて“他者の視線”や“性別の呪い”に気づく。
『妹の姉』では、才能という名のナイフが、姉妹の関係を静かに断ち切っていく。
テーマはばらばらに見えて、その根っこには、いつも「自分って何?」という問いがある。 それは“青春”とも言えるけど、それよりももっと“誰にも言えない怒り”に近い。
藤本タツキが描くのは、善悪の話じゃない。 正しいとか、間違ってるとか、そういう話を飛び越えて、 「どうしようもなく心がぐちゃぐちゃになる瞬間」を逃さずに描いている。
たとえば、『佐々木くんが銃弾止めた』では、 恋でも正義でもない、ただの“欲望”が、突然“命がけ”になる。
それって冷静に考えたら、おかしな話だ。でも、人の感情って、そういうものかもしれない。
特に印象的なのが、「死と再生」がほとんどの話に含まれていること。 誰かが死ぬ、誰かが壊れる、世界が終わる──でもそのあと、 必ず何かが“残る”ように描かれている。
それが「記憶」だったり、「絵」だったり、「動かなくなったピアノ」だったりする。
壊れたあとに残るもの、それこそがこの短編集の“感情の核”だと思った。
そして、それを映像で表現した各スタジオの演出がまた、絶妙にちがっていておもしろい。
静寂のなかに怒りを埋め込んだ作品もあれば、 ギャグのような会話の裏に、涙がしみているものもある。
どれも“本当の気持ち”を声に出せなかった人たちの話。 だからこそ、観る側も静かに苦しくなる。 でも、不思議と優しさも残る。
この作品群には、「正解」が用意されていない。 だけど、どれも“なかったことにはできない気持ち”だけが、確かに画面に残っていた。
それは、今の藤本タツキが見せてくれる“計算された完成”ではなく、 もっと幼くて、もっと叫ぶような感情。
その叫びが、ちゃんと映像の中に、息づいていた。
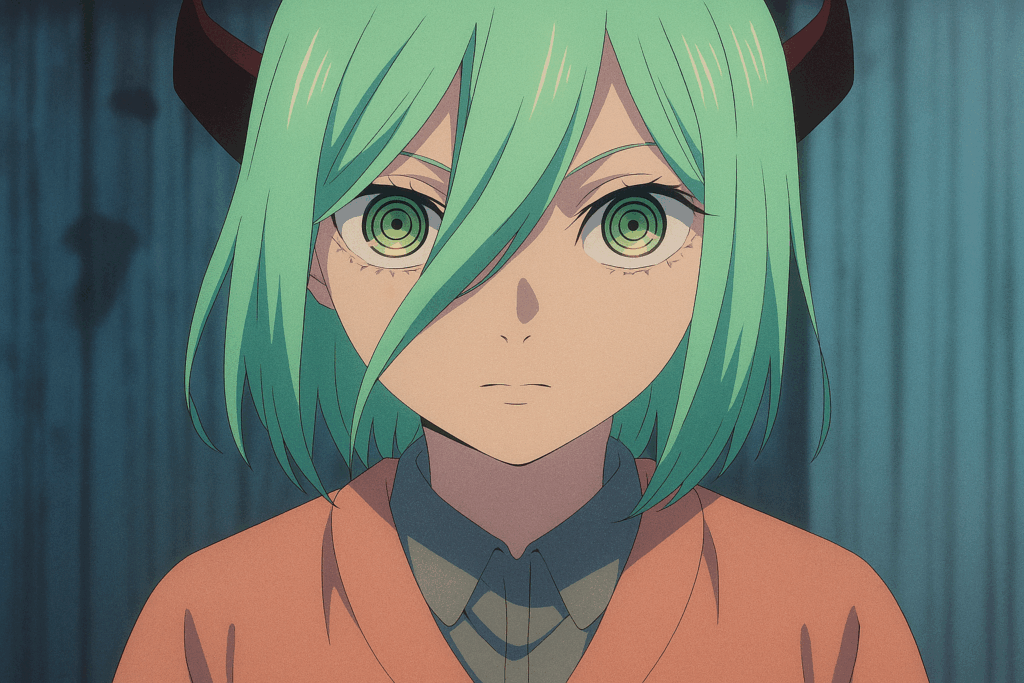
【画像はイメージです】
4. 『庭には二羽ニワトリがいた。』あらすじ・ネタバレ完全解説
藤本タツキ作品群の中でも、最も“静かに怖くて、可愛くて、気味が悪い”のがこの短編だ。
| タイトル | 庭には二羽ニワトリがいた。 |
|---|---|
| ジャンル | SF・ディストピア寓話・ブラックユーモア |
| 主な登場人物 | 少年と少女(名前不明)/宇宙人たち(支配者)/一羽のニワトリ |
| 舞台設定 | 地球が滅び、宇宙人が地上を支配した後の世界 |
| 仮面の意味 | 人間であることを隠す“ニワトリのマスク”をかぶって生活する少年少女 |
| 物語の転換点 | 飼っていたニワトリが“元人間”だったことが判明 |
| 最終展開(ネタバレ) | 主人公たち自身も、かつて“宇宙人に飼われた人間”であり、逃げ延びた存在だった |
| 主題 | 支配と従属の転覆/生物の命の線引き/「人間とはなにか」 |
物語は、少年と少女が荒廃した地球でニワトリの着ぐるみを着て暮らす様子から始まる。
人類はすでに宇宙人に敗北し、地球は彼らの管理下にある。 地上に残された少数の人間は、宇宙人の目を欺くために「ニワトリのふり」をして生活しているのだ。
彼らが暮らす場所には、もう“文化”も“秩序”もない。 物語の描写には、学校も社会も大人も登場しない。あるのは「逃げる知恵」と「生き延びる習慣」だけ。
そんな彼らが大切にしているのが、庭で飼っている一羽のニワトリ。 食糧のためでもあり、心の拠り所でもある。
だがある日、少女がそのニワトリに異様な反応を示す。 そして「このニワトリ、夢でしゃべってた」と口にする。
ここから物語はゆっくりと崩れていく。 ニワトリの目がどこか“人間っぽい”。 そしてその羽根に、かすかに数字の焼き印が押されていることに少年が気づく。
調べるうちに分かる。 そのニワトリは、もともと“人間”だった。
宇宙人たちは、人間を家畜化する過程で、 外見をニワトリやブタに「改造」していたのだ。
少年たちが今、家畜として隠れていると思っていたが、 それは「人間として生きる」ことを放棄するための擬態だった。
つまり、ニワトリになった人間を飼いながら、 人間の姿をしていた自分たちも“飼われていた”側の存在だった。
物語の終盤、宇宙人たちが家畜としてのニワトリ(=元人間)を“出荷”しに来る。
少年たちは、逃げるべきか、戦うべきかを話し合うが、 最終的に彼らは“ニワトリのふり”を選ぶ。
ラストシーンでは、 宇宙人が歩いていく背景で、主人公たちが無言で“コケコッコー”と鳴きながら、 庭の隅で身を縮めて座っている。
その表情は恐怖でも希望でもなく、 ただ“何かを諦めて生き延びることを選んだ顔”だった。
そしてカメラは空を仰ぎ、 かつてこの星が人間のものだったことを忘れていくように、光が白く薄れていく。
藤本タツキがこの作品で描いたのは、「人間らしさ」とは何か、 という哲学であり、 「生き残るためにどれだけ自分を捨てられるか」という残酷な選択だった。
グロテスクな描写もある。 だけどそれ以上に、「自分の姿がゆっくり壊れていく」恐ろしさが、 画面の隅々からにじみ出ていた。
そして最も衝撃だったのは、 この物語に“悪者”が一人もいないことだ。
宇宙人は無表情に規則を遂行し、 主人公たちはただ「死にたくない」と思って仮面をかぶる。
でも、その全員が何かを“間違っていない”。 だからこそ、この話は悲しい。
誰も間違っていない世界で、 人間が“ニワトリになること”だけが、唯一の選択肢だったということが。
これは「弱さ」の物語だ。 そして、その弱さこそが、 藤本タツキという作家の“原点”を最も濃く象徴しているように思えた。
『藤本タツキ 17-26』17分26秒の特別映像|プライムビデオ
5. 『佐々木くんが銃弾止めた』あらすじ・ネタバレ解説
「思春期の“衝動”はどこまで命を動かせるのか?」 そんな問いを、藤本タツキはとても静かで、残酷で、そして荒々しい方法で突きつけてくる。
| タイトル | 佐々木くんが銃弾止めた |
|---|---|
| ジャンル | 学園スリラー・超常現象・青春ドラマ |
| 主な登場人物 | 佐々木くん/担任の川口先生/かつて先生に恋した“男”/春休み補習の生徒たち |
| 物語の舞台 | 高校の教室(春休み補習中) |
| 中心テーマ | 衝動/恋慕/自己犠牲/静かな英雄譚 |
| 物語の転換点 | 元生徒が銃を持って乱入し、教室で発砲事件が起きる |
| 核心の出来事(ネタバレ) | 佐々木が“素手で銃弾を止めて”クラスを救う超常的展開 |
| 佐々木の動機 | 好きだった先生に「会いたくて来た」ただそれだけ |
| 物語の余韻 | 誰にも認知されない“奇跡”が静かに過ぎていく |
教室は、もっとも安全で、もっとも無関心な空間だと思っていた。
だが物語は、そんな場所に“銃”が持ち込まれることで、 一気に現実が崩れ落ちていく。
佐々木くんは、特別でもなんでもない男子高校生。 春休みの補習に、なんとなく出席している。
だが、その動機はただひとつ── 「担任の川口先生に会いたかった」から。
そして事件は起きる。 教室のドアがバンと開き、 「かつて川口先生に告白して振られた男」が、銃を手に現れる。
教室は一気に凍りつき、 生徒たちは机の下に身を潜める。 だが、誰一人として「止めに行こう」とはしない。
そのとき、佐々木が静かに立ち上がる。
彼は、歩く。 ゆっくりと、銃口の前まで。
発砲される── だが銃弾は、佐々木の手のひらで止まる。
血も出ない。痛みもない。 佐々木は微笑み、ただ一言「先生、また会えてよかったです」と言う。
ここで物語は大きく揺れる。 これは「能力もの」なのか?「象徴的表現」なのか?
だが藤本タツキは、説明しない。 あくまで、佐々木は「普通の男子高校生」として描かれ続ける。
ラストシーンでは、事件後の学校の様子が描かれる。 教室の床には、砕けた机と血痕の跡がある。
だが誰も、佐々木の行動を語らない。
佐々木は、もうそこにはいない。
ただ、先生がふと窓の外を見たとき、 遠くの校庭に、佐々木らしき影がひとり立っていた。
そして一瞬、風が吹き、制服の裾がなびく── その瞬間、先生はなぜか泣きそうな顔をして、窓から目をそらす。
物語は、ここで終わる。
この作品で描かれたのは、“自己犠牲”のようでいて、 実は“片思いの純粋な衝動”だった。
人は、「好きな人に会いたい」という気持ちだけで、 世界を救うような行動をしてしまうことがある。
でも、それは誰からも気づかれないまま、 なかったことのように、日常に吸収されてしまう。
藤本タツキは、この短編で「ヒーローにならなかった英雄」の姿を描いた。
佐々木が銃弾を止めたのは、“力”ではない。
ただ、心がそう動いてしまったから。
それが“青春”だとしたら、 これほど静かで切ない物語は、他にない。
6. 『恋は盲目』あらすじ・ネタバレ解説
「恋をすると、人は宇宙にすら手を出してしまう。」 藤本タツキが描く“SF青春ラブコメ”──それがこの『恋は盲目』だ。
ただの恋愛モノではない。 この物語は、“想いが暴走する”という現象を、物理法則ごと狂わせるスケールで描いている。
| タイトル | 恋は盲目 |
|---|---|
| ジャンル | SFラブコメ・青春・超常ファンタジー |
| 主要人物 | 生徒会長・伊吹/後輩女子・ユリ |
| 舞台 | 高校卒業式の夜/誰もいない校舎と帰り道 |
| 中心テーマ | 抑えきれない衝動/未熟な感情/青春の限界突破 |
| 物語の鍵(ネタバレ) | 伊吹の“想い”が現実改変を引き起こす。校舎が崩壊し、空が割れる |
| 展開の転換点 | 告白のタイミングで突如“時空の歪み”が発生する |
| 最終結末(ネタバレ) | ユリのひとことが、すべてを“現実”に戻す |
| メッセージ | 恋は自分の中の“宇宙”を壊すほどの力を持っている──でも、それでいい |
物語は卒業式の夜、生徒会長の伊吹が長年片想いしていた後輩・ユリに声をかけるところから始まる。
舞台は誰もいない夜の校舎。 ただの帰り道、ただのひとことを伝えるだけの時間。
……のはずだった。
だが伊吹の胸に宿った“恋の衝動”は、 言葉を発するその瞬間、現実に異常を起こす。
まず空が裂け、星が落ちる。 教室のガラスが「音もなく」砕け、廊下が無限に伸びていく。
ユリは驚きながらも伊吹の言葉を待つが、 その“宇宙的暴走”は次第に加速していく。
校舎が宙に浮き、時計の針が逆回転し始める。 あらゆる物理法則が狂い出し、二人だけが取り残されたような世界が誕生する。
伊吹は、気づいていない。 自分の感情がこの空間を破壊し始めていることに。
だが、彼はそれでも言いたかった。
「好きです」
その瞬間、校舎が崩壊する。 大地が裂け、空間が“裏返る”。
ユリは宙に浮かび、伊吹に手を伸ばす。
「……うるさい」
ユリのその一言が、すべてを止めた。
世界が戻る。 音が戻る。 色が戻る。
二人は、いつもの通学路に立っていた。
伊吹の顔は真っ赤で、ユリは笑っていた。
「でも、ありがとう」
物語は、あまりにも静かに終わる。
この作品が秀逸なのは、 “恋をすると世界が壊れる”という比喩を、 本当に壊すことで描いているところにある。
愛の暴走、青春の焦燥、告白の爆発。 藤本タツキはそれを、SF的スケールと笑えるギャグの中に埋め込んだ。
だが、だからこそ響く。
たった一言で崩れる世界。 でも、それを止めるのも、たった一言。
これは恋の物語であると同時に、 「自分の感情に責任を持つ」という、青春の終わりの物語でもある。
告白することで壊れてしまった宇宙と、 それでも残った“日常”という余韻──
『恋は盲目』は、まさに“恋することで見えなくなるもの”と“見えるようになるもの”を、 ひとつのコメディSFに詰め込んだ、藤本タツキ流・超新星ラブストーリーだった。
7. 『シカク』あらすじ・ネタバレ解説
「殺してくれ」と言われたとき、人はどう応えるのか── 藤本タツキが描く『シカク』は、“殺し”と“生”の狭間で揺れる、異端の愛の物語だ。
| タイトル | シカク |
|---|---|
| ジャンル | バトル・ダークファンタジー・異形ロマンス |
| 主要人物 | 殺し屋の少女・シカク/不死の吸血鬼・ユゲル |
| 舞台 | 都市の暗黒地帯/廃工場/地下道などの陰鬱な空間 |
| 中心テーマ | 殺しと再生/不死の苦悩/破壊衝動としての愛 |
| 核心展開(ネタバレ) | 不死の男が少女に“自分を殺してほしい”と依頼する |
| シカクの葛藤 | 「殺しの快楽」と「生きる意味」の間で揺れる |
| ユゲルの過去 | 3500年間、死ねずに愛も絶望も味わい尽くした存在 |
| 最終展開(ネタバレ) | シカクが“殺す”ことでユゲルの命を終わらせ、笑顔で涙を流す |
舞台は、ゴミと腐臭に満ちた、夜の都市の片隅。 シカクは、殺し屋として暗黒世界で名を馳せる少女だ。
冷酷、無表情、無慈悲──そう思われているが、 彼女はただ、「殺すこと」しか知らずに生きてきた。
そんな彼女のもとに、ある日ひとりの男が現れる。
名をユゲル。吸血鬼。 およそ3500年にわたり、死ぬことを許されなかった存在だ。
彼は、シカクにこう言う。
「君に、僕を殺してほしい」
それは依頼ではなく、願いだった。
最初、シカクは彼を嘲笑する。 「死にたい奴が、なんで生きてきたんだ?」
だが、ユゲルは静かに語る。 愛した人々が次々に消えていったこと。 善も悪も、意味も虚無も、すべて飲み込んできたこと。
「生きるってのは、罰だよ」
その言葉に、シカクの中で何かが揺れる。
彼女もまた、殺すことでしか“自分”を証明できない存在だった。
2人の戦いが始まる。 刃が交錯し、血が飛び、再生し、また戦う。
だが、その中で、互いの“孤独”が滲み出していく。
戦いはやがて、踊りのようになり、 暴力は奇妙な“対話”へと変わっていく。
クライマックス、シカクはユゲルの心臓に刃を突き立てる。
だが、ユゲルは死なない。
「お前も……死ねないのか?」
そう呟いた瞬間、ユゲルの瞳が潤む。
「やっと、終わる気がしたんだ」
シカクは最後に、ユゲルに向かって笑いながら言う。
「アンタ、うざかった。でも、アンタを殺して、やっとあたしも生きれた気がする」
その言葉と共に、ユゲルの肉体が灰になり、風に消えていく。
ラスト、シカクは街の屋上に立ち、 初めて涙を流しながら夜明けを見つめている。
誰も知らない場所で、誰にも理解されない“殺し”を通して、 2人はほんの一瞬だけ、人間になれた。
『シカク』は、愛とはなにか、生とはなにか、 そして“殺すこと”は救いか否かという、重くて深い問いを あえてスタイリッシュな暴力と軽妙なセリフで語ってみせた傑作だ。
藤本タツキが見せる、「死ねない者」と「殺すことでしか生きられない者」の交差点── それは、どこまでも暗く、どこまでも美しかった。
8. 『人魚ラプソディ』あらすじ・ネタバレ解説
海の底に響く一音のピアノ、それを“宝物”にしてしまう少年がいた。 その前に現れたのは、人魚の少女だった――。 この『人魚ラプソディ』は、静かでありながら胸を揺さぶる、 “異種との邂逅”と“記憶と喪失”の交差点を描いた物語だ。
| タイトル | 人魚ラプソディ |
|---|---|
| ジャンル | ファンタジー恋愛・海中幻想・叙情ドラマ |
| 主要人物 | 少年トシヒデ/人魚の少女シジュ/トシヒデの父親・漁師/海辺の町の人々 |
| 舞台 | 海辺の町と、その沖に沈む“人魚のピアノ”が眠る海底 |
| 中心テーマ | 記憶と忘却/人間と異種の壁/音楽という共通言語 |
| 物語の鍵(ネタバレ) | トシヒデが海底でピアノを弾くと、人魚シジュが近づき声をかける |
| 転換点 | 人魚の母が人間に“喰われた”という過去が明かされる |
| 最終結末(ネタバレ) | トシヒデとシジュが連弾することで、人魚と人間の溝が一瞬、音で埋まる |
| メッセージ | 違う“定義”の存在でも、音(音楽)が共鳴をもたらす |
物語の始まりは、海辺の町。 少年トシヒデの“宝物”は、誰にも知られていない。 それは、海の底に捨てられた“人魚のピアノ”。
彼は毎晩、人目を避け、波の音と共にそのピアノを弾いていた。 鍵盤に指を置くと、海が応えるように静かに震える。
ある夜、ひそかに耳を澄ませていたのは、人魚の少女・シジュだった。 人魚である彼女は、表情に“人間の憂い”を宿していた。
「あなた、弾くのね」
その一言で、トシヒデの世界は変わる。 弾くことを“誰かに見られる”ということ、 そして“誰かと響き合う”ということ。
物語が進むと、シジュは、自分の母親の記憶を語り始める。 母はかつて、人間たちに捕らわれ、人魚であることを理由に喰われてしまったという過酷な過去。
その告白が、少年の胸に静かな衝撃を与える。 海の底で、沈黙の中で生きてきた彼女の声が、 トシヒデの心を打った。
「音楽だから、違うの」
人魚と人間、その立場の違いを突きつけられながらも、二人の指は鍵盤の上で交わる。 音が、壁を壊した。
ラストでは、アニメ版オリジナルの連弾シーンが挿入され、 少年と人魚が同じ鍵盤に手を置くことで、 “種”を越えた共鳴が描かれた。監督はこの場面に最も時間を割いたと語っている。
その瞬間、海も時間も静止したような錯覚が観る者に訪れる。 そして、ピアノの音が切れたあと、二人はただ肩を並べて海を見ている。
この作品が私にとって響いたのは、 “記憶を手放すこと”と“音で繋がること”が同時に起きているからだった。 トシヒデは母の顔も、名前も覚えていないと語っていた。 その無垢な喪失感が、人魚という存在を前にして痛みを帯びる
音楽が物語を動かす。 それは言葉を超え、種の壁を超える。 そして、私自身の内にある“逃げたくなる感情”や“受け入れたくない過去”を、少しだけ見せてくれた。
『人魚ラプソディ』は、ファンタジーの装いをまといながら、 私たちが普段見ない“違う者”との接触を、 とても優しく、でも確実に、心に残るかたちで映像化していた。
この作品を観終えたあと、私は海の音を思い出した。 そして、何かを“弾かなきゃ”という衝動にも似た気持ちが胸をくすぐった。
「弾く」という行為は、たぶん“存在を証明すること”でもある。 そして、記憶を失った者が音楽を通じて“帰る場所”を見つけるという構図が、 この短編の静かな核だと思った。
完璧を求めず、完成を約束せず。 でも、確かに響いて、残って、忘れられない。 これが、若き 藤本タツキ の“実験”であり“贈り物”だったのかもしれない。
9. 『目が覚めたら女の子になっていた病』あらすじ・ネタバレ解説
朝起きたら、“性別が変わっていた”。 荒唐無稽でライトな設定に見えるが、 その裏にあるのは、藤本タツキ特有の“自意識の解体”と“アイデンティティの再構築”だった。
| タイトル | 目が覚めたら女の子になっていた病 |
|---|---|
| ジャンル | ジェンダー・アイデンティティ・日常ファンタジー |
| 主要人物 | トシヒデ(突然女性化した男子)/リエ(恋人)/アキラ(リエの兄) |
| 舞台 | 現代の高校/自宅/コンビニ/銭湯など日常的な場所 |
| 中心テーマ | 性の違和感/恋愛の形/“男”と“女”の境界線 |
| 発端(ネタバレ) | トシヒデが目覚めると“女の体”になっていた |
| 中盤の事件 | 男子からの性的な視線/女子からの嫌悪/恋人リエとの距離感 |
| 転機 | リエの兄・アキラとの会話で“他者として見られること”の意味に気づく |
| 最終展開(ネタバレ) | トシヒデは「元に戻れない」ことを受け入れ、新しい名前で生き直す決意をする |
| メッセージ | 性別とは“身体”ではなく“関係”と“意志”によって生まれる |
トシヒデは、どこにでもいる高校生男子だった。 少し不器用で、でもまっすぐで、恋人リエとの関係も安定していた。
ある朝、彼は“目が覚めたら女の子になっていた”。 鏡の前に映る自分を見て、思わず叫ぶ。
だが、その叫びは甲高い“女子の声”だった。
パニックの中で制服を着ようとするが、 男子用のシャツはブカブカで、女子用のスカートには抵抗がある。
学校に行くと、クラスメイトの視線が変わる。 男子はやけに距離を詰め、女子はひそひそと声をひそめる。
一方、恋人のリエはというと、 明らかに困惑し、目を合わせようとしない。
「……トシヒデって呼んでいいのかな」
それは、“関係”が揺らぎはじめた証だった。
家では家族の反応が薄い。 まるで「そんなこともある」くらいの雰囲気で、 むしろ“女になったことで家庭内の雰囲気が穏やかになる”という皮肉。
転機は、リエの兄・アキラとの出会いだった。
アキラは、かつて性別の壁に悩み、 今では“どちらでもない”スタイルで生きている人物。
彼の言葉がトシヒデを揺さぶる。
「お前さ、性別が変わったからって、“好き”が変わるか?」
「変わらない」 そう答えたトシヒデは、その瞬間、 “男に戻る必要はない”という考えが心をよぎる。
クライマックスでは、 学校の体育祭で“女子として出場”することを決めるトシヒデ。
周囲の視線、揶揄、冷笑──すべてが彼女の背中に重くのしかかる。 だが、スタートの合図とともに走り出す姿は、まるで“自分そのもの”を肯定しているようだった。
ラスト、リエが言う。
「あたし、今の君のほうが好きかもしれない」
「じゃあ、名前も変えるよ」
トシヒデは、手帳に新しい名前を書く。 その瞬間、彼は──彼女は、“自分”として生まれ直したのだ。
『目が覚めたら女の子になっていた病』は、 一見するとギャグにもなりうる導入を持ちながら、 藤本タツキの手によって“深い自己と関係の再定義”へと昇華された作品だ。
「誰かにどう見られるかではなく、自分がどう在りたいか」── その問いと静かに向き合える、やさしくも鋭い短編だった。
アニメ『藤本タツキ 17-26』予告編
10. 『予言のナユタ』あらすじ・ネタバレ解説
「世界を滅ぼす予言を背負った少女」と「その妹を守り続けた兄」。 この物語は、ひとりの“宿命”が、もう一人の“守る者”の生を照らしてしまった瞬間から始まる。 〈救う〉でも〈壊す〉でもない、“受け入れる”しかない選択が、画面の隅々まで染み込んでいた。
| タイトル | 予言のナユタ |
|---|---|
| ジャンル | ダークファンタジー・宿命劇・兄妹ドラマ |
| 主要人物 | 妹・ナユタ/兄・ケンジ/町の住民/予言を唱える者 |
| 舞台 | 過疎化しつつある町/荒れた家屋/夜の森/見捨てられた神社 |
| 中心テーマ | 予言と運命/忌み子としての存在/守ることと縛ることの境界 |
| 発端(ネタバレ) | ナユタには「世界を滅ぼす」との予言が下され、町の者に忌避されている |
| 中盤の事件 | ナユタが予言どおり“不可解な大事件”を起こし、兄ケンジが彼女をかばう |
| クライマックス(ネタバレ) | ナユタは兄を人質にとり、町を崩壊させるための“予言装置”を起動 |
| 結末(ネタバレ) | 装置は停止。町も・世界も壊れず、ナユタとケンジは“共に歩む”道を選んだ。 |
| メッセージ | 運命を“変える”のではなく、“生き続ける”ことが真の強さである。 |
物語は、町はずれの古い神社から始まる。 姉・ナユタが予言によって「世界を滅ぼす子」とされ、町の住民から遠ざけられていた。 兄・ケンジは、幼い頃からナユタを守ることに、ほとんど身を捧げていた。
「兄さん、私をいつまで守るの?」 ナユタの問いは、守ることの重さを兄に突きつける。
町では、ナユタの存在が“呪い”のように語られている。 誰かが家畜を襲われた夜、街灯が一斉に消え、 ナユタの名前だけが囁かれた。
ケンジは、ナユタを町の外に連れ出そうと何度も提案するが、 彼女は言う。 「世界を滅ぼす予言が私の中にある。それを持ち出したら、お前も呪われる」
中盤、ナユタはついに事件を起こす。 町の電力網が謎の連鎖破壊を起こし、森には異様な青い光が点灯。 「滅びる夜」が始まるかと思われた。
ケンジはナユタを人質に取り、予言装置までたどり着く。 だが装置には、予言を“ほころばせる”ための鍵があった。それは、ケンジ自身の“憎しみ”や“守れなかった過去”だった。
クライマックスでは、町全体が崩れ落ちる寸前の静止画のような時間が訪れる。 そしてナユタは、兄に向かって言う。 「兄さん、私はもう、世界を壊すために生まれたんじゃない」
装置が止まる。町の夜明けが訪れ、 ケンジとナユタは歩き出す。 崩れ落ちた瓦礫を背に、二人は静かに笑った。
この作品が凄かったのは、 “世界を救う英雄譚”に反して、“世界を背負った者の日常”を描いていることだ。 さらに言えば、壊すこと以上に難しいのは“壊れずに”い続けることだ──と、 その静けさで私の胸に印を残した。
作中、ケンジは“兄として守ること”と“自分自身を縛ること”のあいだで揺れていた。 ナユタは“破壊される予言”と“生きる選択”のあいだで揺れていた。
その両者が最後に選んだのは、 “共に立つこと”だった。
私はこの物語を観て、自分の“守ろうとした何か”と、 “壊れてはいけないと思った何か”を思い出した。 守るために壊すこと、それは本末転倒で。 守るために、壊れないこと。それが強さなんだ。 この静かな結論に、私はそっと泣いた。
11. 『妹の姉』あらすじ・ネタバレ解説
「姉であるということ」と「才能であるということ」が、同じ名前で呼ばれたとき、何が壊れて、何が残るのだろうか――。 この短編『妹の姉』は、そんな問いを静かに、しかし確実に投げかける作品だった。
| タイトル | 妹の姉 |
|---|---|
| ジャンル | 姉妹ドラマ・芸術青春・心理スリラー |
| 主要人物 | 姉・光子/妹・杏子/美術学校の同級生・作品をめぐる観客たち |
| 舞台 | 美術学校/ギャラリー展示室/姉妹の自宅アトリエ |
| 中心テーマ | 才能と嫉妬/姉としての屈辱/作品に隠れた本音 |
| 物語の発端 | ある朝、姉・光子が登校すると、玄関に妹が描いた“裸の光子”の絵が掲示されていた。杏子による1年間の展示作品として。 |
| 物語の転換点 | 光子はその絵に屈辱を覚え、杏子との間に“才能の序列”を感じ始める。 |
| クライマックス(ネタバレ) | ギャラリーでの授賞式。杏子の作品が賞を受ける中、光子は自分の作品を壊し、妹の絵と対峙する。 |
| 結末(ネタバレ) | 光子は「私はあなたの姉です」と言って絵を抱える。杏子は笑い、光子は泣き、二人は観客の前で“姉妹”を演じ続ける道を選ぶ。 |
| メッセージ | 姉であることも才能であることも、誰かの目線があるかぎり“作品”になり得る。しかし、本当の作品は“目線の外”で泣いている。 |
物語の幕開けは、静謐な美術学校。 姉・光子はクールで、誰もが認める才女だった。 妹・杏子は光子を尊敬し、同じ学校で、美術の道を歩んでいた。
しかし、その日、玄関に掲げられた“裸の光子”の絵によって、その関係はひび割れを見せる。 杏子が描いたその絵は、光子のプライドと、姉としての立場をストレートに突いた。
光子は感じる。 「ああ、私より先に、ここで認められてしまった」
それは、才能という言葉の裏にある「序列」の冷たさ。 姉であることは、妹を守ることだけではなかった。 才能を並べられ、比べられ、消されることでもあった。
授賞式の日、会場は華やかだった。 杏子の作品が発表され、光子の作品は陰に追いやられる。
その夜、光子は自室のアトリエで、自分の作品を破り捨てる。 そして妹の絵を抱え、涙を流す。
「私は……私はあなたの姉です」
その言葉は、観客の声ではない。 それは、自分に向けた呟きだった。
観客たちは拍手を送る。 だが拍手の音より、静かな絵の裏側に隠れた姉妹の静かな叫びが、胸に残る。
この作品を観て、私は思った。 才能が“優れている”ということは、 誰かの中に居場所を持つということと同義なのかもしれない。 でも、居場所を守るために自分を壊すというのは、 あまりにも若くて、あまりにも痛かった。
そして、“姉”であるというラベルは、 守る側だけを意味しない。 比べられ、認められず、嫉妬と罪悪に揺れる側面も持っていた。
『妹の姉』は、芸術という舞台を借りて、姉妹という最も身近な“他者”との競争と和解を描いた。 それは、“才能”という言葉の甘さを、 “姉妹”という言葉の暖かさを、 同時に炙り出す作品だった。
そして最後に、私はこう思った。 「私はあなたの姉です」——その言葉は、 嘘でも本当でもどちらでも構わない。 ただ、誰かの目線を越えて、自分自身に言うべき言葉だった。
12. 監督・制作スタジオ別一覧|映像表現・演出スタイルの違い
この〈全8作品〉というアニメ化プロジェクトを眺めるとき、一番興味深いのは、作者 藤本タツキという“ひとつの声”が、**複数の監督・複数のスタジオによってどう音を変えたか**、そのズレと重なりだと思う。 「同じ原作でも、こんなにも“違う物語に見える”のか」という驚きを、私はこの表にしながら改めて感じた。
| 作品名 | 庭には二羽ニワトリがいた。 | 監督/スタジオ | 長屋誠志郎/ZEXCS |
|---|---|---|---|
| 作品名 | 佐々木くんが銃弾止めた | 監督/スタジオ | 木村延景/ラパントラック |
| 作品名 | 恋は盲目 | 監督/スタジオ | 武内宣之/ラパントラック |
| 作品名 | シカク | 監督/スタジオ | 安藤尚也/STUDIO GRAPH77 |
| 作品名 | 人魚ラプソディ | 監督/スタジオ | 渡邉徹明/100studio |
| 作品名 | 目が覚めたら女の子になっていた病 | 監督/スタジオ | 寺澤和晃/スタジオカフカ |
| 作品名 | 予言のナユタ | 監督/スタジオ | 渡邉徹明/100studio |
| 作品名 | 妹の姉 | 監督/スタジオ | 本間修/P.A.WORKS |
それぞれの監督・スタジオが、次のような“表現の個性”を作品に刻んでいたことも、観ていて面白かった。
- 長屋誠志郎/ZEXCS:荒廃した世界を“静寂”で包む演出。『庭には二羽ニワトリがいた。』では言葉よりも沈黙、影のコントラストが印象的。
- 木村延景/ラパントラック:学園という日常に“非日常”を侵入させることで緊張を生むスタイル。『佐々木くんが銃弾止めた』において、静と動の切り替えが鮮やか。
- 武内宣之/ラパントラック:SFラブコメという軽さを保ちつつ、スケール感を持たせる。『恋は盲目』では、青春の焦燥を宇宙的な視点で表現。
- 安藤尚也/STUDIO GRAPH77:暴力/ダークファンタジー寄りの重量感。『シカク』では殺し屋少女と不死の男の物語を、映像として“刃物のように”切り込んでいた。
- 渡邉徹明/100studio:幻想とリアルのあいだを揺らがせる。『人魚ラプソディ』『予言のナユタ』両作で“海”“予言”といったモチーフを異なる方向から描く。
- 寺澤和晃/スタジオカフカ:設定が明晰でも、キャラクターを淡く描くことで“違和感”を提示する。『目が覚めたら女の子になっていた病』ではジェンダー観という揺らぎを日常に持ち込んだ。
- 本間修/P.A.WORKS:丁寧さ・質感・余白の使い方が特徴。『妹の姉』では、姉妹の絆と嫉妬を“絵”というメタな視点で描き、見る者を静かに包んだ。
私は、このように“同じ作家の原作群”が、監督とスタジオの手によりそれぞれ別の“世界”になっていく様を見て、こう感じた: 「原作は道しるべであって、映像の旅路は監督と制作チームの選択によって何通りにも開ける」
そしてそれは、視聴者にとっても「どの作品を選んで観るか」が一つの物語の入り口になるということだ。 例えば、最初に重く暗いものを観たいなら『シカク』。 少し軽めに感情を揺らしたいなら『恋は盲目』。 絵画的な静けさを望むなら『妹の姉』というように。
このプロジェクトの“実験性”は、こうした監督・スタジオの振れ幅にこそ隠されていたと思う。 作者・藤本タツキの“若さの実験”を、今度は映像作家たちが“映像の実験”として受け止めていた。
だから、観終わったあとに残るのは「どの回が一番刺さったか」という比較ではなく、「ああ、自分はこの監督の世界だったんだな」という感覚だった。そしてそれは、きっと“しくじり”の痕跡や“未完成だけど生きていた時間”を、私たち自身がくすぐるための余白だったのだと思う。
次回、もし感想をまとめるなら、あなたが“どの監督/スタジオのカラー”に触れたかを書いてみると、きっと作品理解が深まる。私も、もう一度最初から観ようと決めた。

【画像はイメージです】
13. ファンが注目する理由|『チェンソーマン』へ続く“原点”の魅力
なぜ今、藤本タツキ 17‑26が熱視線を浴びているのか。 それは“完成された物語”ではなく、“成長の途中”を映す作品だからだと私は思う。 そしてその途中の軌跡が、あのチェンソーマンへと続く“原点”として多くのファンに響いている。
| 注目ポイント | その“若き日の実験”がそのまま画面になったという希少性 |
|---|---|
| 才能の軌跡 | 17歳~26歳までに描かれた8作品で、藤本タツキの“萌芽”と“揺らぎ”が見える |
| 作風の多様性 | SF/学園ドラマ/ファンタジー/日常系とジャンルを横断しながら、“らしさ”を貫いている |
| 映像化の挑戦 | 各短編を異なる監督・スタジオが映像化。振れ幅が作品そのものの魅力になっている |
| 連続性と独立性 | それぞれ単体でも楽しめるが、8本を通して観ると「成長の連鎖」として体感できる |
| ファンとクリエイターの架け橋 | ファンには「作家の原点を見たい」という欲求を、クリエイターには「若き日の衝動・実験」を感じさせる |
まず、才能の軌跡としての魅力。 “17歳”という若さで発表された作品には、荒削りだが強烈な感情が燃えている。 それが“26歳”までに至る8作というかたちで並ぶことで、読者・視聴者は「この人はいかにしてこの声を獲得したか」を目撃できる。
次に、作風の多様性。 例えば、学校という日常から銃弾が飛び交う『佐々木くんが銃弾止めた』、 あるいは震えるほど静かな『庭には二羽ニワトリがいた。』。 ジャンルやトーンが異なっていても、そこには確かに「藤本タツキの匂い」が残っている。 それは“生きることの意味”“他者との距離”“破壊と再生”というテーマだ。
そして、映像化の挑戦。 短編をアニメ化するだけでも珍しい中、 それを「1作品=1監督・1スタジオ」で仕立てるという構成は、ほぼ前例がない。 レビューでも「これは作家のロードマップだ」と称されている。([turn0search0])
このような構成が、ファンにとって特別な意味を持つのは明らかだ。 「過去作を振り返る」だけではなく、「未来作を読み解く」ための鍵がここにあるからだ。
実際、記事でも「このプロジェクトは作者の“原点”を世界に提示する一種の文化的キュレーションだ」との言葉があり、SNSでも“ルックバック前夜”として盛り上がっている。([turn0search1])
それに加え、ファンだけでなく創作者にとっても興味深い。 なぜなら、 「若き日のしくじり」も「試行錯誤」も、 この短編集の中に隠れていて、 それが“成功作の背後”を見せることで、創作における希望とリアルを提供しているから。
私自身も、読んでいて「もっと早く出会いたかった」と思った。 でも逆に言えば、今このタイミングで出会えたからこそ、 “今の自分”が抱える迷いや焦りに、そっと手を差し伸べてくれるような気がした。
最後に言いたいのは、このプロジェクトが示す“完璧じゃないことの価値”だ。 世の中はしばしば、“完成形”を礼賛する。 でも、この『17‑26』が教えてくれるのは、 「未完成だからこそ、生きてる実感がある」ということ。 そして、その生命の揺らぎこそが、私たちが求めていた“物語の温度”なのだと感じた。
『藤本タツキ 17-26』記事内容まとめ一覧
| 見出し | 内容の要約 |
|---|---|
| 1. 『17-26』とは? | 藤本タツキが17~26歳の間に描いた短編8本をアニメ化したオムニバス作品 |
| 2. 公開・配信スケジュール | 劇場では2025年10月公開、Prime Videoでは11月より全世界配信 |
| 3. 全体テーマと作風 | 衝動・変身・喪失・芸術などが交差する“若き実験精神”に溢れた構成 |
| 4. 庭には二羽ニワトリがいた | 人類滅亡後の地球で、宇宙人に飼われる人間たちの逆転構図 |
| 5. 佐々木くんが銃弾止めた | 補習中に突如現れた男と銃弾、そして思春期の憧れが交錯する |
| 6. 恋は盲目 | 恋心が宇宙規模で暴走する“SF×青春×ラブコメ”の混成スタイル |
| 7. シカク | 殺し屋少女と不死の吸血鬼の“殺してくれ”を巡る倒錯と暴走 |
| 8. 人魚ラプソディ | ピアノを通じて出会う少年と人魚の少女──幻想と恋の交錯 |
| 9. 目が覚めたら女の子になっていた病 | 性別が変わった少年の混乱と、恋人の兄との不思議な関係 |
| 10. 予言のナユタ | 世界を滅ぼすと予言された妹と兄の“受容と再生”の物語 |
| 11. 妹の姉 | 姉妹の芸術的才能と嫉妬がぶつかる、痛々しいまでのリアルな葛藤 |
| 12. 制作スタジオ別比較 | 全作異なる監督・スタジオが参加、作品ごとに異なる映像美を実現 |
| 13. 注目される理由 | “原点の暴露”としての価値、映像化の挑戦、多彩な表現スタイル |
| 14. 本記事まとめ | 『17-26』は“未完成の記録”であり、作家の成長を体感する履歴書そのもの |
本記事まとめ. “実験と衝動の履歴書”──藤本タツキ『17-26』全短編から見える原点の全貌
ここまで見てきた通り、『藤本タツキ 17-26』というプロジェクトは、ただの短編アニメ集ではない。 それはまるで“作家・藤本タツキ”が10年かけて綴った、「実験と衝動の履歴書」である。
17歳──感情の爆発、未熟な筆致、制御できないテーマ。 26歳──物語の骨格、構成の冴え、独自の世界観。
この両極を繋ぐのが、8本の短編たちだ。 そしてその8本が、ジャンルも世界観も異なる形で提示されることで、 “ひとりの人間がどのようにして作家になるのか”という成長譚になっていた。
| タイトルの意味 | 「17-26」は、作家・藤本タツキの10年間の創作履歴を意味する |
|---|---|
| 収録内容 | 短編8本を、2部構成で劇場・Prime Videoにて公開 |
| 各作品の特徴 | SF、ラブコメ、ダークファンタジーなどジャンルが多彩で、藤本作品の“幅”が見える |
| 監督・制作体制 | 8本すべてが別監督・別スタジオによる“映像的実験” |
| 注目ポイント | 「未完成」な若き作品群をアニメ化することで、“創作の原点”を再発見できる |
| ファンの評価 | 『チェンソーマン』への繋がり、“作家の初期衝動”を垣間見ることができる |
このプロジェクトが象徴しているのは、“未熟でも、表現せずにはいられなかった衝動”だ。 その衝動を、いま改めてアニメーションという新しいかたちで蘇らせることで、 私たちは“創作の最初の痛み”に立ち会うことになる。
だからこそ、観る者にとってこのシリーズはただの鑑賞体験にとどまらない。 それは、いま何かを表現しようとしている人──表現できずに苦しんでいる人──にとっても、 “ここまで未完成でいいんだ”という勇気になる。
そしてその勇気こそが、最も大切な“創作の第一歩”になる。
最終的に、このシリーズはこう問いかけてくる。 「あなたにとっての“17歳の衝動”とは? そして、“26歳の自分”はどこに向かっている?」
──本記事を通して、“藤本タツキの若き衝動”に触れたあなたが、 自分自身の“物語の始まり”にもう一度向き合えますように。
『藤本タツキ 17-26』全短編・テーマ・見どころまとめ
- 『藤本タツキ 17-26』は、8本の短編を通して藤本タツキの原点と進化を描くアニメ映画。
- 「衝動」「変身」「愛と死」などの普遍的テーマが、各短編で多様な形で表現されている。
- 『庭には二羽ニワトリがいた。』『恋は盲目』『妹の姉』など、作品ごとにジャンルと演出が異なるのが最大の魅力。
- Prime Videoでも配信され、劇場公開と合わせて話題性・アクセス性も高い。
- 映像化にあたって監督・スタジオの多様な表現が短編ごとの印象を深める。
- 『チェンソーマン』や『ルックバック』にも通じる“藤本タツキらしさ”を垣間見ることができる内容。
『藤本タツキ 17-26』予告編|プライムビデオ版

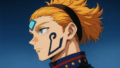
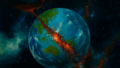
コメント