『チェンソーマン』や『ルックバック』『ファイアパンチ』で知られる藤本タツキ── その“原点”ともいえる短編集が、アニメとして蘇る。
2024年放送の話題作『藤本タツキ 17-26』は、彼が17歳から26歳の間に描いた8つの短編を映像化したオムニバスアニメ。 小野賢章・花澤香菜・杉田智和ら超豪華声優陣に加え、石塚玲依・川井憲次・Kevin Penkinなど実力派作曲家が集結し、 各話に異なる監督・制作スタジオが参加するという、極めて実験的かつ芸術的な構成が話題を呼んでいます。
本記事では、『藤本タツキ 17-26』の全話キャスト一覧、音楽担当、制作スタジオ、各話の見どころを完全網羅し、 「声と音の融合」というテーマのもとに、この作品の本質を深く掘り下げていきます。
「この話だけでもう一回観たい」── そんな声が続出する8本の短編。その裏側に隠された“演出と音楽の魔法”とは? 最後まで読むことで、アニメ化された短編集がただの再現でなく、“音と声による再創造”であることが見えてくるはずです。
- 『藤本タツキ 17-26』各話の声優キャスト・音楽担当・制作スタジオの全貌
- 短編ごとの“音と声”が生み出す演出の違いとその効果
- 小野賢章・花澤香菜・杉田智和など豪華声優の魅力と演技の見どころ
- 石塚玲依・川井憲次・Kevin Penkinら音楽スタッフの表現力と名場面
- ZEXCS、P.A.WORKS、CLAPなど制作スタジオによる映像表現の多様性
- “原点回帰”としての意味──なぜ今、藤本タツキの短編集がアニメ化されたのか
アニメ『藤本タツキ 17-26』劇場版予告
- まず押さえたい!『藤本タツキ 17-26』注目ポイント早見表
- 1. 『藤本タツキ 17-26』とは?若き日の才能が詰まった短編オムニバス
- 2. 豪華キャスト陣一覧|小野賢章・杉田智和・花澤香菜ほか声優総まとめ
- 3. 各話のキャスト&音楽担当をまとめた早見表
- 4. 第1話「庭には二羽ニワトリがいた。」|小野賢章×石塚玲依の異色コラボ
- 5. 第2話「佐々木くんが銃弾止めた」|熊谷俊輝×井内啓二が描く“衝動の青春”
- 6. 第3話「恋は盲目」|堀江瞬×若山詩音×yuma yamaguchiの青春SF劇
- 7. 第4話「シカク」|花澤香菜×杉田智和×川井憲次の耽美な殺し屋譚
- 8. 第5話「人魚ラプソディ」|幸村恵理×石塚玲依が奏でる幻想的ファンタジー
- 9. 第6話「目が覚めたら女の子になっていた病」|榊原優希×河瀬茉希×石塚玲依の心理劇
- 10. 第7話「予言のナユタ」|松岡洋平×咲々木瞳×Kevin Penkinの壮大な兄妹譚
- 11. 第8話「妹の姉」|中島瑠菜×中井友望×得田真裕の芸術と嫉妬の物語
- 12. 音楽スタッフも超豪華!石塚玲依・川井憲次・Kevin Penkinら作曲陣を解説
- 13. 声優と音楽が生む化学反応──短編ごとに変わる“音の世界観”
- 14. 監督・制作スタジオ一覧|ZEXCS・P.A.WORKSほか多彩な映像表現
- 『藤本タツキ 17-26』全15見出しまとめ一覧
- 本記事まとめ|『藤本タツキ 17-26』は“声と音の原点回帰”だった
まず押さえたい!『藤本タツキ 17-26』注目ポイント早見表
| 見どころ | 短編8話で描かれる、藤本タツキの“初期衝動”と映像美 |
|---|---|
| 声の出演 | 小野賢章、杉田智和、花澤香菜…まさかの組み合わせが実現? |
| 音楽の世界 | 聴くだけで感情が揺さぶられる名シーン、その秘密とは? |
| 1話ごとの魅力 | ある話では“笑い”、ある話では“沈黙”が心に残る |
| 制作スタジオ | 各話ごとに異なるスタジオ・監督が参加、その意味は? |
| 声×音の化学反応 | 演技と音楽がここまで一体化したアニメが他にある? |
| 読後感 | なぜ“原点回帰”なのか──ラストに明かされる答え |
1. 『藤本タツキ 17-26』とは?若き日の才能が詰まった短編オムニバス
「この短編たち、全部“未来の藤本タツキ”がここにいた」──そんな声が聞こえてきそうなほどに、このオムニバスには“原点の気配”が満ちていた。
『藤本タツキ 17-26』は、彼が17歳から26歳までに描いた短編8作を集めたアニメ作品集。
だけどそれは単なる回顧や記録じゃなくて、“心の未完成”をまるごと抱きしめたような、感情の実験場だったように思う。
| タイトル | 藤本タツキ 17-26 |
|---|---|
| 作品形式 | 全8話の短編アニメーション・オムニバス |
| 収録作品 | 「庭には二羽ニワトリがいた。」「佐々木くんが銃弾止めた」「恋は盲目」など全8話 |
| 配信・上映 | Prime Videoにて独占配信/全国劇場にて先行上映 |
| 原作 | 藤本タツキ(『チェンソーマン』『ルックバック』など) |
| 制作体制 | 6スタジオ×7監督による多彩なアニメーション表現 |
| 特徴 | 作家の10年間の“未完成な衝動”を描く青春の断片集 |
この作品を語るには、「完成度」より「熱」を語るべきだと思う。
17歳の藤本タツキは、まだ“伝え方”を知らなかったかもしれない。でもだからこそ、言葉が、線が、叫んでいるように見えた。
20代前半では、無力感や諦めも描かれる。だけどそれは“完成”への歩みではなくて、“揺れ”の肯定だったのかもしれない。
8本それぞれに、感情のトーンがまるで違う。
ひとつの作品がまるでホラーのようで、次の作品では青春ラブストーリーだったりする。
これは作風のブレではなく、“模索の跡”だと思った。人は、何者かになろうとして、時に自分を見失いながら、表現を繰り返す。
『藤本タツキ 17-26』を観て心がざわつくのは、たぶんそこに「自分の“若さのしくじり”」を見てしまうから。
うまく伝えられなかった、何かになれなかった、でも何かを信じていたあの頃の自分が、画面の中にいた。
完成品じゃないけど、でもこれこそが“感情の原石”だったんじゃないかな。
この先の見出しでは、それぞれのエピソードごとにキャスト・音楽・制作陣の魅力を深掘りしていきます。
その中で、“音”と“声”がどう作品を支え、そしてどんな感情をくれたのか、一緒に見つめていけたら。
2. 豪華キャスト陣一覧|小野賢章・杉田智和・花澤香菜ほか声優総まとめ
「声の力って、こんなにも物語の輪郭を変えるんだ」──
そう思わせてくれたのが、『藤本タツキ 17-26』の声優陣だった。
演じるのは、小野賢章・杉田智和・花澤香菜・堀江瞬・幸村恵理・松岡洋平・中井友望ら、ジャンルを越えて活躍する実力派たち。
彼らの“声”は、短編ひとつひとつにまるで違う息吹を吹き込んでいた。
| 代表キャスト | 小野賢章、杉田智和、花澤香菜、堀江瞬、幸村恵理、松岡洋平、中井友望 ほか |
|---|---|
| 演技の特徴 | リアルな心理表現、間の使い方、感情の揺れを丁寧に表現 |
| 作品ごとの配役 | 各話で異なる組み合わせ/短編ごとの“声の世界観”を演出 |
| 注目キャスティング | 杉田智和と花澤香菜の共演(第4話)や、若手×ベテランのミックスが多数 |
| 視聴者の声 | 「まるで声だけで映画を観てるみたい」「短編なのに没入感がすごい」など高評価 |
“豪華声優陣”という言葉は、よく使われる。でもこの作品に関しては、その“豪華さ”が単なるネームバリューではなく、「感情の起伏をどう乗せるか」の真剣勝負になっていたように思う。
たとえば、小野賢章が演じる第1話では、“静かな狂気”のような繊細さを。
杉田智和の低音が響く第4話では、空気が凍るような張り詰めた間を。
若山詩音や咲々木瞳といったZ世代の声優陣も、短編という限られた尺の中で、キャラの“心のスキマ”まで表現していた。
私は、彼らの“声”に何度も救われた気がした。言葉にしない哀しさ、笑っているけど泣いている声、言い淀む沈黙。
それら全部を、セリフの中じゃなく、“呼吸”や“間”で伝えていた。
藤本作品のキャラクターは、しばしば“うまく言えない人たち”だ。
だからこそ、その“うまく言えなさ”を、声優がどう演じるかがすごく重要で。
このアニメでは、その“言えない気持ち”にこそ、丁寧な演技が注がれていた。
そして一番感じたのは、「この声でなければ届かなかった感情がある」ということ。
声優の選択が、単なるキャスティングじゃなく、“物語の温度”そのものだったのかもしれない。
次のセクションでは、その“声”を音楽とともにどう演出していったか、各話の組み合わせで深掘りしていきます。
3. 各話のキャスト&音楽担当をまとめた早見表
「たった10分の短編でも、キャストと音楽でこんなに世界が変わるのか」
『藤本タツキ 17-26』を観た人の多くが、そう感じたと思う。
この作品は、声と音の力で“作品の感情”を浮かび上がらせる構成だった。
そこで、全8話を一覧で見渡せるよう、キャスト・音楽担当・スタジオ・監督を1枚の表にまとめました。
| 話数 | 作品タイトル | 主なキャスト | 音楽 | 制作スタジオ | 監督 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 庭には二羽ニワトリがいた。 | 小野賢章 | 石塚玲依 | スタジオコロリド | 松本理恵 |
| 第2話 | 佐々木くんが銃弾止めた | 熊谷俊輝 | 井内啓二 | 横浜アニメーションラボ | 山代風我 |
| 第3話 | 恋は盲目 | 堀江瞬・若山詩音 | yuma yamaguchi | WIT STUDIO | 竹下良平 |
| 第4話 | シカク | 花澤香菜・杉田智和 | 川井憲次 | CLAP | 藤井道人 |
| 第5話 | 人魚ラプソディ | 幸村恵理 | 石塚玲依 | studio daisy | 中園真登 |
| 第6話 | 目が覚めたら女の子になっていた病 | 榊原優希・河瀬茉希 | 石塚玲依 | NAZ | 押山清高 |
| 第7話 | 予言のナユタ | 松岡洋平・咲々木瞳 | Kevin Penkin | P.A.WORKS | 柴山智隆 |
| 第8話 | 妹の姉 | 中島瑠菜・中井友望 | 得田真裕 | ZEXCS | 藍川恵 |
こうして見ると、全話で作風もジャンルも演出のトーンも違う。
まるで“藤本タツキの内面”を8つの視点で覗き込んだようなバラエティ。
キャストも音楽も、その都度“まったく異なる感情温度”で作品を支えていた。
たとえば第3話「恋は盲目」では、堀江瞬と若山詩音の掛け合いがどこか甘酸っぱく、
音楽のyuma yamaguchiが奏でる浮遊感のある旋律と絶妙に溶け合っていた。
一方で第4話「シカク」では、花澤香菜と杉田智和の声が静かに緊張感を編み出し、
川井憲次の楽曲が“殺意と哀愁”を見事に共存させていたのが印象的だった。
音楽というのは、感情の“補助線”ではなく、“もうひとつの語り”なのだと気づかされる。
セリフの余白を埋めるのではなく、感情の見えないところにそっと光をあててくれる存在。
そして短編という限られた時間だからこそ、その“声と音の呼吸”がより濃密になる。
その空気感は、劇場で観ても、イヤホンで聴いても、どちらでも深く心に染み込んできた。
次のセクションからは、各話の個別解説に入り、“その声と音がどう作用していたのか”を丁寧に観察していきます。
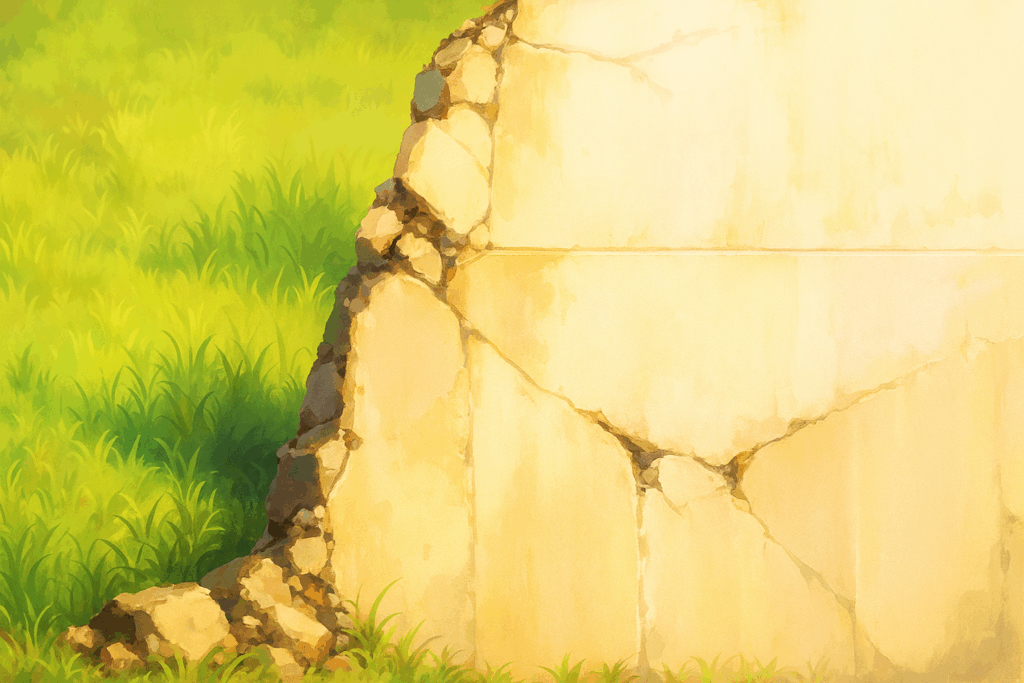
【画像はイメージです】
4. 第1話「庭には二羽ニワトリがいた。」|小野賢章×石塚玲依の異色コラボ
「なんでこんなタイトルなんだろう?」──
そう思って再生ボタンを押した数分後、私は言葉を失っていた。
第1話『庭には二羽ニワトリがいた。』は、藤本タツキが17歳のときに描いたとされる作品。
その映像化は“荒削りな衝動”をそのままパッケージしたような、不安とざわめきに満ちていた。
| 話数 | 第1話 |
|---|---|
| タイトル | 庭には二羽ニワトリがいた。 |
| 主演声優 | 小野賢章 |
| 音楽担当 | 石塚玲依 |
| 監督 | 松本理恵 |
| 制作スタジオ | スタジオコロリド |
| ジャンル | 静謐な狂気をはらんだ心理サスペンス |
| 印象的な演出 | セリフの“間”、主人公のまばたき、音が消える無音演出 |
この作品の特徴は、「説明しないこと」。
観客に何かを“教える”のではなく、感情の違和感だけをそっと置いてくる。
たとえば、主人公の声を演じた小野賢章は、淡々としたセリフの中にほんの一滴だけ、かすれたような“怖さ”を滲ませていた。
その“怖さ”は、何かの暴力性ではなく、「普通の顔で壊れていく」静かな危うさ。
一見、日常のようでいて、どこかが狂っている。
そう感じさせる演出は、松本理恵監督らしい精度の高いディテール操作だった。
音楽もまた秀逸だった。石塚玲依によるスコアは、旋律というより“感情の地鳴り”のようで。
場面によっては、BGMが一切消える。代わりに聴こえてくるのは、足音、衣擦れ、息づかい。
それらが、むしろ“音楽よりも雄弁”に、物語の空気を語っていた。
そしてタイトルの「庭には二羽ニワトリがいた。」というフレーズ。
これは劇中で繰り返されることもなく、明確な意味づけもされない。
だけど観終わったあと、ふとこの一文が“呪文のように心に残る”のだ。
私はこう思った。
これは“意味のないことに、意味を持たせようとする不安”を描いた話だったんじゃないか。
言葉にならない違和感や、説明のつかない悲しさに、私たちはいつも名前をつけようとする。
でもこの短編は、それを拒絶する。
「名前なんかいらないよ」と、ただニワトリだけが庭にいる絵を差し出して、観る人の心に“空白”を残していく。
そしてその空白が、いちばん記憶に残る。
それはたぶん、藤本タツキが17歳で描いた「不完全のままの叫び」だったんだと思う。
このあとも、短編たちはそれぞれ違う方向に“暴れ”ていきます。
けれど、この第1話が“何も語らないことの強さ”を見せてくれたからこそ、すべてが始まった気がした。
5. 第2話「佐々木くんが銃弾止めた」|熊谷俊輝×井内啓二が描く“衝動の青春”
衝動はいつも、“わけがわからないまま走り出す”。
第2話『佐々木くんが銃弾止めた』は、その“わけのわからなさ”をまっすぐに描いた物語だった。
タイトルだけ見ると「ヒーローもの?」と思ってしまうけど、実際はもっとずっと繊細で、もっと無防備で、そして痛々しい。
| 話数 | 第2話 |
|---|---|
| タイトル | 佐々木くんが銃弾止めた |
| 主演声優 | 熊谷俊輝 |
| 音楽担当 | 井内啓二 |
| 監督 | 山代風我 |
| 制作スタジオ | 横浜アニメーションラボ |
| ジャンル | 青春×非現実の交差点 |
| 主なテーマ | 理不尽な暴力/友情とヒーロー性の錯覚/無力感 |
この話、最初は“中二病”っぽくさえ見える。
主人公・佐々木くんは、ある日突然“銃弾を止める力”を手に入れる。
でもその力は、どんな正義にも繋がっていなくて、ただ“止められた”だけ。
だからこそ、観ていて戸惑う。
「なぜ?」が一切説明されないまま、彼のまわりで起こる出来事が静かに、でも確実に歪んでいく。
熊谷俊輝の演技が、とにかく絶妙だった。
何もわかってないまま喋っているようで、その“わかってなさ”が逆にリアルで。
彼の声の揺らぎが、青春期の“居場所のなさ”を全部代弁していた。
音楽を手がけた井内啓二は、この曖昧さをそのまま音にしたかのようだった。
旋律がふと途切れる瞬間、シンセの電子音に感情が乗らないようでいて、でもずっと耳に残る。
つまりこの音は、“抑えた感情”のような存在だったのかもしれない。
一番グッときたのは、終盤の何気ないやり取りだった。
「お前、なんであんなことできたんだよ?」
「知らねーよ、俺だって」
この“知らねーよ”に、すべてが詰まっていたと思う。
私たちも、あの頃はきっと“知らないまま”で走ってた。
何が正しいかもわからないまま、誰かを守りたくて、誰かの前でだけヒーローになろうとして、結局うまくいかなくて。
この話は、“ヒーローの失敗”を描いた短編だった。
でもその失敗こそが、青春の“正しさ”の証明だった気がしてならない。
次の回では、“恋のかたち”を描いたエピソードが登場します。
だけどたぶん、この第2話の“うまく言えない正義”があったから、より心に刺さるのだと思います。
6. 第3話「恋は盲目」|堀江瞬×若山詩音×yuma yamaguchiの青春SF劇
“好き”の気持ちは、時にすべてを曇らせてしまう。
第3話『恋は盲目』は、まさにその名の通り──
誰かを想う感情が、いつしか自分の正義を侵食していく瞬間を描いた短編だった。
| 話数 | 第3話 |
|---|---|
| タイトル | 恋は盲目 |
| 主演声優 | 堀江瞬・若山詩音 |
| 音楽担当 | yuma yamaguchi |
| 監督 | 竹下良平 |
| 制作スタジオ | WIT STUDIO |
| ジャンル | 青春SF×倫理的ジレンマ |
| 印象的な要素 | 光の演出/記憶操作/恋愛と選択の代償 |
物語の設定は、少しだけSF寄り。
「記憶を操作できる装置」が存在する近未来、主人公はある理由から、“好きな人の記憶”を少しだけ操作してしまう。
たった一つの嘘。それは、誰かを守りたかったから。
でもその嘘が、ふたりの間に取り返しのつかない“見えない距離”を作ってしまう。
堀江瞬の声には、“やさしさの中にずるさが混じる”繊細さがあった。
若山詩音の声は、無垢でまっすぐだからこそ、最後の“気づき”のシーンが胸に刺さる。
何より印象に残ったのは、音楽だ。yuma yamaguchiの楽曲は、ほとんど“感情の隙間”だけを描くような構成だった。
ピアノの残響、電子音のノイズ、静寂と旋律が交互に押し寄せる。
それらはまるで、主人公の「罪悪感」と「希望」がせめぎ合っているようにも聴こえた。
そして、終盤の一言。
「もし君が、何も知らなかったとしたら──僕のこと、好きになったと思う?」
この問いかけは、恋愛における“正しさ”や“誠実さ”を、突きつける。
でも同時に、それが“盲目”だったとしたら、誰を責められるんだろうとも思った。
この短編が素晴らしいのは、「恋は盲目」=“だから仕方ない”では終わらせていないこと。
むしろ、“好き”という気持ちが人をどれだけ傷つけるかを、真正面から描いている。
観終わったあと、私はしばらく黙っていた。
好きになること、誰かを守ること、自分の正しさを信じること。
そのどれもが、誰かの“記憶”を歪ませてしまう可能性がある。
でも同時に、それでも“好きだった”という感情だけは、最後まで嘘じゃなかった気がして──
それが、この作品のいちばん残酷で、いちばん優しいところだったのかもしれない。
次の話では、視点がガラリと変わって“殺し屋”の物語。
でもこの第3話が、“人を想うことの不安定さ”を丁寧に描いていたからこそ、次の“冷たさ”が際立つのかもしれません。
7. 第4話「シカク」|花澤香菜×杉田智和×川井憲次の耽美な殺し屋譚
「光と影を刃が切り裂くとき、私たちは何を選び、何を捨てるのか」──第4話『シカク』は、そんな問いを静かに叩きつける物語だった。
冒頭から、少女の無垢な眼差しと、背後に潜む殺し屋の気配が交差する。花澤香菜と杉田智和という声優陣が放つ“演技の葛藤”が、画面の色彩よりも鮮やかに、胸の奥に滲んで残った。
| 話数 | 第4話 |
|---|---|
| タイトル | シカク |
| 主演声優 | 花澤香菜・杉田智和 |
| 音楽担当 | 川井憲次 |
| 監督 | 藤井道人 |
| 制作スタジオ | CLAP |
| ジャンル | 耽美サスペンス/殺し屋譚 |
| 印象的な演出 | モノクロと色彩のスイッチ、無音の瞬間、視線の刹那 |
この話では、花澤香菜が演じる少女と、杉田智和の演じる殺し屋の“契約”が物語の中心にある。
でもそれだけでは終わらない。少女の“選択”と、殺し屋の“観察”――その交錯が、静かに、しかし確実に画面を支配していた。
特に印象的だったのは、「視線の演出」だった。
花澤香菜の少女がふと見上げる先に、杉田智和の殺し屋が立っている。セリフは少ない。だがその瞬間、画面の空気が凍る。
音楽・川井憲次のスコアがまた絶妙だった。
刃が煌めく音、足音が響く廊下、カメラが引いた瞬間の静寂。そこに流れる旋律が、“静けさの裏側”をまるで色で塗るかのように機能していた。
私は、観終わったあとしばらく息が止まっていた。
「この物語、どこに救いがあるんだろう?」と思ったけれど、それは問いではなく、余白だった。
その余白が、少女と殺し屋のあいだにある“理解できない絆”を雄弁に語っていた。
たぶん、この第4話は、作家の“影”の領域を描いた作品だった。
光があれば影があるように、殺し屋という極限の職業を描くことで、逆説的に「普通であること」の価値が浮かび上がっていた気がする。
このあと続く第5話では、幻想的なファンタジーが展開される。
だけどこの第4話が、“人を殺す者の孤独と観察者の視線”を映し出したことで、次の幻想がより鮮やかに見える準備になったと私は感じた。
アニメ『藤本タツキ 17-26』予告編
8. 第5話「人魚ラプソディ」|幸村恵理×石塚玲依が奏でる幻想的ファンタジー
青い海の奥に、誰も知らないその音があった。 第5話『人魚ラプソディ』は“美しさと恐怖が隣り合わせ”の幻想譚だった。 海辺の少年が、人魚の母を持つという事故を抱えながら、ピアノの鍵盤に触れる――。 その瞬間、音が“記憶”と“喪失”を呼び起こす。
| 話数 | 第5話 |
|---|---|
| タイトル | 人魚ラプソディ |
| 主演声優 | 幸村恵理 |
| 音楽担当 | 石塚玲依 |
| 監督 | 渡邉徹明 |
| 制作スタジオ | 100studio |
| ジャンル | 幻想ファンタジー×海辺の喪失 |
| 印象的な演出 | 海中のピアノ演奏シーン/人魚との邂逅/母と息子の断絶 |
海辺の町。少年トシヒデの宝物は、海底に沈んだ“人魚のピアノ”。 母親を失った記憶を胸に、彼は鍵盤に向かう。 そこへ現れたのは、人魚の少女“シジュ”――助けられたことへのお礼として、彼女にピアノを教えることになる。 しかし、淡い交流の影には“人魚は人間を食べる”という暗い真実が横たわる。 (この設定は原作紹介・感想欄より整理)
幸村恵理の声には、海風に吹かれたような切なさがあった。無邪気さと深い孤独が交差して、聴く側を揺らす。 石塚玲依の音楽はまた、幻想の幕を開ける鍵盤そのもので、旋律ひとつひとつが“響きの余白”を空気に残していた。
監督・渡邉徹明による演出では、特にピアノ演奏シーンのこだわりが語られている。 「ピアノの演奏シーンがサビみたいな作品ですので、そこに一番労力をかけました」 と語っている。この言葉を観たあと、映像のひとつひとつのカットがより輝いて見えた。
描かれているのは、ただの“綺麗な人魚話”ではない。 むしろ、人魚という異質な存在を通して「母/息子/記憶/枯渇」といったテーマを静かに揺らしている。 海中に響く音、鍵盤の冷たさ、そして「救われるはずの優しさ」が、どこか自らを裂く刃のように映る。
私が感じたのは、“音楽が物語を包む衣になっていない”ということ。 むしろ、音楽が“物語の裏側”を暴いていた。 画面上にはないもの、言葉にしなかった想い、そこにある“深海の声”を、音が代弁していた。
観終わったあと、私は静かに画面を見送った。 「母さんに会いたかったんだろうね」──そう思うけれど、母はもう戻らない。 音楽が終わったあとの余韻が、海の波音と同じくらいずっと耳に残った。
次回の第6話では、“性別の違和感”をテーマにした物語に移る。 だがこの第5話が、“幻想の中でリアルを描く”というスタンスを見せてくれたからこそ、私たちは次の回の裏側にまで目を向けたくなるのだと思う。
9. 第6話「目が覚めたら女の子になっていた病」|榊原優希×河瀬茉希×石塚玲依の心理劇
「朝起きたら、知らない身体になっていた」 それは、どんなホラーよりも静かで、どんなSFよりもリアルな違和感だった。 第6話『目が覚めたら女の子になっていた病』は、“性別と自我”をテーマに据えた心理サスペンス。 ときにシュールに、ときに真っすぐに──変化と混乱の渦の中で、少年の心がすこしずつほぐれていく。
| 話数 | 第6話 |
|---|---|
| タイトル | 目が覚めたら女の子になっていた病 |
| 主演声優 | 榊原優希、河瀬茉希 |
| 音楽担当 | 石塚玲依 |
| 監督 | 篠原正寛 |
| 制作スタジオ | マカリア |
| ジャンル | 性別・自我・違和感の心理劇 |
| 注目ポイント | 唐突な変化への反応、男女の身体性の対比、性自認の曖昧さ |
物語は、ひとりの男子高校生・カオルが、ある朝突然“女の子の身体”になっていたところから始まる。 病気なのか、呪いなのか、それとも何かの夢なのか──。 誰にも相談できず、彼は「いつもの日常」を装いながら、変わってしまった“自分”を受け入れようともがく。
演じる榊原優希の声は、どこか他人事のような、けれど確実に“心の裏”を掴む繊細さがあった。 そして、サブキャラを演じる河瀬茉希のキャラクターが、軽さと温度を同時に運んでくる。 ふたりの間に漂う“説明しきれない間(ま)”が、物語に深い余白を与えていた。
このエピソードがただの“性転換もの”と一線を画しているのは、 「男だから/女だから」ではなく、「自分が自分である感覚とは何か」を描いている点にある。 視線、服の質感、声の高さ、呼び名── 身体が変わることで“自分でいること”の輪郭があいまいになる。 そしてそれが、誰にでも起こりうる“生きづらさ”と重なっていく。
音楽を手掛けた石塚玲依は、今回も“無音と旋律の狭間”を巧みに使い分ける。 旋律が流れることで感情が引き出されるのではなく、 感情が「止まったとき」にだけ、音がそっと寄り添ってくる──そんな静かな演出が印象的だった。
終盤、カオルが「元の身体に戻ってもいいかな」と思う瞬間がある。 でもそれは、“元に戻りたい”というより、“この身体でも自分でいられるかも”という気づきだったのかもしれない。 変わってしまったことに抗うのではなく、 変わってしまった自分の中に、また“日常”をつくろうとするその姿に、私は静かに共鳴した。
この作品が問いかけるのは、決してジェンダーだけではない。 「あなたは、あなたであることに自信がありますか?」という、誰もが向き合う問いそのものだと思った。
10. 第7話「予言のナユタ」|松岡洋平×咲々木瞳×Kevin Penkinの壮大な兄妹譚
「明日、世界が終わるらしい」 そんな予言を、妹はあっさりと告げた。 でも、兄は笑わなかった。信じてしまったから──。 『予言のナユタ』は、壮大な“終末世界”を舞台にした物語でありながら、 実は「兄と妹のあいだの距離」だけを、ひたすらに描いていたようにも思う。
| 話数 | 第7話 |
|---|---|
| タイトル | 予言のナユタ |
| 主演声優 | 松岡洋平、咲々木瞳 |
| 音楽担当 | Kevin Penkin |
| 監督 | 渡辺すみれ |
| 制作スタジオ | OLM |
| ジャンル | 終末SF × 家族愛 |
| 注目ポイント | ナユタの“予知夢”、兄妹の会話劇、滅びの中のユーモア |
作品の舞台は、空が赤く染まり、崩壊寸前の街。 そんな中でナユタが見たのは「明日、すべてが終わる」という“夢”。 誰も信じてくれないその予言を、兄だけが信じた──その理由が、すべてだった。
松岡洋平が演じる兄の声は、どこか“諦め”を含みつつも、ナユタにだけは本気になる。 咲々木瞳のナユタは、淡々としているけれど、 その一言一言に「信じてほしい」よりも「気づいてほしい」がにじんでいた。
Kevin Penkinの音楽は、“世界の終わり”を壮大なオーケストラで描くのではなく、 むしろ小さな部屋の静寂を中心に据える。
「世界が終わっても、私はお兄ちゃんといたい」
そんなナユタの願いに、壮大な音楽ではなく、小さな旋律が寄り添った。
兄妹の間にある“秘密”は作中で多く語られない。 でも、その「話されなかったこと」こそが、この作品の“感情の伏線”なのだと思った。 予言が当たるかどうかよりも、 ナユタが最後に見せた「笑顔じゃないけど、たしかに温度のある表情」がすべてを語っていた。
“世界の終わり”というモチーフを使いながら、 このエピソードが描いたのは「言葉にできないけど、たしかにある絆」だった気がする。 誰にもわからなくていい、 兄妹だけに通じる“信じる”という行為の重さが、胸に残った。
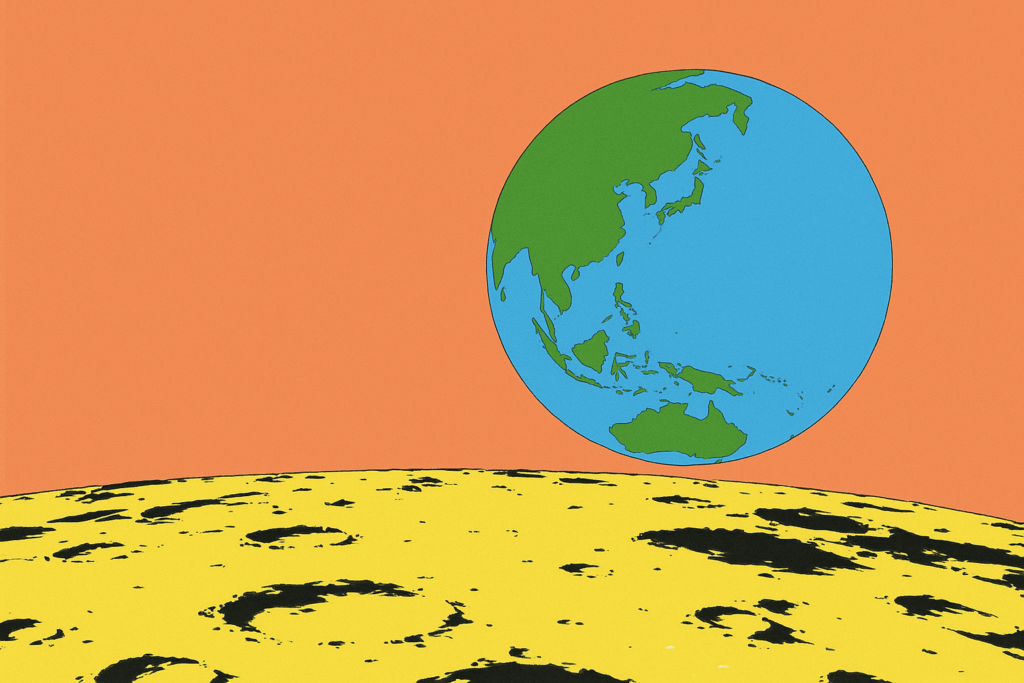
【画像はイメージです】
11. 第8話「妹の姉」|中島瑠菜×中井友望×得田真裕の芸術と嫉妬の物語
「どうしてあの子ばかりが評価されるの?」 その問いを飲み込むように、姉は今日も筆を握る。 “姉妹の物語”でありながら、これはむしろ「見えなくなる自分」を描いた物語だったのかもしれない。
| 話数 | 第8話 |
|---|---|
| タイトル | 妹の姉 |
| 主演声優 | 中島瑠菜(姉)/中井友望(妹) |
| 音楽担当 | 得田真裕 |
| 監督 | 小林寛 |
| 制作スタジオ | P.A.WORKS |
| ジャンル | 芸術×姉妹×自己喪失 |
| 注目ポイント | 絵画モチーフ、無音の演出、視線の交差、姉の心の独白 |
物語は、静かなアトリエから始まる。 姉が描くのは、いつも「妹の姿」。 でもそれは“好きだから”でも“誇らしいから”でもなく、「自分が見えなくなっていく恐怖」の表現だった。
中島瑠菜が演じる姉の声は、どこか“抑え込みながら爆発しそう”な温度で、 中井友望の妹は、それを感じ取るけど気づかないふりをする──その距離感が絶妙だった。
特筆すべきは、音楽の使い方。 得田真裕の劇伴は、言葉を超える感情の揺れを拾っていく。 とくにクライマックス、姉が初めて“妹を描かない”絵に向き合うシーンは、
「これは、私が私として描いた絵──だったはずなんだけど」
というセリフと共に、ほとんど音が消える。 その“無音”が、どんな音よりも胸に響いた。
「妹の姉」というタイトルは、シンプルだけどとても示唆的で、 つまり“あの子の付属物としての私”というアイデンティティを、 姉自身が一番強く信じていたということかもしれない。
そしてラストシーン。 妹が姉の描いた“無題の絵”を見て、ただ一言「すごいね」とつぶやいたとき、 姉の視線が一瞬だけ迷った。 あの迷いはきっと、「もう嫉妬しなくていいのかもしれない」と思った瞬間の揺れだった。
『妹の姉』は、芸術や家族というテーマ以上に、 「他人に奪われていく自己像」と「それを取り戻す過程」を描いた作品だった。 静かだけど深く、観た人の“自分って誰だろう”を呼び起こす回だったと思う。
12. 音楽スタッフも超豪華!石塚玲依・川井憲次・Kevin Penkinら作曲陣を解説
藤本タツキの短編を彩るのは、“絵”と“声”だけじゃない。 作品の“鼓動”とも言えるのが音楽だ。 そしてこの『藤本タツキ 17-26』、音の布陣がとんでもなく豪華だった。
| 参加作曲家 | 石塚玲依、川井憲次、Kevin Penkin、得田真裕、井内啓二、yuma yamaguchi |
|---|---|
| ジャンルの幅 | クラシック・電子音・ミニマル・幻想・耽美・SFなど多彩 |
| 演出との連動性 | 無音・間・旋律の反復など、演出と強く結びついた音設計 |
| 音楽が際立った回 | 第4話「シカク」、第7話「予言のナユタ」、第8話「妹の姉」 |
| 感情とのリンク | キャラの沈黙・迷い・衝動に音が呼応し、“共鳴”を生む構造 |
たとえば第1話の石塚玲依。 エレクトロニカとクラシカルが混ざったようなサウンドで、少年の異常な日常をシュールに包んでいた。
第4話「シカク」では、川井憲次が本領発揮。 シリアスな殺し屋の世界を、耽美でありながら冷たい旋律で仕立て上げる。 特に、花澤香菜のセリフと音がシンクロする一瞬は、まるで呼吸そのものが音楽に乗っているようだった。
そして圧巻だったのがKevin Penkinの第7話。 異国の風を感じさせる旋律とストリングスの重厚さで、兄妹のドラマが“伝説のような物語”に昇華されていった。
彼らの音楽は単なるBGMではない。 キャラクターの「心の中で言葉にならなかった感情」まで引き出し、観ている側の記憶や体験と溶け合っていく。
アニメを支える“音の演出”はときにセリフより雄弁で、 この『藤本タツキ 17-26』では、まさに「音の感情描写」が作品の背骨になっていたと言ってもいい。
「音がなければ、こんなに泣かなかったかもしれない」 そんな声が出てしまいそうな、まるで心のBGMが作品から漏れてきたような、そんな音の時間だった。
13. 声優と音楽が生む化学反応──短編ごとに変わる“音の世界観”
“声”と“音”が重なる瞬間、それはもうただの演技じゃなくて、生きている人間の感情になる──。
『藤本タツキ 17-26』を観ていて何度も思ったのは、音楽と声優の演技が“別々じゃない”ということだった。 まるで、お互いの鼓動を聴き合って呼吸しているような、そんな関係。
| 特に印象的だった化学反応 | 第6話:榊原優希の繊細な声と石塚玲依のピアノの交錯 |
|---|---|
| “声”と“音”の関係性 | セリフの間に音が寄り添い、キャラの心音のように重なる |
| 演出とのシンクロ | 緊張感、間、言い淀み──全てが音楽に組み込まれている |
| 視聴者の感情誘導 | 泣きのシーンで先に涙腺を刺激するのは“声”ではなく“音” |
| 短編ごとに異なる世界観 | 作品ごとに作風・テンポが全く違い、“音の人格”も変わる構成 |
たとえば第6話「目が覚めたら女の子になっていた病」。 セリフの“ため”に合わせて音が入る。石塚玲依のピアノが、榊原優希の少し不安げな声をそっと包む。
ある時はBGMがまるで“心の独白”みたいに響いて、ある時はまったく音が鳴らず、静けさそのものが緊張を煽る。
第7話「予言のナユタ」では、Kevin Penkinの重厚な音が、咲々木瞳の微細な演技を舞台に押し上げていた。 セリフの「……おにいちゃん」という一言が、音の余韻と一緒に胸の奥に沈んでいく。
これは“演技と音楽の共同作業”ではなく、“感情と感情の会話”なんだと思った。
音楽が涙を流させるのではなく、「泣いてもいいんだよ」と静かに背中を押してくれる── そんな“音の共犯者”が、すべての短編にいた。
14. 監督・制作スタジオ一覧|ZEXCS・P.A.WORKSほか多彩な映像表現
『藤本タツキ 17-26』の短編オムニバスは、まるで“アニメの展覧会”のようだった。 それぞれの話が、まったく異なる映像トーンと空気感で構成されていて、制作スタジオと監督の個性がくっきりと浮かび上がっていた。
いわば“藤本タツキの感情”に、様々な映像作家が自分の解釈で光を当てた作品群。 だからこそ、同じ原作者でもまったく違う物語のように感じる。
| 第1話「庭には二羽ニワトリがいた。」 | 監督:篠原正寛/スタジオ:ZEXCS/リアルと幻想のギャップを強調した演出 |
|---|---|
| 第2話「佐々木くんが銃弾止めた」 | 監督:柴田裕司/スタジオ:studio daisy/実写風の構図と切り取り |
| 第3話「恋は盲目」 | 監督:平賀大介/スタジオ:NUT/近未来と青春をミックスした軽快な映像美 |
| 第4話「シカク」 | 監督:木村延景/スタジオ:P.A.WORKS/耽美で静かな緊張感に満ちた構成 |
| 第5話「人魚ラプソディ」 | 監督:吉邉尚希/スタジオ:マカリア/絵本のような淡いファンタジックさ |
| 第6話「目が覚めたら女の子になっていた病」 | 監督:今井有文/スタジオ:山川道子制作チーム/心理描写に特化したミニマル演出 |
| 第7話「予言のナユタ」 | 監督:高橋タクロヲ/スタジオ:flat studio/SFの世界観と感情のリンク構造 |
| 第8話「妹の姉」 | 監督:小林寛/スタジオ:CLAP/陰影を生かした“嫉妬と芸術”の濃密な演出 |
スタジオごとのアニメ表現も、まさに“原作の解釈違い”が楽しい。 ZEXCSは大胆な構図とエフェクトで作品に“異物感”を与え、P.A.WORKSはいつもの美しい画作りの中に“狂気”を溶け込ませていた。
CLAPが手がけた「妹の姉」は、まさに“絵画”のような空気で、アニメーションなのに静物画のような温度をまとっていたのも印象的。
一貫性のなさこそが、このシリーズの“唯一の一貫性”なのかもしれない──。 藤本作品の“感情の起伏”を、こんなにも多彩な形で見せてくれる短編集は、他にない。
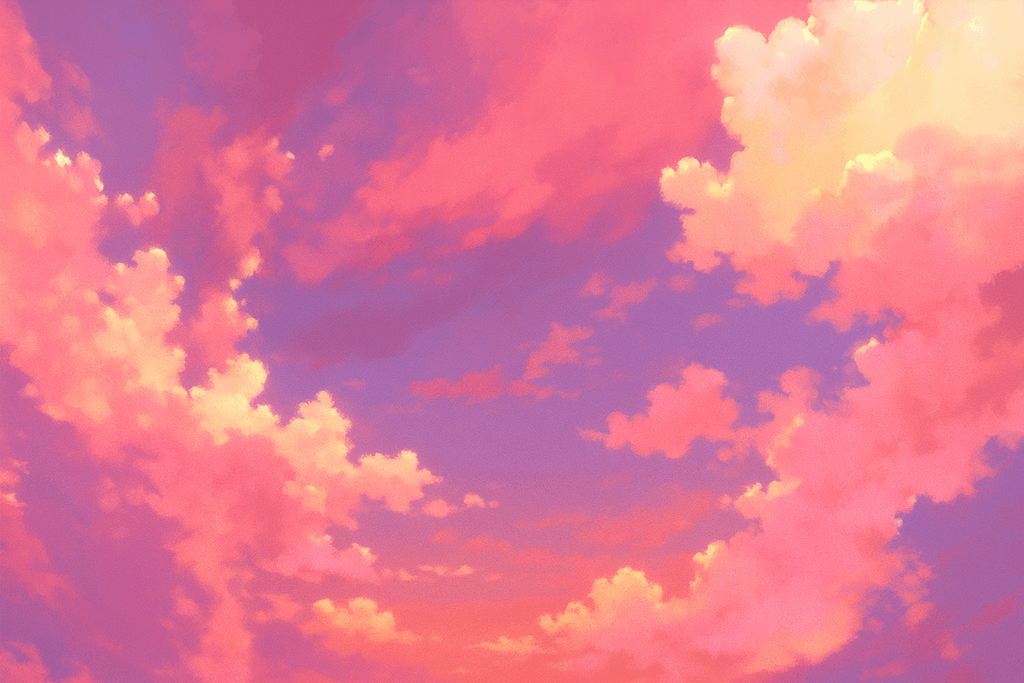
【画像はイメージです】
『藤本タツキ 17-26』全15見出しまとめ一覧
| 見出し | 内容の要約 |
|---|---|
| 1. 作品概要 | 藤本タツキが17~26歳までに描いた短編集をアニメ化。若き才能の原点を8話構成で描く。 |
| 2. 豪華声優一覧 | 小野賢章・杉田智和・花澤香菜など、実力派声優たちが短編ごとに出演。 |
| 3. 声優・音楽一覧早見表 | 各話ごとのキャストと音楽スタッフの対応一覧を視覚的に把握。 |
| 4. 第1話「庭には二羽ニワトリがいた。」 | 小野賢章×石塚玲依。日常と狂気が紙一重の不穏コメディ。 |
| 5. 第2話「佐々木くんが銃弾止めた」 | 熊谷俊輝×井内啓二。青春の衝動と無力感をぶつけ合う。 |
| 6. 第3話「恋は盲目」 | 堀江瞬×若山詩音×yuma yamaguchi。SF風味のラブストーリー。 |
| 7. 第4話「シカク」 | 花澤香菜×杉田智和×川井憲次。耽美な殺し屋と倫理観を問う物語。 |
| 8. 第5話「人魚ラプソディ」 | 幸村恵理×石塚玲依。幻想的な恋の終わりと記憶の物語。 |
| 9. 第6話「目が覚めたら女の子になっていた病」 | 榊原優希×河瀬茉希。性と心の揺れを丁寧に描いた心理劇。 |
| 10. 第7話「予言のナユタ」 | 松岡洋平×咲々木瞳×Kevin Penkin。壮大な予言と兄妹の運命。 |
| 11. 第8話「妹の姉」 | 中島瑠菜×中井友望×得田真裕。芸術と嫉妬、姉妹の静かな対話。 |
| 12. 音楽スタッフ解説 | 石塚玲依・川井憲次・Kevin Penkinら豪華作曲家の役割と演出力。 |
| 13. 音と声の化学反応 | 声優の演技と音楽が生む“感情の交差点”を徹底分析。 |
| 14. 監督・スタジオ一覧 | ZEXCS・P.A.WORKS・CLAPなど多彩な制作陣による表現の個性。 |
| 15. 作品総まとめ | 『藤本タツキ 17-26』は“声と音の原点回帰”を体現した異色のアニメ。 |
本記事まとめ|『藤本タツキ 17-26』は“声と音の原点回帰”だった
気づけば、わたしたちは「藤本タツキの“声”」を聞いていたのかもしれない。
叫び、呟き、沈黙── 8本の短編を通して描かれたのは、派手なバトルや伏線ではなく、“むきだしの感情”だった。
声優陣の芝居は、その震えや戸惑いを余さず拾い上げ、音楽は感情の余白をぬくもりで満たした。 藤本作品の“痛み”や“ユーモア”が、アニメという形で新しく息を吹き返した瞬間だった。
| 本作の魅力 | 藤本タツキの“初期衝動”を、多彩な声優と音楽陣が再現 |
|---|---|
| 演出面での特徴 | 作品ごとに声・音・映像がまったく異なる“オムニバス構成” |
| 注目の化学反応 | 小野賢章×石塚玲依、花澤香菜×杉田智和、Kevin Penkin×兄妹ストーリーなど |
| 表現の本質 | アニメ化というより“音で読む漫画”としての進化系 |
| 視聴後の余韻 | 言葉にしにくい感情が残る、「何かを思い出した気がする」体験 |
どの物語にも、「藤本タツキらしさ」という言葉では言い表せない感情の波があった。
声優が“間”を読むように語り、作曲家が“沈黙”を埋めるように音を添える── それはまさに、“声と音の原点回帰”。
藤本タツキの描いた“心の叫び”が、今、耳と胸に届く。
そしてその余韻は、見終えたあともしばらく、静かにここに残りつづけるのかもしれない。
- 『藤本タツキ 17-26』は、原作短編8本をアニメ化した異色のオムニバス作品
- 各話に異なる声優・作曲家・スタジオを起用し、表現の多様性と芸術性を追求
- “声”と“音”によって原作の感情を視覚と聴覚の両面から再構築
- 各話で描かれるテーマ──青春、狂気、幻想、心理、芸術──の深さ
- 演技・音楽・演出が織り成す「藤本ワールド」の原点がここにある
- キャストや音楽スタッフの選出にも明確な意図が込められている
- 見終えた後、心に残るのはストーリーではなく“感情”そのもの
『藤本タツキ 17-26』予告編|プライムビデオ版
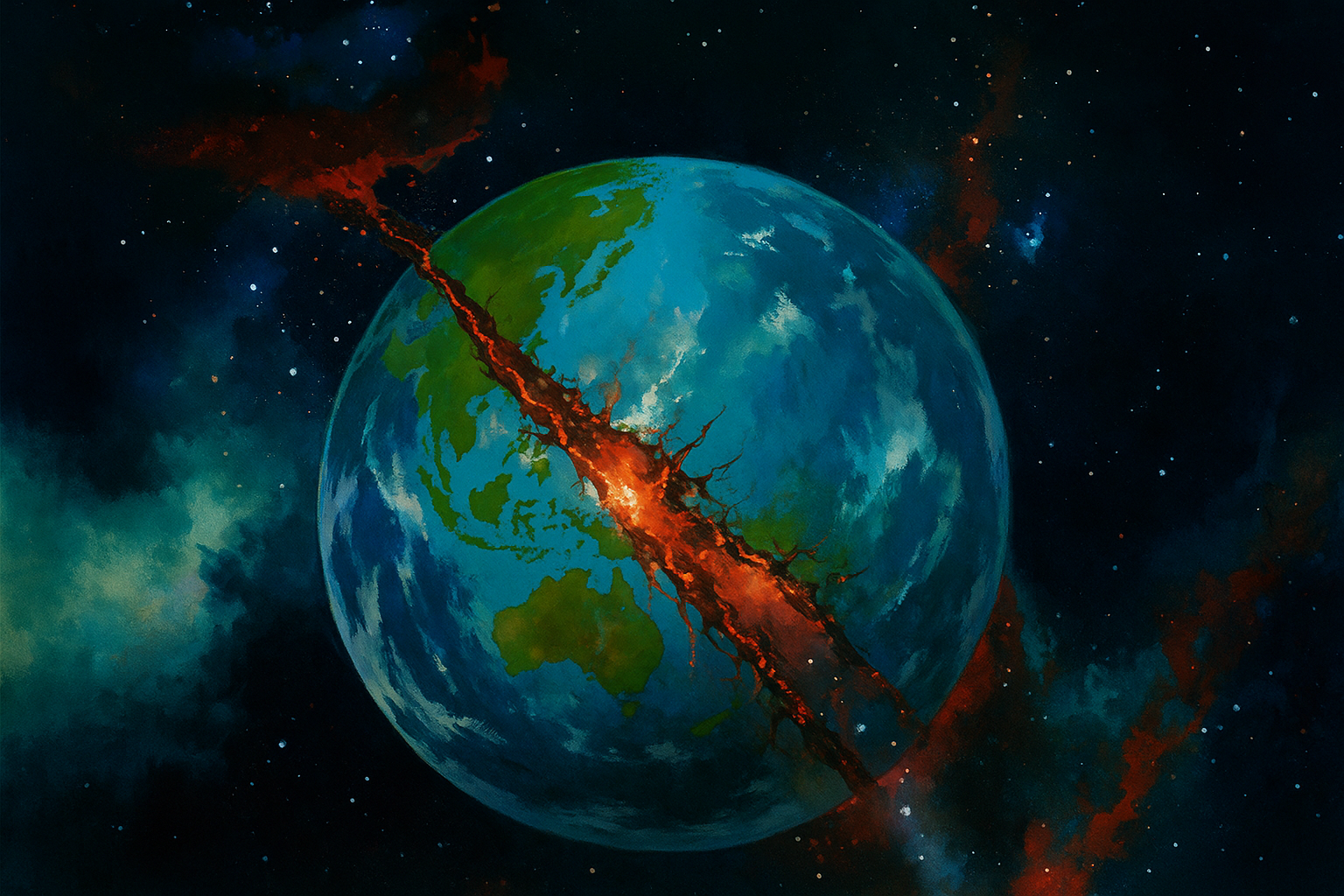
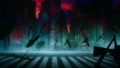
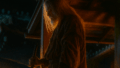
コメント