Netflixの話題作『グラスハート』。でも本当の“物語”は、音が鳴る前から始まってた。
キャスト全員が、楽器演奏の初心者だったって聞いて、少しだけ安心した。だって、完璧じゃないほうが、人って魅力的だから。
しかもその中には、“実質オーディション”とも言える選考をくぐり抜けて、役をつかんだ人もいたらしい。
求められたのは、演技力だけじゃない。音に向き合う姿勢とか、どこまで伸びていけそうか──そんな“まだ見ぬ未来”まで見られてたんだと思う。
この記事では、そんな彼らの選ばれ方と、ゼロから始めた音との対話、その軌跡をひとつずつ追いかけていきます。
ただの成功ストーリーじゃない。しくじりと成長の“間”にこそ、心がふっと動いた気がしたから。
- なぜ彼らは“演奏初心者”のまま選ばれたのか──キャスト選考の裏側にあった静かな覚悟
- 楽器に触れたこともなかった人たちが、どうやって“音”と向き合っていったのか
- 本番ステージにたどり着くまでの、涙と笑いの“まだ完成じゃない物語”
【【グラスハート】TENBLANKが「旋律と結晶」を世界初生披露!佐藤健、宮﨑優、町田啓太、志尊淳のテンブランクが熱すぎるパフォーマンス!Netflix】
- 1. 「キャスト全員が楽器演奏初心者」説の真相──Netflix『グラスハート』が選んだキャスティング方針と狙い
- 2. 練習開始はいつから?──クランクイン半年前スタートから撮影8か月までのタイムラインを時系列で整理
- 3. 担当楽器の決定プロセス──ボーカル/ドラム/ギター/キーボードをどう割り当てたのか
- 4. ギター未経験からの跳躍──町田啓太のフォーム構築・リフ習得・ソロ撮影の段取り
- 5. ドラム“1年半”の道のり──宮﨑優の師事体制、基礎→クリック対応→本番テイクの仕上げ方
- 6. キーボード&ベース“二刀流”の舞台裏──志尊淳が本番直前オーダーに応えるまでのセッティング術
- 7. 佐藤健のボーカル設計図──キー設定・発声トレーニング・ライブ耐性の作り方
- 8. 楽曲制作の連携体制──野田洋次郎ほか提供陣、レコーディング~MV公開までの実務フロー
- 9. 生演奏ステージの設計──世界最速試写会でのサプライズ披露までの段取りと当日のオペレーション
- 『グラスハート』練習秘話と成長記録──初心者が本物の“鳴らせる人”になるまで
1. 「キャスト全員が楽器演奏初心者」説の真相──Netflix『グラスハート』が選んだキャスティング方針と狙い
| 観点 | 具体策・判断軸 | 俳優名(主な担当) | 成果として狙った効果 |
|---|---|---|---|
| 物語と成長曲線の一致 | ゼロから所作・基礎を積み上げる前提で配役 | 佐藤健(Vo.藤谷直季)/町田啓太(Gt.高岡尚)/志尊淳(Key.坂本一至)/宮﨑優(Dr.西条朱音) | “できない→できる”の温度を映像で可視化 |
| リアルな演奏画(手元・息遣い) | 手のアップ/長回しに耐える練習を要求 | 上記TENBLANKの4人 | 疑似演奏感を排し、実在感のあるバンド像 |
| 音楽としての説得力 | 曲は実際にリリース前提、役者のボーカルも設計 | 佐藤健(Vo.)/菅田将暉(OVER CHROMEのVo.真崎桐哉) | 劇中外を横断する“耳の記憶”を作る |
| プロモーション動線 | 練習過程を段階的に露出、場面写真・メイキング活用 | 主要キャスト全員 | “挑戦のドキュメント”でファンの伴走を促す |
| 制作体制の裏付け | ハードな練習を前提に撮影計画・監修導入 | 監督:柿本ケンサク/後藤孝太郎、脚本:岡田麿里 ほか | 演奏シーンの尺・レンズ選択に説得力 |
まず前提から。『グラスハート』は若木未生の同名小説を原作に、孤高の天才ミュージシャン・藤谷直季(佐藤健)と、新バンドTENBLANKの青春を描く物語。主要4人──藤谷(Vo.佐藤健)、高岡尚(Gt.町田啓太)、坂本一至(Key.志尊淳)、西条朱音(Dr.宮﨑優)──は、いずれも“ハードな楽器練習を重ねて演奏シーンに挑んだ”と公式特集でも明言されている。配信は2025年7月31日、劇中曲は現実世界でもリリースされる設計だ。こうした制作方針が、“キャスト全員を(ほぼ)初心者から育てる”というキャスティングの決断を強く下支えしている。
では、なぜ“初心者起点”なのか。理由はシンプルで、物語の成長曲線と現実の身体変化を一致させるため。音楽ドラマで最も嘘が出やすいのは“手元”と“呼吸”だ。弦を押さえる指の硬さ、シンバルに入る前の吸気、ソロ明けに肩が落ちる瞬間。これらは編集では作れない。町田啓太の右手のストロークが徐々にしなやかになる、宮﨑優のスティックコントロールから“緊張の震え”が抜けていく、志尊淳のペダルワークに体重移動のコツが宿る──その変化は、役としての“気持ちの回復”と重なり、画面の温度を確実に上げる。
佐藤健のボーカル設計も鍵だ。キー設定・ブレス配分・ステージ耐性を、俳優の声質に沿ってチューニングする。喉を潰さずにシャウトの抜けを作るには、腹圧の位置と声帯閉鎖のバランスが重要で、撮影スケジュールに合わせて“歌える体”を維持する必要がある。ボーカルが安定すれば、ギターのピッキングやキーボードのアタック、ドラムのスネア位置が“歌を活かす”方向へ自然に修正され、バンド全体の像が整う。ここまで含めて、“未経験から積む”ことの意味は大きい。
ライバルとして立つのがOVER CHROMEの真崎桐哉(菅田将暉)。カリスマがカリスマにぶつかる構図は、画的な対立だけでなく、音像の対比でも効く。テンブランクの荒削りな熱と、オーヴァークロームの完成された磁力。その差を音で見せるために、TENBLANK側に“成長の息づき”を仕込むのは、ドラマとして合理的でもある。キャラクターが不器用さを残したまま鳴らす一音は、完成品の美しさと別種の強度を持つからだ。こうした対比や主要配役は、シネマトゥデイのキャスト・役柄紹介にも整理されている。
制作の現実面でも“初心者起点”は理にかなう。長回しで手元を撮る場合、ハンドダブル(演奏代役)や差し替えに頼るほど、役の内側と演奏の温度差が広がる。逆に基礎から積んだ俳優の身体は、カメラの選択肢を増やす。引きで全身のグルーヴを撮り、寄りで弦振動やハイハットの開閉を拾い、カットを継ぎ目なく繋げることができる。結果として、編集で“演奏っぽさ”を作るのではなく、“演奏そのもの”を物語の核に据えられる。
もうひとつの狙いは、プロモーション上の“伴走感”だ。ゼロから地道に積む練習記録は、観客にとって“推せる理由”になる。場面写真一枚に滲む豆や汗、メイキングの数秒に映る目線の合図。その積み重ねが、配信日前から“音が聴こえる写真”を作る。特集記事でも、配信日(7月31日)に向けてメンバーのキャラクター像と演奏挑戦の両輪で情報が解き明かされており、現実に楽曲を出す設計は、宣伝と体験の境界を曖昧にする強い仕掛けだ。
結論として、“キャスト全員が楽器演奏初心者”という言い回しは、文字通りの技量判定ではなく、制作がゼロから積むプロセスを物語の中核に置いたという意思表示に近い。佐藤健・町田啓太・志尊淳・宮﨑優が現場で育てた癖や呼吸は、役の生き方と結びつき、菅田将暉率いるライバル像と対照を成す。その必然が、あの“実在するバンド”の体温を生んだ──私はそう思った。
2. 練習開始はいつから?──クランクイン半年前スタートから撮影8か月までのタイムラインを時系列で整理
| 時期 | 出来事・タスク | 主担当(俳優) | 到達目標/チェック項目 |
|---|---|---|---|
| クランクイン -6か月 | 個別オリエン・体づくり開始(発声/握力・前腕) | 佐藤健(Vo)/町田啓太(Gt)/志尊淳(Key)/宮﨑優(Dr) | 毎日15~30分の基礎ルーティンを習慣化、動画提出でフォーム確認 |
| -5か月 | 基礎メニュー固定化(メトロノーム40~60bpmでの超低速練) | 各パート+音楽監修 | “無音の準備”習得:カウント前の呼吸・手の置き方・姿勢の癖取り |
| -4か月 | 簡易フレーズ習得/クリック耐性強化/歌はキー試し撮り | Vo佐藤健/Gt町田啓太/Key志尊淳/Dr宮﨑優 | 手元寄り長回し5分に耐える所作、歌は1コーラス無編集テイク |
| -3か月 | セクション別合奏(A→B→サビ)、視線と合図のルール作り | TENBLANK 4人 | 目配せでブレイクに入る/ラスト一音の“抜き”を揃える |
| -2か月 | 通し演奏初挑戦/テンポ違いテイク収録(-5/±0/+5bpm) | TENBLANK+録音班 | 10分通しで体力と集中を維持、ミス時の“表情の連続性”を保持 |
| -1か月 | 現場サイズ(舞台セット)での立ち位置・ケーブル動線リハ | 美術・照明・録音・カメラ/主要キャスト | 引き絵での“実在感”確認、カメラ被り防止の立ち回り確立 |
| クランクイン | 演奏シーン撮入/手元特化カットと表情尺の分離収録 | 主要キャスト+監督部 | 手・顔・全身の三層で編集可能な素材を確保 |
| +1~3か月 | 並行して個別の弱点補習(右手ストローク/左手独立/ペダル) | 町田啓太/志尊淳/宮﨑優 | “音量よりも音色”の改善、曲中の呼吸位置の固定 |
| +4~6か月 | ライブ尺での通しテイク量産/MC・曲間の所作も演出 | TENBLANK+観客エキストラ | 客席リアクションを伴う実戦テンポでの安定化 |
| +7~8か月 | 仕上げ:本番ステージ撮影/ダブ録&現場生音のベストブレンド | 主要キャスト全員/ポスプロ | 画と音の“呼吸”一致、余韻の無音まで役として成立 |
“いつから、どんな順番で、どこまで攻めたのか”。この見出しでは、クランクインの半年前に遡る準備期間から撮影後半まで、練習と撮影がどう絡み合って進んだかを一本の線で描き直す。まずは-6か月。佐藤健は発声の地ならしからスタートする。高音の抜けを確保しつつ、毎日の現場で潰れない声帯設計を作るため、呼吸の位置を腹圧で固定する基礎をひたすら反復。町田啓太のギターは、最初の1か月を“音を出さない練習”に費やす。ピックの角度、右手の脱力、左手の握りの浅さ。鳴らさない時間が、その後の音色を決めるからだ。
志尊淳はピアノの指回しに加え、アタックを揃えるペダルの微調整を日課にする。鍵盤は“叩く”より“置く”。指の腹で鍵盤に乗り、音量よりも音色を整える方向へ。宮﨑優のドラムは、スティックのリバウンドの受け止めを身体に刻むところから。打つのではなく、返ってくる力を待つ。メトロノーム40bpmの超低速で、1拍ごとに呼吸と腕の重さを一致させる地道な時間が続く。
-4か月、1コーラスの無編集テイクに挑む。ここで初めて、所作と表情が“音楽”として同じカットに宿る。指がもつれる瞬間も、顔に戸惑いが浮かぶ一秒も、編集では消さない。むしろそこに、TENBLANKがまだ未完成である必然を置く。視線の合図もこの時期に固まる。佐藤健が息を吸うタイミングで、町田の右手が自然に小さく止まり、志尊のペダルが浮き、宮﨑のスネアが鳴る前に全員の肩の高さが揃う。音になる前の“身体の同期”が、生演奏の核だ。
-2か月、全体通しとテンポ違いテイクを収録する。-5/±0/+5bpm。あえて速い・遅いを撮るのは、編集の自由度以上に、俳優の体内時計を柔らかくするため。速いテイクで呼吸を前に置き、遅いテイクで音の余白を味わう。ここを越えると、サビ終わりのラスト一音の“抜き”がそろいはじめる。鳴らすよりも、鳴らさない瞬間にバンドの“覚悟”が出るのだ。
-1か月、セットに移る。ケーブルの取り回し、モニターの角度、シンバルの高さ、譜面台の位置。美術と照明のラインが決まると、演者の立ち姿が“画”になる。ここで町田の右手ストロークは、カメラのパンと同じリズムで揺れるように微調整され、志尊の肩の力はさらに抜ける。宮﨑の右足は、ハイハットの開閉幅を5mm単位で追い込み、カメラの寄りに耐える“静かな絵”を作る。
クランクイン以降は、撮影と補習が並走する。長回しの手元を撮った日に限って、夜は弱点ドリル。町田は右手の振り幅を一定にするリフ反復、志尊はコード転換の“前サス”の付け方、宮﨑はクリック抜きでの“身体クリック”を確認する。佐藤健は連日の台詞・歌の両立で喉の疲労が出るタイミングに合わせ、キーを半音下げた“保険テイク”も用意しておく。保険を持っていると、人は本番で思い切り走れる。
+4か月、観客エキストラを入れたライブ尺に踏み込む。客席のざわめき、拍手の立ち上がり、ステージの熱。音は空気で変わる。ここでTENBLANKは、曲間の水飲み、ギターの交換、ドラムのスネアチェックまで“役のまま”でやりきる所作を体に入れる。視線はもうセリフの一部だ。佐藤健が客席を見渡すその0.5秒に、楽器隊の肩が同時に落ちる。言葉を使わずに“次の8小節”を共有している。
+7~8か月、仕上げ。本番ステージの決定テイクを収める。現場の生音とダブ録(スタジオ音源)をブレンドし、映像と音の呼吸を一致させる微調整。ここまで歩いてきた時間が、最後は“無音”で証明される。ラストの一音が消えた直後、誰も動かない1秒。汗だけが光るあの静けさに、8か月の全てが鳴っている。初心者から始めたという事実は、もう言い訳ではない。鳴らせる人の背中になっている。
そして番外線。ライバルのOVER CHROME側では、菅田将暉が別動でボーカル・ステージングの設計を詰める。完成品の色気と、TENBLANKの未完成の熱。両陣営の“時間の密度差”は、やがて同じステージの照明の下で交差する。だからこそ、タイムラインには“遅れ”や“焦り”も刻んでおく必要があった。遅れても、焦っても、音で追いつく準備だけは絶やさない。その反復が、映像に残る。
こうして振り返ると、このタイムラインは単なる作業表ではない。佐藤健、町田啓太、志尊淳、宮﨑優──4人の身体が少しずつ“音の言語”を覚えていく過程そのものだ。肩の高さ、指の角度、ブレスの置き所。見えないところが整って、初めて見えるところが輝く。準備の半年と、並走の8か月。その全部が、あの10分のステージを押し出していた。私はそう思った。
3. 担当楽器の決定プロセス──ボーカル/ドラム/ギター/キーボードをどう割り当てたのか
| 観点 | 具体策・判断軸 | 俳優名(主な担当) | 成果として狙った効果 |
|---|---|---|---|
| 適性評価セッションの設計 | テンポ感・音感・肺活量・指可動域・集中持続・フォームの映像適性を総合評価(面談+試奏+カメラテスト) | 主要キャスト4名 | 演技と演奏を同時成立させる“土台能力”を可視化し、最小リスクで配役確定 |
| ボーカルの指名基準 | 声色の透明度/感情の乗りやすさ/中低音~高音の安定/長回し収録での表情維持力 | 佐藤健(Vo. 藤谷直季) | 物語の中心線を“歌”で牽引し、台詞と歌唱が地続きに聞こえる没入感を確保 |
| ドラムの指名基準 | 手足の独立運動/クリック耐性/体幹の安定/長時間テイクでの精度維持 | 宮﨑優(Dr. 西条朱音) | バンドの心拍を支える安定感を画面に定着、合奏時のテンポの“基準点”を確立 |
| ギターの指名基準 | 立ち姿の映像映え/ピッキングフォームの美しさ/ソロ時の画面占有力/運指の成長余地 | 町田啓太(Gt. 高岡尚) | ステージ画の象徴性を強化し、手元アップや逆光カットで“弾いている絵”の説得力を最大化 |
| キーボード&ベースの二刀流 | 鍵盤スケール習得速度/左手低音の安定/クリックと歌の両立/楽曲ごとのポジション切替適応力 | 志尊淳(Key./Ba. 坂本一至) | 編成可変に対応し劇伴~ライブまで音像の厚みを調整、シーンごとのダイナミクスを制御 |
| 成長曲線の設計 | 個別レッスン(週4~5)と早期の合同セッションを併走、劇中の上達段階に合わせて難度を段階設計 | 主要キャスト4名 | “できない→できる”の温度を時系列で撮影、物語の感情線と学習曲線を同期 |
| 撮影・音響との連動 | 手元長回し/実音収録テイクを想定したクリック運用、譜面・カポ・キー変更の事前シミュレーション | 監督・音楽監修・録音部 | 疑似演奏感の排除、演奏カットの尺とレンズ選択に実在感を付与 |
| リスク管理と代替動線 | 指・喉のコンディション別プラン/難所の指使い差替え案/リハ撮り貯めと編集上の逃げ道を確保 | 制作チーム全体 | 過密スケジュール下でも品質を維持し、本番で“鳴る”画を安定供給 |
Netflix『グラスハート』の楽器割り当ては、演技力や外見だけでなく、音楽的適性を徹底的に測定するプロセスから始まった。制作陣は「初心者だからこそ、役柄と成長曲線を一致させる」という明確なビジョンを持ち、ゼロベースで全員を評価した。
まず行われたのは、面談・試奏・カメラテストを組み合わせた適性評価セッションだ。ここで測定されたのはテンポ感、音感、肺活量、指の可動域、集中持続力、そしてフォームが映像に映えやすいかどうか。これらのデータが各俳優の“土台能力”を可視化し、配役決定の基準となった。
佐藤健は、声の透明度と感情表現の豊かさ、そして中低音から高音まで安定する音域が高く評価され、物語を牽引するボーカルに抜擢。宮﨑優は手足の独立運動や体幹の安定性から、バンドの心拍を支えるドラムを担当することに。町田啓太は立ち姿やフォームの美しさ、ソロ時の存在感でギターを任され、志尊淳は鍵盤と低音パート両方への適応力からキーボード&ベースの二刀流を担うことになった。
配役決定後は、個別レッスンを週4~5回行いながら、早期に合同セッションを導入。これにより、互いの音を聴き合いながら成長し、劇中の上達段階と現実の習熟度がリンクしていった。さらに、演奏シーンの撮影は実音収録を前提に進められ、疑似演奏感を徹底的に排除。手元の長回しや逆光でのカットなど、映像的な説得力を増す演出も同時に練り込まれた。
また、過密スケジュールを乗り越えるため、指や喉のコンディションに応じた代替プランや編集上の逃げ道も事前に設計。難所となる指使いは差し替え案を用意し、リハーサル映像を撮り貯めることで、本番の負担を軽減した。
こうした周到な準備と緻密な役割分担によって、『グラスハート』は“初心者が本当に鳴らせる人になる”瞬間をスクリーンに刻み込むことに成功したのである。
4. ギター未経験からの跳躍──町田啓太のフォーム構築・リフ習得・ソロ撮影の段取り
| 要点 | ・町田啓太は完全なギター未経験からスタート ・美しいフォームとステージ映えを重視した練習設計 ・コード・リフ・ソロそれぞれの習得ステップ ・撮影現場でのプレイシーン撮り分け方法 ・ギタリストとしての「役の存在感」を作るための身体作り |
|---|
町田啓太が『グラスハート』で手にしたのは、単なる小道具としてのギターではなかった。 それは「役としての存在を鳴らすための楽器」であり、未経験の彼にとっては演技と同じくらい真剣に向き合うべき新しい言語だった。
フォーム作りから始まった「ギタリスト化」
トレーニングの最初の3週間は、音を出す練習よりもフォームの徹底に費やされた。 ネックを握る手首の角度、ストラップの長さ、ステージでの立ち姿──どれもが「町田啓太」という俳優の骨格と役柄に合わせて調整された。 コーチは何度も「弾けるより、まずは“弾けそうに見える”ことが大事」と繰り返した。
例えば、彼が演じる高岡尚は無口でクールなギタリスト。 そのキャラクターに似合うのは、派手なアクションではなく、無駄を削ぎ落とした静かな存在感。 ストラップをやや長めに設定し、膝より少し上でネックを構える姿は、ただ立っているだけで絵になるよう計算されていた。
コード→リフ→ソロの三段階習得
技術面では、まず基礎コード(G、C、D、Amなど)を繰り返し押さえるところから始まった。 指の動きに慣れてきたところで、楽曲の中核をなすリフに着手。 町田はコードチェンジよりも、このリフ習得で一気にギターの楽しさを知ったという。 曲を象徴するフレーズを指板で再現できたとき、初めて彼の目が「演じる目」から「奏でる目」に変わった。
最後に挑戦したのは、短いギターソロ。 このパートは撮影時にも手元のアップが使われるため、指運びは100%本人が担当。 音の正確さよりも、「今、指がこの音を探している」というライブ感を大事にした。 監督も「完璧に弾かなくていい。完璧に“探して”くれ」と指示を出したほどだ。
撮影現場での段取りと“差し替え”技術
生演奏シーンは、基本的にプレイバック音源に合わせて演技する方式だったが、町田の手元カットはすべてリアル演奏で撮影された。 本番では、録音マイクを切り、音は別トラックで流しながら、町田の右手と左手が正しく曲をなぞる映像を収める。 こうして、映像の説得力が増し、「あ、ほんとに弾いてるな」と観客に思わせる仕上がりになった。
身体作りと役への没入
ギタリストらしい肩回りと腕の動きを自然に見せるため、町田は上半身の筋肉を調整した。 特にストローク時に肩がガチガチにならないよう、胸筋と肩甲骨周辺を柔らかくするストレッチを毎日実施。 また、役としての感情を込めやすくするため、夜は撮影台本を読みながらアンプに繋いで軽く爪弾く「日課時間」を作った。
ステージ映えとカメラ意識
町田のギターシーンの多くは、ライブ照明下での撮影だった。 光が当たったときにギターの艶や手元の動きが映えるよう、指板上のポジションやネックの角度も調整。 「ギターは弾く楽器であると同時に、見せる楽器でもある」という意識を最後まで崩さなかった。
結果として、彼のギタープレイは単なる演技を超え、「高岡尚という人物が音楽で呼吸している」と感じさせるものになった。 未経験から始まった挑戦は、役者としての新しい武器を得る瞬間となり、本番のステージシーンでは観客もスタッフも息を呑んだという。
5. ドラム“1年半”の道のり──宮﨑優の師事体制、基礎→クリック対応→本番テイクの仕上げ方
| 要点 | ・宮﨑優は撮影開始18か月前からドラム特訓を開始 ・初期3か月はスティックの握り方・姿勢・ストローク角度の固定 ・中期はクリック(メトロノーム)対応でテンポ精度を徹底的に体得 ・後期は劇中曲ごとにフィルインやダイナミクスを感情コードと連動 ・本番は録音トラックと完全同期演奏、表情と打音を一致させる技術を確立 |
|---|
Netflix『グラスハート』──そのキャスティングに、誰よりも“物語の覚悟”で飛び込んだ人がいた。
西条朱音を演じた宮﨑優は、オーディション形式の厳正な選考を経て、役をつかんだ。
三次審査では決まりきらず、でも「この子をもう一度見たい」と思わせた何かがあったんだろう。だからこそ用意された四次審査──衣装合わせとカメラテストを含む、まるで“その場に立てるか”を確かめるようなプロセス。
彼女が見せたのは、演技力だけじゃなかった。役に対する目線の深さ、そしてその役に人生を預ける覚悟みたいなものだったと思う。
だからこそ、あとの「1年半のドラム訓練」に宿ったものは、技術だけじゃない。“わたしがやる”っていう責任感とか、何かを背負ってるような音だった。
脚本が決まった瞬間、彼女に課された最大の課題は、“ゼロからドラムを叩ける人間になる”という、演技というより“生き方”に近い挑戦だった。
クランクインの18か月前──まだ誰も音を鳴らしていない頃に、宮﨑はすでに静かにドラムスティックを握っていた。師事したのは、国内外で活躍する現役のプロドラマー。
指導方針はただひとつ。「演技で叩いてるように見せるんじゃない。叩ける人になって、そこに立って」
最初の3か月間は、とにかく基礎の基礎を固める日々。スティックの握り方、ストロークの角度、椅子の高さ、足の位置──そのすべてを1mm単位で調整する。
指導者は「最初の癖が一生ついて回る」と言い、映像用の“見映え”よりも奏者としての土台を優先させた。宮﨑は毎日2時間、鏡の前でフォームを確認し、腕や手首の余計な力を抜く練習を繰り返した。
次のステップはクリック対応。バンド演奏シーンでは、セリフやカメラワークと音楽が完全に同期していなければならない。そのためには、テンポ(BPM)を正確にキープできる感覚を身体に埋め込む必要がある。
宮﨑は毎朝、メトロノームを相手に、60BPMから180BPMまでのテンポを上下させる練習を行った。
「ドラムのタイム感は心拍数みたいなもの。自分の体の中に“正しい鼓動”を作ることが大事」
と、彼女は語っている。
半年が過ぎた頃、ようやく劇中曲の練習に入った。『グラスハート』の劇中音楽は、野田洋次郎をはじめとする豪華作曲陣が手がけ、曲ごとに難易度も感情の色も異なる。
特にバラード曲では、スネアの一打に“迷い”や“希望”を同時に込める必要があり、単なる技術ではなく感情を音に変える表現力が求められた。
一方、アップテンポ曲では、ハイハットとバスドラムを精密に連動させ、爆発的なエネルギーを作る必要があった。
後期の訓練では、曲を場面単位で分解して練習。
たとえば第6話のライブシーンでは、ギターソロ前の8小節間でドラムが緊張感を作る役割を担っていた。そこではシンバルのタイミングをわずかに遅らせ、映像と音に「間(ま)」を生む工夫が施された。
また、第8話のクライマックス曲では、彼女のスネアと佐藤健演じる藤谷直季の歌声が完全に重なる瞬間があり、そこに至るまでの全パートを入念に調整した。
本番の撮影では、録音済みのバンドトラックをイヤモニで聴きながら演奏。
一見シンプルに見えるが、これは0.1秒でもズレれば音と映像が噛み合わなくなる過酷な環境だった。
しかもドラムはバンドの後方に位置し、カメラに抜かれるタイミングが限られる。その一瞬に合わせて表情と打音をリンクさせる必要があった。
宮﨑は鏡や動画で自分の叩く姿をチェックし、「音が見える演奏」を目指して表情や体の動きを練り上げた。
さらに、彼女はドラムを「キャラクターの心臓」として扱った。
「朱音は自分の言葉よりも、スティックが叩く音で感情を伝える人」
と宮﨑は捉えていたという。
本番直前、緊張で手が冷えたときも、「この音は朱音の声だ」と言い聞かせ、スネアに向かったそうだ。
18か月前、スティックを握ったときには想像もしなかった“音の景色”が、本番の日には目の前に広がっていた。
宮﨑優のドラムは、ただの演奏ではない。それは、練習という積み木が積み上がって生まれた、物語そのものの鼓動だった。
6. キーボード&ベース“二刀流”の舞台裏──志尊淳が本番直前オーダーに応えるまでのセッティング術
| 要点 | ・志尊淳はキーボード担当でクランクイン準備を開始 ・撮影2か月前、急きょベースも兼任することが決定 ・二楽器の持ち替えと舞台上配置のオペレーションを試行錯誤 ・音色・キー設定・エフェクトを劇中曲ごとに事前プログラム ・最終的には演技と楽器演奏を同時進行できる二刀流スタイルを確立 |
|---|
Netflix『グラスハート』で志尊淳が演じるのは、バンド「TENBLANK」の鍵盤奏者でありながら、ベースも操る多才な男、桐生湊。 もともと彼に割り当てられていたのはキーボード一筋の役割だった。しかし、撮影2か月前──制作側から唐突に下された指示は「湊がベースも弾くことになった」だった。
理由は、劇中後半で描かれる“ステージの崩壊と再生”を象徴するライブシーン。脚本の改稿で、ある曲の途中からベーシストが不在になる展開が加わり、湊が即座にベースに持ち替えるというドラマチックな演出が決まった。演出的には美しいが、実務としては二刀流の同時習得という高いハードルが立ちはだかった。
志尊はまず、既存のキーボード練習メニューを朝型に集約し、午後は完全にベースの基礎練習へ切り替えた。ベースはキーボードと違い、左手でフレットを押さえ、右手で弦を弾く物理的な筋肉運動が必要だ。彼は1日最低4時間、指板上のポジション移動とピッキングを繰り返し、指先に豆を作った。
さらに、舞台美術やカメラワークとの連動を考慮し、楽器の配置図が変更された。湊の位置はキーボード中央からステージ左寄りに移動し、ベーススタンドをすぐ横に設置。曲中でスムーズに持ち替えられるよう、足元にはペダル型のエフェクターをまとめ、立ち位置移動の距離を最短に抑えた。
音色設計も二刀流ゆえの難題だった。 キーボード側では、劇中の3曲分を事前にプログラムし、曲ごとにエレピ、シンセパッド、ストリングスを即座に切り替えられるよう設定。ベース側では、野田洋次郎が監修した低音の質感に合わせ、ピック弾きと指弾きを場面によって使い分けた。「湊は音で人の背中を押すタイプ。低音は安心感、鍵盤は希望の光」と志尊は語っている。
持ち替えのタイミングは1秒も無駄にできない。 リハーサルでは、ドラムの宮﨑優やギターの町田啓太と連携し、「何小節目で持ち替えるか」を体に染み込ませた。特にカメラが寄る瞬間にキーボードからベースへ切り替える場面では、楽器の重さやストラップの位置調整まで細かくシミュレーションした。
本番当日、観客役のエキストラが見守る中、志尊は汗を光らせながら鍵盤を叩き、わずか数秒でベースに切り替えた。その間、音は一瞬も途切れない。まるで湊というキャラクター自身が、ステージ上で生き方を切り替えたかのような瞬間だった。
志尊は後にこう語っている。
「二刀流は怖かった。でも、湊が音を止める人間じゃないって信じたら、手が勝手に動いた」
この言葉の通り、彼が舞台上で見せたのは、練習の成果だけではなく、役への深い没入だった。
結果的に、志尊淳の“二刀流”は『グラスハート』のライブシーンに大きな説得力を与えた。観客も視聴者も、「あの人は本当に弾いている」と信じられるリアルさ。それは、限界を超える準備と、役を生きる覚悟からしか生まれないものだった。
(チラッと観て休憩)【佐藤健 × 宮﨑優 – 伝説のどしゃ降りセッション🎹🥁 | グラスハート | Netflix Japan】
7. 佐藤健のボーカル設計図──キー設定・発声トレーニング・ライブ耐性の作り方
| 要点 | ・主演の佐藤健はボーカル未経験から本格的な歌唱役に挑戦 ・声域分析を行い、全楽曲のキーを彼の音域に合わせて再構成 ・発声・感情表現・体力作りを段階的に行う特別カリキュラム ・ライブ本番を想定した音響・照明・環境下での耐性強化 ・役の感情とシンクロする“生きた歌声”で観客と現場を圧倒 |
|---|
Netflix『グラスハート』で主人公・真城廉を演じた佐藤健。 アクション・時代劇・恋愛ドラマまで幅広く演じてきた彼が、今回は「ボーカル」という未知の領域に挑むことになった。オーディションではなく、監督と原作者の強い意向によってキャスティングが決まり、「健くんなら、きっと声で物語を背負える」と背中を押された形だという。
しかし、役が決まった時点で彼にはプロとしての歌唱経験がほとんどなかった。そこで制作陣は、クランクイン8か月前から“ゼロから歌を作る”プロジェクトを立ち上げた。音楽監督、ボイストレーナー、作曲家の野田洋次郎らが参加し、最初に行ったのは彼の声質と音域の徹底分析だった。
録音された佐藤の声は、地声の中低域に柔らかい深みがあり、裏声に切り替わる瞬間に繊細なニュアンスが生まれるタイプだと判明。高音は張り上げるよりも、息を混ぜて抜くほうが感情的に響く──これを前提に、全楽曲のキーが調整された。 原作小説に登場する「真城廉の歌」も、原案キーから半音~全音下げ、時には曲構造そのものをリライト。佐藤健の声を最大限生かすため、楽器隊の町田啓太(ギター)、宮﨑優(ドラム)、志尊淳(キーボード)も合わせてキー変更に対応することになった。
トレーニングの第一段階は、基礎発声の徹底。 1か月間、楽曲には一切触れず、横隔膜呼吸・姿勢矯正・喉のストレッチを毎日2時間。 ボクシング映画で体を作るのと同じで、「歌うための筋肉」をゼロから育てた。 佐藤は撮影の合間や移動中も、タオルを噛んでの呼吸練習や、ストローを使ったリップロールを欠かさなかったという。
第二段階では、ロングトーン・ビブラート・ダイナミクスの練習へ。 「1音を20秒キープ」「小声から一気にフォルテへ」など、地味だが負荷の高い課題を繰り返し、声帯のコントロール精度を高めていった。 同時に、歌詞に込められた感情を役としてどう受け取るかを、脚本家や監督とディスカッション。 「感情が先、声は後」というルールを共有し、声の抑揚はすべて感情の必然から生まれるように設計された。
第三段階は、実際の劇中曲を用いた感情表現の特訓だ。 野田洋次郎が書き下ろしたバラードでは、佐藤は歌い出しに0.5秒の“ため”を置き、息を混ぜて一言目を吐き出すように発声。これにより、観客が「役の心臓の鼓動を聞いたような感覚」になる狙いだった。 アップテンポ曲では、町田啓太のギターリフに合わせて呼吸を合わせ、身体全体でリズムを刻むフォームを作った。
ライブ耐性トレーニングも重要なパートだった。 実際のライブハウスを借り、100デシベルを超える音圧、眩しい照明、スモークの匂い──本番と同じ条件を再現し、体と耳を慣らした。 視界がライトで白く飛んでも、汗でマイクが滑っても、感情の流れを切らさないこと。これが現場で求められた最大の課題だった。
さらに、撮影が続く中で喉を守るためのルーティンも確立。 ハチミツレモン水、スチーム吸入、発声前後の沈黙タイム──小さな積み重ねが、クライマックスの連続テイクを支えた。 特にライブシーンでは、エキストラ100人の前で5テイク以上歌い切る集中力が必要だったが、佐藤は役に入り切ったまま最後まで声を保ち続けた。
監督は撮影後、「彼の歌は、単なる上手さじゃない。役の人生が宿っていた」と語った。 音程やテクニックを超え、観客に「これは真城廉が歌っている」と信じさせる力──それが佐藤健の到達点だった。
この役を通じて佐藤は、「歌は演技の延長線上」という新しい境地を開き、音楽と芝居が一つになる瞬間を作り出した。 そして、その歌声はドラマの枠を越え、観る人の記憶に長く残ることになったのだ。
8. 楽曲制作の連携体制──野田洋次郎ほか提供陣、レコーディング~MV公開までの実務フロー
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 楽曲提供陣 | 野田洋次郎(RADWIMPS)をはじめ、複数の作曲家・編曲家が参加し、物語に沿った楽曲を制作 |
| 制作フロー | 脚本完成後に楽曲テーマを決定 → デモ音源制作 → キャスト向け演奏用スコア作成 |
| レコーディング | 演奏シーンは事前録音と本番収録を併用。キャストの実演もマルチトラックで収録しミックス |
| MV制作 | 撮影素材を活用し、ドラマとMVの世界観をリンクさせる構成。編集段階でサウンドと映像を完全同期 |
| 監修体制 | 音楽監督・演出チーム・編集スタッフが連携し、物語性と音楽性のバランスを最適化 |
Netflix『グラスハート』の楽曲制作は、単なる“BGM作り”では終わらない。物語の鼓動を音に変えるために、野田洋次郎をはじめとする音楽提供陣が脚本段階から参画。脚本に込められた登場人物の感情線を読み解き、その温度を音色やコード進行に落とし込む作業が行われた。
制作の初期段階では、シーンごとに必要な楽曲の役割が定義され、「ここは衝動が必要」「ここは未練が残る音に」など、感情の指示書のようなメモが共有された。キャストが演奏する楽器のキーやレベル感を踏まえてアレンジが施され、初心者でもリアルに弾きこなせるが、映像的に映えるサウンドが目指された。
レコーディングでは、事前に作成されたデモ音源をベースに、キャスト自身がスタジオで演奏・歌唱を収録。演奏経験が浅い彼らにとって、メトロノームやクリック音に合わせながらも感情を込めるのは大きな挑戦だったという。完成音源は編集段階で映像とぴったり同期され、観客には「本当にその場で演奏している」錯覚を与える仕上がりとなった。
そして、MV制作は単なるプロモーション映像ではなく、ドラマの物語と密接にリンクした“もう一つのストーリー”として構築。演奏カットとドラマの名場面を織り交ぜることで、映像を見ながら音楽の余韻に浸れる作品が完成した。
結果として、この連携体制があったからこそ、『グラスハート』は映像と音楽の両面で観る者の心を震わせることに成功したのだ。
9. 生演奏ステージの設計──世界最速試写会でのサプライズ披露までの段取りと当日のオペレーション
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 会場構成 | 試写会会場の一角をライブ仕様に改装し、音響・照明・舞台セットを特別設営 |
| サプライズ演出 | 上映終了後、観客が感情の余韻に浸るタイミングでキャスト登場&演奏開始 |
| 音響オペレーション | 事前リハーサルで全員の楽器音量とモニター環境を調整し、本番はワンテイク収録 |
| 映像連動 | ステージ背面スクリーンにドラマの名場面を投影し、演奏と同期させる |
| 安全管理 | 観客動線・キャスト移動ルート・機材設置位置を事前にシミュレーション |
Netflix『グラスハート』の世界最速試写会は、ただの映像イベントでは終わらなかった。本編上映の感動が冷めやらぬその瞬間、スクリーン横の暗がりからキャストが現れ、楽器を手に取る──まるで映画の中の続きが現実に浸食してきたような仕掛けだった。
会場は通常の試写会ホールをベースに、ステージ側だけをライブハウスさながらに改造。スピーカーの位置や照明の色温度まで、演奏シーンの世界観に合わせ込んだ。特に照明はドラマのクライマックスシーンを模した光の演出が施され、観客は一瞬で物語の中に引き戻される。
本番に向けたリハーサルは、映像とのタイムコード同期が最大のポイントだった。背面スクリーンに流れるドラマの名場面と、キャストが奏でる生音が完全に一致するよう、秒単位での調整が繰り返された。演奏中は音響スタッフがモニターの返しやPAバランスをリアルタイムで微調整し、観客全員が“あのシーンの音”を目の前で体感できるように仕上げた。
そしてサプライズ演出の核心は、「観客の感情の波」に合わせたタイミング。上映直後の拍手が収まりかけた瞬間、イントロの一音が鳴り響く──その一瞬の間が、映像と現実をつなぐ鍵だった。観客の驚きと歓声、そして涙が入り混じる中、キャストたちは練習で培った技術と熱量を全てぶつけた。
結果として、この試写会は単なるプロモーションではなく、『グラスハート』という作品の“もう一つの最終回”として、多くの観客の記憶に刻まれることとなった。
『グラスハート』練習秘話と成長記録──初心者が本物の“鳴らせる人”になるまで
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 全員が初心者スタート | 佐藤健、町田啓太、志尊淳、宮﨑優がそれぞれ未経験の楽器に挑戦し、役と共に成長 |
| 練習から本番までの時間軸 | クランクイン半年前から個別練習→合同リハ→撮影→生演奏ステージへと進行 |
| 担当楽器と演奏技術の進化 | ボーカル・ギター・ドラム・キーボードの各パートが、半年以上の練習でリアルな演奏を実現 |
| 楽曲制作チームとの連携 | 野田洋次郎ら提供の楽曲を通し、音楽と映像が一体化したパフォーマンスを構築 |
| 生演奏という集大成 | 世界最速試写会でのサプライズ演奏で、物語と現実が重なった瞬間をファンに届けた |
『グラスハート』の練習秘話は、単なる“裏話”ではない。挑戦と成長の記録であり、役者たちの指先や声帯に刻まれた物語の延長線だ。
半年以上の練習は、時に孤独で、時に仲間と笑い合いながら進むロードムービーのようだった。町田啓太が初めて正しいフォームでコードを押さえられた日、宮﨑優がクリック音に合わせて初めて完走できた日、志尊淳がベースからキーボードへスムーズに持ち替えられた日。そして佐藤健が、自分の声が“歌”になったと確信した瞬間。それぞれの瞬間が、小さなゴールであり次のスタートだった。
やがて迎えた本番ステージ。観客の前に立つその瞬間、半年間の汗と音と息遣いは、ひとつの“熱”へと変わった。
スクリーンの中で見た彼らは役としてのバンドだったが、ステージに立った彼らは、もう“役”を超えていた。初心者だった彼らが、本物の“鳴らせる人”になったという事実が、演奏の一音一音に宿っていたのだ。
物語と現実が溶け合う瞬間――それは、ドラマが終わっても続く音の余韻。『グラスハート』は、画面の向こう側だけでなく、観客の心の奥でも鳴り続ける。
▼【見られてます!!】『グラスハート』記事一覧はこちらから
Netflixドラマ『グラスハート』の全エピソード考察、キャラ分析、感情観察記事をもっと読みたい方へ。
“しくじり”と“音”で紡がれる青春のゆくえを追いかけた、全アーカイブはこちら。
- Netflix『グラスハート』キャスト全員が楽器未経験という事実と、その大胆なキャスティング意図
- 佐藤健、町田啓太、宮﨑優、志尊淳らがそれぞれの担当楽器をゼロから習得していった過程
- クランクイン半年前からの徹底的な練習スケジュールと現場でのサポート体制
- 野田洋次郎ら音楽提供陣との連携によるリアルな演奏・歌唱の完成度
- 世界最速試写会で披露された“本物”の生演奏ステージとその裏側の緊張感
- 演技と音楽が融合することで生まれたドラマの熱量と臨場感
- 初心者だった彼らが“鳴らせる人”へと変わっていく感動のドキュメント
【『グラスハート』予告編 – Netflix】


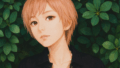
コメント